かたなしなるもの
白砂が裸足の指の間から溢れる。
ひと足踏むごとに、サクサクと鳴る砂が心地いい。
振り返れば、浜辺の小屋が小さく見える。海岸線に沿って、随分遠くまで歩いてきたらしい。
少年は砂を両手に掬った。粒がキラキラと光りながら、風に乗って散らばる。この辺りの砂は水晶が混じっているようだ。
少年は砂を使って細工物を作ることを生業としている、砂採りだ。
砂を小瓶に詰めて瓶にリボンをつけたり、貝を貼ったりして装飾品を作り、市場で売る。珊瑚や水晶の混じった砂の細工物はそれなりに売れ、少年1人の食を支えるくらいにはなった。
暫く歩くと、白い岩に囲まれた入り江があった。初めてくる場所だ。純白の砂。ひたひたと静かに波が打ち寄せる。
少年は浜辺に降りた。すると、波がざぶりと持ち上がり、少年の前に大きな生き物が現れた。
彼の背丈より大きいが、見上げるほどでもない。初めて会う生き物だ。
目も口もない丸い大きな頭部は半透明で、海月のように透けて、レースのようなひらひらした鰭を纏っている。
「こんにちは」と少年が挨拶すると、その生き物も「やあ、こんにちは」挨拶を返し「君はどこから来たんだい?」と問うた。
「向こうの浜辺から来たんだ」と少年は指差した。「僕は砂採りなんだ。綺麗な砂を集めてる。ここの浜辺は綺麗だね」
「そうだろ。ゆっくりしていけばいいよ」
生き物は得意げに言った。
少年は入り江を散策し、白い砂浜に腰を下ろした。
生き物は先端の平たい触手で、砂つぶを拾っては浴びた。砂は粘液で肌にくっついてキラキラと光る。
少年が「綺麗だね」と言うと、生き物は「そんなことないよ」と言いながら、見せびらかすようにくるりと回る。
「こんな貝だってあるんだよ」
生き物は桜色の貝殻を触手で拾っては見せた。「あげるよ」と言って様々な貝殻を沢山くれる。
「ありがとう」
少年は上着を脱いで貰った貝殻を包んだ。
「海の中では僕は人気者なんだ」と生き物は言う。「綺麗だとよく言われるし、鯨や鯱とも友達だ」
海の中のことなど自分に関係ないし、なんとも思わない。けれど、機嫌よく話すので、「それは良いね」と曖昧に相槌を打つ。
生き物は砂に詳しい。砂つぶに混じったものをあれは硝子、あれは瑪瑙、あれは琥珀と解説して器用に選り分ける。「綺麗な粒だけをつけたいんだ」と集めた砂を浴びる。
「そろそろ帰るよ」と少年は腰を上げた。
「明日またおいでよ」と生き物は言い、触手を差し出した。
握手をする。
寒天か葛切りのような、つるつるひんやりとした手触り。
小屋に帰り、貰った色とりどりの貝殻を机に出して、山に盛った。少年は微笑んだ。1人浜辺に来て初めての友達だ。なんの生き物なのかわからないけれど。話をしてて楽しかった。
そうだ。せっかく貰ったのだから。少年は貝殻に穴を開け、繋いでいくつも首飾りを作る。
次の日入り江に行くと、待っていたように、生き物が海から上がってきた。
「昨日の貝、首飾りに加工したら、結構売れたんだ。ありがとう」と少年は礼を言う。
「へえ」と生き物からなにか含みのある返事が返ってくる。
貝は売るための材料にくれたのではないのか?少年は砂採りなのだと言ったのに。少しだけ引っかかったがすぐに忘れた。
「泳がないか」と生き物が誘った。
少年は生き物に続いて海に潜った。遠くに生き物と同じような、キラキラしたものが何頭も泳いでいる。周りを魚達が取り囲んで舞っている。綺麗な魚を引き連れてた、王様の行列のようだ。
「華やかだね」と少年は見惚れる。
「あんなの綺麗に見えても、ただ砂つけてるだけじゃないか。貝や珊瑚までくっつけて、節操がない。綺麗な砂をだけを選んでつけなきゃ意味がないよ」と生き物は不機嫌そうに言う。
そんなに違うかなと少年は思う。
生き物は同類の飾り方が自分に似ている時も、微妙な反応を示す。貝殻や珊瑚で飾ってたり、自分の飾り方と遠いときは褒める。まだまだと思うものは励ましている。だが、綺麗で独創的で優れてるとしか思えないのに、批判する時がある。
褒める時はいいけど、批判する時は含みがある。僕に言わなくていいのに、まるで僕にもそう思えと思ってるみたいだとちらっと思う。
だが、だんだんわかってきた。生き物がくさすのは意識している時らしい。ほめるのは意識しない時だ。ライバル視が羨望になり、それを口にせずにおれないのだ。批判は認めてる証なのだと思うと、逆に批判するものほど優れているのだなと見るようになった。
「ここの砂はどれも綺麗だと思うよ」と少年が言うと「そうだろ」と生き物は胸をはる。
ここの生き物達は、綺麗な砂の在りかをよく知っている。水晶の白や翡翠の緑やサファイアの青やアメジストの紫やルビーの紅や琥珀の橙。身を飾るために砂を纏う。
僕は砂採りなのだから纏ったりはしない。でも、砂を売りたいな。ここの砂で作った装飾品を好ましいと思う人は、きっと沢山いるだろう。
少年は岩場の青や紅の砂を採集し、浜辺のさまざまな色の砂を掬って袋に収める。
砂を加工するととても綺麗だろうな。入り江の生き物達が身体に纏っているように、紙や板にくっつけてもいい。水槽にいれても綺麗だろう。植木鉢に撒いても綺麗だろう。
少年は集めた砂を色ごとに分け、持ってきた画用紙に糊を塗って砂を撒いた。紙の上で砂は絵の具となり、鮮やかに形を作る。少年は虹と海の絵を描いた。
生き物が近寄って来た。
「見て。砂で描いてみたんだ」と少年は言った。
だがそれを見てた生き物は、少年から紙を取り上げた。パラパラと砂が零れる。
あまりのことにすぐには声が出なかった。
「せっかく描いたのに、何するんだよ」
少年が抗議すると、生き物は怒鳴った。
「何を取った」
びっくりしている少年の手から袋を奪い、生き物はその砂を頭から浴びた。
「この場所の砂は全て私のものだ。一粒たりとも取ることは許さない。君は他の場所で取ればいいじゃないか。ふん、こんなの描いても売れるもんか」
生き物は紙をぺらっと地面に捨て、あからさまに不機嫌な様子で海に潜ってしまった。
少年はあっけに取られた。貝は沢山くれたくせに、何を怒っているんだろう。砂は纏うもので、砂絵は違うとでも言うのだろうか。僕の砂絵が売れようが売れまいが、生き物には関係ないだろうに。
ならば魚ならばいいだろうか。入り江の魚は赤や青や色とりどり。鮮やかに水槽に映えるだろう。
少年は網を投げて入り江の小魚を捕り、魚籠に入れた。魚籠の中で魚はぴちぴちと跳ねる。
すると「何をしている」と怒鳴り声がした。
ザブリと大きな水音と共に、生き物が波の間から現れた。皮膚を赤黒く染めて烈火のごとく怒っている。生き物は素早く触手を伸ばして、彼から魚の入った魚籠を奪った。
「ちょっと、何するんだよ」
「盗っ人め」生き物は唸り声を上げ、少年を罵倒した。
生き物の丸い顔に筋目が走った。丸い頭の下から細かい歯のついた大きな口が現れ、頭部が割れてヒトデのように大きく開いた。少年は戦慄し後退りする。生き物は魚籠の中を口にあけて、次々と魚を丸呑みにした。
「ここの魚は全て私のものだ。一匹たりとて奪うのは許さない。盗っ人、盗っ人、なんて悪いことをするんだ。自分でわからないのか」
「全て?何言ってんの」
「私の言うことをきかないと、友達をやめるからな」
生き物は言い捨てて 海に潜ってしまった。
少年は家に戻り、ベッドに座ると頭をクシャクシャとかいた。
酷く心が疲労している。僕は落ち込んでいるのだ。生き物を怒らせた。何か僕が悪いことをしたんだろう。怒らせるのは辛いことだ。
だが時間が経つにつれ、もやもやと違う感情が渦巻いてきた。
生き物は僕の何を悪いと言ってるんだ。わからない。生き物は自分を盗っ人と呼んだ。だが同じ入り江の同種族のもの達には言わない。ぶつくさと文句を言うだけだ。
同じ入り江に在るものでも、貝殻を取っても文句を言われたことはない。
自分はいつも通り砂を取っただけだ。それが生業なのだから。僕は果たして悪いことしたんだろうか?
苛立ちも生まれてきた。言うことをきかないと友達をやめるからなってなんだ。
翌日、少年はいつものように浜辺に出たものの、はたと立ち止まった。裸足の足を見下ろす。
何処に行こうか。右側に行けば船着場、左に行けば生き物のいる入り江。どっちに行くか迷った。毎日会ってた生き物だけど、今日はあまり会いたくない。
迷ったすえ、船着場に向かって歩くことにした。
船着場に到着し、桟橋に腰掛けた。並んだ船を眺める。桟橋に座って足をゆらゆらとさせる。水面に映る黒い影が足と一緒に揺れる。数匹の黒い魚の影が脚の影を追う。
お昼過ぎになった。そろそろ食事時だし、帰ろうか。
水面を眺めていると「やあ、水を一杯くれないか」と遠くから声をかけられた。
桟橋の向こうから、1人の青年が手を振って歩いてくる。
「いいよ」と少年は水筒を渡した。
青年は喉を鳴らして水飲むと少年に水筒を返し、「悪い。残り少なくなっちまった」と謝った。
「いいよ、僕はそんなに喉乾いてないから」
「すまない。俺は漁師だ。この辺りは俺の漁場だ。君を知ってるよ。よく向こうの入り江で化物と話してる子だね」
青年は入り江の方向を指差した。
「化物じゃないよ。僕の友達だよ。ひどいな」
「ではあの生き物はなんだ。魚か海月か」
「僕もよくわからないんだけど。化物じゃないよ」
「ふうん、今日は入り江に行かないのか?」
「ちょっとね」
漁師は少年の隣に座り、顔を覗き込んだ。
「どうしたんだ。元気がないようだな」
「怒らせてしまったんだ」
少年は生き物との間にあった出来事を漁師に話した。誰かに話したかった。
漁師は「ふん」と鼻を鳴らす。
「そいつは随分自慢が好きみたいだな。自分はこんなに綺麗だ、こんなに知り合いがいるってひけらかしてる。お前を羨ましがらせようとしてんじゃねえのか。俺なら自慢話うぜえって聞いてらんねえよ。そいつに知り合いを紹介してくれと言ったら、嫌な顔するんだろうな」
「知らないくせに。会ったことないのにわからないだろ」
「そいつの自慢話聞いて、面倒くさくねえか」
「別に、羨ましくないし。知らない人達の関係に興味ないし。そういう話したいんだなと思うだけ」
「お前に自分を凄い奴だと評価しろと言ってるように聞こえるけどな。お前はそいつを凄い奴だと思ってるのか?」
少年はちょっと考えて答える。「そうは思ってないかな。尊敬する部分もあるよ。砂のことよく知ってるし、砂を自分を飾るのに使うなんて、面白いと思う。僕にとっては砂は装飾品を作る材料だから。僕は対等だと思ってるつもりなんだ。海と陸で住むとこは違うけど。似たところもあるし」
「そいつはお前をどう思ってるんだろうな」
少年は考える。「向こうも対等だと思ってると、そう思ってたけど。でも、よくわからなくなったよ。砂や魚のことなんかであんなに怒るなんて。ほかの魚や海豚や鯨だっているし、他に砂で飾ってる生き物もいる。なんで僕にだけダメだと言うのかわからないんだ」
「理不尽だと思うんだな」
「怒らせたくないよ。でも、納得できないんだ」
「俺もそれは理不尽だと思うぜ」
「そう思う?」
「その化物は入り江の所有者じゃないだろう。他の魚と同様に棲んでるだけだ。入り江はそいつの領土ではあるまい。砂浜もそいつのものでもあるまい。魚もそいつのために周りにいるのではない。砂も海も誰のものでもない。そいつが作ったものではないのだから。砂は砂、魚は魚だ。自分のものなどと言える理はないだろう」
「僕もそう思ってたんだけど」
入り江の者達は砂で、自分の思うように飾っているのだ。装飾品と身を飾るの違いはあるにしても、砂を使いたいと思ってはいけないのだろうか。
「たかが砂や魚で、なぜそんなことを言うのか、俺はそいつを知らないからわからねえけどな。そいつが自分が正しくて、お前が悪いと思わせたいってことはわかるぜ」
「でも、仲良くしたいんだ。友達だし。砂や魚は欲しいよ。でも怒らせたくはない」
「よし、待ってろよ」
漁師は船の中に入り、魚籠を2つ持って戻ってきた。片方の魚籠から小魚を出し、もうひとつの魚籠に分けると、少年に渡す。
「俺が捕った魚を君にやるよ。持ち主は獲った俺だから、そいつは何も言えないはずだ」
緑や青や色とりどり。確かに入り江の魚だ。
「いいの?」
「構わねえよ。勝手に網に入ってた魚だ。食えねえし、いらねえから、海に返そうと思ってた」
「ありがとう。嬉しい」
「俺はどんなに綺麗だろうと、砂なんかに興味はない。小さくて綺麗な魚よりも、大きくて旨い魚の方が何倍もいい。それが俺にとって価値あるものだ。その化物にとっての価値あるものもお前とは違うだろう」漁師は続ける。「お前にとって価値あるものはなんだ」
夕刻になり、少年が小屋に戻ると、玄関の前で蠢く影がいた。目を凝らすと、彼の家の前にいるのはあの生き物だった。
「来るのが遅いから来たよ」と生き物は言った。
怒っているかと思っていたのに上機嫌だ。どういうわけだろう。
「ところでさ。さっき誰と話してた」
と生き物は聞く。何気ない調子で聞いているつもりだろうが、どこからか見てたのだろうか。ちょっと嫌だな、思う。
生き物の透明だった表皮が、うっすらと灰色に濁って見える。
「漁師だって言ってたよ」答えると「あの盗人が」と生き物は憤り、さらに表皮を濁らせた。
「あいつの言うことなど聞いてはいけない」
まるで指図するような口調に、嫌だな、と思う。生き物は魚の入った籠を見つけて触手で触れた。
「この籠の中身はなんだい?」
「あ、それはその漁師からもらった魚が入ってるんだ」
少年は魚籠を取ろうとしたが、その手は遮られた。生き物は籠の中を見て怒鳴った。
「これは私のものじゃないか!」
「違うよ。漁師が捕って僕にくれたんだ」少年は魚籠を取り返して抱きしめた。「もとは漁師のものだったんだよ」
「盗っ人、盗っ人!」
生き物は怒鳴ると、触手を伸ばして魚籠を取り上げた。
「痛!」と少年は手をひっこめて指を見る。ぷくりと針でついたような血が吹き出てきた。生き物の触手に棘が付いているのに、はじめて気がついた。
「その魚は私のものだ」
生き物はみるみるどす黒く色を変えた。深海魚のようにぬらぬらした表皮。棘のついた触手。
頭が天頂部から裂けてひとでのように開いた。細かい歯のある口が現れ、魚籠から魚を触手で取り出し、ぱくりと食らった
目の前にいるのは、醜悪な化物だ。
「返して!」と叫び、少年は生き物から魚籠を奪い返した。弾みで魚は床にばら撒かれ、ぴちぴちと跳ねる。
化物が魚を拾っている間に、少年は船着場にむかって駆け出した。漁師が船に乗り込もうとしているのが見えた。
「待ってよ」と桟橋を走りながら少年は声を上げた。
「なんだ?血相変えて。今船を出すところだぞ」
「お願い、一緒に乗せて」
「お前も漁師になるのか」漁師は問うた。
「入り江で釣りはしたことあるけど、船で漁はしたことがないよ。まだどうするか決められないけれど、一緒に船に乗りたいんだ」と答えた。
「よし、来い!」
漁師は少年の手を引いて、甲板に引き上げた。
船は出航した。
漁師の船は魚を求めて航海を続ける。港に寄っては魚を売り、また航海に出る。
少年は漁の手伝いをする。漁師の食事を作ったり、一緒に船の掃除もする。でも漁師にはなれそうもない。そう言うと、構わねえから乗ってろよと漁師は言う。漁場の浜辺に寄った時は、時々瓶に砂を詰めてみる。
立ち寄る浜辺には、それぞれ彩り豊かな砂がある。それぞれの良さがある。珊瑚や貝殻を混ぜて、瓶に色とりどりの砂を詰めれば虹のように華やかだ。市場に漁師の魚と一緒に持っていくと、買っていく人もいる。
「綺麗なものだな。女子供が喜ぶ」と漁師は言う。
穏やかに日々が過ぎたある日、少年は漁師に言った。
「あの入り江に行ってみたいんだ」
「あれと仲直りしたいのか。あいつは望んでないかも知れないぞ」
「頭にきたけれど、それは向こうも同じじゃないかと思うんだ。お互いの譲れないとこはあるけど、非を認めあえば解決できると思うんだ」
漁師は眉根を寄せて言う。「正直、俺がお前にやった魚をちょろまかす奴なんざ、俺は評価しないぜ。俺を盗人と言いやがって。俺はどこでだって魚を獲ってやるぜ。それを盗人と言うならそいつも盗人だろう。詐欺師や盗人ほど自分が同じ被害に遭うと、烈火のごとく憤るもんだ。ふざけた話だが、詐欺師も盗人も自分だけが得をしたいもんだからな」
「でも、怒ってたから口が滑っただけで、本気じゃなかったかもしれない」
「思ってもねえことは言わねえよ。俺のことまで盗っ人と言いやがったのは本気だろう。腹が立つ話だぜ」
「でも、君には面と向かってそんなことは言わないと思うよ」
「言わなきゃいいってもんじゃねえよ。だが、お前にだけ言うなら、尚更怒っていいと思うぜ。やつはお前より砂や魚の方が大事なんだろう」
「そんなことないと思うけど」
「俺は砂なんかに興味ない。君やそいつに価値があるものであっても、俺には塵芥に等しいぜ。人より物が大事とは思えないしな。だが、そいつはその塵芥が上なんだろう 」
そうなんだろうか。仲が良いと思っていたのは自分の方だけだったのだろうか。
「でなければ不条理なことを言っても平気なくらい、お前を舐めてたってことだろうな。盗人と言われたんだろ。盗人なんて仲の良い奴に普通は言わねえよ。家に来た時そいつが上機嫌だったのは、気が済んだからだ。でも俺のやった魚を見て逆上したんだろう。思い通りになってなかったからだろうさ」
「でも、思い通りにすることに、なんの意味があるんだろう」
「上に立ちたいんだろうよ。自分の思い通りにするために、わざと怒ったり泣いたりしてみせる奴もいるんだ。そいつの怒りは本物なのか。お前の行動の支配が目的だったのではないのか?そうじゃないと言い切れるのか?お前はそれでもその化物と付き合っていけるのか」
「それは、わからないよ」
「もしあいつが変わってなかったなら、お前はどうするんだ」
「わからないよ。会ってみないことには」少年は、はっと気づいて、漁師を見つめる。「心配してくれるんだね」
「そういうわけじゃないが」漁師は少年の頭を撫でて言う。「いい結果が出るといいな」
船は入り江の隅の、自然の岩で出来た船着場に着いた。少年を下ろし、漁師は一回りしたら戻ると言って船を出した。
漁師の船がいなくなると、生き物が岩の隅から顔を出した。何事もなかったように少年に近寄ると、話しかけてきた。
「久しぶりだね。どうしてたんだい」
「船に乗ってたんだよ」
「あの漁師の船かい。あ、そうだ。君が置いていった魚は干物にしたからあげるよ」
生き物は魚籠を差し出した。中に小魚の干物が入っている。僕奪ったくせにとちょっと鼻白む。漁師から貰った魚だ。断る理由はないので受け取る。
「遊んで行かないか」と生き物は言う。
生き物はいつものように、透明な皮膚にキラキラした砂を纏っていた。だが目を凝らすと表皮の下の黒い表皮が透けてみえる。
目を逸らして、少年は化物と話をした。いつかのように砂の話、魚の話。でも、話題は同じなのに何故か楽しいと思えない。
揉めた時のことも、どうしても切り出せない。その話をして仲直りに来たつもりなのに、言う気になれない。何故なんだろう。
生き物の表皮の下で、ぐにょりと黒い真皮が蠢く。少年は気持ち悪くて、吐き気をもよおしそうになった。見ないふりをしながら話すのが辛くなってきた。
少年の意を組んだかのように、岩場の船着場に船が到着し、漁師に呼ばれた。
「じゃあそろそろ行くよ」と少年は立ち上がった。
「そうかい、またおいでよ」
生き物が握手をしようと触手を伸ばした。
透明な触手の下に鋭い棘が動く。少し躊躇したが、握手をする。
ぐちゃりと軟かくぬめっとした気持ち悪い感触。急いで手をもぎ離した。なんでもないよ、と無理に笑顔を作り、少年は急いで船に戻った。
船は出港した。漁師が隣に来て、少年の肩を抱いた。温かさにほっとする。
「平気か」と漁師に尋ねられ、少年はほろほろと泣いた。
「貴方は結果を予想してたんだね」
「そいつは自分は何一つ悪くないと思っているのだろう。君の怒りに気付いていないのだろう。ならば話などできないと思っていたよ」
「友達だったんだ」少年は嗚咽をこらえた。「話すのは楽しかったし、物知りでいろんなこと教えてくれたし、親切な時もあった」
「そうか」
「一緒に過ごすのが、僕の好きな時間だったんだ」
「そうか」
僕は自分がどうしたいのか、選ぶつもりだった。会って決めようと思っていた。でも選ぶ余地などなかった。生き物を見るのも触れるのも、気持ち悪かった。
かの生き物は、僕の目には元のように映っていると思っているのだろう。黒い真皮が透けて見えていると知らずに。
彼はあやすように少年の肩を撫でて言った。
「俺には大したことには思えないよ。たかが砂や小魚が原因で揉めるなんて、くだらないことだ。だが問題は表層ではなく、根にあるんだろう。それが君に選択させたんだ」
「前と違って、生き物の話すことがひとつも心に入って来ないんだ。楽しくないんだよ」
生き物の頭部には牙があり、触手には棘があるのだと、今の僕は知っている。牙は僕の魚を喰らい、棘は僕を傷つけた。
「例え他人を害することでも、思うだけなら、知られなければ、行動に移さなければ、罪じゃない。だが、相手の標的が自分と知っては難しいだろう。しかも行動するなら、まず共にはいられないだろう」
「前はそうではなかったよ。いい生き物だったんだ」
「良いだけの者なんていないよ。君も相手にとって、良いだけの者ではなかったんだろう」
「お互い良い者ではいられないのかな」
「だから君を悪と罵り、良い者に戻そうとしたんだ。自分に都合の良い者にな。自分を被害者に据えたい者にとって、自分を加害者と思いやすい者は格好の獲物だ。強気な者には言わない。俺から見ると君に悪いところなどないよ。変える必要もないんだ」
「ずっと友達だと思っていたんだ。そうじゃなかったんだろうか」
生き物にとって自分は間抜けに見え、御し易かったのだろうか。だから自分の価値観を押し付け、操ろうとしたのだろうか。
「友達だったんだろう。けれども、誰しも調子の悪い時には醜くなり、調子の良い時には美しくなるもんだ。どちらも本当の姿なのだろう。嫉妬、虚栄、恐れ、欲望、渇望、醜さの種は様々だ。悪い時にこそ本性は出る。誰も進んで醜くなりたくはないんだ」漁師は空仰ぐ。「だが避けられない」
「気持ち悪かったんだ」
生き物は、海を住処とする他の者の前では、晒さぬであろう醜い姿を、少年には平気で晒した。
「あんなのは見たくなかった。気持ち悪かったんだ。会ったらもう終わりだなんて、思わなかったよ」
「だからこそ人は上辺を美しく装うんだ。エゴを正しいことのように嘯き、自分は被害者と吹聴する。自分の言動の影響力を知っていて口にするのだ。思い通りにしようとして貶めるんだ。だが、装うのにかまけて、その醜さに気づかないんだろう」
「なんで言うんだろう。なんで見せるんだろう。僕なら隠して飲み込んでしまうのに」
「少しでも相手への影響力を持つのなら、王が家臣に、上司が部下に、先輩が後輩に、先生が生徒に、親が子供に、その影響力を行使しない方が珍しいくらいだろう。意が通らない相手には決して言わない。言う相手は選んでるってことだ」
「僕らに上下関係なんかなかったのに」
いや、対等だと思ってなかったならば、あれの言動も行動も納得できてしまう。理不尽に見えたのは前提が違ったのだと。相手が嫌うわけがないと、奢るからできるのだ。
「はじめは違ったかもな。関係は移ろいゆくものだ」漁師は言う。「醜さを現した者もいずれ、何事もなかったように、装いなおすだろう。美しさも以前のように戻るだろう。だがお前にはあれの表皮の下が見える。もう見ないふりはできない。いつかはその状態を受け入れたとしても、同じ状況になれば、またあれは君に醜さを露呈するのだと知っている」
生き物は僕を抑えつけようとした。僕は自分が流されやすいと知ったけど、あれはきっと前から知っていた。ならば似た状況には陥れば、同じことはまた起きる。
操ろうとする者に心を許してはならない。操られたりしない強い人には違うとしても。僕にとってこれほど醜いものはない。これほどの悪はないのだ。美しく見えていたものは失われた。
「もう2度と元には戻らないのかな」
「安心しろよ。今失ったものがあっても得るものもあるさ」
彼は遠くなる入り江を振り返った。もう生き物はいない。
「あれはもう海の中に戻ったんだろう。そこがあれの居場所だ。君とは違う。君はあの島を出て俺の船に乗ったんだ。入り江を訪れない限り会うこともないよ」
「もう会わない方がいいのかな」
「気持ち悪いと思ったのだろう。それでも、毎日顔を会わせるなら、幻滅した心を慣らして、付き合い方を探せただろう。そうする手もある」
「もう無理だよ」
入り江に行きたいと思えない。会っても辛いだけだ。
「ならば毎日顔を会わせる必要がないのを、今は幸いだと思うしかない」
「そんなことが幸いだなんて」だがそう思っている自分がいる。
「距離を置くのも必要だってことだ。だが、それは自分の見方を変えるためだ。相手が変わるなんて期待はしない方が無難だろう。君の怒りをあれは知ることはないからだ。変わらない前提での在り方を探る方がいい」
「もう心を許すことはできないんだね」
「相手との丁度いい距離がわかれば、いつか平常心で会えるかも知れない。それまでに、何が醜さの引鉄になるのか見極めるんだ。相容れない存在なのだと、心に留めて警戒するんだ。むき出しの心で会う相手ではないと。君の身を守るために。心を守るために」
「きっと生き物にとっては、僕が悪なんろうだね」
「そうだろうな。悪とするものも怒りを感じるものも、人によって違う。あれにあれの悪があるように。君に君の悪がある。絶対悪もあるけれど、大抵の悪は相対的なものだ。人の数だけ悪がある」それから、と漁師は付け加える。「何に喜ぶかより何に怒るかの方が、善とするものより悪とするものが、人を分けるものだ。きみが何を悪として何に怒りを感じるのか、考えるといい」海を見ていた漁師は少年に視線を移した。「それが君が君たる証だ」
「貴方にもあるの?」
「もちろんあるよ。つきあってればそのうちわかるさ」と彼は笑う。
漁師にも僕のようなことがあったのだろうか。少年は漁師の瞳が青みがかった碧色であるのに気づいた。髪は日に焼けて小麦色になっているが、元は栗色であることにも気づいた。
「君があの日、船着場に向かって歩いたから、俺に会ったように。違う場所には違う世界があるんだ。見ろよ。海は広大なんだ」
彼は立ち上がって船の帆を張った。帆は風を含んでスピードを増す。入り江はどんどん遠くなっていく。
「向こうは向こうで楽しくやってるさ。こっちはこっちで楽しくやらないとな」漁師はまた笑う。
船はさわさわと海を切り裂いて進んでゆく。少年は海水に手を浸した。冴えざえと冷たい潮。握手をした時の生き物の感触が洗い流されてゆく。飛沫が飛んで袖を濡らす。
波は海の皮膚のようだ。飛沫は海の血潮であるのだろうか。いつか傷口は塞がり、泡となり再び波となり打ち寄せるだろう。
この僕もいつかそうなれる。
END
たったひとつの冴えたやりかた(全年齢版)

1・かの日の怪物
久方ぶりの自宅への帰り道のことだった。
出久は膝に抱えていたリュックを担ぐと、電車を降りた。
黄昏の空に烏の鳴き声が遠く響く。家々のシルエットを、夕焼けが橙色に縁取っている。落陽は出久のすぐ前を歩く、幼馴染の小麦色の髪も、紅に染めあげてゆく。
「家なんざ、かったりいぜ、クソが」
勝己が出久に聞かせるともなく呟いた。
独り言なのか、自分に話しかけてるのか、どっちだろう。返事をしていいものかどうか迷い「う、ん」と生返事をする。
隣を歩けばいいのだろうけど、つい前後に並んでしまうのは、長年の癖のようなものだ。
三連休に寮に一斉清掃が入ることになり、その間生徒達は一時帰宅することになった。長期休暇ですらあまり家に帰りたがらない勝己も、今回は帰宅を余儀なくされ、不貞腐れていた。
五時半を告げるメロディが通りに流れる。公園から跳ねるように出てきた数人の子供達が、側を走り過ぎてゆく。それぞれの家に帰るのだろう。子供達は分かれ道で、バイバイと手を振って別れていった。僕らもあのメロディに急かされたなと懐かしくなる。
勝己や仲間達と毎日遊んだ公園。ブランコも砂場も滑り台も、少し色褪せてるけどほとんど変わっていない。勝己との距離が離れていくにつれ、次第に足が遠のいてしまったけれど。
「あ?てめえは週末にしょっ中帰ってるだろうが」
思いがけず返事が返ってきた。ちょっと焦って答える。
「う、うん、そうだね。お母さん待ってるし」
「こっちじゃ個性も使えねえし、家ですることなんて何もねえわ。親はあれしろこれしろってうるせえしよ」
学校なら堂々と個性を使用できるだけに、勝己はもどかしさを感じているのだろう。
「かっちゃんはこっちで昔の友達に会ったりしないの?」
「あ?一度も会ってねえよ」
「え、そうなんだ」
「今更会いたくもねえ。過ぎたもん振り返ってる暇なんざねえわ」
よく勝己は仲間とつるんでいたけど、そんなものだろうか。自分には会いたいような旧友はいないから、わからない。無個性と揶揄されていたのだ。思い出したくない。雄英で出会った、側にいてくれる本当の友達を大切にしたい。
しかし、苦い思い出もあるけれど、それも君と友達のように歩いている今に繋がっているのだ。友達のように、としか形容できないのがもどかしいけれども。
子どもの頃だって、勝己に憧れてひっついてたけれど、友達といえただろうか。彼がどう思って自分のような鈍臭い子供を、仲間に入れてくれたのかは知らない。来るもの拒まずという、親分肌だったのだろうか。今更聞いても教えてはくれないだろう。
今も勝己が自分をどう思っているのかは分からない。でも、漸く嫌われてはいないと、思えるようになった。少しずつでも打ち解けていって、いつか本当に友達になれればと、願わずにはいられない。
勝己は立ち止り、くるりと振り向いた。
「な、何?かっちゃん?」
心の声を聞かれていたように錯覚してしまい、ドキッとする。面と向かうと緊張感してしまう癖は、そうそう抜けはしない。
「おいデク、先行くわ」
とそれだけ言うと、勝己はずんずんと早足で去ってしまった。
「あ、またね。かっちゃん」慌てて後姿に呼びかける。
別れ際に声をかけてくれるなんて、前なら考えられなかった。ちょっと嬉しくなり、ふわふわと心が浮ついた。
橙色の空が朱色を帯びてきた。雲が紫色の夜の衣を纏い始めている。
団地の入り口に入った時だ。「久しぶりだな、デク」と背後から声をかけられた。振り向くと見覚えのある顔。
「俺だよ、俺」
「あ、ああ、うん」
思い出した。幼稚園からの幼馴染の1人だ。小学校3年生のクラス換えで別々になるまで、勝己達とつるんでいた。
「カツキと同じ雄英に入ったんだってな。テレビで雄英の体育祭見たぜ」
なんと答えていいものか。「あ、うん」と戸惑いながら返す。
「お前、個性あったのかよ。すげえな。で、やっぱりいまだにカツキにいじられてんだな。障害物競走でも騎馬戦でも、お前に突っかかってたよな。あいつ昔からひどかったよな」
君も一緒になっていじめてきたろ。と思ったが言わない。覚えてないのだろうか。「今のかっちゃんはそんなことないよ」と答えておく。
「あいつが?マジかよ」
それにしても、と思う。いじめた方はどうして何もなかったかのように、平気で話しかけてこれるのだろう。フレンドリーに来られると、どうしていいのか困ってしまう。
小学生の頃なんて、いじめも遊びも曖昧なんだろうか。何をしたか忘れているのだろうか。こっちは今も苦手だというのに。傷つけた方にとっては取るに足りないことでも、傷つけられた方は覚えてるんだ。
それとも、今だに昔を引きずっている勝己だけが例外なのだろうか。
切れ目なく続いた腐れ縁。拗れに拗れた関係は、やっと望んでいたような形に落ち着いた。昔のことを知る人には意外かもしれないけれど。
「今だから言うけどよ。カツキがお前を気に入ってたってこと、知ってたか」
何気ない軽い調子で幼馴染は言った。いつ話を切り上げようかと、迷っていたところに意表を突かれる。
「へあ?」
「変な声が出してんなよ。あいつお前を意識してただろーが」
「え?なに、いきなりなんで?そんなことないだろ」
「あいつ、いつもお前を揶揄ってたろ。それに何かうまくいくと、いつも嬉しそうにお前だけに振ってただろ。カツキが上なのは当たり前なのによ」
「まあ、そうだったけど。馬鹿にされてたんじゃない」
自分との差を見せつけて悦にいる。勝己はいつもそうだった。
「あれはよ、お前の反応が欲しかったんだろ。オールマイトカードだって、いいの出ると真っ先にお前と見せ合ってたし。他の奴にはそういうの、振らねえの気づいてたか?お前だけデクって徒名決めて呼んでたしよ」
「徒名は皆につけてたじゃないか」
雄英でも轟くんや麗日さんや切島くん、上鳴くん達を、おかしな名前で呼んでた。最近は呼ばないけど。
「いや、俺らを徒名で呼ぶ時は、ただの悪態だろ。全然違うわ。あいつお前だけ特別だったんだよ」
全然そうは思えないけど、勝己のそんな行動が、傍目には好きだからだと思われたのだろうか。
「そんな風に見えてたんだ。意外だよ」
幼馴染はじっと出久を見つめ、徐ろに口を開いた。
「今だから言うけどよ、俺らはカツキがお前に恋してんだと思ってたんだぜ」
突飛な言葉に、頭が真っ白になった。
「え、え、恋?かっちゃんが?なんでそうなるの?今の話のどこに、そんな要素があるんだよ」
「恋してるとしか思えねえだろ」
「あり得ないよ!あのかっちゃんだよ」
勝己に好意を持たれてたってだけでも想像し難いのに。好意だけならまだしも、恋慕なんて飛躍し過ぎだろう。
「お前もいつもあいつにくっついてたし、俺らはお前もあいつを好きなんだって思ってたぜ」
「僕が?そんなわけないだろ」
ぶんぶんと頭を振って否定する。
「ああ、お前は段々離れたてったしな」
「それは」離れたくて離れたわけじゃないけれど、彼に個性が発現してから、徐々に歯車が狂っていったのだ。
「根拠はあるぜ。お前がつるまなくなってから、俺らはカツキは落ち着くかと思ったんだぜ。でもお前は知らねえかもしんねえけど、あいつ苛々しながらも、いつもお前を目で追ってたんだ。去る奴追わねえあいつが、わざわざ追いかけて、結局はお前に構うしよ。あいつはなんも変わらなかったんだよな」
「あれは構ってたんじゃないだろ」
少しイラッとして口調に出てしまった。いじめられてたんだ。いくらなんでも過去改変が過ぎるだろう。
勝己の存在は、時に怪物のように自分を威圧した。憧れと恐れと形容できない様々な感情が渦巻いて、マーブリングの模様のように心の中で混濁していた。話していると当時の黒い心が蘇ってきそうだ。今の彼は違うのに。
早く話を終わらせたい。手を上げて「じゃあこれで」と言おうとしたところで幼馴染が口を開いた。
「あのよお、カツキが荒れたのは、お前がこっちをヴィランに仕立てたからじゃねえか」「え?どういうこと?」出久は驚いて問い返す。
「俺らがヒーローごっこしたりして、ちょっとヴィラン役の奴小突いたりすっと、いつもお前はそいつを庇いやがったろ。それがあいつは気に食わなかったんだ。お前も一緒にこっち側に加われば、カツキは怒んなかったと思うぜ」
びっくりした。そんな風に思っていたのか。かといっていじめる側に加われるわけがなかったけれど。
「カツキは強えけど、どんな強え奴でも弁慶の泣き所っつうのがあんだよな。それがお前なんだよ。お前と揉めるまでは、あいつはやんちゃなガキ大将だったろ」
彼が変わったのは、個性発現してからじゃないのか。いやそれだと4歳からということになる。あの後だって一緒に遊んでた。ではいつからだったんだろう。覚えてない。
「あの頃、あいつはお前に恋してんじゃねえのかって、皆思ってたんだぜ。本人は無自覚だったかも知れねえけどな。でも流石に今はあいつも自覚してんじゃねえの」
「だから恋なんて、何でそんなこと」
「お、そろそろ帰んなきゃな。じゃ、またな」
腕時計を確認すると、幼馴染は風のように去っていった。伸びた影が遠ざかってゆく。
後には動揺して立ち尽くす出久が残された。
恋ってなんだよ。意味がわからないよ。
パソコンで過去のオールマイトの動画をザッピングする。元気を貰う、日課のようなものだ。だが今夜はマウスを動かしながらも、出久は上の空だった。
頭の中に幼馴染の言葉が離れない。彼の言ったことは本当なのだろうか。
勝己が自分を好きだなんて突飛な話だ。大体好いている相手をいじめたりするだろうか。ないない。とてもあり得ないと思う。
けれど、周りには違って見えていたらしいのだ。
窓を開けるとすうっと夜風が吹き抜けた。カーテンが空気を含んでたなびく。眠る夜の町。灯りが蛍のように疎らに散らばっている。
勝己は起きているだろうか。黒に沈んで彼の家は見えないけれども、青白い三日月の下に勝己の家があるはずだ。
恋なんて勘ぐり過ぎた話はともかく、好かれていたのなら。それをあの頃知っていたなら、もっといい関係でいられたのではないだろうか。
勝己は自分をどう思っていたのだろう。昔の話だし、今なら聞いてみてもいいだろうか。確かめないではいられない。
僕は軽く考えていた。だがあまりにも浅薄だった。聞くべきではなかったのだ。
2・凍える羽搏き
連休が終わり、久しぶりに出久は家から直接学校に向かった。休みの間の宿題を入れたリュックは、いつもよりちょっと重い。
駅への道すがら、勝己にばったり会った。
「お、おはよ。かっちゃん」
勝己のことを考えていたところだっただけに、挨拶する声が裏返る。同じ電車に乗るのだから十分あり得ることなのに。
「ああ」と勝己に軽く返される。
昔はこんな挨拶をするだけでも罵倒されたけど、もうそんなことはない。ぶっきらぼうな物言いは変わらずとも、ちゃんと会話だってできる。今みたいなそっけない返事でも、声をかけたら返してくれるのが嬉しい。
「おいデク、ちんたら歩いてんじゃねえよ」
「あ、待ってよ、かっちゃん」
隣に並ぶのはちょっと遠慮して、一歩下がって歩きながら考える。
昨日幼馴染から聞いた話。子供の頃の勝己の真意がやっぱり気になる。今日の彼は比較的穏やかだし、機嫌がいいようだ。さりげなく聞いてみようか。
「あの、かっちゃん」
「んだよ」
「昨日ね、幼稚園の時からの幼馴染に会ったんだ」
「ああ?それがどうした」
「その時変な事言ってたんだ。かっちゃんは昔、僕を好きだったって」
「はああ?」くるっと勝己が振り向いた。「あるわけねえだろが!馬鹿言ってんじゃねえよボケカス。殺すぞクソが」
久方ぶりに淀みない罵倒が降ってきた。しまった、怒らせてしまったと、出久は慌てて言い繕った。
「そうだよね、ゴメン。君が僕を好きなんて。あるわけないよね」
好きだというなら、やはり長い間あんな酷い態度を取るはずがないのだ。無責任な言葉に踊らされて、全く何を馬鹿なこと言ってしまったんだろう。
「彼らが邪推してたんだね。おまけに恋してたんだろうなんて、言ってたよ。おかしいよね」
「黙れよ、デク」
勝己の呟きが耳に入ったけれど、バツが悪くて早口で言い訳を続ける。
「僕らは男同士なのにね。ほんとおかしいよね。恋だなんて。よりによって君がなんてさ、だって…」
勝己の顔が見られず、視線を逸らして否定の言葉を並べ立てた。
だが全部言い終える前に乱暴に口を塞がれる。
「そんなにおかしいかよ?ああデク!」
「んん、かっちゃん?」
「なあデク、てめえはどう思ってんだ」
口を塞ぐ手が少し緩められる。
「どうって?何を」
「俺のことをだ。てめえはどう思ってんだ?」
宣告を待つように俯いて、絞り出すような低い声で、勝己は繰り返した。
「君はすごい人で……」答えながらじわじわと間違いに気づく。違う、彼の聞いていることは違うんだ。
「んなこと聞いてんじゃねえ、デク。てめえは俺をどう思ってんだ」
「僕は……」でも、何を言えばいいんだ。喉に言葉が詰まったようで、次の言葉を継ぐことができない。
「はっ!」勝己は吐き捨てる。「てめえは違うんだろ!わかってんだよ。昔からわかってんだ。てめえは俺を嫌な奴だと思ってんだろ。なのにてめえは俺に聞くのかよ。ああ?デク!ざけんな!」
怒鳴り声とともに床に引き倒された。がつんと後頭部がアスファルトにぶつかる。くわんくわんと視界が揺れる。脳震盪を起こしそうだ。リュックを背負ってなければまともに打撲して、失神していたかもしれない。
「ちが……、かっちゃん」
「黙れよ、デク。それ以上喋んな」
勝己の怒りを押し殺した声。くらくらした頭がざあっと冷える。
「ふざけんなよなあ!てめえにはその気はねえくせに!なんで俺に聞いた!馬鹿にしてんのかよ、クソが。もうなんも喋んな。殺すぞ!ボケカス!クソが!」
激昂した勝己は周りのざわめきをよそに怒鳴る。
「クソが!クソが!そんな目で俺を見んな!俺を見下すな!侮るな!デク!」
出久の襟元を掴んで勝己は咆哮する。苦しい。息ができない。
「クソが!クソが」と罵倒され、漸く手荒に振りほどかれた。
出久は空気を吸い込んで、咳き込む。勝己は舌打ちして、何見てんだと周囲を威嚇して歩き去った。
久しぶりに感じる彼への恐怖。震えが止まらない。と同時に、彼の怒りに燃えた瞳と言葉に気づかされた。
僕はなんてことをしてしまったんだ。かの幼馴染の言っていたことは本当だったのだ。恋してたのだ。かっちゃんが僕を。信じられないことに。
でも、それを指摘することで、彼が激昂するなんて思わなかった。ただ、子供の頃の勝己に、好意を持たれてたのならいいなと思って、確認してみたかっただけなのだ。どちらにせよ過去の話なのだから。昔のことは振り返らないと勝己は言っていたから。
昔のことではなかったのか。君は今も恋を。
時間が戻るなら馬鹿なことを言ってしまう前に戻したい。遠ざかる勝己の背中。追いつきたいのに、謝りたいのに、足が竦んで動かない。
「緑谷、どうしたんだ?」
予鈴ギリギリに教室に駆け込んだ出久に、轟が話しかけてきた。
慌てて「何が?なんか変?」と服をぱたぱたと叩く。服についた砂は掃ってきたつもりだけど、不自然なところがあるのだろうか。
「あいつだ、どうしたんだ?」と轟は視線で窓際に佇む勝己を示す。
目を向けてぞくっと背筋に冷気が走る。勝己の全身から吹き出す怒りのオーラが、目に見えるようだ。
「朝から爆豪の奴、酷え荒れようだぜ」
「だよなあ?近寄るだけですぐ爆破させてきやがる。生きた地雷みてえだ。またお前ら喧嘩したのかよ」
切島に尋ねられ、「僕が?なんで」とどきりとする。
「爆豪があんだけ荒れるなんて、お前関連以外にねえだろ。あいつにとってお前は特別なんだからよ」
「そんなわけないよ!」
「ど、どうしたんだ、お前までムキになってよ」
「ご、ごめん」みんなにも勝己が幼馴染の言ってたように見えているのかと、焦ってしまった。切島は何か納得したような表情で尋ねる。
「やっぱり、お前らなんか揉めてんだろ。何があったよ」
「何があったんだ?緑谷くん」
通りかかった飯田にも聞かれる。原因が自分なのは決定事項とさられたらしい。弱ったな。でも当たってるし。少し考えて、答える。
「言えないんだ。心配かけてごめんね。大丈夫、なんとかするから」
無理に笑顔を作る。言えるわけがない。考えにくいが、もし逆の立場だったのなら、最悪なのは他の誰かに知られることだ。誰にも相談できない。一人でなんとかするしかない。
僕はかっちゃんを恋愛対象に思えるだろうか。と考えてみる。
無理だ。想像するのも難しい。男同士だ。とても考えられない。ましてやあのかっちゃんだ。
真意を知らなかったとはいえ、長年いがみ合ってきたのだ。以前よりもマシになったけど、今もさほど会話できるわけでもない。到底気持ちに応えることなんて出来ない。近すぎて遠い。それがかっちゃんと僕との距離なんだ。
君も僕となんて、考えられないと思ってたんじゃないだろうか。
きっとそうだ。だからずっと黙っていたんだ。ひょっとして、雄英ではない別の高校に行けと、勝己が自分に強いたのは、それが理由だったのではないだろうか。
僕にしても君にしても、いつか恋人を作るとすれば異性だろう。それに相性のいい相手にすべきだろう。君は君を怖がらない相手、僕は僕で緊張しない相手。君もそう思ってたんだろう。
それなのに、僕は君の心を暴いてしまった。
君の気持ちなんて知るべきじゃなかった。知らなければ、いつかはなかったことになったんだ。僕に知られるなんて、君にとって屈辱以外の何者でもないんだろう。
好かれてる可能性を知った時は嬉しかった。本当だったのに、今の僕の気持ちは沈んでる。こんなことになるなんて。どうすればいいんだろう。
出久は顔を上げて、正面にある勝己の背中を見つめる。彼の側に寄れるのは、前後に座る授業中だけだ。
僕が仕出かしたことなんだ。何もしなければ、今度こそ君との関係は、修復不可能になるかも知れない。謝るしかない。
どう言っていいのかわからないけど。ほかに思いつかない。君が許してくれるまで何度でも謝ろう。
皆の目があるから、教室では話すことはできない。休み時間に教室を出た勝己の後を追う。渡り廊下に一人でいるのを見計らって、出久は恐る恐る話しかけた。
「かっちゃん、その、話が」
「クソデクが!寄んじゃねえよ」
勝己は掌をこちらに向けて構えてる。
「かっちゃん、ごめん。僕はずっと君に嫌われてると思ってたんだ。だから、確認したかっただけなんだよ。怒らせるつもりじゃなかったんだ」
「喋んじゃねえっつったろうが!」
「聞かなかったことにするよ。忘れるから、かっちゃん、だから」
瞬間、眼前で火花が散った。危険を察知して横に飛び退く。顔のすぐ側で爆発が起こった。
キーンと耳鳴りがする。直撃コースだ。
「あ、危ないだろ。かっちゃん」
「はっ!次は容赦しねえ。退け!」
肩を捕まれ、ぐっと乱暴に押しのけられた。足がもつれて倒れそうになり、円柱にもたれかかる。
簡単に許してくれるなんて思ってない。でも、許してくれるまで諦めない。出久はじんじんと痛む肩を摩った。
それから何日も、出久は勝己を追いかけては、幾度も謝ろうとした。そのたびに勝己は視線で殺せるほどの敵意を向けて、出久を罵倒した。
出久が寄ろうとしただけでも、掌から火花を散らして威嚇する。諍いを止めようとしたクラスメイトも、とばっちりを受ける。取りつく島もない。出久の神経は次第に磨耗していった。
ふと教室の窓の外に目をやる。
窓枠に区切られた、重苦しく空を覆う鉛色の雲。まるで僕の心のようだ。出久はふうっと溜息を吐く。
子供の頃のことじゃないか。いや、今もだとしても。なんでいつまでもへそ曲げるんだよ、と恨めしく思ってしまう。でも悪いのは自分なのだ。
傷つけるつもりはなくても、相手が傷ついたなら、怒りを覚えたのなら、傷つけた者は悪なのだ。僕は昔のいじめっ子をそう断罪していた。身を持って知っている罪だ。なのに僕も彼らと同じことをしてしまったのだ。
薄曇りの空に、ぱらぱらと木々の葉を打つ音。雨だ。
教室の硝子を叩く雨粒を見ているうちに、出久の心は過去に引き込まれた。
子供の頃の勝己は純粋に、憧れそのものだった。勝ち気な赤い瞳、上級生にも怯まないタフさ。彼のようになりたかった。
オールマイトを知ってからは、目標は彼に変わってしまったけれど。それでも勝己の不屈の闘志や勝利を諦めない辛抱強さには、未だ変わらず憧れてやまない。
気性が激しさは君の個性に相応しく、生命力そのもののような君が眩しい。
でも、憧れと恋慕は全く違うものだ。
雨が強くなってきた。窓硝子に水滴が幾筋も跡を付けてゆく。
「放課後、待ってろよ」と中学生の時に勝己に何度も言われた。
中学生の頃の勝己の取巻き連中は、小学生以前の仲間と違い、出久を虐めたりはしなかった。というより自分には目もくれなかった。それが普通だ。無個性な奴にわざわざ絡みにくるほど、彼らも暇じゃない。
だが帰りのHRの前に度々、勝己は彼らから離れて出久の方に来ては、一方的に告げるのだ。放課後に待ってろと。
何の用なのか、聞いても言ってくれない。だから、きっとろくなことがないに違いないと思い、待つことはなかった。逆になるべく早くに帰ろうとした。
その度に勝己に見つかって詰られた。捕まって校舎裏や廊下の隅に連れて行かれて、小突かれたり、頭を抑えこまれたりした。
やはりろくなことがないんだと、何度言われても一度も待ったりしなかった。でも逃げようとしても逃げ切ることは出来ず、いつも捕まった。
今みたいな雨の日だ。
早く帰るのではなく、裏をついて遅く帰ろうとしたのに、勝己に見つかってしまった。
廊下の窓硝子を雫が伝って流れていた。勝己は自分を床に組み敷いて、下腹の上に馬乗りになっていた。両腕は拘束された。万力のように締められた手首が痛かった。
「逃げんな」
吐息がかかるほど、勝己は顔を近づけた。
「逃げんなクソが。待ってろっつったろーが!いつもいつも逆らいやがって」
じわりと勝己の掌が汗ばんできたのを、掴まれた手首に感じた。
「クソナードのくせに。虫ケラのくせに。クソが!クソが!この俺がてめえなんかに!」
勝己は出久の手首を束ねて片手で拘束し直し、自由になった手で頬を撫でた。ひたりと湿った感触。ニトロを含有する汗。硬い掌が発火し、頬を爆破するんじゃないかと怯えた。
個性の使用は禁止だから、勝己は相手に酷い火傷を負わせたりしない。手加減するのに長けてる。わかってても、かたかたと震えて、歯の根が合わなった。いつ殴られるのか、爆破されるのかと恐れた。
ギリッと歯ぎしりをし、「待ってろと言っただろうが!」と言って見下ろす勝己が、ただ怖くて時が過ぎるのを、解放してくれるのを待った。
あの時、勝己は出久を抑えこんで、顔に触れただけで何もしなかった。
廊下の床の硬さと冷たさ。
下腹を圧迫する勝己の重み。
「逃げんな、逃げんな」と譫言のように繰り返された言葉。
頬に触れる体温の高い掌。
雨だれがコンクリートを打つ音。
群青色の雲が垂れ込めた空。
今、恐怖の記憶が違った意味を持って思い出される。あの時勝己は、自分を傷つけるつもりではなかったのだろうか。
何度も呼び出す理由を、難癖つけるつもりなのだと決めつけていた。いつも怖がってばかりだった。
声が震えて体が震えた。条件反射になっていたくらいに。それは逆に彼を傷つけていたのだろうか。もう聞けるわけがない。
小学生の時の仲間だけじゃなく、ひょっとして中学生の頃の勝己の取巻きの連中も、彼の心に気付いていたのだろうか。自分に構う勝己を、呆れたように見ているだけだった彼らも。
ただ怖がって、勝己を避けるので精いっぱいで、何故絡んでくるのかなんて、一度も考えたことはなかった。
思い至るわけがないよ。僕は君が何を考えてるかわからなかったんだから。
君のことを嫌な奴だと思っていたよ。君のせいで僕の小中学時代の学校生活は灰色だったんだ。
でも1番楽しかった思い出も、君とのものなんだ。
君はいつも逃げるなと言っていた。ずっと僕は逃げていた。でももう、君と対話することから逃げたくない。逃げてはいけないんだ。
授業が終わると、出久は教室を出て行く勝己を追いかけた。
「かっちゃん!」と呼ぶが止まってはくれない。呼びながら廊下を追いかける。
勝己は階段の踊り場で「ああ?」と振り向いて、やっと立ち止まってくれた。
「しつこく付いて回りやがって。何が言いてえんだ」
「君の気持ちは嬉しかったんだよ、本当だよ」
「は!嬉しい、かよ」と勝己は吐き捨てるように言う。「随分余裕の口振りだよな。てめえ、優越感かよ」
「違うよ、君とは意味が違うけど、僕はずっと君とわかりあいたかったんだ。やっと君と和解したのに、こんなことでまた仲違いしたくないんだ」
「は!てめえにとってはこんなことかよ。ムカつくことしか言わねえな。クソが」
「ちが、ごめん、君を怒らせるつもりはなかったんだ。馬鹿にするつもりなんて、絶対なかった。そのことはわかって欲しいんだ」
「はあん、そうか」勝己は歪んだ笑みを浮かべる。「俺に悪く思われたくねえってか。大した偽善者だぜ」
「そんな。僕はそんなつもりじゃないよ」
「じゃあなんだ。てめえは俺にどうして欲しいんだ。俺に許して欲しいのかよ。は!随分図々しい言い草じゃねえか。おいデク、悪気がなければ、なんでも許されるなんて思うなよ」
何を言えば君に届くのだろう。どう言えば君は聞いてくれるのだろう。
「どうすれば、償えるの?かっちゃん。償えるならなんでもするよ」
思い余って紡いだ言葉は、正しかったのだろうか。
言ってすぐに後悔した。何を口走ってるんだ。僕は。償うなんておかしいだろ。
項垂れた出久を勝己は冷たく見据える。重たい沈黙が流れた。
「なんでもすんのかよ」
いたたまれなくなった頃、勝己はやっと言葉を発した。冷たい声。しかし、出久は返事してくれたことにほっとした。
「うん。僕にできることならだけど。あ、もちろん法律に触れるようなことは駄目だよ。何をすればいい?」
「じゃあてめえ、俺に抱かれるか」勝己は顔を近づけた。鼻が触れそうなくらいの距離で繰り返す。「抱かせろや。デク」
抱く、という言葉が頭の中でくわんくわんとエコーする。
「それは……無理だよ」震える声でやっと答える。
「ああ?なんでもっつったよな!てめえ」
「君に、こ、恋してないのにできないよ」
「はっ!できねえってか。できねえなら、なんでもするなんて言うんじゃねえ!クソが」
勝己の形相が変わる。爆破される?直当てから逃げられない距離だ。
「おいおい、なんだなんだ!喧嘩かよ」
「なんだか知んねえけど、まだ怒ってんのかよ、爆豪」
上鳴と切島が通りかかった。助かったと安堵する。
「うるせえ!てめえらには関係ねえ」
勝己はドンっと出久の胸を突くと、去って行った。弾みで出久はよろけ、壁に背をぶつけて尻餅をつく。
「大丈夫か、緑谷。あいつのことは熱り冷めるまでほっとくしかねえんじゃねえか。時間が立てばあいつの怒りも収まるだろうし」
「ああ、どうにもならねえことはあるからな。時間が全部解決してくれるとは言えねえけど。待つしかねえこともあるぜ」
切島と上鳴は自分を案じてくれてる。荒ぶる勝己に近寄る危険は、彼らもよくわかっているのだ。
「うん、でも時間を置いたりしたら、修復がきかなくなるかも知れない」
「うーん、そんなことねえと思うけど、いや、言い切れねえか。お前ら何年も揉めてたんだもんな」と上鳴は困り顔で腕を組む。
「もう嫌なんだ。何もしないで悪化するのを眺めてるだけなんて」
「そうか、ある意味奴と戦うってことだな。拳を交えて解決する方法を選ぶのも一理あるぜ。漢だもんな」
「ちょ、ちょっと違うよ。切島くん。でも、煙たがられても、やめるわけにはいかない」
「そっか」上鳴が肩を叩く。「理由、やっぱり言えねえのか?力になれるかも知んねえぜ」
「ううん、ごめん。言えなくて」
「そうか、でも困ったら言えよな。いつでも聞くぜ」
「ありがとう」胸がきゅうっと暖かくなる。
級友達は優しい。相談すればきっと助けてくれるだろう。でも、そのためには勝己のことを、言わなきゃならなくなる。彼がずっと隠していたことを。それだけは駄目だ。
もしかして幼馴染達のように、彼らも勝己の心に気づいているのだろうか。いや、推測するのはよそう。自分で解決すべきことなんだ。
だがその日も、勝己は頑なに出久に怒りを向けた。謝ろうとするほどに、勝己はさらに態度を硬化させていった。関係を修復する糸口すら見つからない。かえって仲はどんどん悪化していく。焦るほどに歯車が狂っていく。
徒労に終わる日々は出久を消耗させた。それでも、捨ておけないのだ。放っておいてはヒーローになれない。彼の怒りは自分の所為なのだから。
出久は寮の自室に戻ると、鞄を下ろして溜息を吐いた。今日も勝己は剣呑として、一言も出久と話そうとしなかった。
好意を持たれていた。本来なら嬉しいことのはずだ。なのに辛いだけだなんて。
何故、好意だけじゃなく恋なんだろう。
何故好意だけを抱いてくれなかったんだろう。
恋ってなんなんだろう。
子供の頃の勝己に好かれていたと聞いて、信じられないと思ったけど嬉しかった。でも恋と聞いて戸惑った。頭ではそんなに違いがあると思えなかったのに。でも心のどこかで、明確な違いを感じ取っていたんだろう。
勝己は抱かせろと言ったのだ。そんな風に自分を、見ていたのだ。
恋の正体はどんなにオブラートに包んでも、情欲なのかも知れない。恋は好意とは似て非なるものなんだ。
好意は感情で、情欲は本能だ。
ならば。性欲さえ解消できれば、落ち着いてくれるのか。
そうだ、一度抱かせればいいんだ。勝己が言ったように。
することすればスッキリするし、怒りも静まるんじゃないだろうか。自分も男だから、本能に抗えないことはわかる。男ってそういうとこがあるもんだし。
出久は立ち上がり、パソコンを起動した。小窓に検索したことのない言葉を打ち込む。
このまま険悪になるだけなんて僕は嫌だ。折角縮まった距離を諦めるなんて嫌だ。どうなるのかはわからない。でも、何もしないよりマシだ。とりあえずかっちゃんに提案してみよう。罵倒されたならそれまでだ。
それに、抱かせろなんて、言ってるだけで、いざとなれば冷静になるかも知れない。
僕は切羽詰まっていた。自分の傲慢さに気づいていなかったのだ。
3・戸惑う牙
「かっちゃん、起きてる?」
皆が寝静まった頃に、出久は勝己の部屋を訪れ、ドアをノックした。
「入っていいかな」と問うてみる。
返事はないけれど、起きてるようだ。衣擦れの音がする。ノブを掴むとくるりと回った。鍵はかかってない。
「お邪魔するよ、かっちゃん」
そろそろと部屋に足を踏み入れる。暗い室内に廊下の光が差し込んだ。
「寄んな」
ベッドの方から、低い唸るような声がした。夜の猛禽類のような、赤々と光る瞳が威嚇してくる。視線が合って怯んだが、勇気を奮って出久は後ろ手に扉を閉める。ドアの隙間から漏れる光が、闇に細く筋をつけて消えた。
「こんな夜にわざわざ来てよお、なんだデク、犯されてえのかよ」
勝己は起き上がってデスクライトを点けると、ベッドに戻って座った。
「お、か、」
直接的な言葉にぞくりとする。慄いて後退りしたのを勝己は見逃さない。ニヤリと笑って立ち上がり歩み寄ると、いきなり足を払って出久を絨毯の上に引き倒した。
馬乗りになって、見下ろしてくる勝己は悪鬼のようだ。怖くてたまらない。ひくっと喉が鳴る。
でも逃げちゃいけない。覚悟してきたのだ。出久はすうっと息を吸った。
「それで君の怒りが収まるのなら、いいよ」
「はあ?てめえ、わかってんのかよ。セックスするっつってんだぞ」
ごくりと唾を飲む。「いいよ、何をするのかはわかってるから」
とりあえず調べてはみたのだ。男同士のやり方を。正直、余計に怖くなってしまったのだけど。
「いいよ」と勝己をまっすぐに見上げる。
一回やってみたら、彼の鬱憤が解消されるかも知れないと、その可能性に賭けたのだ。グラウンドベータでの対決の時みたいに。
勝己は驚いて硬直している。意表を突けたようだ。
「わかってるだと?おい、デク」
すうっと部屋の温度が冷えたような気がした。
「かっちゃん?」
「てめえ、まさか、やったことあんのかよ。言え!誰にやられやがった!」
知ってると言ったから、経験したと解釈されてしまったのか?しかもやられたって、男にってこと?
「ないない!ないよ!なんでそうなるんだ」
「クソが!紛らわしいわ!」
「君もしたことないよね?」
「ああ?うるせえわ、クソナード!」
「ないよね?だったらさ、一回やってみようよ?ね?」
「てめえは……」
そう言いかけて勝己は黙ってしまった。冷静になると恥ずかしさが押し寄せてくる。何言ってるんだろう、僕は。まるで僕から積極的に誘ってるみたいじゃないか。かっちゃん呆気に取られてないか?
ひょっとして、抱くって言ってたのも、言葉だけで本気じゃなかったかも。
「ご、ごめん、君にその気がなければ、今のなしで」
出久は狼狽えた。顔が羞恥で熱くなる
「身体だけなら、てことかよ。てめえはまた!また!」勝己は拳を床に叩きつける。「俺を虚仮にしやがって!クソが、クソが!」
「違うよ。虚仮にしてなんかない、かっちゃん」
怒らせてしまった。また間違ってしまったのか。
だが罵倒しながらも、勝己は出久の顎を掴んで口を開けさせ、口付けた。隙間なく唇で塞いで食らうようなキス。歯がぶつかった。吐息を奪われる。
本気だ。かっちゃん。口内を這う舌の音が内側から鼓膜を震わせる。
キスを交わしながら、勝己は出久を抱き起こし、、縺れるようにベッドに倒れ込んだ。
食むようなキスが続き、音を立てて唇が離される。勝己は出久のTシャツの中に手を入れて肌を弄り、邪魔だとばかり破りそうなほど荒々しくシャツを剥いだ。体を起こして勝己もTシャツを脱ぐ。性急さに戸惑って、出久はハーフパンツにかけられた手を押さえた。
「ま、待って、かっちゃん」
「ああ?んだよ!」
出久を見下ろすギラついた瞳は、獰猛な獣のようだ。
「やっぱり難しいんじゃないかな。男同士なんて」
「ああ!今更てめえ、ざけんじゃねえ!舐めんな。できるわ!」
「もう一度確認するけど、かっちゃんも経験ないよね」
「あ?それがどうした」
「べ、勉強してからの方がよくない?」
「デクてめえ、逃げんのか。ここまできて怖気づいたのかよ」
「そ、そんなことないよ」
覚悟してきたくせに、いざとなると怖い。それを看破されている。
「もう遅えわ。クソが」
あっという間に一糸纏わぬ姿にされた。勝己も裸になり、出久の上にのしかかり身体を重ねてくる。
ひたりと直に触れる人の皮膚。引き締まった筋肉の重み。胸と腹に感じる自分より少し高い体温。下腹部に体毛と硬いものが当たってる。これは、勝己のあれだ。勃起してる。かあっと顔から火が出そうになる。
勝己の唇が首に触れて押し当てられ、ちゅうっと吸い付く。出久は目を瞑った。もう、止められないんだ。
キスは跡を付けながら、胸、腹、脇腹に降りてゆく。
脱力した身体がずしりと重ねられる。ふうっと首元で勝己が息をつく。
この生々しさが恋なんだ。
好きということと恋じゃ全然違うんだ。
疲労で手足が重い。頭に霞がかかったようだ。
ポツリと勝己が呟く。「自己犠牲かよ。反吐が出るぜ」
ぎゅうっと抱きしめられた。抱き潰されそうだ。
「かっちゃん」出久は呼んでみた。喘ぎ過ぎて、声が枯れている。
「デク、デク」と勝己は呼ぶ。どちらのものとも知れない汗で濡れた肌。
背にまわされた皮の分厚い勝己の掌が、じわりと熱を帯びてゆく。
「殺す。てめえを殺してやる。クソが」
かっちゃんの怒りは収まらなかったのか。情欲を解消しても。そう簡単にはいくはずなかったんだ。全然簡単じゃなかったけれど。
うっすらとニトロの香りが漂う。かっちゃんの掌が汗ばんでるんだ。このまま爆破されるんだろうか。くっついてたら、かっちゃんも火の粉を浴びるけれど。疲れて動けないから避けられないな。
でも怖いと思わない。何故だろう。不思議だ。
出久はすうっと意識を手放した。
4・ぬかるみの足跡
翌朝。目覚めると間近に勝己の顔があった。吃驚してひゅうっと息を呑み、硬直する。
「やっと起きたんかよ、デク」
「う、ん、おはよう」
昨晩は勝己の部屋で寝てしまったのか。ふたりとも裸のままだ。いつから寝顔を見られてたのだろうか。
背中は、痛くない。爆破されなかったんだ、とほっとする。
「てめえ、寝落ちしやがって。クソが」
勝己の口調は落ち着いている。文句を言ってるけれども、言葉に棘はない。機嫌が治ってるようだ。
勝己は出久の背中に腕を回し、ぎゅうっと抱きしめてきた。身体が密着する。目の前に綺麗な鎖骨。分厚い胸。身動ぎすると、力強い腕が逃がさないとでも言うように、封じ込めてくる。
微かに甘い、勝己の匂いだ。
「朝飯食いにいくか?」
と話しかけられ、コクコクと首肯する。やっぱり機嫌がいい。
嵐のようだった昨夜の行為。最初の噛みつくようなキスに、きっと酷く扱われるだろうと覚悟していた。手荒いセックスを覚悟していた。だが、入れられた時はすごく痛かったものの、前戯は念入り行われたし、挿入した時も痛くないかと聞かれた。思いの外優しい抱き方だった。
「折角の機会なんだから、楽しまなきゃ損だろうが。童貞」
出久の思考を読んだように、勝己は揶揄ってくる。勝己は出久の額にキスをして腕を解くと、ベッドから抜け出して、立ち上がった。
「君もだろ」と言って見上げると、勝己のペニスが目に入った。どきりとして目を逸らす。
昨日の勃起した状態と違い、通常の形に戻っている。あれが昨夜僕の中に入って、暴れ回ってたんだ。君と身体を繋げたなんて信じられない。今更ながら頬が熱くなる。
「今更なに照れてんだ、てめえ」
勝己はニヤッと笑い、腰を揺らして振って見せる。子供みたいだ。
「腹減ったな」と言いながら、勝己は脱ぎ散らかした服を拾って、身に付けている。
自分も服を着なきゃ、と出久は腰を上げようとしたが、股の間に違和感を感じ、「うわあ」と呻いて突っ伏した。まだ挟まっているかのような感触が、昨晩の出来事を現実なのだと突きつけてくる。
勝己は呆れたように笑うと、散らばった出久の服を「さっさと着ろよ」と投げて寄越した。礼を言って受け取り、そそくさと身に付ける。
「まだ時間あるし、さくっとシャワーでも浴びに行くか、デク」
「そうだね。汗かいちゃったし」
立ち上がろうとして、痛みに足元がふらついた。ざまあねえな、とにやつく勝己に腕を支えられる。
風呂場を出て、上機嫌の勝己と廊下を連れだって歩く。尻の痛みはシャワーを浴びたおかげで、幾分か和らいだ。
出久は自分に言い聞かせる。僕は間違ってなかったよね。
食堂の入り口で、丁度出てきた上鳴とすれ違い、声をかけられた。
「うっす、お揃いで珍しいじゃねえか、爆豪、緑谷」
「おはよう。上鳴くん」
「でもおせえじゃん。俺もだけどよ。ちょっと寝坊しちまってよ。皆先に食って、学校行っちまったぜ」
「ね、寝汗かいたから、シャワー浴びてたんだ。朝浴びると気持ちいいよね」ちょっと狼狽えて早口になる。
「そっか。爆豪、なんか機嫌いいじゃねえか。お前ら仲直りしたのかよ」
「うっせえ、クソが」
「う、うん。おかげさまで」
「何が原因だったのか、やっぱり言えねえか、緑谷」
「うんまあ、大したことじゃないんだ。心配かけてごめん」
「おい、遅えんだろうが、無駄口たたいてんじゃねえ。行くぞ、デク」
勝己に腕を肘で突かれる。
「うん、じゃ、上鳴くん、学校でね」。
「緑谷、あのよ」と上鳴は言いかけて口籠り、再び口を開く。「俺が言えることでもねえな。よかったな、爆豪。もう喧嘩すんなよ」
「うるせえわ。飯食ったんだろ、さっさと行けや」
朝食を乗せたトレーを持って勝己は席に着き、腕を引っ張ると隣に出久を座らせた。勝己と隣あって食べるなんて久しぶりだ。合宿以来だろうか。
パンを齧りながらふと思い至る。ひょっとして、さっき上鳴くんは僕じゃなく、かっちゃんによかったなって言ったのだろうか。
気づいているのかも知れない。いつも勝己の側にいる彼らだ。でも聞かないでいてくれるのも、きっと優しさなのだ。どこまで知ってるのかなんて聞けないけれど。
でも、ほんとにこれで良かったのだろうか。セックスはしたけれど、勝己の意に沿えるわけじゃない。機嫌はいいのは一時的なもので、また怒り出すのかも知れない。その場しのぎに過ぎないのだ。でも他に方法を思いつかなかった。
その日の勝己は出久だけでなく、周りに対しても穏やかだった。久々に訪れた平和な日だった。
性欲を解消したからだろうか。即物的な方法だったけれども。これで良かったんだ、と出久は安堵した。
しかし、その安堵はほんの短い間だった。
放課後になり、寮に戻ると勝己が玄関先で待っていた。
「かっちゃん?どうしたの?」
勝己はこっち来いとばかりに指を曲げる。出久が側に歩み寄ると、肩を抱き、耳元で囁いた。
「おいデク、後で部屋に来いや」
「え?なんで」
「わかんだろーが」
出久は驚いて離れようとしたが、肩を強く掴まれ、逃れられない。
「あれは、一回だけのはずだよね?」
「ああ?何言ってんだてめえ」
勝己に腕を取られ、引きずられるように部屋に連れ込まれる。
「誰が一回で終いだっつったよ。俺の気の済むまで、てめえは俺の相手をすんだよ」
「でも、僕は君をそんな風には思えないんだよ」
「てめえの気持ちなんか知るかよ!」
「かっちゃん、でも」
「俺は一生言わねえつもりだったんだ。暴いたのはてめえだ。面白半分によ」
「そんな、面白半分になんて、違うよ」
「償いてえんだろ。許して欲しいんだろ。おら脱げ!今からセックスすんだよ」
勝己は出久をベッドに突き飛ばし、ズボンのベルトを外した。戸惑う出久に覆い被さると、口付ける。確かに一度だけなんて約束はしてない。ならばもう一度と言われても呑むしかないのか。
うつ伏せにされ、丹念に慣らされ、背後から貫かれる。
揺さぶられるほどに、身体を穿ち、埋めてゆく。
最奥まで抜いては挿れられる質量。
汗ばんだ身体に被さる重みと、名を呼ぶ熱を含んだ声。
熱い楔は緩やかに身体を穿ち、奥深くで動きを止める。
背後から抱きしめる腕は、離してはくれず、出久が身じろぎすると、さらに力が籠められた。
勝己は落ち着いた。これまでの荒れようが嘘のように。
無闇に人に噛み付かなくなったので、クラスメイトもほっとしている。
だが、元に戻ったわけではない。疲労が激しい時以外は、出久は毎夜のように性交を求められた。二度目の時に宣告されたのだ。勝己の気の済むまで続けるのだと。出久に断る道理はなかった。
とはいえ、勝己は口調は荒いが抱き方は優しく、事後はとても機嫌がよい。断る理由はもはやなかった。
背中に感じる鍛えられた筋肉。汗ばんだ皮膚がひたりと吸い付く。再びデク、と呼ぶ声と共に、首筋に熱い息が吹きかけられる。
勝己とのセックスは、優しかったり激しかったり、日によって気まぐれだ。
ベッドですることが多いけど、今みたいに違う場所ですることもある。明かりをつけたままでされたり、姿見の前で挿入されたり、恥ずかしくなるようなこともする。
でも、なるべく勝己がしたいようにさせた。セックスした後の彼は機嫌がいいからだ。出すもの出せばすっきりする。即物的だが男の生理とはそういうものだ。
けれども、これでいいのだろうか?
一度だけだと思ってたのに、もう何回彼としたのかわからない。
気持ちが伴わないのに、身体だけが慣れてくるのだ。身体を重ねることに、受け入れることに。ペニスを咥えるなんてこと、ちょっと前ならとても考えられなかった。
本当にこれで良かったのだろうか。
泥濘に足を取られて這い上がれなくなるのではないだろうか。
迷いは膨らみ、煩悶は澱のように沈殿していった。
5・甘噛みと囁き
ある日から、ぱたりと勝己は出久を誘わなくなった。
寮に帰っても挨拶程度の話しかせず、ましてや色事を匂わせるようなことは、全く言わなくなった。
始めはその気がない日もあるのだろう、と思った出久だったが、毎日のように部屋に連れ込んで抱いていたのだ。何もない日が何日も続くと、何か気に触ることをしたのだろうか、と不安になってきた。思い出せる限り身に覚えはない。
勝己は怒ってる様子もなく、出久を無視するわけでもない。気まぐれに過ぎないのだろうか。
出久は戸惑った。勝己の真意がわからない。セックスのことなんて聞きにくいのだけど、気になってしまう。
「あの、かっちゃんいる?」
ドアをノックすると、「入れよ、デク」と中から返事が返ってきた。ぶっきらぼうだけれど、不機嫌ではないようだ。
「あんだ?デク」
勝己はベッドに座っており、出久を見据えて促す。どう切りだそう。意を決して勝己の部屋に来たけれど。
「かっちゃん、その、もうしないの?」逡巡したすえについ直球で問うてみる。
「あ?何をだ?」
「その、あれのことだけど」出久は言葉を探すが思いつかない。
「あー?セックスしてえのかよ」
「そ、そういう意味じゃないよ。その、もういいのかなって」
「へえ」勝己は目を細める。「セックスじゃねえならなんだ」
「ごめん、好きでも、毎日したいわけじゃないよね、じゃ」
恥ずかしくなって、部屋を出ようとする出久の背中に「待てや、デク」と勝己は呼びかける。
「てめえ、勘違いしてんだろ」
「なんのこと?」出久は振り返った。
「てめえ、俺がてめえを好きでやってたと、思ってんのかよ」
「かっちゃん?」
勝己は悪辣な笑みを浮かべた。勝己が勝利を確信して、相手に勝ち誇る時の表情だ。嫌な予感がした。
「はっは、俺がいつてめえを好きだと言ったよ」
「え?だって君が」
いや、確かに勝己ははっきりとは言ったことはない。でも、そんなこと。一体彼は何を言ってるんだ。
「俺は一度もてめえを好きだなんて、言ったことねえよなあ、デク。てめえが勘違いしただけだろーがよ」
「でも、かっちゃん」
指先が冷たくなってゆく。
勝己は嘲笑った。「はっは!俺に抱かれてよがって、気持ちよかったんだよなあ。デク!雌みてえに俺のちんこ咥えこんで、悦んでたもんなあ」
何も言葉を発せられない。頭が熱くなってくる。喉に石が詰まったようだ。
「だって君は。君がそうだと思ったから、だから僕は君に抱かれたんだ」
なんとか言葉を絞り出す。そうじゃなければ、何故抱かせろなんて言ったんだ。何のために自分は抱かれたんだ。勝己は膝を叩いて笑う。
「はっ!いい気になってたんだろう。俺に抱かせてやってるつもりだったんだろーが。好かれてると思い込んでよ。馬鹿はてめえだ。まんまとてめえで童貞捨てさせてもらったわ!」
勝己の言葉が突き刺さる。勝己は自分嘲笑うために抱いたというのか。
指先を凍らせた冷気が腕を登って胸に届く。すうっと心臓が冷えてゆく。足元が崩れて沈み込んでしまうような錯覚を覚える。
勝己の笑い声が頭に反響する。
立ってられない。もうこれ以上ここにいられない。
「そっか。君がもういいなら、もう終わりなんだね」
「ああ?」
「でも、男相手で童貞を捨てたことには、ならないと思うよ。かっちゃん」
平静を保とうとしても声が震える。勝己の顔を見られない。踵を返して部屋を出ると
出久は廊下を駆けた。
後ろから勝己の怒鳴り声が聞こえる。でも振り返ってられない。
足早に階段を駆け下りて自室に駆け込み、ベッドに突っ伏した。
好きではなかったと勝己は言った。恋じゃなかったのか。自分が勘違いしてただけだったのか。
でも最初に恋という言葉をうっかり口にしてしまい、否定してしまった時の勝己の怒りは、本物だったのだ。無駄な偽りを言う彼ではない。なら、答えは一つだ。
抱いて想いを遂げたから醒めたのだ。もう恋はなくなったのだ。
もとより恋というのも、ただの子供の頃からの、思い込みだったのかも知れない。彼にとっても不本意な思いだったんだ。
これで良かったんだ。
溜まっていた諸々を解消されて、かっちゃんの怒りは収まったのだ。僕はもう自由になったのだ。
なのに。解放されたはずなのに。思いのほか傷ついている心に気づかされる。ほろほろと涙が溢れて止まらない。刀で裂かれたように、胸が痛む。
ああ、今の僕は君に恋をしているのだ。君をそんな風に思ってなどなかったのに。
悲しくて苦しくて堪らない。終わってしまってから気づくなんて。
望むと望まざるに関わらず、恋は予期せぬ時に嵐のように心を蹂躙するものなんだ。まるで災難のようだ。
「身体で堕ちるなんてあんまりだ」
声に出してみる。言葉にするとなんて月並みなんだろう。
ああ、そうか。肌の触れ合いも人の交流方法のひとつなのだ。
君の体温が、睦言が、身を貫く熱が。言葉じゃ伝え合うことのできない、君との唯一の対話の方法だったのだ。
「馬鹿なのは僕だ」
僕の愚かさを君はわかっていたんだろう。君のことを慮るのなら、たとえ長くかかるとしても、僕は君の心が整理されるまで、待つべきだったのだ。二度と心を開いてくれなくても、甘んじて受けるべきだったのだ。
でも僕は待てなかった。君との関係をもう二度と悪化させたくなかった。取り返しようがなく距離ができてしまうことを恐れた。
でもそれ以上に、僕は君を傷つけた悪者になりたくなかった。罪悪感に苛まれたくなかった。きっと君のためなどではなかったのだ。
自分のために人の心を操ろうとするなんて傲慢だ。だからこうなるのは当然のことなんだ。偽善者の報いなんだ。
涙の雫で枕が濡れてしまった。
かっちゃんとのことはもう忘れよう。過ちは償ったのだ。かっちゃんは僕を貶めて、気は晴れただろう。
今夜は無理だけれども、涙が止まらないけれど、明日になればきっと立ち直れる。
「大丈夫。僕なら大丈夫だ」声に出してみる。暗示をかけるように繰り返す。「大丈夫。何もなかったように、元に戻れるはずだ」
僕らの間には、何もなかったんだと思えるようになれる。
「デク!てめえ!」
バタンと勢いよくドアが開けられた。目を釣り上げて、勝己が立っている。
「かっちゃん?な、何だよ」
「はっ!なんだてめえ、べそかいてんじゃねえかよ。泣き虫がよ」
出久の顔を見て、勝己の形相が和らぎ、得意げに嘲笑う。
「こ、これは別に、なんでもない。何しに来たんだ」
急いで身体を起こして涙を拭った。勝己はズカズカと部屋に入ると、出久の肩を掴み、どすんと押し倒す。
「な、何?なんのつもりだよ、かっちゃん。君とはもう関係ないだろ」
「ああ?なんだてめえ、その言い草はよ。謝るときはしつこく食らいついてきたくせによ。今回はあっさり引き下がりやがって。クソが!」
「だって、もう僕らは終わったんだろ。かっちゃんの気は済んだろ。これ以上何だよ」
「はあ?ボケカス!勝手に終わらせてんじゃねえわ。誰がやめるっつったよ。クソが」
「かっちゃん?」
「てめえはほんとにカスだな。んなこったろうと思ったわ。自分から手の中に転がり落ちて来た馬鹿を、この俺が逃すわけねえわ!」
勘違いだと言ったくせに、訳がわからない。
「君に恋心がないのならもう付き合う理由がないよね?」
「あるわ。おいデク!てめえ、俺に抱かれたいんだよなあ。認めろや」
「かか、かっちゃん?意味がわからないよ」
「抱かれてえんだろが!デク、てめえさっき身体で堕ちたっつったよな」
「き、聞いてたの?」
勝己はいつからドアの外にいたのだろう。まるで気づかなかった。こっそり来て聞き耳を立てていたのか。どこから独り言を聞かれていたのだろうか。
「違うよ、あれは」
顔がかあっと熱くなる。どう言い繕えばいいんだろう。
「てめえ、自分で恋に堕ちたと思ってんのか?」
「え?どういう意味」
「はっは!てめえは勝手に堕ちたんじゃねえよ。俺がてめえを堕としたんだ。てめえは堕とされたんだ、この俺によ」
「かっちゃん?何言ってるの」
「てめえがいきなり部屋に来て、俺にやっていいって言いやがった時、マジで殺意が湧いたぜ。ンなことあっさり言えるってことがよ。てめえにはその程度のことなのかよってな。これ以上ねえってくらいムカついて、てめえをめちゃくちゃにしてやろうかと思ったわ」
「ごめん、かっちゃん」
今ならどれだけ心無いことを言ったのか、理解できる。
「だけどな」と勝己は続けた。「思い直したんだ。てめえは贖罪にきたんだ。てめえ勝手な贖罪だがよ。乱暴にしたら、てめえの思い通りになっちまう。一度抱いただけで済ませてたまるかってんだ。だから、てめえを堕とすことにしたんだ。計算通り、てめえはまんまと堕ちた。認めろよ、デク。俺に抱かれてえんだろうがよお。なあ、そうだろ、クソナード」
「かっちゃん」
「俺はてめえが好きじゃねえ!全然好きじゃねえわ!でも、てめえは俺を好きなんだろ。欲しいんだろうが。そう言えや。肯定しろやデク!」
好きじゃないと言いながら、堕としたという。認めろと迫り、僕に好きだと言わせようとする。矛盾してる。むちゃくちゃだ。
でも。僕はほっとしている。かっちゃんの恋が醒めたんじゃないということに。
君が僕を欲しいと思うように、今は僕も君を欲しいと思っているんだ。君がここに来てくれたことを、理不尽な言葉を、嬉しいと思ってるんだ。
君の思惑にまんまと乗せられたのかも知れないけれど。もう墜ちる前に戻れはしないんだ。
出久は肯定の返事として、こくりと頷いた。勝己は満足そうに口角を上げる。
「はっは!デク、デク!もう今までみてえに手加減してやらねえ。コンドームなんざつけるかよ。一晩に一回で足りるかよ。これからだ。全部これからだ。俺が飽きるまでずっとてめえは俺のもんだ。飽きなきゃあ一生、死ぬまでずうっと俺のもんだからな。覚悟しろや」
勝己は勝ち誇ったように笑う。
あれ?条件が酷くなったようだぞ。かっちゃんにしては優しいやり方だと思っていたけど、やはり手加減してたんだ。
勝己は出久の唇を食むように甘噛みし、がぶりと噛み付くように深いキスをする。
口腔を荒々しく暴れる舌。最初の交わりの時のような濃厚な口付け。息を奪われる。窒息しそうだ。
漸く唇が離れ、開放されてやっと空気を吸い込む。
赤い瞳が返事を促すように見下ろす。
彼は相当押さえていたのだ。それは今のキスでよくわかった。今後は容赦しないと、そう目で告げている。
本気のかっちゃん相手に、どうなっちゃうんだろう。でも怖くはない。
「うん、わ、かったよ」
呼吸がまだ戻らない。途切れ途切れに言葉を紡ぐ。勝己はすうっと目を細める。
再び唇の触れそうなほどかがみ込み、吐息混じりの声で囁く。
「でも、ちったあてめえの言うことも聞いてやるわ。言えよ、デク。俺にどうして欲しいんだ」
ああ、彼は僕の何倍も我儘で傲慢で、一枚も二枚も上手だったのだ。
6・橙色の思い出
「疲れたよ、かっちゃん」
ふうふうと息を弾ませて、僕は前を歩くかっちゃんに呼びかける。
裏山を流れる川の上流に遡って、随分と歩いてきた気がする。
鶺鴒だろうか。川面をついっと滑るように飛んでいる。
セキレイ。イザナミとイザナギが、尾を振るの見て何かを知ったんだっけ。前にかっちゃんが得意げに教えてくれたけど、思い出せない。
川べりの岩が下流に比べて、かなり大きくなってきた。ゴツゴツした岩で足が滑りそうになる。
ふいっと前を赤蜻蛉が横切った。
「だらしねえな、デク」
かっちゃんが手を伸ばした。僕はその手に縋るように捕まる。肉厚な掌はしっかりしてて頼もしくて、安心する。
そのまま手を繋いで歩を進めた。川の流れが次第に細くなり、岩を穿った小ぶりな滝に繋がってゆく。
ようやくかっちゃんは立ち止まった。着いたぜ。と顎をしゃくる。
見上げると、空を覆うように2つの大きな岩が聳えていた。大きな岩と岩は寄り添うようにくっついている。岩の間に挟まれて、人がやっと通れるくらいの隙間があり、隙間の向こうには遠く山の端が見える。
「もうちょっと待てや。そろそろだ」
「何?何か起こるの?かっちゃん」
「黙って見てろや」
かっちゃんはウキウキしてるみたいだ。
ふと、岩の隙間の上部がキラリと光った。
「何なに?」
隙間を覗いてみると、紅色の夕陽が見えた。陽が降りるに連れ、眩しく光が射し込んで広がり、両方の岩肌を橙色に塗りつぶしてゆく。美しさに疲れも吹っ飛んだ。
「すごく綺麗だね。かっちゃん」
「こないだ山登ってて、ここを見つけたんだぜ。俺の特別な場所だ」と言い、くるっと僕を見る。「てめえだから見せてやんだからな」
かっちゃんは得意げだ。特別と聞いて嬉しくなった。手を繋いだまま、しばらく見惚れているとかっちゃんが口を開いた。
「デク、見せてやったんだから、てめえの特別を寄越せよ」
「え?見返りがいるの?」びっくりして聞き返した。
「たりめーだ、クソが!」
頼んだわけでもないのに、お礼を要求されるんだ。やっぱりかっちゃんだった。
とはいえ、夕陽はとても綺麗だし、かっちゃんの言葉が嬉しかった。
僕にも彼に見せられるような、いい景色はないだろうかと考えてみたが、思いつかない。
「ごめん、かっちゃん。僕は素敵な場所なんて知らないんだ」
「クソが。場所じゃねえ」
「じゃあ、もの?」まさかと思って、恐る恐る聞いた。「僕のオールマイトのフィギュアとか?」
「クソが!てめえのお宝なんぞいんねえ。俺はてめえみてえなコレクターじゃねえよ」
「でも、僕は何も持ってないんだよ」
君と違って、という言葉は飲み込む。ここで言う言葉じゃない。
「あんだろ。てめえの特別を寄越せって言ってんだ」
「だから、持ってないよ」
かっちゃんはふくっと膨れてしまった。
「わかんないよ。かっちゃん」
「クソナードが」
それっきりかっちゃんは黙ってしまった。視線を僕から外して、岩に向けてしまう。怒ったのだろうか。そっと顔を伺う。
眉間に皺は寄ってないし、そんなに機嫌を損ねたわけじゃないようだ。
かっちゃんは僕の手をきゅっと握り直し、そのまま一緒にポケットに入れた。ジャンパーの中で、かっちゃんの手がすりすりと僕の手を摩る。
川からの風で思ったより冷えていたみたいだ。かっちゃんの体温に手が温められる。
「特別を寄越せや」
かっちゃんはぽつりと繰り返す。
岩の隙間から覗く橙色の空が朱い色に染まってゆく。
夕陽は色の白い幼馴染の頬も赤く染めていく。
END
たったひとつの冴えたやりかた(R18版)

1・かの日の怪物
久方ぶりの自宅への帰り道のことだった。
出久は膝に抱えていたリュックを担ぐと、電車を降りた。
黄昏の空に烏の鳴き声が遠く響く。家々のシルエットを、夕焼けが橙色に縁取っている。落陽は出久のすぐ前を歩く、幼馴染の小麦色の髪も、紅に染めあげてゆく。
「家なんざ、かったりいぜ、クソが」
勝己が出久に聞かせるともなく呟いた。
独り言なのか、自分に話しかけてるのか、どっちだろう。返事をしていいものかどうか迷い「う、ん」と生返事をする。
隣を歩けばいいのだろうけど、つい前後に並んでしまうのは、長年の癖のようなものだ。
三連休に寮に一斉清掃が入ることになり、その間生徒達は一時帰宅することになった。長期休暇ですらあまり家に帰りたがらない勝己も、今回は帰宅を余儀なくされ、不貞腐れていた。
五時半を告げるメロディが通りに流れる。公園から跳ねるように出てきた数人の子供達が、側を走り過ぎてゆく。それぞれの家に帰るのだろう。子供達は分かれ道で、バイバイと手を振って別れていった。僕らもあのメロディに急かされたなと懐かしくなる。
勝己や仲間達と毎日遊んだ公園。ブランコも砂場も滑り台も、少し色褪せてるけどほとんど変わっていない。勝己との距離が離れていくにつれ、次第に足が遠のいてしまったけれど。
「あ?てめえは週末にしょっ中帰ってるだろうが」
思いがけず返事が返ってきた。ちょっと焦って答える。
「う、うん、そうだね。お母さん待ってるし」
「こっちじゃ個性も使えねえし、家ですることなんて何もねえわ。親はあれしろこれしろってうるせえしよ」
学校なら堂々と個性を使用できるだけに、勝己はもどかしさを感じているのだろう。
「かっちゃんはこっちで昔の友達に会ったりしないの?」
「あ?一度も会ってねえよ」
「え、そうなんだ」
「今更会いたくもねえ。過ぎたもん振り返ってる暇なんざねえわ」
よく勝己は仲間とつるんでいたけど、そんなものだろうか。自分には会いたいような旧友はいないから、わからない。無個性と揶揄されていたのだ。思い出したくない。雄英で出会った、側にいてくれる本当の友達を大切にしたい。
しかし、苦い思い出もあるけれど、それも君と友達のように歩いている今に繋がっているのだ。友達のように、としか形容できないのがもどかしいけれども。
子どもの頃だって、勝己に憧れてひっついてたけれど、友達といえただろうか。彼がどう思って自分のような鈍臭い子供を、仲間に入れてくれたのかは知らない。来るもの拒まずという、親分肌だったのだろうか。今更聞いても教えてはくれないだろう。
今も勝己が自分をどう思っているのかは分からない。でも、漸く嫌われてはいないと、思えるようになった。少しずつでも打ち解けていって、いつか本当に友達になれればと、願わずにはいられない。
勝己は立ち止り、くるりと振り向いた。
「な、何?かっちゃん?」
心の声を聞かれていたように錯覚してしまい、ドキッとする。面と向かうと緊張感してしまう癖は、そうそう抜けはしない。
「おいデク、先行くわ」
とそれだけ言うと、勝己はずんずんと早足で去ってしまった。
「あ、またね。かっちゃん」慌てて後姿に呼びかける。
別れ際に声をかけてくれるなんて、前なら考えられなかった。ちょっと嬉しくなり、ふわふわと心が浮ついた。
橙色の空が朱色を帯びてきた。雲が紫色の夜の衣を纏い始めている。
団地の入り口に入った時だ。「久しぶりだな、デク」と背後から声をかけられた。振り向くと見覚えのある顔。
「俺だよ、俺」
「あ、ああ、うん」
思い出した。幼稚園からの幼馴染の1人だ。小学校3年生のクラス換えで別々になるまで、勝己達とつるんでいた。
「カツキと同じ雄英に入ったんだってな。テレビで雄英の体育祭見たぜ」
なんと答えていいものか。「あ、うん」と戸惑いながら返す。
「お前、個性あったのかよ。すげえな。で、やっぱりいまだにカツキにいじられてんだな。障害物競走でも騎馬戦でも、お前に突っかかってたよな。あいつ昔からひどかったよな」
君も一緒になっていじめてきたろ。と思ったが言わない。覚えてないのだろうか。「今のかっちゃんはそんなことないよ」と答えておく。
「あいつが?マジかよ」
それにしても、と思う。いじめた方はどうして何もなかったかのように、平気で話しかけてこれるのだろう。フレンドリーに来られると、どうしていいのか困ってしまう。
小学生の頃なんて、いじめも遊びも曖昧なんだろうか。何をしたか忘れているのだろうか。こっちは今も苦手だというのに。傷つけた方にとっては取るに足りないことでも、傷つけられた方は覚えてるんだ。
それとも、今だに昔を引きずっている勝己だけが例外なのだろうか。
切れ目なく続いた腐れ縁。拗れに拗れた関係は、やっと望んでいたような形に落ち着いた。昔のことを知る人には意外かもしれないけれど。
「今だから言うけどよ。カツキがお前を気に入ってたってこと、知ってたか」
何気ない軽い調子で幼馴染は言った。いつ話を切り上げようかと、迷っていたところに意表を突かれる。
「へあ?」
「変な声が出してんなよ。あいつお前を意識してただろーが」
「え?なに、いきなりなんで?そんなことないだろ」
「あいつ、いつもお前を揶揄ってたろ。それに何かうまくいくと、いつも嬉しそうにお前だけに振ってただろ。カツキが上なのは当たり前なのによ」
「まあ、そうだったけど。馬鹿にされてたんじゃない」
自分との差を見せつけて悦にいる。勝己はいつもそうだった。
「あれはよ、お前の反応が欲しかったんだろ。オールマイトカードだって、いいの出ると真っ先にお前と見せ合ってたし。他の奴にはそういうの、振らねえの気づいてたか?お前だけデクって徒名決めて呼んでたしよ」
「徒名は皆につけてたじゃないか」
雄英でも轟くんや麗日さんや切島くん、上鳴くん達を、おかしな名前で呼んでた。最近は呼ばないけど。
「いや、俺らを徒名で呼ぶ時は、ただの悪態だろ。全然違うわ。あいつお前だけ特別だったんだよ」
全然そうは思えないけど、勝己のそんな行動が、傍目には好きだからだと思われたのだろうか。
「そんな風に見えてたんだ。意外だよ」
幼馴染はじっと出久を見つめ、徐ろに口を開いた。
「今だから言うけどよ、俺らはカツキがお前に恋してんだと思ってたんだぜ」
突飛な言葉に、頭が真っ白になった。
「え、え、恋?かっちゃんが?なんでそうなるの?今の話のどこに、そんな要素があるんだよ」
「恋してるとしか思えねえだろ」
「あり得ないよ!あのかっちゃんだよ」
勝己に好意を持たれてたってだけでも想像し難いのに。好意だけならまだしも、恋慕なんて飛躍し過ぎだろう。
「お前もいつもあいつにくっついてたし、俺らはお前もあいつを好きなんだって思ってたぜ」
「僕が?そんなわけないだろ」
ぶんぶんと頭を振って否定する。
「ああ、お前は段々離れたてったしな」
「それは」離れたくて離れたわけじゃないけれど、彼に個性が発現してから、徐々に歯車が狂っていったのだ。
「根拠はあるぜ。お前がつるまなくなってから、俺らはカツキは落ち着くかと思ったんだぜ。でもお前は知らねえかもしんねえけど、あいつ苛々しながらも、いつもお前を目で追ってたんだ。去る奴追わねえあいつが、わざわざ追いかけて、結局はお前に構うしよ。あいつはなんも変わらなかったんだよな」
「あれは構ってたんじゃないだろ」
少しイラッとして口調に出てしまった。いじめられてたんだ。いくらなんでも過去改変が過ぎるだろう。
勝己の存在は、時に怪物のように自分を威圧した。憧れと恐れと形容できない様々な感情が渦巻いて、マーブリングの模様のように心の中で混濁していた。話していると当時の黒い心が蘇ってきそうだ。今の彼は違うのに。
早く話を終わらせたい。手を上げて「じゃあこれで」と言おうとしたところで幼馴染が口を開いた。
「あのよお、カツキが荒れたのは、お前がこっちをヴィランに仕立てたからじゃねえか」「え?どういうこと?」出久は驚いて問い返す。
「俺らがヒーローごっこしたりして、ちょっとヴィラン役の奴小突いたりすっと、いつもお前はそいつを庇いやがったろ。それがあいつは気に食わなかったんだ。お前も一緒にこっち側に加われば、カツキは怒んなかったと思うぜ」
びっくりした。そんな風に思っていたのか。かといっていじめる側に加われるわけがなかったけれど。
「カツキは強えけど、どんな強え奴でも弁慶の泣き所っつうのがあんだよな。それがお前なんだよ。お前と揉めるまでは、あいつはやんちゃなガキ大将だったろ」
彼が変わったのは、個性発現してからじゃないのか。いやそれだと4歳からということになる。あの後だって一緒に遊んでた。ではいつからだったんだろう。覚えてない。
「あの頃、あいつはお前に恋してんじゃねえのかって、皆思ってたんだぜ。本人は無自覚だったかも知れねえけどな。でも流石に今はあいつも自覚してんじゃねえの」
「だから恋なんて、何でそんなこと」
「お、そろそろ帰んなきゃな。じゃ、またな」
腕時計を確認すると、幼馴染は風のように去っていった。伸びた影が遠ざかってゆく。
後には動揺して立ち尽くす出久が残された。
恋ってなんだよ。意味がわからないよ。
パソコンで過去のオールマイトの動画をザッピングする。元気を貰う、日課のようなものだ。だが今夜はマウスを動かしながらも、出久は上の空だった。
頭の中に幼馴染の言葉が離れない。彼の言ったことは本当なのだろうか。
勝己が自分を好きだなんて突飛な話だ。大体好いている相手をいじめたりするだろうか。ないない。とてもあり得ないと思う。
けれど、周りには違って見えていたらしいのだ。
窓を開けるとすうっと夜風が吹き抜けた。カーテンが空気を含んでたなびく。眠る夜の町。灯りが蛍のように疎らに散らばっている。
勝己は起きているだろうか。黒に沈んで彼の家は見えないけれども、青白い三日月の下に勝己の家があるはずだ。
恋なんて勘ぐり過ぎた話はともかく、好かれていたのなら。それをあの頃知っていたなら、もっといい関係でいられたのではないだろうか。
勝己は自分をどう思っていたのだろう。昔の話だし、今なら聞いてみてもいいだろうか。確かめないではいられない。
僕は軽く考えていた。だがあまりにも浅薄だった。聞くべきではなかったのだ。
2・凍える羽搏き
連休が終わり、久しぶりに出久は家から直接学校に向かった。休みの間の宿題を入れたリュックは、いつもよりちょっと重い。
駅への道すがら、勝己にばったり会った。
「お、おはよ。かっちゃん」
勝己のことを考えていたところだっただけに、挨拶する声が裏返る。同じ電車に乗るのだから十分あり得ることなのに。
「ああ」と勝己に軽く返される。
昔はこんな挨拶をするだけでも罵倒されたけど、もうそんなことはない。ぶっきらぼうな物言いは変わらずとも、ちゃんと会話だってできる。今みたいなそっけない返事でも、声をかけたら返してくれるのが嬉しい。
「おいデク、ちんたら歩いてんじゃねえよ」
「あ、待ってよ、かっちゃん」
隣に並ぶのはちょっと遠慮して、一歩下がって歩きながら考える。
昨日幼馴染から聞いた話。子供の頃の勝己の真意がやっぱり気になる。今日の彼は比較的穏やかだし、機嫌がいいようだ。さりげなく聞いてみようか。
「あの、かっちゃん」
「んだよ」
「昨日ね、幼稚園の時からの幼馴染に会ったんだ」
「ああ?それがどうした」
「その時変な事言ってたんだ。かっちゃんは昔、僕を好きだったって」
「はああ?」くるっと勝己が振り向いた。「あるわけねえだろが!馬鹿言ってんじゃねえよボケカス。殺すぞクソが」
久方ぶりに淀みない罵倒が降ってきた。しまった、怒らせてしまったと、出久は慌てて言い繕った。
「そうだよね、ゴメン。君が僕を好きなんて。あるわけないよね」
好きだというなら、やはり長い間あんな酷い態度を取るはずがないのだ。無責任な言葉に踊らされて、全く何を馬鹿なこと言ってしまったんだろう。
「彼らが邪推してたんだね。おまけに恋してたんだろうなんて、言ってたよ。おかしいよね」
「黙れよ、デク」
勝己の呟きが耳に入ったけれど、バツが悪くて早口で言い訳を続ける。
「僕らは男同士なのにね。ほんとおかしいよね。恋だなんて。よりによって君がなんてさ、だって…」
勝己の顔が見られず、視線を逸らして否定の言葉を並べ立てた。
だが全部言い終える前に乱暴に口を塞がれる。
「そんなにおかしいかよ?ああデク!」
「んん、かっちゃん?」
「なあデク、てめえはどう思ってんだ」
口を塞ぐ手が少し緩められる。
「どうって?何を」
「俺のことをだ。てめえはどう思ってんだ?」
宣告を待つように俯いて、絞り出すような低い声で、勝己は繰り返した。
「君はすごい人で……」答えながらじわじわと間違いに気づく。違う、彼の聞いていることは違うんだ。
「んなこと聞いてんじゃねえ、デク。てめえは俺をどう思ってんだ」
「僕は……」でも、何を言えばいいんだ。喉に言葉が詰まったようで、次の言葉を継ぐことができない。
「はっ!」勝己は吐き捨てる。「てめえは違うんだろ!わかってんだよ。昔からわかってんだ。てめえは俺を嫌な奴だと思ってんだろ。なのにてめえは俺に聞くのかよ。ああ?デク!ざけんな!」
怒鳴り声とともに床に引き倒された。がつんと後頭部がアスファルトにぶつかる。くわんくわんと視界が揺れる。脳震盪を起こしそうだ。リュックを背負ってなければまともに打撲して、失神していたかもしれない。
「ちが……、かっちゃん」
「黙れよ、デク。それ以上喋んな」
勝己の怒りを押し殺した声。くらくらした頭がざあっと冷える。
「ふざけんなよなあ!てめえにはその気はねえくせに!なんで俺に聞いた!馬鹿にしてんのかよ、クソが。もうなんも喋んな。殺すぞ!ボケカス!クソが!」
激昂した勝己は周りのざわめきをよそに怒鳴る。
「クソが!クソが!そんな目で俺を見んな!俺を見下すな!侮るな!デク!」
出久の襟元を掴んで勝己は咆哮する。苦しい。息ができない。
「クソが!クソが」と罵倒され、漸く手荒に振りほどかれた。
出久は空気を吸い込んで、咳き込む。勝己は舌打ちして、何見てんだと周囲を威嚇して歩き去った。
久しぶりに感じる彼への恐怖。震えが止まらない。と同時に、彼の怒りに燃えた瞳と言葉に気づかされた。
僕はなんてことをしてしまったんだ。かの幼馴染の言っていたことは本当だったのだ。恋してたのだ。かっちゃんが僕を。信じられないことに。
でも、それを指摘することで、彼が激昂するなんて思わなかった。ただ、子供の頃の勝己に、好意を持たれてたのならいいなと思って、確認してみたかっただけなのだ。どちらにせよ過去の話なのだから。昔のことは振り返らないと勝己は言っていたから。
昔のことではなかったのか。君は今も恋を。
時間が戻るなら馬鹿なことを言ってしまう前に戻したい。遠ざかる勝己の背中。追いつきたいのに、謝りたいのに、足が竦んで動かない。
「緑谷、どうしたんだ?」
予鈴ギリギリに教室に駆け込んだ出久に、轟が話しかけてきた。
慌てて「何が?なんか変?」と服をぱたぱたと叩く。服についた砂は掃ってきたつもりだけど、不自然なところがあるのだろうか。
「あいつだ、どうしたんだ?」と轟は視線で窓際に佇む勝己を示す。
目を向けてぞくっと背筋に冷気が走る。勝己の全身から吹き出す怒りのオーラが、目に見えるようだ。
「朝から爆豪の奴、酷え荒れようだぜ」
「だよなあ?近寄るだけですぐ爆破させてきやがる。生きた地雷みてえだ。またお前ら喧嘩したのかよ」
切島に尋ねられ、「僕が?なんで」とどきりとする。
「爆豪があんだけ荒れるなんて、お前関連以外にねえだろ。あいつにとってお前は特別なんだからよ」
「そんなわけないよ!」
「ど、どうしたんだ、お前までムキになってよ」
「ご、ごめん」みんなにも勝己が幼馴染の言ってたように見えているのかと、焦ってしまった。切島は何か納得したような表情で尋ねる。
「やっぱり、お前らなんか揉めてんだろ。何があったよ」
「何があったんだ?緑谷くん」
通りかかった飯田にも聞かれる。原因が自分なのは決定事項とさられたらしい。弱ったな。でも当たってるし。少し考えて、答える。
「言えないんだ。心配かけてごめんね。大丈夫、なんとかするから」
無理に笑顔を作る。言えるわけがない。考えにくいが、もし逆の立場だったのなら、最悪なのは他の誰かに知られることだ。誰にも相談できない。一人でなんとかするしかない。
僕はかっちゃんを恋愛対象に思えるだろうか。と考えてみる。
無理だ。想像するのも難しい。男同士だ。とても考えられない。ましてやあのかっちゃんだ。
真意を知らなかったとはいえ、長年いがみ合ってきたのだ。以前よりもマシになったけど、今もさほど会話できるわけでもない。到底気持ちに応えることなんて出来ない。近すぎて遠い。それがかっちゃんと僕との距離なんだ。
君も僕となんて、考えられないと思ってたんじゃないだろうか。
きっとそうだ。だからずっと黙っていたんだ。ひょっとして、雄英ではない別の高校に行けと、勝己が自分に強いたのは、それが理由だったのではないだろうか。
僕にしても君にしても、いつか恋人を作るとすれば異性だろう。それに相性のいい相手にすべきだろう。君は君を怖がらない相手、僕は僕で緊張しない相手。君もそう思ってたんだろう。
それなのに、僕は君の心を暴いてしまった。
君の気持ちなんて知るべきじゃなかった。知らなければ、いつかはなかったことになったんだ。僕に知られるなんて、君にとって屈辱以外の何者でもないんだろう。
好かれてる可能性を知った時は嬉しかった。本当だったのに、今の僕の気持ちは沈んでる。こんなことになるなんて。どうすればいいんだろう。
出久は顔を上げて、正面にある勝己の背中を見つめる。彼の側に寄れるのは、前後に座る授業中だけだ。
僕が仕出かしたことなんだ。何もしなければ、今度こそ君との関係は、修復不可能になるかも知れない。謝るしかない。
どう言っていいのかわからないけど。ほかに思いつかない。君が許してくれるまで何度でも謝ろう。
皆の目があるから、教室では話すことはできない。休み時間に教室を出た勝己の後を追う。渡り廊下に一人でいるのを見計らって、出久は恐る恐る話しかけた。
「かっちゃん、その、話が」
「クソデクが!寄んじゃねえよ」
勝己は掌をこちらに向けて構えてる。
「かっちゃん、ごめん。僕はずっと君に嫌われてると思ってたんだ。だから、確認したかっただけなんだよ。怒らせるつもりじゃなかったんだ」
「喋んじゃねえっつったろうが!」
「聞かなかったことにするよ。忘れるから、かっちゃん、だから」
瞬間、眼前で火花が散った。危険を察知して横に飛び退く。顔のすぐ側で爆発が起こった。
キーンと耳鳴りがする。直撃コースだ。
「あ、危ないだろ。かっちゃん」
「はっ!次は容赦しねえ。退け!」
肩を捕まれ、ぐっと乱暴に押しのけられた。足がもつれて倒れそうになり、円柱にもたれかかる。
簡単に許してくれるなんて思ってない。でも、許してくれるまで諦めない。出久はじんじんと痛む肩を摩った。
それから何日も、出久は勝己を追いかけては、幾度も謝ろうとした。そのたびに勝己は視線で殺せるほどの敵意を向けて、出久を罵倒した。
出久が寄ろうとしただけでも、掌から火花を散らして威嚇する。諍いを止めようとしたクラスメイトも、とばっちりを受ける。取りつく島もない。出久の神経は次第に磨耗していった。
ふと教室の窓の外に目をやる。
窓枠に区切られた、重苦しく空を覆う鉛色の雲。まるで僕の心のようだ。出久はふうっと溜息を吐く。
子供の頃のことじゃないか。いや、今もだとしても。なんでいつまでもへそ曲げるんだよ、と恨めしく思ってしまう。でも悪いのは自分なのだ。
傷つけるつもりはなくても、相手が傷ついたなら、怒りを覚えたのなら、傷つけた者は悪なのだ。僕は昔のいじめっ子をそう断罪していた。身を持って知っている罪だ。なのに僕も彼らと同じことをしてしまったのだ。
薄曇りの空に、ぱらぱらと木々の葉を打つ音。雨だ。
教室の硝子を叩く雨粒を見ているうちに、出久の心は過去に引き込まれた。
子供の頃の勝己は純粋に、憧れそのものだった。勝ち気な赤い瞳、上級生にも怯まないタフさ。彼のようになりたかった。
オールマイトを知ってからは、目標は彼に変わってしまったけれど。それでも勝己の不屈の闘志や勝利を諦めない辛抱強さには、未だ変わらず憧れてやまない。
気性が激しさは君の個性に相応しく、生命力そのもののような君が眩しい。
でも、憧れと恋慕は全く違うものだ。
雨が強くなってきた。窓硝子に水滴が幾筋も跡を付けてゆく。
「放課後、待ってろよ」と中学生の時に勝己に何度も言われた。
中学生の頃の勝己の取巻き連中は、小学生以前の仲間と違い、出久を虐めたりはしなかった。というより自分には目もくれなかった。それが普通だ。無個性な奴にわざわざ絡みにくるほど、彼らも暇じゃない。
だが帰りのHRの前に度々、勝己は彼らから離れて出久の方に来ては、一方的に告げるのだ。放課後に待ってろと。
何の用なのか、聞いても言ってくれない。だから、きっとろくなことがないに違いないと思い、待つことはなかった。逆になるべく早くに帰ろうとした。
その度に勝己に見つかって詰られた。捕まって校舎裏や廊下の隅に連れて行かれて、小突かれたり、頭を抑えこまれたりした。
やはりろくなことがないんだと、何度言われても一度も待ったりしなかった。でも逃げようとしても逃げ切ることは出来ず、いつも捕まった。
今みたいな雨の日だ。
早く帰るのではなく、裏をついて遅く帰ろうとしたのに、勝己に見つかってしまった。
廊下の窓硝子を雫が伝って流れていた。勝己は自分を床に組み敷いて、下腹の上に馬乗りになっていた。両腕は拘束された。万力のように締められた手首が痛かった。
「逃げんな」
吐息がかかるほど、勝己は顔を近づけた。
「逃げんなクソが。待ってろっつったろーが!いつもいつも逆らいやがって」
じわりと勝己の掌が汗ばんできたのを、掴まれた手首に感じた。
「クソナードのくせに。虫ケラのくせに。クソが!クソが!この俺がてめえなんかに!」
勝己は出久の手首を束ねて片手で拘束し直し、自由になった手で頬を撫でた。ひたりと湿った感触。ニトロを含有する汗。硬い掌が発火し、頬を爆破するんじゃないかと怯えた。
個性の使用は禁止だから、勝己は相手に酷い火傷を負わせたりしない。手加減するのに長けてる。わかってても、かたかたと震えて、歯の根が合わなった。いつ殴られるのか、爆破されるのかと恐れた。
ギリッと歯ぎしりをし、「待ってろと言っただろうが!」と言って見下ろす勝己が、ただ怖くて時が過ぎるのを、解放してくれるのを待った。
あの時、勝己は出久を抑えこんで、顔に触れただけで何もしなかった。
廊下の床の硬さと冷たさ。
下腹を圧迫する勝己の重み。
「逃げんな、逃げんな」と譫言のように繰り返された言葉。
頬に触れる体温の高い掌。
雨だれがコンクリートを打つ音。
群青色の雲が垂れ込めた空。
今、恐怖の記憶が違った意味を持って思い出される。あの時勝己は、自分を傷つけるつもりではなかったのだろうか。
何度も呼び出す理由を、難癖つけるつもりなのだと決めつけていた。いつも怖がってばかりだった。
声が震えて体が震えた。条件反射になっていたくらいに。それは逆に彼を傷つけていたのだろうか。もう聞けるわけがない。
小学生の時の仲間だけじゃなく、ひょっとして中学生の頃の勝己の取巻きの連中も、彼の心に気付いていたのだろうか。自分に構う勝己を、呆れたように見ているだけだった彼らも。
ただ怖がって、勝己を避けるので精いっぱいで、何故絡んでくるのかなんて、一度も考えたことはなかった。
思い至るわけがないよ。僕は君が何を考えてるかわからなかったんだから。
君のことを嫌な奴だと思っていたよ。君のせいで僕の小中学時代の学校生活は灰色だったんだ。
でも1番楽しかった思い出も、君とのものなんだ。
君はいつも逃げるなと言っていた。ずっと僕は逃げていた。でももう、君と対話することから逃げたくない。逃げてはいけないんだ。
授業が終わると、出久は教室を出て行く勝己を追いかけた。
「かっちゃん!」と呼ぶが止まってはくれない。呼びながら廊下を追いかける。
勝己は階段の踊り場で「ああ?」と振り向いて、やっと立ち止まってくれた。
「しつこく付いて回りやがって。何が言いてえんだ」
「君の気持ちは嬉しかったんだよ、本当だよ」
「は!嬉しい、かよ」と勝己は吐き捨てるように言う。「随分余裕の口振りだよな。てめえ、優越感かよ」
「違うよ、君とは意味が違うけど、僕はずっと君とわかりあいたかったんだ。やっと君と和解したのに、こんなことでまた仲違いしたくないんだ」
「は!てめえにとってはこんなことかよ。ムカつくことしか言わねえな。クソが」
「ちが、ごめん、君を怒らせるつもりはなかったんだ。馬鹿にするつもりなんて、絶対なかった。そのことはわかって欲しいんだ」
「はあん、そうか」勝己は歪んだ笑みを浮かべる。「俺に悪く思われたくねえってか。大した偽善者だぜ」
「そんな。僕はそんなつもりじゃないよ」
「じゃあなんだ。てめえは俺にどうして欲しいんだ。俺に許して欲しいのかよ。は!随分図々しい言い草じゃねえか。おいデク、悪気がなければ、なんでも許されるなんて思うなよ」
何を言えば君に届くのだろう。どう言えば君は聞いてくれるのだろう。
「どうすれば、償えるの?かっちゃん。償えるならなんでもするよ」
思い余って紡いだ言葉は、正しかったのだろうか。
言ってすぐに後悔した。何を口走ってるんだ。僕は。償うなんておかしいだろ。
項垂れた出久を勝己は冷たく見据える。重たい沈黙が流れた。
「なんでもすんのかよ」
いたたまれなくなった頃、勝己はやっと言葉を発した。冷たい声。しかし、出久は返事してくれたことにほっとした。
「うん。僕にできることならだけど。あ、もちろん法律に触れるようなことは駄目だよ。何をすればいい?」
「じゃあてめえ、俺に抱かれるか」勝己は顔を近づけた。鼻が触れそうなくらいの距離で繰り返す。「抱かせろや。デク」
抱く、という言葉が頭の中でくわんくわんとエコーする。
「それは……無理だよ」震える声でやっと答える。
「ああ?なんでもっつったよな!てめえ」
「君に、こ、恋してないのにできないよ」
「はっ!できねえってか。できねえなら、なんでもするなんて言うんじゃねえ!クソが」
勝己の形相が変わる。爆破される?直当てから逃げられない距離だ。
「おいおい、なんだなんだ!喧嘩かよ」
「なんだか知んねえけど、まだ怒ってんのかよ、爆豪」
上鳴と切島が通りかかった。助かったと安堵する。
「うるせえ!てめえらには関係ねえ」
勝己はドンっと出久の胸を突くと、去って行った。弾みで出久はよろけ、壁に背をぶつけて尻餅をつく。
「大丈夫か、緑谷。あいつのことは熱り冷めるまでほっとくしかねえんじゃねえか。時間が立てばあいつの怒りも収まるだろうし」
「ああ、どうにもならねえことはあるからな。時間が全部解決してくれるとは言えねえけど。待つしかねえこともあるぜ」
切島と上鳴は自分を案じてくれてる。荒ぶる勝己に近寄る危険は、彼らもよくわかっているのだ。
「うん、でも時間を置いたりしたら、修復がきかなくなるかも知れない」
「うーん、そんなことねえと思うけど、いや、言い切れねえか。お前ら何年も揉めてたんだもんな」と上鳴は困り顔で腕を組む。
「もう嫌なんだ。何もしないで悪化するのを眺めてるだけなんて」
「そうか、ある意味奴と戦うってことだな。拳を交えて解決する方法を選ぶのも一理あるぜ。漢だもんな」
「ちょ、ちょっと違うよ。切島くん。でも、煙たがられても、やめるわけにはいかない」
「そっか」上鳴が肩を叩く。「理由、やっぱり言えねえのか?力になれるかも知んねえぜ」
「ううん、ごめん。言えなくて」
「そうか、でも困ったら言えよな。いつでも聞くぜ」
「ありがとう」胸がきゅうっと暖かくなる。
級友達は優しい。相談すればきっと助けてくれるだろう。でも、そのためには勝己のことを、言わなきゃならなくなる。彼がずっと隠していたことを。それだけは駄目だ。
もしかして幼馴染達のように、彼らも勝己の心に気づいているのだろうか。いや、推測するのはよそう。自分で解決すべきことなんだ。
だがその日も、勝己は頑なに出久に怒りを向けた。謝ろうとするほどに、勝己はさらに態度を硬化させていった。関係を修復する糸口すら見つからない。かえって仲はどんどん悪化していく。焦るほどに歯車が狂っていく。
徒労に終わる日々は出久を消耗させた。それでも、捨ておけないのだ。放っておいてはヒーローになれない。彼の怒りは自分の所為なのだから。
出久は寮の自室に戻ると、鞄を下ろして溜息を吐いた。今日も勝己は剣呑として、一言も出久と話そうとしなかった。
好意を持たれていた。本来なら嬉しいことのはずだ。なのに辛いだけだなんて。
何故、好意だけじゃなく恋なんだろう。
何故好意だけを抱いてくれなかったんだろう。
恋ってなんなんだろう。
子供の頃の勝己に好かれていたと聞いて、信じられないと思ったけど嬉しかった。でも恋と聞いて戸惑った。頭ではそんなに違いがあると思えなかったのに。でも心のどこかで、明確な違いを感じ取っていたんだろう。
勝己は抱かせろと言ったのだ。そんな風に自分を、見ていたのだ。
恋の正体はどんなにオブラートに包んでも、情欲なのかも知れない。恋は好意とは似て非なるものなんだ。
好意は感情で、情欲は本能だ。
ならば。性欲さえ解消できれば、落ち着いてくれるのか。
そうだ、一度抱かせればいいんだ。勝己が言ったように。
することすればスッキリするし、怒りも静まるんじゃないだろうか。自分も男だから、本能に抗えないことはわかる。男ってそういうとこがあるもんだし。
出久は立ち上がり、パソコンを起動した。小窓に検索したことのない言葉を打ち込む。
このまま険悪になるだけなんて僕は嫌だ。折角縮まった距離を諦めるなんて嫌だ。どうなるのかはわからない。でも、何もしないよりマシだ。とりあえずかっちゃんに提案してみよう。罵倒されたならそれまでだ。
それに、抱かせろなんて、言ってるだけで、いざとなれば冷静になるかも知れない。
僕は切羽詰まっていた。自分の傲慢さに気づいていなかったのだ。
3・戸惑う牙
「かっちゃん、起きてる?」
皆が寝静まった頃に、出久は勝己の部屋を訪れ、ドアをノックした。
「入っていいかな」と問うてみる。
返事はないけれど、起きてるようだ。衣擦れの音がする。ノブを掴むとくるりと回った。鍵はかかってない。
「お邪魔するよ、かっちゃん」
そろそろと部屋に足を踏み入れる。暗い室内に廊下の光が差し込んだ。
「寄んな」
ベッドの方から、低い唸るような声がした。夜の猛禽類のような、赤々と光る瞳が威嚇してくる。視線が合って怯んだが、勇気を奮って出久は後ろ手に扉を閉める。ドアの隙間から漏れる光が、闇に細く筋をつけて消えた。
「こんな夜にわざわざ来てよお、なんだデク、犯されてえのかよ」
勝己は起き上がってデスクライトを点けると、ベッドに戻って座った。
「お、か、」
直接的な言葉にぞくりとする。慄いて後退りしたのを勝己は見逃さない。ニヤリと笑って立ち上がり歩み寄ると、いきなり足を払って出久を絨毯の上に引き倒した。
馬乗りになって、見下ろしてくる勝己は悪鬼のようだ。怖くてたまらない。ひくっと喉が鳴る。
でも逃げちゃいけない。覚悟してきたのだ。出久はすうっと息を吸った。
「それで君の怒りが収まるのなら、いいよ」
「はあ?てめえ、わかってんのかよ。セックスするっつってんだぞ」
ごくりと唾を飲む。「いいよ、何をするのかはわかってるから」
とりあえず調べてはみたのだ。男同士のやり方を。正直、余計に怖くなってしまったのだけど。
「いいよ」と勝己をまっすぐに見上げる。
一回やってみたら、彼の鬱憤が解消されるかも知れないと、その可能性に賭けたのだ。グラウンドベータでの対決の時みたいに。
勝己は驚いて硬直している。意表を突けたようだ。
「わかってるだと?おい、デク」
すうっと部屋の温度が冷えたような気がした。
「かっちゃん?」
「てめえ、まさか、やったことあんのかよ。言え!誰にやられやがった!」
知ってると言ったから、経験したと解釈されてしまったのか?しかもやられたって、男にってこと?
「ないない!ないよ!なんでそうなるんだ」
「クソが!紛らわしいわ!」
「君もしたことないよね?」
「ああ?うるせえわ、クソナード!」
「ないよね?だったらさ、一回やってみようよ?ね?」
「てめえは……」
そう言いかけて勝己は黙ってしまった。冷静になると恥ずかしさが押し寄せてくる。何言ってるんだろう、僕は。まるで僕から積極的に誘ってるみたいじゃないか。かっちゃん呆気に取られてないか?
ひょっとして、抱くって言ってたのも、言葉だけで本気じゃなかったかも。
「ご、ごめん、君にその気がなければ、今のなしで」
出久は狼狽えた。顔が羞恥で熱くなる
「身体だけなら、てことかよ。てめえはまた!また!」勝己は拳を床に叩きつける。「俺を虚仮にしやがって!クソが、クソが!」
「違うよ。虚仮にしてなんかない、かっちゃん」
怒らせてしまった。また間違ってしまったのか。
だが罵倒しながらも、勝己は出久の顎を掴んで口を開けさせ、口付けた。隙間なく唇で塞いで食らうようなキス。歯がぶつかった。吐息を奪われる。
本気だ。かっちゃん。口内を這う舌の音が内側から鼓膜を震わせる。
キスを交わしながら、勝己は出久を抱き起こし、、縺れるようにベッドに倒れ込んだ。
食むようなキスが続き、音を立てて唇が離される。勝己は出久のTシャツの中に手を入れて肌を弄り、邪魔だとばかり破りそうなほど荒々しくシャツを剥いだ。体を起こして勝己もTシャツを脱ぐ。性急さに戸惑って、出久はハーフパンツにかけられた手を押さえた。
「ま、待って、かっちゃん」
「ああ?んだよ!」
出久を見下ろすギラついた瞳は、獰猛な獣のようだ。
「やっぱり難しいんじゃないかな。男同士なんて」
「ああ!今更てめえ、ざけんじゃねえ!舐めんな。できるわ!」
「もう一度確認するけど、かっちゃんも経験ないよね」
「あ?それがどうした」
「べ、勉強してからの方がよくない?」
「デクてめえ、逃げんのか。ここまできて怖気づいたのかよ」
「そ、そんなことないよ」
覚悟してきたくせに、いざとなると怖い。それを看破されている。
「もう遅えわ。クソが」
あっという間に一糸纏わぬ姿にされた。勝己も裸になり、出久の上にのしかかり身体を重ねてくる。
ひたりと直に触れる人の皮膚。引き締まった筋肉の重み。胸と腹に感じる自分より少し高い体温。下腹部に体毛と硬いものが当たってる。これは、勝己のあれだ。勃起してる。かあっと顔から火が出そうになる。
勝己の唇が首に触れて押し当てられ、ちゅうっと吸い付く。出久は目を瞑った。もう、止められないんだ。
キスは跡を付けながら、胸、腹、脇腹に降りてゆく。足が広げられ、内腿にも落ちる。唇が触れると擽ったく、吸い付かれるとちくりと痛い。吸われた跡が赤くなってる。
勝己の指がするすると出久の陰茎に絡まり擦り始める。
「わわ、かっちゃん」
人の指に触られるなんて、恥ずかしさで前を隠したくなり、上体を起こす。勝己のものが見えた。完全に屹立して存在を誇示している。出久の下腹部を弄っていた勝己は、寝てろや、と出久の胸を押してシーツに押し付ける。
人の勃起したものを見ることって、あまりない。というか全然ない。でも、かっちゃんのかなり大きくない?比較対象は自分のものくらいだけど。
「邪魔だ。手どけろよ」
無意識に勝己の手を抑えてようだ。勝己は出久の額にこつりと自分の額を当てる。間近で紡がれる勝己の声が熱を帯びている。
「あ、ご、ごめん」
括れを勝己の指になぞられ、竿を包む皮膚が擦られて、中心が熱くなってくる。顔に当たる勝己の吐息が荒い。かっちゃん、興奮しているんだ。
半分くらい勃起したところで、勝己は出久のものと自分のものとを合わせて、片手で握りこむと上下に扱き始めた。密着した陰茎の根元から亀頭まで、分厚い皮膚の掌に包み込まれる。
「あ、かっちゃっ、」
「へっ、エロい顔」
勝己は指先で、出久の先端の孔を捏ねる。
吐息とともに、出久の口からあふっと変な声が漏れた。頭の中に火花が散る。出久は登りつめ、勝己の手に射精してしまった。
「気持ちいいんか、デク」
こくりと頷くとキスをされる。キスをしながら、勝己は後孔の周囲を探る。ぬるりと指が入ってきた。
「わあ、何?」
「てめえの出したもん返してるだけだぜ」
「でも、そんなとこ触るなんて」
と言ってから気づく。男同士ならそこに入れるんだった。やはり触りあうだけでは済まないのか。
「オイルも何もねえからよ。てめえので代用すんぞ」
唇を貪られ舌を絡め取られながら、指が体内に入ってくる感覚も感じる。中と外の触覚が混じりあい混乱する。勝己は精液を後孔に丹念に塗り込んでゆく。かき混ぜられ、深く浅く嬲られる、指が増やされ、擦られる内部に熱が増してゆく。おかしくなりそうだ。
「ふあ、ふ、」
「だいぶ柔らかくなってきたな。三本も入りゃあ、いけっだろ」
三本も、いつの間に入れられてたんだろう。
足を広げられ、中心に勝己のものが押し当てられる。怒張して筋の張ったペニス。弾力のある丸みを帯びた肉の感触に、ひくっと喉がなる。
勝己が腰を振った。窄まりをぐっと突かれる。先端が入り口を広げ、精液の滑りでぬるっとめり込んだ。
「いあ、痛、痛いよかっちゃん」
身体を抉られる痛みに、出久は悲鳴を上げた。内側を広げられ、身体が軋むようだ。
「無理だよ。あ、うっ、あ」
勝己も眉根を寄せている。かっちゃん、締め付けられて君もきついんだろ。なのになんで僕に入れようとするんだ。なんでこんなことをしたいんだ。
「力抜け」と勝己は掠れ気味の声で言う。「息をゆっくり吐けよ。痛みが引くからよ」
言われるままに。力を抜いたその瞬間に、勝己が強く腰を揺すった。
ぬっと雁首が窄まりを越えて入ってくる。あ、かっちゃん嘘ついたんだ。
押し込まれ中を埋める大きさに、はあ!と息を呑む。下腹部が焼けつくようだ。
「痛えか」と勝己が聞いた。
息が詰まって声が出ない。目尻から涙が零れ落ちる。でも自分からすると言ったんだ。ふるふる、と首を横に振る。
「よし!我慢しろよ。先が入りゃあ、いけっからよ」
勝己は出久の上に覆い被さり、前後に腰を振る。抜き挿しして、体内を肉棒で小刻みに擦る。熱を擦り付ける。ぬっぬっと内壁を貫いてくる勝己のペニス。身体を引き裂いて穿たれる、熱い勃起したもの存在感。何もなかった場所に虚が作られ、勝己の身体の一部で埋められる。
勝己は顔を上げてにっと笑うと、「案外スムーズに入んな」と出久の頬を撫でた。
恥ずかしくなり、きゅっと力を入れてしまう。生々しく感じる、微かに弾力のある屹立の形。締めることでかえって圧迫が増した。「んん、う」 と、喘いでしまう。
「お、てめえな」と勝己はふうっと息を吐く。「阿呆が。まだいかせんなよ」
膝頭を掴まれさらに足を広げられた。勝己は強く局部を押し付け、さらに深く突き上げる。
たまらず「ああ!」と出久は喘ぎ声を上げた。
勝己の荒い息遣い。押し込まれる熱。後孔に勝己の陰部の金毛が触れる。少し、擽ったい。
「はあ、入ったぜ。これで逃げられねえよなあ、デク」
全部入ってしまったんだ。体内の最奥に勝己のペニスを受け入れるなんて。こんなこと、恋人でもないのに、してよかったんだろうか。今更だけど。
まるで脈打つ肉の杭に串刺しにされたようだ。捕まってしまったのだろうか。逃げて追われて捕まった、中学生の時の廊下での出来事を、なんで今思い出すんだろう。
ほっとしたところで引き抜かれ、再び挿れられ、ずんっと奥を突かれた。「んあ、あ」と出久は悶える。
「まだ序の口だぜ。デク」
勝己は腰を引いては貫いて、内部を擦り続ける。下腹部を内側から圧迫し、隙間なく埋める。肌を打ち付ける音。体内を行き来する太い肉茎。出久は「ああ、ああ」と悲鳴とも喘ぎ声ともつかない声を上げる。
勝己に犯されている。窄まりを抉り広げる雁首、引き攣れる竿の皮膚。揺さぶられるたびに彼の陰嚢が尻を打ち、音を立てる。
痛くて堪らないのに、奥深くから快感が湧き上がってきた。痒いような痺れるような初めての感覚。吐息に甘い声が混じる。
「えっろ」と勝己は艶めいた笑みを浮かべた。
感じたのが恥ずかしくなる。喘ぎ声が漏れそうになり、歯を食いしばった。気づいた勝己が低い声で促す。
「デク、我慢すんじゃねえ、声出せよ」
妖しく鼓膜を擽る囁き。そんな、快感に喘ぐ声なんて聞かれたくない、と首を振る。舌打ちして勝己が口付けする。深く口内を侵すキス。舌を絡めながらも、勝己は容赦なく突き上げる。喘ぐ声が勝己に呑み込まれる。
唇が離れた。かっちゃん、と名を呼ぶ。自分じゃないような掠れた甘い声。
「いい声出すじゃねえか。気持ちいいんかよ。デク」
勝己は嬉しそうに笑う。「初めてで気持ちいいとか、素質あんじゃねえか」
「わ、わかんない。や、あ、あ」
手首を掴まれシーツに押し付けられた。途端に勝己の腰を揺するスピードが上がる。
「あ、ああ!」と嬌声を上げてしまう。
ずり上がれないように固定され、身体を揺さぶられる。熱の塊に内壁を抉られ燃えるようだ。体内を行き来する勝己の一部。結合した部分から侵食されていく。身体の中を抉っては擦り、火をくべて熱を残して引き抜き、また熱を押し込んでくる。
「てめえの中でいくからな」と勝己は呟いた。
接合部を押し付けて、勝己は低く呻く。ぶるりと中でペニスが膨れたような気がした。注がれる熱い飛沫。身体の中が濡れてゆくのを感じる。
僕の中で射精したんだ。人の身体の中に出すなんて。かっちゃん、そんなことできちゃうんだ。雄のマーキングみたいなものなのかな。精液なんて、ティッシュでくるんで捨てるものとしか思ってなかった。
ぬぷりと性器が引き抜かれ、圧迫感から解放された。
脱力した身体がずしりと重ねられる。ふうっと首元で勝己が息をつく。
この生々しさが恋なんだ。
好きということと恋じゃ全然違うんだ。
疲労で手足が重い。頭に霞がかかったようだ。
ポツリと勝己が呟く。「自己犠牲かよ。反吐が出るぜ」
ぎゅうっと抱きしめられた。抱き潰されそうだ。
「かっちゃん」出久は呼んでみた。喘ぎ過ぎて、声が枯れている。
「デク、デク」と勝己は呼ぶ。どちらのものとも知れない汗で濡れた肌。
背にまわされた皮の分厚い勝己の掌が、じわりと熱を帯びてゆく。
「殺す。てめえを殺してやる。クソが」
かっちゃんの怒りは収まらなかったのか。情欲を解消しても。そう簡単にはいくはずなかったんだ。全然簡単じゃなかったけれど。
うっすらとニトロの香りが漂う。かっちゃんの掌が汗ばんでるんだ。このまま爆破されるんだろうか。くっついてたら、かっちゃんも火の粉を浴びるけれど。疲れて動けないから避けられないな。
でも怖いと思わない。何故だろう。不思議だ。
出久はすうっと意識を手放した。
4・ぬかるみの足跡
翌朝。目覚めると間近に勝己の顔があった。吃驚してひゅうっと息を呑み、硬直する。
「やっと起きたんかよ、デク」
「う、ん、おはよう」
昨晩は勝己の部屋で寝てしまったのか。ふたりとも裸のままだ。いつから寝顔を見られてたのだろうか。
背中は、痛くない。爆破されなかったんだ、とほっとする。
「てめえ、寝落ちしやがって。クソが」
勝己の口調は落ち着いている。文句を言ってるけれども、言葉に棘はない。機嫌が治ってるようだ。
勝己は出久の背中に腕を回し、ぎゅうっと抱きしめてきた。身体が密着する。目の前に綺麗な鎖骨。分厚い胸。身動ぎすると、力強い腕が逃がさないとでも言うように、封じ込めてくる。
微かに甘い、勝己の匂いだ。
「朝飯食いにいくか?」
と話しかけられ、コクコクと首肯する。やっぱり機嫌がいい。
嵐のようだった昨夜の行為。最初の噛みつくようなキスに、きっと酷く扱われるだろうと覚悟していた。手荒いセックスを覚悟していた。だが、入れられた時はすごく痛かったものの、前戯は念入り行われたし、挿入した時も痛くないかと聞かれた。思いの外優しい抱き方だった。
「折角の機会なんだから、楽しまなきゃ損だろうが。童貞」
出久の思考を読んだように、勝己は揶揄ってくる。勝己は出久の額にキスをして腕を解くと、ベッドから抜け出して、立ち上がった。
「君もだろ」と言って見上げると、勝己のペニスが目に入った。どきりとして目を逸らす。
昨日の勃起した状態と違い、通常の形に戻っている。あれが昨夜僕の中に入って、暴れ回ってたんだ。君と身体を繋げたなんて信じられない。今更ながら頬が熱くなる。
「今更なに照れてんだ、てめえ」
勝己はニヤッと笑い、腰を揺らして振って見せる。子供みたいだ。
「腹減ったな」と言いながら、勝己は脱ぎ散らかした服を拾って、身に付けている。
自分も服を着なきゃ、と出久は腰を上げようとしたが、股の間に違和感を感じ、「うわあ」と呻いて突っ伏した。まだ挟まっているかのような感触が、昨晩の出来事を現実なのだと突きつけてくる。
勝己は呆れたように笑うと、散らばった出久の服を「さっさと着ろよ」と投げて寄越した。礼を言って受け取り、そそくさと身に付ける。
「まだ時間あるし、さくっとシャワーでも浴びに行くか、デク」
「そうだね。汗かいちゃったし」
立ち上がろうとして、痛みに足元がふらついた。ざまあねえな、とにやつく勝己に腕を支えられる。
風呂場を出て、上機嫌の勝己と廊下を連れだって歩く。尻の痛みはシャワーを浴びたおかげで、幾分か和らいだ。
出久は自分に言い聞かせる。僕は間違ってなかったよね。
食堂の入り口で、丁度出てきた上鳴とすれ違い、声をかけられた。
「うっす、お揃いで珍しいじゃねえか、爆豪、緑谷」
「おはよう。上鳴くん」
「でもおせえじゃん。俺もだけどよ。ちょっと寝坊しちまってよ。皆先に食って、学校行っちまったぜ」
「ね、寝汗かいたから、シャワー浴びてたんだ。朝浴びると気持ちいいよね」ちょっと狼狽えて早口になる。
「そっか。爆豪、なんか機嫌いいじゃねえか。お前ら仲直りしたのかよ」
「うっせえ、クソが」
「う、うん。おかげさまで」
「何が原因だったのか、やっぱり言えねえか、緑谷」
「うんまあ、大したことじゃないんだ。心配かけてごめん」
「おい、遅えんだろうが、無駄口たたいてんじゃねえ。行くぞ、デク」
勝己に腕を肘で突かれる。
「うん、じゃ、上鳴くん、学校でね」。
「緑谷、あのよ」と上鳴は言いかけて口籠り、再び口を開く。「俺が言えることでもねえな。よかったな、爆豪。もう喧嘩すんなよ」
「うるせえわ。飯食ったんだろ、さっさと行けや」
朝食を乗せたトレーを持って勝己は席に着き、腕を引っ張ると隣に出久を座らせた。勝己と隣あって食べるなんて久しぶりだ。合宿以来だろうか。
パンを齧りながらふと思い至る。ひょっとして、さっき上鳴くんは僕じゃなく、かっちゃんによかったなって言ったのだろうか。
気づいているのかも知れない。いつも勝己の側にいる彼らだ。でも聞かないでいてくれるのも、きっと優しさなのだ。どこまで知ってるのかなんて聞けないけれど。
でも、ほんとにこれで良かったのだろうか。セックスはしたけれど、勝己の意に沿えるわけじゃない。機嫌はいいのは一時的なもので、また怒り出すのかも知れない。その場しのぎに過ぎないのだ。でも他に方法を思いつかなかった。
その日の勝己は出久だけでなく、周りに対しても穏やかだった。久々に訪れた平和な日だった。
性欲を解消したからだろうか。即物的な方法だったけれども。これで良かったんだ、と出久は安堵した。
しかし、その安堵はほんの短い間だった。
放課後になり、寮に戻ると勝己が玄関先で待っていた。
「かっちゃん?どうしたの?」
勝己はこっち来いとばかりに指を曲げる。出久が側に歩み寄ると、肩を抱き、耳元で囁いた。
「おいデク、後で部屋に来いや」
「え?なんで」
「わかんだろーが」
出久は驚いて離れようとしたが、肩を強く掴まれ、逃れられない。
「あれは、一回だけのはずだよね?」
「ああ?何言ってんだてめえ」
勝己に腕を取られ、引きずられるように部屋に連れ込まれる。
「誰が一回で終いだっつったよ。俺の気の済むまで、てめえは俺の相手をすんだよ」
「でも、僕は君をそんな風には思えないんだよ」
「てめえの気持ちなんか知るかよ!」
「かっちゃん、でも」
「俺は一生言わねえつもりだったんだ。暴いたのはてめえだ。面白半分によ」
「そんな、面白半分になんて、違うよ」
「償いてえんだろ。許して欲しいんだろ。おら脱げ!今からセックスすんだよ」
勝己は出久をベッドに突き飛ばし、ズボンのベルトを外した。戸惑う出久に覆い被さると、口付ける。確かに一度だけなんて約束はしてない。ならばもう一度と言われても呑むしかないのか。
うつ伏せにされ、丹念に慣らされ、背後から貫かれる。
揺さぶられるほどに、身体を穿ち、埋めてゆく。
最奥まで抜いては挿れられる質量。
汗ばんだ身体に被さる重みと、名を呼ぶ熱を含んだ声。
熱い楔は緩やかに身体を穿ち、奥深くで動きを止める。
背後から抱きしめる腕は、離してはくれず、出久が身じろぎすると、さらに力が籠められた。
勝己は落ち着いた。これまでの荒れようが嘘のように。
無闇に人に噛み付かなくなったので、クラスメイトもほっとしている。
だが、元に戻ったわけではない。疲労が激しい時以外は、出久は毎夜のように性交を求められた。二度目の時に宣告されたのだ。勝己の気の済むまで続けるのだと。出久に断る道理はなかった。
とはいえ、勝己は口調は荒いが抱き方は優しく、事後はとても機嫌がよい。断る理由はもはやなかった。
「かっちゃん」と呼びかける。
ちゅぷちゅぷと下肢からしていた音が止み、ペニスを包んでいた熱が離れる。
「気持ちいいなら言えよ、デク」
部屋に入るなり、出久はべッドに押し倒された。すぐさまハーフパンツと下着を脱がされる。
剥き出しになった下肢に顔を埋め、勝己は口淫を始めた。勝己の舌が巧みに出久のものを舐め回す。深く咥えて、頬を窄めて前後に絞る。鮮烈な快感に支配される。
「かっちゃん、やめ、出ちゃう」
勝己はほっておくと、時々吸い上げて呑んでしまう。でも、やはり人の口の中で果てるのは抵抗がある。恥ずかしさと罪悪感が伴う行為。
「やめ、てよ、かっちゃん、離して」
出久が必死で頼むと、登りつめる前に止めてくれた。ほっとする。だが、括れをきゅっと指で圧迫して、射精を許してくれない。中心に熱が篭って辛くなってきた。哀願するように勝己を見つめる。
「いきてえか」
と問われ、こくんと頷く。
「なら俺のもしろや、デク」
勝己はボクサーパンツを脱いでベッドサイドに立ち、意地悪そうな顔で見下ろす。
半端な状態で堰き止められた。出してしまいたい。でも勝己の前で、自分で扱いていけるわけがない。
身のうちに暴れる熱を堪えつつ、身体を起こし、勝己の前に跪く。フェラチオなんてまだしたことない。でもかっちゃんは僕にしてるんだ。僕もやらなきゃ。
そそり立つ彼のものをそっと掴む。目の前で見るとより大きく感じる。思ったより口を大きく開けなきゃ入らない。頬張るように咥える。
口内に導くと、案外咥えられるもんだなと思う。先端を舐め回し、括れの溝に沿って舌先を這わせ、血管を辿るように滑らせる。勝己がくくっと含み笑いをした。
「てめえ、よくしゃぶれるよな」
勝己の言葉に、かあっと頬が熱くなる。
「君だってしてただろ」
「ああ、文句あんのかよ。俺はいいんだよ。てめえの急所、食らってやるつもりでしてんだからよ」
にやっと悪戯っぽく口の端を上げて勝己は笑う。「いつ噛みついてやろうかってな」
本気だろうか。きゅっと股が縮こまる。
再び勝己のものを口に含んで舐め、竿を半分くらい頬張る。
「なあデク」熱に浮かされたような声で、勝己は囁く。「こうすんだよ」
勝己は出久の頭を掴んで、前後にゆっくり揺すった。
「ん、んー」口内を行き来する勝己のもの。主導権を奪われ、喉の奥を突かれそうでちょっと怖い。舌先に濃い海水のような先走りの味がした。
「全部飲めよ」と勝己は低く囁く。
ぞくりとして見上げると、「はっ、ビビったんか。冗談だ」と勝己は言い、出久の口を解放した。
出久の唇を親指でなぞり、勝己は言う。「俺は全然飲めるぜ。てめえは嫌かよ?」
さっきはびっくりしたけれど、嫌だったわけじゃない気がする。出久が首を横に振ると、勝己はニヤッと片頬で笑う。
「上も脱げよ」と勝己は出久のシャツを上に引っ張り、剥ぎ取った。
二人とも裸になり、立ったまま抱き合いキスを交わす。肩甲骨から腰回りまで勝己の掌に愛撫される。
カーテンを閉めてるとはいえ、裸のシルエットが外から見えてしまいそうだ。内心焦ってしまうが、勝己は気にならないのだろうか。
口づけを貪りながら、勝己は出久の尻を掴んで揉み、出久の後孔を指で探った。突いたりなぞったりして弄ぶ。
かっちゃん、もう入れる気なのか。でもまだベッドに移動しないのかな、と思っていると、勝己は出久をくるりと後ろを向かせた。
背後に立って腰を掴み、「机に手をつけよ」と言う。
ドキッとする。ここで入れるつもりなんだ。
広い机の上に置いてあるのは、ノートパソコンだけだ。机の角が面か、どこに手を付けばいいのか迷い、机の上を撫でる。
この姿勢は、立ちバックって言うんだっけ。すごく恥ずかしいんだけど。振り返って、縋るように勝己の顔を見つめる。勝己は悪戯っぽく笑い、くいっと顎で促す。
仕方なく、出久は腰を曲げて、机の上に手をついた。勝己は尻の肉を掴んで割り開き、陰嚢から後孔まで撫で上げる。擽ったくて、あふ、声を上げてしまい、勝己に聞かれたかと焦る。
勝己は窄まりにぐっと指を入れて確かめると、「いけそうだな」と言うなり勃ち上がったものを押し当て、挿入し始めた。
窄まりをゆっくりと広げられていく感覚。圧迫感が堪らず、はあ、と吐息が溢れる。
ゼリー付きのコンドームをつければ、さほど慣らさなくても入ってしまう。勝己の大きさに身体が慣れてしまったのだろう。痛みもあるけど擦られると気持ちいい。
でもまだ中はまだそんなに柔らかくないから、穿たれる感覚は鮮烈だ。
勝己のペニスが内壁に引っかかるように入ってゆく。出久は動きに合わせて「ん、ん、」と小さく喘ぐ。
体内にある勝己の形と感触を、生々しく感じてしまう。太さ、硬さ、覚えてしまった勝己の存在感が堪らない。
勝己は出久の肩を掴んで、腰を打ち付ける。初めてこそ生で挿入された上に中出しされたが、今はいつもコンドームを使ってくれる。
「立ったままだと絨毯汚しちゃうよ」
勃起した自分のものから先走りが出てきた。片手で先を押さえるが不安になる。
「ああ?細けえこと言ってんじゃねえよ」
「でも。気になるよ」
「じゃあ、つけてやるわ」
勝己はコンドームのパッケージを噛み破って、後ろから手を回し、出久のペニスに器用に装着した。
「いっちまえよ」
勝己は耳元で息を吹きかけると、性器を扱きながら、雁で体内の前立腺の膨らみをぐりぐり突き上げ、出久の射精を促す。
「あ、あ」と喘ぎ、出久はコンドームの中に吐精した。途端に勝己に強く突き上げられ、ひあっと悲鳴をあげる。
激しく突かれて脱力した身体を支えられず、机に突っ伏す。ガクガクと激しく揺さぶられる。深くはゆっくりと、浅くは激しく、巧みに攻められる。
「いくぜ」と勝己は告げると、ズンッと奥を何度も突き上げた。
デク、と呟いて、勝己は背中に覆いかぶさる。達したのだろう。触れている勝己の胸がビクビクっと震える。
背中に感じる鍛えられた筋肉。汗ばんだ皮膚がひたりと吸い付く。再びデク、と呼ぶ声と共に、首筋に熱い息が吹きかけられる。
勝己とのセックスは、優しかったり激しかったり、日によって気まぐれだ。
ベッドですることが多いけど、今みたいに違う場所ですることもある。明かりをつけたままでされたり、姿見の前で挿入されたり、恥ずかしくなるようなこともする。
でも、なるべく勝己がしたいようにさせた。セックスした後の彼は機嫌がいいからだ。出すもの出せばすっきりする。即物的だが男の生理とはそういうものだ。
けれども、これでいいのだろうか?
一度だけだと思ってたのに、もう何回彼としたのかわからない。
気持ちが伴わないのに、身体だけが慣れてくるのだ。身体を重ねることに、受け入れることに。ペニスを咥えるなんてこと、ちょっと前ならとても考えられなかった。
本当にこれで良かったのだろうか。
泥濘に足を取られて這い上がれなくなるのではないだろうか。
迷いは膨らみ、煩悶は澱のように沈殿していった。
5・甘噛みと囁き
ある日から、ぱたりと勝己は出久を誘わなくなった。
寮に帰っても挨拶程度の話しかせず、ましてや色事を匂わせるようなことは、全く言わなくなった。
始めはその気がない日もあるのだろう、と思った出久だったが、毎日のように部屋に連れ込んで抱いていたのだ。何もない日が何日も続くと、何か気に触ることをしたのだろうか、と不安になってきた。思い出せる限り身に覚えはない。
勝己は怒ってる様子もなく、出久を無視するわけでもない。気まぐれに過ぎないのだろうか。
出久は戸惑った。勝己の真意がわからない。セックスのことなんて聞きにくいのだけど、気になってしまう。
「あの、かっちゃんいる?」
ドアをノックすると、「入れよ、デク」と中から返事が返ってきた。ぶっきらぼうだけれど、不機嫌ではないようだ。
「あんだ?デク」
勝己はベッドに座っており、出久を見据えて促す。どう切りだそう。意を決して勝己の部屋に来たけれど。
「かっちゃん、その、もうしないの?」逡巡したすえについ直球で問うてみる。
「あ?何をだ?」
「その、あれのことだけど」出久は言葉を探すが思いつかない。
「あー?セックスしてえのかよ」
「そ、そういう意味じゃないよ。その、もういいのかなって」
「へえ」勝己は目を細める。「セックスじゃねえならなんだ」
「ごめん、好きでも、毎日したいわけじゃないよね、じゃ」
恥ずかしくなって、部屋を出ようとする出久の背中に「待てや、デク」と勝己は呼びかける。
「てめえ、勘違いしてんだろ」
「なんのこと?」出久は振り返った。
「てめえ、俺がてめえを好きでやってたと、思ってんのかよ」
「かっちゃん?」
勝己は悪辣な笑みを浮かべた。勝己が勝利を確信して、相手に勝ち誇る時の表情だ。嫌な予感がした。
「はっは、俺がいつてめえを好きだと言ったよ」
「え?だって君が」
いや、確かに勝己ははっきりとは言ったことはない。でも、そんなこと。一体彼は何を言ってるんだ。
「俺は一度もてめえを好きだなんて、言ったことねえよなあ、デク。てめえが勘違いしただけだろーがよ」
「でも、かっちゃん」
指先が冷たくなってゆく。
勝己は嘲笑った。「はっは!俺に抱かれてよがって、気持ちよかったんだよなあ。デク!雌みてえに俺のちんこ咥えこんで、悦んでたもんなあ」
何も言葉を発せられない。頭が熱くなってくる。喉に石が詰まったようだ。
「だって君は。君がそうだと思ったから、だから僕は君に抱かれたんだ」
なんとか言葉を絞り出す。そうじゃなければ、何故抱かせろなんて言ったんだ。何のために自分は抱かれたんだ。勝己は膝を叩いて笑う。
「はっ!いい気になってたんだろう。俺に抱かせてやってるつもりだったんだろーが。好かれてると思い込んでよ。馬鹿はてめえだ。まんまとてめえで童貞捨てさせてもらったわ!」
勝己の言葉が突き刺さる。勝己は自分嘲笑うために抱いたというのか。
指先を凍らせた冷気が腕を登って胸に届く。すうっと心臓が冷えてゆく。足元が崩れて沈み込んでしまうような錯覚を覚える。
勝己の笑い声が頭に反響する。
立ってられない。もうこれ以上ここにいられない。
「そっか。君がもういいなら、もう終わりなんだね」
「ああ?」
「でも、男相手で童貞を捨てたことには、ならないと思うよ。かっちゃん」
平静を保とうとしても声が震える。勝己の顔を見られない。踵を返して部屋を出ると
出久は廊下を駆けた。
後ろから勝己の怒鳴り声が聞こえる。でも振り返ってられない。
足早に階段を駆け下りて自室に駆け込み、ベッドに突っ伏した。
好きではなかったと勝己は言った。恋じゃなかったのか。自分が勘違いしてただけだったのか。
でも最初に恋という言葉をうっかり口にしてしまい、否定してしまった時の勝己の怒りは、本物だったのだ。無駄な偽りを言う彼ではない。なら、答えは一つだ。
抱いて想いを遂げたから醒めたのだ。もう恋はなくなったのだ。
もとより恋というのも、ただの子供の頃からの、思い込みだったのかも知れない。彼にとっても不本意な思いだったんだ。
これで良かったんだ。
溜まっていた諸々を解消されて、かっちゃんの怒りは収まったのだ。僕はもう自由になったのだ。
なのに。解放されたはずなのに。思いのほか傷ついている心に気づかされる。ほろほろと涙が溢れて止まらない。刀で裂かれたように、胸が痛む。
ああ、今の僕は君に恋をしているのだ。君をそんな風に思ってなどなかったのに。
悲しくて苦しくて堪らない。終わってしまってから気づくなんて。
望むと望まざるに関わらず、恋は予期せぬ時に嵐のように心を蹂躙するものなんだ。まるで災難のようだ。
「身体で堕ちるなんてあんまりだ」
声に出してみる。言葉にするとなんて月並みなんだろう。
ああ、そうか。肌の触れ合いも人の交流方法のひとつなのだ。
君の体温が、睦言が、身を貫く熱が。言葉じゃ伝え合うことのできない、君との唯一の対話の方法だったのだ。
「馬鹿なのは僕だ」
僕の愚かさを君はわかっていたんだろう。君のことを慮るのなら、たとえ長くかかるとしても、僕は君の心が整理されるまで、待つべきだったのだ。二度と心を開いてくれなくても、甘んじて受けるべきだったのだ。
でも僕は待てなかった。君との関係をもう二度と悪化させたくなかった。取り返しようがなく距離ができてしまうことを恐れた。
でもそれ以上に、僕は君を傷つけた悪者になりたくなかった。罪悪感に苛まれたくなかった。きっと君のためなどではなかったのだ。
自分のために人の心を操ろうとするなんて傲慢だ。だからこうなるのは当然のことなんだ。偽善者の報いなんだ。
涙の雫で枕が濡れてしまった。
かっちゃんとのことはもう忘れよう。過ちは償ったのだ。かっちゃんは僕を貶めて、気は晴れただろう。
今夜は無理だけれども、涙が止まらないけれど、明日になればきっと立ち直れる。
「大丈夫。僕なら大丈夫だ」声に出してみる。暗示をかけるように繰り返す。「大丈夫。何もなかったように、元に戻れるはずだ」
僕らの間には、何もなかったんだと思えるようになれる。
「デク!てめえ!」
バタンと勢いよくドアが開けられた。目を釣り上げて、勝己が立っている。
「かっちゃん?な、何だよ」
「はっ!なんだてめえ、べそかいてんじゃねえかよ。泣き虫がよ」
出久の顔を見て、勝己の形相が和らぎ、得意げに嘲笑う。
「こ、これは別に、なんでもない。何しに来たんだ」
急いで身体を起こして涙を拭った。勝己はズカズカと部屋に入ると、出久の肩を掴み、どすんと押し倒す。
「な、何?なんのつもりだよ、かっちゃん。君とはもう関係ないだろ」
「ああ?なんだてめえ、その言い草はよ。謝るときはしつこく食らいついてきたくせによ。今回はあっさり引き下がりやがって。クソが!」
「だって、もう僕らは終わったんだろ。かっちゃんの気は済んだろ。これ以上何だよ」
「はあ?ボケカス!勝手に終わらせてんじゃねえわ。誰がやめるっつったよ。クソが」
「かっちゃん?」
「てめえはほんとにカスだな。んなこったろうと思ったわ。自分から手の中に転がり落ちて来た馬鹿を、この俺が逃すわけねえわ!」
勘違いだと言ったくせに、訳がわからない。
「君に恋心がないのならもう付き合う理由がないよね?」
「あるわ。おいデク!てめえ、俺に抱かれたいんだよなあ。認めろや」
「かか、かっちゃん?意味がわからないよ」
「抱かれてえんだろが!デク、てめえさっき身体で堕ちたっつったよな」
「き、聞いてたの?」
勝己はいつからドアの外にいたのだろう。まるで気づかなかった。こっそり来て聞き耳を立てていたのか。どこから独り言を聞かれていたのだろうか。
「違うよ、あれは」
顔がかあっと熱くなる。どう言い繕えばいいんだろう。
「てめえ、自分で恋に堕ちたと思ってんのか?」
「え?どういう意味」
「はっは!てめえは勝手に堕ちたんじゃねえよ。俺がてめえを堕としたんだ。てめえは堕とされたんだ、この俺によ」
「かっちゃん?何言ってるの」
「てめえがいきなり部屋に来て、俺にやっていいって言いやがった時、マジで殺意が湧いたぜ。ンなことあっさり言えるってことがよ。てめえにはその程度のことなのかよってな。これ以上ねえってくらいムカついて、てめえをめちゃくちゃにしてやろうかと思ったわ」
「ごめん、かっちゃん」
今ならどれだけ心無いことを言ったのか、理解できる。
「だけどな」と勝己は続けた。「思い直したんだ。てめえは贖罪にきたんだ。てめえ勝手な贖罪だがよ。乱暴にしたら、てめえの思い通りになっちまう。一度抱いただけで済ませてたまるかってんだ。だから、てめえを堕とすことにしたんだ。計算通り、てめえはまんまと堕ちた。認めろよ、デク。俺に抱かれてえんだろうがよお。なあ、そうだろ、クソナード」
「かっちゃん」
「俺はてめえが好きじゃねえ!全然好きじゃねえわ!でも、てめえは俺を好きなんだろ。欲しいんだろうが。そう言えや。肯定しろやデク!」
好きじゃないと言いながら、堕としたという。認めろと迫り、僕に好きだと言わせようとする。矛盾してる。むちゃくちゃだ。
でも。僕はほっとしている。かっちゃんの恋が醒めたんじゃないということに。
君が僕を欲しいと思うように、今は僕も君を欲しいと思っているんだ。君がここに来てくれたことを、理不尽な言葉を、嬉しいと思ってるんだ。
君の思惑にまんまと乗せられたのかも知れないけれど。もう墜ちる前に戻れはしないんだ。
出久は肯定の返事として、こくりと頷いた。勝己は満足そうに口角を上げる。
「はっは!デク、デク!もう今までみてえに手加減してやらねえ。コンドームなんざつけるかよ。一晩に一回で足りるかよ。これからだ。全部これからだ。俺が飽きるまでずっとてめえは俺のもんだ。飽きなきゃあ一生、死ぬまでずうっと俺のもんだからな。覚悟しろや」
勝己は勝ち誇ったように笑う。
あれ?条件が酷くなったようだぞ。かっちゃんにしては優しいやり方だと思っていたけど、やはり手加減してたんだ。
勝己は出久の唇を食むように甘噛みし、がぶりと噛み付くように深いキスをする。
口腔を荒々しく暴れる舌。最初の交わりの時のような濃厚な口付け。息を奪われる。窒息しそうだ。
漸く唇が離れ、開放されてやっと空気を吸い込む。
赤い瞳が返事を促すように見下ろす。
彼は相当押さえていたのだ。それは今のキスでよくわかった。今後は容赦しないと、そう目で告げている。
本気のかっちゃん相手に、どうなっちゃうんだろう。でも怖くはない。
「うん、わ、かったよ」
呼吸がまだ戻らない。途切れ途切れに言葉を紡ぐ。勝己はすうっと目を細める。
再び唇の触れそうなほどかがみ込み、吐息混じりの声で囁く。
「でも、ちったあてめえの言うことも聞いてやるわ。言えよ、デク。俺にどうして欲しいんだ」
ああ、彼は僕の何倍も我儘で傲慢で、一枚も二枚も上手だったのだ。
6・橙色の思い出
「疲れたよ、かっちゃん」
ふうふうと息を弾ませて、僕は前を歩くかっちゃんに呼びかける。
裏山を流れる川の上流に遡って、随分と歩いてきた気がする。
鶺鴒だろうか。川面をついっと滑るように飛んでいる。
セキレイ。イザナミとイザナギが、尾を振るの見て何かを知ったんだっけ。前にかっちゃんが得意げに教えてくれたけど、思い出せない。
川べりの岩が下流に比べて、かなり大きくなってきた。ゴツゴツした岩で足が滑りそうになる。
ふいっと前を赤蜻蛉が横切った。
「だらしねえな、デク」
かっちゃんが手を伸ばした。僕はその手に縋るように捕まる。肉厚な掌はしっかりしてて頼もしくて、安心する。
そのまま手を繋いで歩を進めた。川の流れが次第に細くなり、岩を穿った小ぶりな滝に繋がってゆく。
ようやくかっちゃんは立ち止まった。着いたぜ。と顎をしゃくる。
見上げると、空を覆うように2つの大きな岩が聳えていた。大きな岩と岩は寄り添うようにくっついている。岩の間に挟まれて、人がやっと通れるくらいの隙間があり、隙間の向こうには遠く山の端が見える。
「もうちょっと待てや。そろそろだ」
「何?何か起こるの?かっちゃん」
「黙って見てろや」
かっちゃんはウキウキしてるみたいだ。
ふと、岩の隙間の上部がキラリと光った。
「何なに?」
隙間を覗いてみると、紅色の夕陽が見えた。陽が降りるに連れ、眩しく光が射し込んで広がり、両方の岩肌を橙色に塗りつぶしてゆく。美しさに疲れも吹っ飛んだ。
「すごく綺麗だね。かっちゃん」
「こないだ山登ってて、ここを見つけたんだぜ。俺の特別な場所だ」と言い、くるっと僕を見る。「てめえだから見せてやんだからな」
かっちゃんは得意げだ。特別と聞いて嬉しくなった。手を繋いだまま、しばらく見惚れているとかっちゃんが口を開いた。
「デク、見せてやったんだから、てめえの特別を寄越せよ」
「え?見返りがいるの?」びっくりして聞き返した。
「たりめーだ、クソが!」
頼んだわけでもないのに、お礼を要求されるんだ。やっぱりかっちゃんだった。
とはいえ、夕陽はとても綺麗だし、かっちゃんの言葉が嬉しかった。
僕にも彼に見せられるような、いい景色はないだろうかと考えてみたが、思いつかない。
「ごめん、かっちゃん。僕は素敵な場所なんて知らないんだ」
「クソが。場所じゃねえ」
「じゃあ、もの?」まさかと思って、恐る恐る聞いた。「僕のオールマイトのフィギュアとか?」
「クソが!てめえのお宝なんぞいんねえ。俺はてめえみてえなコレクターじゃねえよ」
「でも、僕は何も持ってないんだよ」
君と違って、という言葉は飲み込む。ここで言う言葉じゃない。
「あんだろ。てめえの特別を寄越せって言ってんだ」
「だから、持ってないよ」
かっちゃんはふくっと膨れてしまった。
「わかんないよ。かっちゃん」
「クソナードが」
それっきりかっちゃんは黙ってしまった。視線を僕から外して、岩に向けてしまう。怒ったのだろうか。そっと顔を伺う。
眉間に皺は寄ってないし、そんなに機嫌を損ねたわけじゃないようだ。
かっちゃんは僕の手をきゅっと握り直し、そのまま一緒にポケットに入れた。ジャンパーの中で、かっちゃんの手がすりすりと僕の手を摩る。
川からの風で思ったより冷えていたみたいだ。かっちゃんの体温に手が温められる。
「特別を寄越せや」
かっちゃんはぽつりと繰り返す。
岩の隙間から覗く橙色の空が朱い色に染まってゆく。
夕陽は色の白い幼馴染の頬も赤く染めていく。
END
習作・人形遊戯(R18)

勝己は車の後部座席のドアを開け、抱えていたズシリと重い人形を座席に積んだ。
グズグズしちゃいられない。急がなければ。運転席に移動してエンジンをかける。
雪の結晶がちらほらと目の前を舞った。
クソが、もう追いついて来やがった。
廃ビルの窓を破壊して氷柱が飛び出し、みるみるうちに夜空に氷のスロープが伸びる。氷の道は車の前の地面に、地響きを立てて突き刺さった。
ビルの窓から人影が降り立ち、スロープを滑り降りてくる。
轟の野郎、ムカつく奴だ。あっという間に距離を詰めやがった。爆速でここまで走ってきたというのに。
轟はジャンプして、ボンネットの上に降り立った。
「おい、爆豪」
「そこどけよ轟。止めんのかよ」
「いや、止める気は無い。俺も行く」
「はあ?」
「1人では緑谷にかかった個性を、解除できないはずだろう、爆豪」
勝己は歯噛みする。その通りだ。
「くそっ勝手にしろ。てめえに出来んのかよ」
「できる。緑谷のためだからな」そう言うと轟は助手席に乗り込んだ。
「クソが!ボンネットに足跡つけやがって!」
「すまなかったな。何処に行くつもりだ」
「俺んちだ、クソが!仮にもヒーローがこんな人形持って、ホテルに入れるかよ」
後部座席を振り返り、寝かせた人形を見て轟は微笑む。
「本当に緑谷にそっくりだな。目を瞑ってる姿は、高校の頃からほとんど変わらないな」
抑揚の希薄な口調に、優しげな色が朧気に滲むのがなんとなく不快だ。いや、ものすごくムカつく。
クソデクが。全く間抜けな奴だ。後先考えねえで飛び出しやがって。いつだって世話を焼かせやがる。
「幼馴染なんだってな。昔からあんななのか緑谷は」
高校一年生の体育祭の時に、轟は勝己にそう言った。出久と戦って、奴の抱えてきたものを壊された直後に。
憑き物の取れたように穏やかな声だった。腹が立った。
ああ、その通りだ。てめえの知らねえ昔から何度も何度も、あいつに俺はぶっ壊されてきた。こうありたいという理想は、あいつへの衝動で無茶苦茶になった。自分が濁って汚れていくような苦痛を、てめえは知らねえだろう。
堪え難い執着と屈辱と、理想像とは違う俺を受け入れるのは、出久への衝動に名前を付けることと同義だった。
一回ぶっ壊されただけのてめえとは、レベルも年季も違うんだ。
「もう一度聞くがな。何すっかわかってんだろうな」
「当然だ。聞くまでもないだろう」
「クソが」平然と言ってのけるのが忌々しい。
「恩を返したいからな」
轟は車窓に目をやる。轟の視線の先。廃ビルの下には警察車両が集まっている。出久の本当の身体もあそこにある。
恩返しなんざ、今じゃなくていいじゃねえか。別の機会にやれや、と勝己は心の中で毒づいた。
出久はヴィランを単身でアジトまで追い詰めたが、返り討ちに遭い、敵の個性にかかった。
轟と勝己が駆けつけた時には、既に出久の身体はぐったりとした、動かない抜け殻となっていた。
ヴィランの個性は己の作った人型の人形に、相手の姿形の意識と感覚を同調させるというものだった。つまり意識はこの出久の身体にはない。
追ってきた勝己と轟の姿を認め、ヴィランは得意げな顔から一変して顔色を変えた。逃走しようとしたヴィランを「てめえ!死ねやあ!クソカス!」と勝己は爆破で吹っ飛ばした。
ヴィランは壁に叩きつけられ、壁にめり込んだ。衝撃で壁は放射状にひび割れて崩れ、ヴィランはコンクリートの欠片ごと落下した。
「おい、てめえ、デクはどこだ?いや、デクの入った人形か。どこだ。起きろクソが」
勝己は昏倒したヴィランを揺さぶった。
「この倉庫の人形の中にあるんだろう」
轟は落ち着いて答えた。勝己はヴィランから手を放し、轟は手錠と縄を出して犯人を拘束し始めた。
「クソが」
やっと人形の保管倉庫を突き止めたというのに、ヴィランを捕獲出来ず、自分が人形になるとは、なんて間抜けなんだ。
勝己は用心深く周囲を見回した。左右の棚には、のっぺらぼうの球体関節の人形の群が、整然と並べられている。顔には浅い目鼻立ちのくぼみはあるが眼球はない。男性型と女性型があり、身体のフォルムは滑らかで、どこか生々しい。
人の意識がダウンロードされた人形は、顔がついているはずだ。1つ1つ見て行くと、出久の顔をした人形が棚に座っていた。
「てめえか、デク」
顔を近づけて問うたが返事はない。薄眼を開けているが、手をかざしても反応せず、何も見えていないようだ。
頬に触れるとほんのり温かく、皮膚を押すと弾力がある。髪の毛はナイロンの糸か何かだろうか。本物の毛髪じゃないが、出久の髪型になっている。
体格も模しているのだろう。男女とも細身で中性的な他の人形より、筋肉がついた青年らしいフォルムになっている。
「あったのか」轟が問うた。
「ああ、馬鹿面をつけた人形があったわ」
勝己は人形を担いだ。人間ほどではないがそこそこ重みがある。
「奴に聞いて、緑谷にかけた個性を解除させねえとな」
「聞くだあ?吐かせんだろ」
轟はヴィランを椅子に縛り付けて、身体を凍らせた。「動けないようにした」と言っているが、聞き出しやすくするためだろう。奴も容赦ねえな。
ヴィランは唸って、意識を取り戻した。
「おはようさん、いい朝だなあ」と勝己は指を鳴らした。生意気なヴィランだったが、手段を選ばないやり方で容赦なく脅して、解除条件を吐かせた。
ヴィランは言った。セックスすれば元に戻る。ただし、二人以上の相手としなければならない。愛玩用のラブドールなのだから、セックスを楽しめるよう作ってある。ドールを通じて本体に感覚は伝わる。触覚も聴覚も味覚もだ、と。
ヒーローデクも型なしだなあ、とヴィランは笑った。
思わずかっとなってぶん殴ると、椅子ごと床に倒れ、ヴィランは気絶した。
「こんな危険な個性の犯人が野放しだったとはな。捕まえられてよかったな」
「へっ!馬鹿が個性をかけられてなきゃあ、これで一見落着だったのによ。クソナードが」
昏倒したヴィランは解凍し、駆けつけた警察に引き渡した。出久の身体は救急車に乗せるために階下に運ばれた。
出久の意識が人形に入ってることは、警察には伏せた。これをまだ渡すわけにはいかない。犯人が意識を回復して、口を割るまでの猶予だが。
「相澤先生は出張中だ。つまり個性解除は戻るまで無理ってことだ。警察に渡しても何もできねえだろう。でも解除方法はわかってんだ。個性にかかったと知られる前に、デクを元に戻せば済む話だ。奴の言うとおり、ヒーローがヴィランにしてやられたなんて間抜けな話、なかったことにしておけばいい」と言うと「なるほど、それもそうだな」と轟も黙っていることに同意したのだ。
警察を見送ると、勝己は人形を抱き上げた。
「じゃあ、このデク人形はもらってくぜ。他に手がねえんだからよ。不本意だが俺がなんとかするわ」
「お前だけじゃダメだろう、緑谷を身体に戻すには、もう1人は必要なんだろうが」
「ああ?てめえもってんじゃねえだろうな?おい、ふざけんなよ!」
轟の言わんとすることを察し、勝己は怒鳴った。
「ヴィランの言葉を聞いたろ。セックスする相手は、ふたり以上必要なんだ」
平然とした表情で、しれっと口にする轟にイラつき、ちっと舌打ちする。
「いいよ、仕方ないもんね」
出久そっくりな声が、人形の喉元から聞こえた。人形が喋ったのか。だが口は動いていないし、表情は変わらない。
「人形の喉に内臓されたスピーカーが、被害者の思考を声に変換するらしいな」
喉仏のあたりだな、と轟は人形の首を摩った。
「僕はいいよ。君も轟くんも。男同士の経験はないけど、僕だっていい大人だし、減るもんじゃなし」
「てめえは黙ってろ!」
勝己は人形を肩に担ぎ上げると、窓から外にジャンプした。着地すると、背後で爆破させてスピードを上げて走った。
結局すぐに追いつかれてしまったのだが。
勝己は人形をベッドの上に無造作に放り投げた。手足の球体関節が擦れて音を立てる。
「おい、乱暴じゃないか」と轟が言う。
「は!人形だろうが」
「いた、感覚はあるんだよ、かっちゃん」
出久はいっちょ前に文句を言う。顔は無表情な人形のままのくせに、
「ごちゃごちゃうっせえわ!動けねえくせに。重いんだよ。てめえが悪いわ」
「そ、そうなの?ごめん動けなくて」
「謝るところじゃないぞ。緑谷」
舌打ちすると、勝己はベッドに上がり、人形を仰向けにして上に跨る。
「じゃあ、やるぜデク」
「性急じゃないか、爆豪」
「うるせえ、早かろうが遅かろうがやるんだろうが、ちゃっちゃと終わらせっぞ。股開けや」
「動けないんだよ、かっちゃん」
「ああ?クソが。仕方ねえな」
出久の膝を立てて股を開かせた。膝も太腿の付け根も、球体関節は曲げた形で固定された。作り物の性器もちゃんと拵えてある。するっと男性器を撫でて、孔に触れる。
「うわあ」と出久が色気のない声を出した。
「んだよてめえ、このくれえでよ」
「何か不都合があったのか?緑谷」轟が問う。
「な、なんでもない。そんなとこ、触られたことないから。かっちゃん、平気なの?」
「ああ?てめえ人形だろうが」
「そうか、そうだね」
「恥ずかしいのか、緑谷。男同士だし気にすんな」
轟の全然フォローにならないフォローに腹が立つ。その男同士でこれから何すると思ってんだ、クソが。3人でなんてふざけんなよ。
本物の出久だったら、こんな状況、許せるわけねえ。人形だと言い聞かせなきゃあ、頭が爆発しちまう。出久が自分のもんになってたら、誰にも触らせやしねえのに。
まだ出久と恋人にもなってねえ。いや、告白もしてねえ。卒業してから何年も経ってるのに、何も始まってもいねえ。クソが!もう待てねえわ。
こんなきっかけになると思わなかったが、いつかは抱くつもりだったのだ。轟も一緒の3Pてのは癪に障るが。てか、頭が沸騰しそうなほどムカついてしょうがねえが。今から出久を抱けるのだという、高揚感は誤魔化せない。
「先にやるぜ」と告げると出久の太腿に触れる。
皮膚に似せた手触りだが、少し違う。性器のあたりに手を滑らせ、後孔に触れて指を突っ込んでかきまわす。ほの温かいが人間の体温より少し低いようだ。
指を2本に増やして、つけ根まで入れては抜くと「や、かっちゃん。やだ」と人形が声を発した。
「おい、爆豪」
「人形だろうが。そろそろ入れっぞ。中は柔らけえからそんなに慣らす必要ねえだろ」
「大丈夫なのか、緑谷」
「わ、わからないよ。初めてだし。僕の身体じゃないし」
「潤滑剤になるものを塗った方がいいだろう。身体は人形とはいえ、初めて受け入れる感覚が伝わるなら、きついだろうしな。そういうものあるか?」
「てめえはいちいちうぜえんだよ。クソが!あるわ」
勝己は卓の中から、ローションのボトルを出した。いつか出久をものにする時のために、買って置いてあったものだ。
「用意がいいな。でもまだ未使用か」
「うるせえ!」
孔に指を出し入れして、丁寧にローションを塗り込む。人形の出久は無表情のままに声だけが「ん、ん、」と悶える。
「俺が先にやるぜ。いいな」
「もう勃起してるのか。早いな」
いちいち癇に障る奴だ。家についた時から元気になってたわ。準備万端だわ。
ズボンの前を寛げて、出久の孔に先端を押し当てた。ひゅっと人形の喉が、息を呑んだような音をたてる。
「待て、これつけろ」
轟はポケットをゴソゴソ探ると、コンドームを差し出した。
「ああ?んなもん要らねえだろ。人形なんだからよ」
「あるぞ。お前の後で挿入する俺の身にもなれ」
こいつ、なんだかんだ言ってやる気満々じゃねえのか。ギリッと歯ぎしりし、コンドームを装着する。ついでに下着ごとズボンを脱ぐ。これで動きやすくなった。
再び自身を押し当てると、出久の腰を手で固定し、強く突き上げ、一気に奥まで貫いた。
「ああ!」と出久が叫んだ。
「痛いのか、緑谷」轟が心配そうに訊いた。
「う、ん、感覚はダイレクトにくるんだよ。あの、かっちゃんいきなりは」
「ああ?てめえ、注文できる立場かよ」
「かっちゃん、もう少しゆっくり。お願いだから」
「うっせえな、てめえは。こうかよ」
根元から先端まで入れて抜いて、ゆっくりと突く。生温かく狭い内側を押し広げてゆく感触。
表情は変わらないが、「んあ、ん」と出久は押し殺した喘ぎ声を上げる。痛みだけではない色を帯びた声だ。
「はっ!デクてめえ、感じてるのかよ」
「そんな、こと、ない、あ、あ」
人形の喉からの甘い発声。快感に嵌ったように、熱っぽく聞こえる。
「素養があんじゃねえのか」
あんだろ。経験なくてこれなら、本物のてめえだってきっと気持ちいいはずだ。
「爆豪、思ったんだが」と轟は口を挟む。「奴はセックスと言ったよな。なら口でもいいんじゃないか」
「はあ?何言ってんだ」
「試してみる価値はあるだろう。緑谷の負担が1回で済むかもしれない」
「てめえ、デクにフェラチオさせようってのかよ!」
「人形だと言ったのはお前だろ。緑谷、どうだ?尻よりは楽じゃないかと思うぞ」
轟が問いかけると「いいよ」と出久は答えた。
「てめえ、何言ってやがる!」勝己は怒鳴った。「デクてめえ、勝手に許可してんじゃねえ」
「だって、轟くんが僕のためにって考えてくれたんだし」
「クソナードが!どんなことすんのかわかってんのかよ」
くそ!てめえが俺のもんなら、絶対にやらせやしねえのに。ざけんじゃねえ。
だが、ものは考えようか。これで轟が出久を犯さないで済むってんなら、しょうがねえ。我慢だ畜生が。沸騰した頭を無理矢理に落ち着かせる。
轟はズボンと下着を脱ぎ去ると、人形の頬を撫でて「口を開いてくれ」と言った。
「ごめん。轟くん、口も動けないんだ」
「そうか、辛かったら言ってくれ」
轟は人形の顔を横に向けて指で口を開かせ、コンドームを装着すると、イチモツを咥えさせた。ぐっと押し入れて、小刻みに腰を振る。
ムカムカと腹が立つ。勝己は少しずつ腰を振るスピードを上げた。がくがくと出久を揺さぶる。球体関節がきゅっきゅっと軋む。
人形とはいえ、出久の顔と感覚を持ってるのだ。本物の出久は病院で昏睡状態だが、挿入の感覚は伝わっているのだろう。
俺がてめえを抱いてんだぜ。今のてめえは球体関節のデク人形だけどよ。感覚はあんだろ。触覚が伝わってんだろ。俺のわかんだろ。
「デク。いくぜ」と告げると「ふ、は」と唸り勝己は射精した。
屹立を引き抜き、コンドームを結んで捨て、荒くなった息を整える。クソが、交替か。それともこれで終わりか。
うっと唸り、人形に口淫させていた轟が顔を上げる。奴もイったらしい。
出久は戻ったのか?
「おいデク、こん中にいんのか?」
声をかけると「いるよ」と返事が返ってきた。暫く待ってみたが、人形の様子は変わらない。
「戻らないようだな。失敗か。試してはみたけど、残念ながら口じゃダメそうだ。やはりセックスじゃないといけないようだな」
悪びれもせず轟は答える。
「はあ?てめコラ!ざけんなよなあ!フェラチオしといて挿入もやんのかよ」
「そういうことになるな」
「クソが!」
しれっと言ってのける轟に勝己は爆発する。やり得かよ、てめえ。轟は出久の足の方に回ってきた。退けと促してきやがる。
「交替だ。負担をかけたくなかったが、緑谷、大丈夫か?あいつの後すぐ入れちまっても」
「だ、大丈夫」人形が答える。
ちっと舌打ちして場所を譲り、頭の方に回る。よく見たら、轟はもうコンドーム装着済みじゃねえか。フェラチオで射精したばっかだろ。いつの間におっ勃てて、コンドームつけてんだよ、こいつ。
轟は人形の膝の関節を曲げて左右に広げ、身体を進める。ふあ、と人形の喉が声を上げる。轟が挿入したらしい。股ぐらを合わせ、足を抱えて揺さぶっている。人形は無表情なままで声を殺して喘ぐ。
轟が優しげに言う。「苦しかったら言えよ。まだ半分くれえだ。止めねえなら、このまま全部入れちまうぜ」
「だ、大丈夫。ふ、は、あ」
口では悶える出久を労る轟だが、容赦なく腰を振り、動きを止めない。ムカついた。出久の機嫌なんか取ってんじゃねえよ。気にすんなら加減しろや。クソが。喘いでんじゃねえわ、クソデク。
そのムカつく口を俺が塞いでやるわ。
「口開けろや。クソデク。コンドームなんかつけねえぞ。俺は」と告げる。
出久は掠れた声で「かっちゃん」と勝己の名を呼ぶ。開いた薄目から瞳が覗き、勝己を見上げる。
眼球は少しだけ動かせるのか。見えているのか?奴は触覚と聴覚と味覚と言っていたが、視覚はどうなんだ。
誘うような上目遣い。てめえも望んでいるみてえじゃねえか。そうだろ。
出久の顔を横に向け、半開きの口を開けさせると、勝己は一気に突っ込んだ。「んん!」と人形の喉から呻き声が聞こえる。
人形の口が勝己のものを呑み込んでゆく。本物なら出久の喉の奥まで届いたろうか。
引き抜いて、再び付け根まで入れる。腰を振るたびにん、ん、と出久の声が響く。本当の肉体じゃねえんだ。多少手荒にしても構わねえだろ。
ふ、と轟が笑う。
「んだよ、轟。何がおかしいんだ」
「いや、何でもない」
「うぜえわ、クソが。言えや」
「いや、ぶっ壊されたら、何が残るんだろうと考えてたんだ。憎しみと怨みだけが、今までの俺を形作っていたものだからな」
「はあ?」
「でもお前を見てると、壊されても新たに構築されるんだとわかるよ」
「ああ?俺はクソデクなんかに、何も壊されちゃいねえわ」
「そうか?」
何を指して言ってやがんだ。わかった風なこと言いやがって。しかも、ピストン運動を止めねえで揺さぶりながらよ。
勝己は怒りのままに腰を振った。出久の口で自分のものが扱かれる。生暖かい口腔。口内の内側を突くと人形の頬が膨れる。
視覚的にエロくて滾るな。だが舌も歯もないし、下の孔と大差ない感触だ。本物の出久の口ならば、どんなにいいだろう。
人形の口の中で勝己は達した。同時に轟が唸り声を上げた。ほぼ同時に達したらしい。荒く息をつきながら引き抜いて、出久の顔を覗きこむ。
薄く目を開けた無表情な顔。虚ろな瞳。
「デク、どうなんだ」
返事はない。眼球も動かない。無表情だが、出久の顔から心なしか、生気のようなものがなくなってきたように見える。
「ただの人形に戻ったのか?」
轟も出久を見つめる。すると、みるみる内に顔面がつるりとしたフォルムに変化していった。
固定されていた球体関節が緩くなり、足がパタリとシーツの上に倒れる。男性器が萎みはじめ、子供のものくらいの大きさに縮んで止まる。筋肉が削げて体格が中性的になり、髪は色が抜けて白髪になる。
人形は倉庫に並んでいたものと同じ、のっぺらぼうに戻った。
出久の本体はどうなった?意識は戻ったのか?無事なのか?もし戻ってなかったらあいつの意識はどうなる。
「クソが!病院に行くしかねえ」
「待て。その前に確認した方がいい」
轟は携帯を取り出して病院に問い合わせ、通話を切ると勝己に向き直った。
「緑谷が目を覚ましたらしい。病院に行くぞ」
「さっき俺が言ったろうが!指図すんな、クソが」
勝己はほっとした表情にならないよう顔を顰める。
「かっちゃん、轟くん」
病院に駆けつけると、ベッドに横になっていた出久が身体を起こした。
「ヴィランは?かっちゃんと轟くんが捕まえたの?」
「開口一番にそれか、緑谷」と轟は呆れたように言う。
「クソが!捕まえたわ。てめえもいただろうがよ」勝己は怒鳴る。
「それが、その、倉庫に入ったのは覚えてるんだけど」
出久は困ったように言った。どうやら倉庫の中でのことを、デクは何一つ覚えてないらしい。もちろん人形に入っていたことは全く記憶にないらしく、話を聞いてびっくりしている。
勝己は半分拍子抜けし、半分は安堵した。初めてがあんな形になってしまったのは、不本意だしな。出久が覚えてないのは幸いか。
人形なんて数に入らねえ。退院したらすぐにモノにしねえとな。
「相澤先生はいないから、個性解除できないはずだよね。どうやって助けてくれたの?」
「俺も覚えてねえんだ。俺達も意識がなくてね」
機転を利かせたつもりなのか、轟はデクに嘘をついた。奴も本当のことを教えるつもりはないようだ。いい判断だが、そりゃ無理のある言い訳じゃねえか。ヴィランを捕縛して奴が意識不明?なんだそりゃあ。
「ふうん?」と案の定出久は首を傾げている。
「うぜえ!事件は解決したんだ。てめえのドジも忘れてやるわ」
「う、うん。そうだね。」
助け舟を出すつもりはねえが、この話題はここまでだ。あのヴィランの個性の解除方法を、出久が誰かに聞いたりしなきゃいけるか。
ま、半分野郎も本当にちゃっちゃと忘れてくれよ。
病室の戸を開けてやると「じゃあな」と轟に声をかける。
「さっさと帰れよ。俺はデクにまだ用があんだからよ」
「ああ、またな」と出久に言うと、轟は腰を上げる。
すれ違いざまに轟は勝己に囁いた。
「お前と分け合うつもりはねえよ」
どういう意味だこの野郎。マジで油断ならねえぜ。
END
パラサイト・フェスタ(全年齢版)
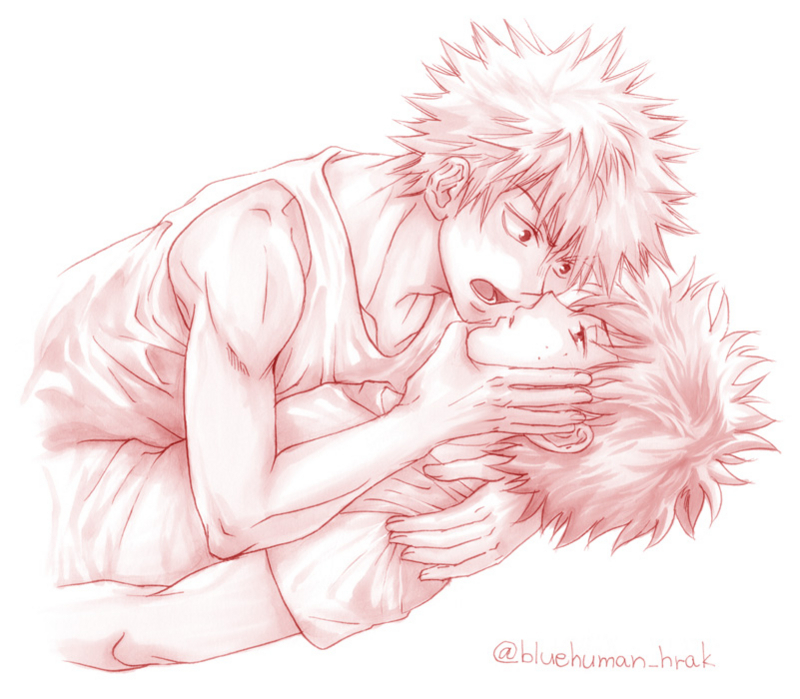
序章
「かっちゃん、あれ何だろ」
幼い頃、ふたりで林の中に遊びに行った時だ。後ろを歩いていた出久が言った。
ふらふら余所見をしているから、ついてくるのが遅れて、待ってよかっちゃん、と追いかけてくるのが常だった。この日は2人だけだから、歩くペースを合わせてやってる。
「あんだ。どうした?デク」
「この虫、どうしてこんなとこで動かなくなってるのかな」
出久の指差す方向にいたのは、草の先に噛み付いたまま死んでる蟻だった。
「ああ、その蟻は冬虫夏草に寄生されてんだ」
「この蟻の中に寄生虫がいるの?」
「いや、寄生虫じゃなくキノコの一種だな。そいつに寄生されると蟻が自分の意思を支配されて、草に登って落ちないように噛み付いて死ぬ。そしたら蟻の中の冬虫夏草が身体から伸びてきて、胞子を周りに撒き散らし、次の寄生先の蟻を待つってわけだ」
自分も本物見るのは初めてだ。かっちゃんはなんでも知ってるね、と出久は微笑む。そうじゃねえよ。てめえがなんでも聞くから勉強してんだろーが。
「蟻にも心があるのかな」
「人間みてえな感情はねえだろ。あるのは本能だけじゃねえか」
「本能。頭の中に聞こえる声じゃあ、自分のものか誰かの声なのかわからないよね」
頭の中で死へと誘う声。判断を狂わせるほどに抗いがたいのものなのだろうか。気味が悪いなと思う。
勝己の袖をそっと掴んで、出久は囁いた。
「怖いね、かっちゃん」
「ほら、早く言わねえともっと奥まで入れちまうぜ。言えよ。欲しいっていえよ。俺のをよお。なあ、デク」
シャツをめくり乳首をコリコリと撫でる。潰しながら捏ねると芯ができてプクリと勃ってくる。
「うあ、や、は、」と出久は苦しげに喘ぐ。
カーテンを閉めた勝己の部屋。薄い布は夕方の日差しを遮り切れず、薄明るく出久の肌を浮かび上がらせる。床には脱ぎ散らかした二人分の制服。勝己は出久の足首に引っかかっていた下着を剥ぎ取って、ぞんざいに服の上に放る。
何一つ自分に本音を言わなくなった出久。下手くそな作り笑いで苛つかせる嘘つきな出久。でも肌を合わせることで、少しだけこいつが隠している内側に触れられる気がした。
触れれば触れるほど、出久の肌に熱に飢える。抗いがたい衝動だ。
けれども時折、身体を重ねた後の、虚ろな出久の瞳を見るたびに、胸を硝子の破片のような棘が刺す。
出久はどう思ってるんだ。
「おい、デク」
身体を繋げている時は、気づかないでいられる心の虚。身体を起こし、乱れた出久の髪をかき上げて瞳を覗く。抱かれながらも反抗的な光を宿していた瞳。快楽に濡れて情動を揺さぶった翡翠のような瞳。今は何を映しているのかわからない硝子玉のようだ。
出久だって肌を合わせることに慣れてきているんだ。身体を重ねることで情が移ったりしねえのか。
俺のことを。
いや、どうだっていいじゃねえか。出久の気持ちなんか置き去りで構わない。抱いて溺れさせてしまえばいいんだ。
中学生の頃の放課後の熟れた時間。高校生になって、たとえ別々の学校になったとしても続くはずだった関係。だがそれはヘドロヴィラン事件と、雄英入学と共に出久が個性を得たことで、あっさり終わりを告げた。
あれから出久に触れていない。
第1章
文化祭に劇をすると決めたのは誰だっただろうか。しかも手間のかかるファンタジーだと?
「アホかよ。稽古する暇なんざねえわ」
勝己は文句を言ったが、面白そう、台詞覚えるの大変そうだけどやってみたい、とクラスの連中からは賛成の声が大きく、多数決で決まってしまった。ちらっと背後を伺うと出久も挙手してやがる。クソナードが。
「めんどくせえわ、クソが。てめえらでやってろよ」
勝己は毒づいた。つかつかと飯田が近寄ってくる。おい、HR中だろうが。相澤先生はいねえけど。
「爆豪くん、やる前から面倒だと決めるのは良くないぞ」
「まあまあ、飯田、爆豪は口ではこう言っても、結構真面目にやるんだぜ。前のバンドの時だって、率先して練習仕切ってたしよ」
上鳴の野郎、余計なことを言いやがる。勝己は睨みつけて顔を顰めた。
「そうだったのか、やる気があるんだな。君を誤解していたようだ。すまない爆豪君」
飯田は机に頭突きしそうな勢いで、腰を直角に曲げた。
「うっぜえええ!勝手にしろよ」
勝己は怒鳴って机を叩き、さりげなく振り向いた。目が合うと、出久は困ったように眉を下げて笑みを作る。胸がざわっと騒いだ。
実を言うと、全員で一つのことをするのに異論はない。一年生の時はバンド班とダンス班に分かれたから、ダンス班の出久が何やってたのか、わからなかったからだ。いまだに引っかかっていることがある。
文化祭当日、買い出しに行ったはずの出久の帰りが遅く、戻って来た時は明らかに消耗してやがった。明らかに何かやらかしたんだ。でも出久の班の奴らは何もあいつに聞かなかった。忙しかったとはいえ、気にならねえのかよ。
文化祭が終わってから呼び出して出久に問いただしたが、口止めされてるのか、答えられないという返事だった。腹が立ったがしょうがねえ。
今回は出し物はひとつだから、てめえに異変があれば丸わかりだ。俺に隠し事はさせねえ。
脚本はオリジナルでいくことになった。クラスコンペで選ばれた粗筋をベースにして、脚本担当の奴らがさらに推敲を重ねたらしい。全員が出演する内容になり、元とはまるで違う物に仕上がった。
期日が間近に迫ったここ数日は、準備でてんてこ舞いだ。衣装や小道具は八百万が個性で用意した。セレブな知識が生かされて、学生の舞台とは思えないゴージャスさだ。おかげで本格的な舞台になりそうだ。八百万に食わせるお菓子を作る係に砂糖が振り分けられたので、ある意味砂糖のおかげでもある。
だが舞台で使うサテン生地やベニヤ板などを作りすぎたようだ。教室がやけに狭くなった。
「食わせすぎじゃねえのか、太らせちまうぞ」と上鳴が余計なことを言って八百万が凹み、「デリカシー!上鳴、お前、謝れ!」と耳郎に怒鳴られている。
創造したものは元素から構成した本物らしいから、一度作ると消えない。使わねえもんは爆破するかと提案したが、もったいないし、まだ使い道があるかも知れないと、余った布や板は上の空き教室にぶち込まれた。
ベニヤ板を使ったセット作りは力仕事なので主に男子の仕事だ。衣装のデコレーションは主に女子が受け持った。
そのはずだったのだが。
「おい、爆豪、俺の衣装の胸に、このエンブレムつけてくれよ」「俺も肩あて縫い付けてくれよ。勇者っぽくよ」と何人かから何故か裁縫を頼まれた。
「ふざけんな、てめえら!自分でやれや」
「出来ねえから頼んでんだよ。女子には別に必要ないだろって断られちまったし」
「もう爆豪は衣装担当でいいんじゃね?女子よりうめえじゃん」
「はあ?てめえらなんでできねえんだ」
「うわ、出たよ、才能マン、世の中にはなあ、頑張ってもできねえことがあるんだよ」
「クソが!全部持って来い。ちゃっちゃと終わらせてやる」
衣装を受け取って出久の姿を探した。出久は窓の側でベニヤ板に覚束ない手付きで釘を打っている。危なっかしくてしょうがない。勝己は出久の側に椅子を寄せて座った。
出久は顔を上げる。「かっちゃん、手伝ってくれるの?」
「は?てめえの仕事だろうが。てめえでやれや。俺は衣装直しすんだよ」
「え、ここで?」
「うっせえ、どこでやろうが構わねえだろうが」
「見られてると、なんか緊張するなあ」と出久は屈託なさげに笑う。
擽ったいような、軽口を叩くような関係に、いつになったら慣れるだろう。クラスの奴らはもう、自分が出久の側にいても誰も不思議がらないが。
「でも、僕は嬉しいよ、かっちゃん」と出久は言う。「一年生の時は担当演目が違ったから、準備もリハーサルも別々だったもんね」
「へっ!近くで見ると、てめえの至らなさがよくわかるわ」
「ひどいなあ。かっちゃんみたいには出来ないよ」
衣装にエンブレムを縫い付けながら、出久を見下ろす。
屈んで金槌を打つ白い出久の頸。熱いのか第二ボタンまで外したシャツの襟から覗く肌。さっきまで静かだった胸の内にさざ波が立つ。
しっとりと手に馴染む、肌理の細かい肌を知っている。襟の合わせ目から手を滑り込ませて温もりを確かめたい。当たり前に抱いていたのが嘘のようだ。今はどう触れればいいのかわからない。
「貸せよ、下手クソが」
焦れて出久の手から金槌を引ったくる。指が触れるだけで、胸が騒めくのが忌々しい。隣にしゃがんで、出久の打った釘を残らず引っこ抜いて打ち直す。
「え?全部駄目?」と出久が言う。
「真っすぐ釘打つこともできねえのかよ」
「ごめん、ありがとう、かっちゃん」
「仲良いな、爆豪」通りかかった瀬呂に揶揄われ、「うるせえ!」と怒鳴る。
クラスの奴らは誰も中学生の頃、勝己と出久が身体の関係だったことを知らない。ガキッぽい出久が毎日のようにセックスしていたなんて、想像すら出来ないだろう。
俺もてめえがいなければ、まだ童貞だったかもな。てめえの他に情欲を掻き立てる奴はいねえんだ。
台詞の多い役は演技力度外視で、とにかく成績で決められた。台詞を覚えられなきゃ話にならねえってわけだ。地味な設定の主人公ということで、主役になっちまった出久や、飯田や轟や丸顔は出ずっぱりだ。台詞の多い奴らは放課後集まって、練習に余念がない。
自分も成績上位ではあるが、「出番の多い役はやらねえ」と言ったら当て書きしてきやがった。役柄はドラゴンマスター。ちょっと気に入った。
文化祭前日の今日はリハーサルだ。全員衣装を着て、セットも配置して、本場さながらである。
背景のセットや垂れ幕は峰田のもいだ玉でくっつけてある。よくくっつくので便利だが、峰田以外が触ると取れなくなるので注意が必要だ。
勝己は舞台裏で出演者の用意を手伝う。全員出演するため、出番のないシーンではそれぞれ裏方に回る形だ。
第一幕「旅の始まり」は旅に出た冒険者・緑谷が兵士・飯田と魔法使い・麗日に出会い意気投合し、魔物を退治するために来たという王子・轟に出会い、目的を合わせて行動を共にする。
第二幕「仲間との出会い」は魔物退治のために仲間を集める展開で、勝己以外のクラス全員が順に登場する。
勝己の出番は第三章からなので、前半はずっと裏方だ。出久が裏方に回るのは、勝己がアジトで報告を受けるシーンだけだ。丁度入れ替わりになる。
出番が終わった奴らからステージをはけて、裏方に回ってきた。
勝己のいるステージの下手に、出久と切島が歩いて来た。切島は笑いを堪えているような表情をしている。カーテンをくぐると、切島は「やったぜ!」と叫んで出久に抱きついた。うんうんと相槌を打って、出久も切島の背に腕を回す。
頭にかっと血が登った。
反射的に「おい、じゃれてんじゃねえ!」と怒鳴る。
切島はにかっと笑うと「いやー、初めて台詞間違えずに言えたから嬉しくてよ」とあっけらかんと言った。
「うん、良かったね」と朗らかに返す出久。
わかってる、これは八つ当たりだ。俺はクラスの奴らみたいに、出久の身体に何気なく触れられはしない。あんな風に抱きしめたりできはしないのだ。
第二幕が終わり、カーテンを下ろして勝己はステージに回った。クソ!今は考えるな!次は俺の出番だ。用意しなきゃいけねえ。
冒険者・緑谷は旅に出て仲間を集め火の山に辿り着いた。第三章は俺が竜のオブジェの上からあいつを見下ろすところからだ。
爆豪 「何か用かよ。ああ?」
轟 「この山に住んでるのはお前か」
爆豪 「それがどうした」
飯田 「麓の村が迷惑をしている。魔物を放つのをやめてくれないか」
爆豪 「なんの話かわからねえな」
轟 「口で言ってもわからないなら、腕付くでということになるが」
爆豪 「おもしれえ、やってみろよ」
緑谷 「待って!ねえ、君はほんとに魔物なの?人間にしかみえないんだけど」
麗日 「騙されたらあかん!魔物は人間に化けるんよ」
飯田 「そうだ。人間に化けて騙すのが奴らの手口だぞ」
緑谷 「でも彼は人間みたいだよ。ねえ、君が本当に麓の村を魔物に襲わせてたの?」
爆豪 「ああ?だから何の話だっつってんだろ。俺あ、ドラゴンマスターだ」
(一拍分黙り、おもむろに口を開く)
爆豪 「てめえは俺を忘れたのか?」
緑谷 「えっ?誰が?」
(緑谷、仲間を見回す)
(爆豪、緑谷を指差す)
爆豪 「てめえだ、クソが。子供の頃にてめえは森で俺と、何度も会ったことがあるはずだ。俺はすぐにわかったぜ」
轟 「お前、奴と友達だったのか」
緑谷 「君が僕の?嘘。覚えてないよ。ドラゴンマスターの友達なんて、いたら忘れないよ」
爆豪 「ああ?てめえ」
緑谷 「子供の頃に森の中に竜がいるって聞いてた。でもドラゴンマスターの竜だから安全だって。森にドラゴンマスターの友達がいたような気がするけど。ほんの小さな頃だけだよ」
(緑谷、ハッとして爆豪に視線を合わせる)
緑谷 「ドラゴンマスターの子供って君だったのか!ええ!全然雰囲気違うよ」
爆豪 「ああ、竜に乗せてやったりしたのに、てめえは段々来なくなった」
緑谷 「勇者の修行を始めたから、森に行かなくなったんだ」
爆豪 「何もかも忘れちまったのか。てめえはそういう奴だよな。クソが」
緑谷 「でもでも、この災厄の原因は君なのか?ええーと、何で悪い魔物みたいなことをするんだよ」
轟 「魔物が本当のことを言うはずがねえぞ。お前の知り合いのふりをしてんじゃねえのか」
爆豪 「ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ!こんなとこでてめえと会うとはな!やんのか?やんねえのか?ああ?かかってこいやデク!」
緑谷 「かっちゃん、台詞台詞、デクじゃないよ」
麗日 「デクくん、かっちゃんも違う!」
飯田 「麗日くん、デクくんじゃなく、ああしまった!
「わやくちゃだな。どうする?」
轟はライティングの八百万の方に視線を向けて声をかける。
「とりあえず映像映すから!通しでやりましょう」
頭を抱えた八百万が、巨大な魔王のシルエットを、ステージ後方のスクリーンに映し出した。
「魔王だ!」という出久の声を合図に、八百万の作った魔物兵人形が舞台袖からわらわらと登場し、客席側からステージにクラス全員が押し寄せた。
グラウンドベータから戻る帰り道。
勝己はオールマイトの後ろを出久と並んでついて行った。
出久の手足は爆破による火傷で赤く腫れ上がっている。俺がやったんだ。とはいえ、出久も思いっ切り殴りやがったから、おあいこだ。
口の中で血の味がする。ジャリッと砂の感触がしたので、地面に血混じりの唾を吐いた。
「オールマイト、いつから見てたんだ」と勝己は訊いた。
「君が罪悪感を吐露したあたりにはいたよ。本当にすまなかった」
「ほぼ初めからじゃねえか。あんた止めねえのかよ」
「止めるべきなのかもしれなかったけど」オールマイトは振り向いた。「止めたくなかった。君達には必要なことだったんだろう」
最初の授業の時だって、俺の暴走を止めなかった。オールマイトの基準はズレている。でもそのズレに俺は救われている。
「あんた、先生に向いてねえわ」
「かっちゃん」出久が困ったように言った。
「そうだね。相澤くん怒ってるよ。でも私のせいでもあるんだし、何とかとりなすよ」
「いらねえ、俺が全部悪いんだからよ」
「かっちゃん、でも応じた僕も悪いんだよ」
「全部俺のせいだっつうんだ!クソが!てめえはすっこんでろや」
てめえを呼び出した時から、退学でも停学でも覚悟の上なんだ。イラッとする。でも腹は立たない。わかっちまったからだろう。
俺のやることは変らねえと言ったけれど、本当は変わっちまった。出久を捩じ伏せればいいと思っていた。それが目的になっていた。でも縋りついて無理やり相手をさせた対決に達成感はなかった。
秘密を分けあって知った。出久はOFAの新しい宿主なのだ。もう目的が達成される日は来ないのだ。
すうっと心に吹き抜ける風。理解とは諦めに似ているのかも知れない。
脱線していた目的が元に戻っただけだ。てめえのように、真っ直ぐに前を見て行けばいいと。もうそうするしかないのだと。
代々受け継がれてきたDNA。DNAを取り込むなんて生々しいなと思う。そういう意味ならば、俺は何度も出久の中に俺のDNAを注ぎこんだんだ。髪の毛と精子は全然違うけれど。
でもてめえの中には何も残せなかったんだろう。
肩を並べた隣で、大きな目で出久が俺を見つめる。昔みたいに。
ガキの頃からてめえが俺に向ける視線が心地よかった。どんなに邪険にしてもついてくる。俺は、てめえが俺に好意を持っているからだと無邪気に信じていた。
瓦礫の下から人々を救う、オールマイトのニュースを一緒に見るまでは。
あの時、出久は俺を見るのと同じ目でオールマイトを見つめていた。
胸がざわついた。てめえはファザコンなんだ、と思った。無自覚にか自覚しているのか知らないが。めったに会えない父親のかわりに、指針となる存在を求めているのだ。はじめは俺だった。次はオールマイトなんだ。
オールマイトに出会ってからてめえは変わった。俺を否定し始めた。もう俺を必要としないのだ。もっと父親的な存在を見つけたから。
てめえが仰ぎ見る地上最強の男。俺はオールマイトを超えてやる。それ以外にてめえを取り戻す術はないんだ。
その手段さえ見失ったのは、ヴィランに攫われた時だ。俺のせいでオールマイトが力を失った。そんなことは望んじゃいなかったのに。俺は超えたかった。強くなることを望んだだけなんだ。
てめえは俺を見なくなった。もう俺を許さないのだろうか。弱い俺を見放すのだろうか。てめえは俺をどう思ってる。オールマイトを壊した俺を。このままもう二度と俺を見なくなるのか。
出久は俺に近寄らない。俺には近付く資格はない。俺からてめえに近寄れないのなら、側に寄る機会はないんだ。悪態もつけない。睨みつけるだけだ。腹の底に渦巻く苦しみはどこにもいけない。
この俺が出久を失う。こんな事態はあり得なかった。話すことも視線を交わすこともなく。負い目を持ったまま距離だけが開いてゆくのか。
限界だった。結局はてめえにぶつけるしかなかったのだ。
出久は何も気づいてなかった。
「君が責任を感じて悩んでたなんて思わなかったよ」と出久は言った。
「俺を鉄面皮だとでも思ってやがったのか」
「ごめん、思ってたかも。君はタフだから」
「クソが!」
あっけらかんと言う出久にムカついて、ペシリと出久の頭を叩く。こっちは頭ン中ぐちゃぐちゃになっていたってのに。
「君のせいじゃないよ、爆豪少年」
「わーってるってんだ、オールマイト。デク、てめえが強くなんなら、俺はその上をいく」
「じゃあ、僕はその上をいかなきゃ」
頭を摩りながら出久が言う。
今まででは考えられないくらい、まともな会話だ。まるで普通の幼馴染のように。少し、てめえに近づけたのか。近づいていけるのか。
どのくらい近づいたんだろう。あれから時々距離を確認する。
「おいデク、てめえは」
俺のことを、と問おうとしては躊躇する。
「何?かっちゃん」
「何でもねえよ」
俺の逡巡をよそに、やっぱりてめえは俺の聞きたいことに答えねえんだ。てめえが俺をどう見てるかじゃねえんだ。
てめえは俺のことをどう思ってるんだ。出久。
直前リハーサルが終わり、クラスの奴らがぞろぞろと講堂を出て行った。
帰る時間までまだ時間がある。何処で時間を潰そうか。
出久はまだ舞台の裏にいるようだ。セットの裏でひそひそと声が聞こえる。竜の張りぼての側で、出久が話しているのは轟だ。足を忍ばせて近寄ってみた。
「僕とかっちゃんの幼馴染設定だけど、必要なのかな」
「必要だろう。キーになるキャラと主人公に何らかの因縁があると、ドラマチックになるしな」
「それはスターウォーズでもあるから、理解できるんだけど」
「それに、演技に反映できるように、メイン役者の設定は本人のバックボーンに合わせてるらしいからな。俺は父親である王に反抗して出奔、飯田は騎士である憧れの兄を目指して武者修行、麗日は両親を手助けするため魔女を目指す。浮かす個性生かして、箒に乗って空飛ぶ魔女ができるからってのもあるな。気持ちが分かるほうが演じやすいって、脚本の奴らが考えたんだろう」
「うん、それはわかるんだけど」出久はポツリと言う。「僕とかっちゃんの役はどういう仲なんだろう」
俺の話かよ。気になってつい聞き耳を立てる。
「一般的な幼馴染と思えばいいんじゃないか」轟が言う。
「それってどんな感じなんだろ。難しいな。僕らは普通じゃなかったから」
「うちも普通の親父とは言い難いけどな。役と切り離して考えてもいいんじゃないか」
「うん。でもちょっとね、考えちゃって。それに魔物に向かって共闘する前にかっちゃんに言う台詞も、どういう気持ちで言えばいいのか、わかんないんだ」
「真面目なのはいいが、考えすぎるなよ」
「僕ね、轟くんちみたいに、いつも家にお父さんがいるのちょっと羨ましいんだ。君とお父さんの関係は難しかったって知ってるけど、僕は子供の頃から、ほとんどお父さんと会えないから」
「隣の芝生って奴だな」
「うん、お父さんよりかっちゃんとの思い出の方が、ずっと多いくらいだよ」
「お前らの関係は俺と親父のよりも、ややこしくみえるけどな」
「うんまあ」出久は苦笑している。「かっちゃんとは色々ありすぎたんだよ。僕の中で彼の存在は大きすぎるんだ。おかしいかな」
「いや、過ごした時間で情が移るものだからな。良くも悪くも」
「うん」と出久は相槌を打ち、ぽつりと続ける。「だから、情が移ってしまったんだよね」
なんだと、デク。
出久の言葉に、勝己は声を出しそうになった。情が移っただと。息を吸い込んでこらえる。
「あいつに比べれば会っていくらも経ってねえけど、お前の存在も俺には大きいぜ」轟が言った。
「轟くん、ありがとう。嬉しいよ」
ぽんぽん、と出久の肩を叩いて、轟はステージを降りて行った。
出久はまだ戻ろうとせず、皆の衣装を畳んでいるようだ。
こっそり聞いてしまった轟との会話。二人とも気づいていなかったのだから、知らないふりをすべきなのだろう。
だがそのつもりはさらさらない。俺には言わない出久の本音だ。直接本心を確かめないではいられない。
情が移ったのだと、確かに出久は言った。あれは俺達の関係を指してたんじゃないのか。
流石に中学生の頃に、俺と身体の関係があったことまでは、轟には言ってないだろうし、奴も気づいていないだろう。昔のことを何も知らない奴にだからこそ言えたんだ。
轟が講堂を出て行ったのを確認し、勝己は出久の側に歩み寄った。足音に気づいて出久は振り向き、目を見開く。
「かっちゃん、いたの?いつから?」
吃驚させたのだろう。出久の手から衣装が滑り落ちた。
「お前らが話し始めたところからだ」
「ええ!あ、あー、そうなんだ。かっちゃん。じゃあ、僕はもう行くね」とそそくさと立ち上がり、小走りに去ろうとする出久の腕を「待てや、コラ」と掴んで引き止める。
「てめえとは色々あったよな。昔っからよ」
「うん、そうだ、ね」
「てめえ、俺に情が移ってんだって?」直球で問うた。
「いや、その」
出久は狼狽して視線を彷徨わせる。もっとはっきり言ってやるか。
「あんだけセックスしたもんな。情も移るか。移るよな。俺もそうだったからよ。なあ、デク。どういう意味だ。ちゃんと言えや」
逃げは許さない。本心を吐くまで離さない。掴んだ腕に力が籠もる。出久はきゅっと唇を引き結んでいたが、溜息をつくと、漸く口を開いた。
「君には絶対に言わないつもりだった。僕は君に好意を持ってたよ」
でも、だから、と出久は俯いて口籠る。勝己は辛抱強く答えを待つつもりだった。だが邪魔が入った。
「おい、緑谷、行かねえのか」
講堂の出口の方から、轟の呼ぶ声が聞こえる。
「クソが!」思わず勝己は悪態をつく。
「うん、行くよ」と出久は轟に返事を返す。「じゃ、かっちゃんあの、手、放して」
まだ、言葉の途中だろ。全部聞いてねえよ。離そうとしない勝己の腕を振りほどこうと、出久は腕を振る。畜生、仕方ねえ。本心は聞いたんだ。解放してやると、出久は転がるように走って行った。
「あいつ、マジかよ」
出久は好意と言った。俺を好きなのかあいつは。いや、だから俺に抱かれてたのか。だよな。でなきゃ何度もやらせやしねえよな。
肌を合わせるほどに執着が沸いた。あいつの体温に匂いに溺れた。溺れてたのは俺だけじゃなかったのか。てめえもだったのか。ならまた欲しいと思っていいんだよな。
だが、出久の言葉の続きが引っかかる。てめえはなんと言おうとしたんだ。
第2章
文化祭一日目の朝。祭日和の雲ひとつない晴れた空。
午後のラストのプログラムであるA組の劇は滞りなく進んだ。
第四章は全員がステージに上がって乱闘するシーンが山場だ。舞台上の出久、勝己、轟、飯田、麗日以外は、見つからないように客席に隠れ、掛け声を上げながらステージに突入した。
魔王が登場すると勝己は人間の側につき、周囲の魔物と戦う展開だ。自分は魔物じゃなく、魔物と同じ山に移り住んでいただけだとかなんとか、出久と掛け合いしながら立ち回る。魔王に二人でとどめを刺すシーンは大いに盛り上がった。爆音を流してスクリーンに映った映像を消すだけだけなのだが。
台詞で大きなミスをする奴もいなかった。ちょっと怪しい奴もいたが、勢いで乗り切ったようだ。
台詞といえば、出久が拘ってた台詞はどれだったんだろう。掛け合いの中に、引っかかるような台詞は特に思い当たらない。
カーテンコールも済んで幕が降りたところで、勝己はステージから出久を連れ出した。盛り上がってるクラスの奴らは気づいてないようだ。
出久は「かっちゃん、戻らないと」と狼狽えたが、「昨日の話の続きだ」と人目につかないステージの裏に連れ込んだ。
通路にはセットや大道具が所狭しと立てかけてある。通り過ぎて隅に連れて行くと、出久の背を壁に押しつけた。
掴んだ腕が熱い。身体の芯が疼く。暫く忘れていた感覚が蘇ってくる。
「デクてめえ、俺が好きなんだろ。そう認めたよな」直球で問うた。
「かっちゃん、それは」
言いかけて出久はまた口籠り、目を逸らす。煮え切らない態度に苛つく。てめえ、今更誤魔化すつもりかよ。
「こっち見ろや」と顎を掴んで上を向かせる。
至近距離。今の出久の瞳に怯えの色はないが、視線はふらふらと迷い戸惑っている。
揺れる緑の瞳に誘われるように、唇を重ねた。濡れたやわらかな感触。肩を抱き、下肢を押し付ける。何度も身体を重ねて知りつくした体温。下半身が熱くなり、ズボンの中で性器が頭をもたげた。やべえ、このままやっちまいそうだ。静まれクソが。
唇を離して出久の顔を見つめる。頬がさっきより赤らんで見えるのは、気のせいではないはずだ。勝己は出久の両肩を掴んだ。
「情が移ってんだろデク。俺も同じなんだ。てめえもだってんなら」出久の耳元に囁く。「またつきあえや。俺と」
ひゅうっと出久から息を呑む音がした。今ならなんら問題ないはずだ。俺はてめえがいいんだ。周り道をしたが、やっとてめえの気持ちが分かった。なら中学生の時と違って、上手くやれんじゃねえか。
だが出久は腕を突っ張り、勝己の身体を突き離した。
「ないない、かっちゃん、ありえないよ」
「はあ?何故だ!」
意味が分からねえ。出久は胸に手を当てて、シャツの合わせ目を掴んで俯いた。何かを隠すかのように。
「てめえ、俺が好きなんだろ!」勝己は頭に来て怒鳴った。
「そ、好きとかじゃなくて、好意を持ってたと思ってたんだ」
「ああ?同じことだろーが。今更誤魔化してんじゃねえよ。認めただろうが。俺もそうだっつってんだろ。問題あんのかよ。あんなら理由を言えよ!」
「代償行為だったんだよ、かっちゃん」
「はあ?情が移ったことか、好意とやらか、何の代償だってんだ。違いあんのかよ」
「僕にとってあの頃の君は憧れで。目指す目標だった。普通はそういう対象は父親なんだろうけど、うちはあんまり会えなかったから、他に目標が必要だった。僕は目指すべき理想像が欲しくて、君にそれを見ていたんだ」
それは、俺がてめえに思っていたことだ。自覚してたのか。俺が出久を分析していたように、出久も自己分析していたのか。だが、それがどうしたというのか。
「俺はてめえの親父じゃねえよ」
「もちろん、本当に父親だなんて思ってないよ。目標だと掲げて、君自身を見てなかったってことなんだ。でもグラウンドベータで君と戦った時、やっと気付いた。君も僕も普通の高校生なんだって。僕の君への気持ちは違ったんだ。君に僕の理想を勝手に押し付けていただけなんだ。酷いことされても憧れる気持ちは変わらなかった。だから好意だと勘違いしてたんだ」出久は顔を上げる。「あれ、スト、なんとか症候群っていうのみたいに。自分の生存権を握る相手を憎みながらも、無意識の内に好きになろうとするっていう」
「ストックホルム症候群かよ」
「そうそれ。恐怖と防衛本能が認識を狂わせてしまうんだろうね。僕は君に憧れていたけど、逆らえば暴力を奮う君が怖かった。性的な遊びを僕相手に君が始めた時も、怖かったよ」
遊び。てめえは遊びだと思ってやがったのか。
「てめえは拒まなかったじゃねえか」
突っ込まれんのわかってんのに、呼べば来たじゃねえかよ。マゾかよ。俺に怯えてるのは知ってたわ。だがあの頃だって、大人しく言いなりになる奴じゃなかったはずだ。殴られても反抗する奴だったろうが。嫌なら逃げろよ、必死で抗えよ。
「今だけだ、すぐ君は飽きる、と思ってたんだ。他の人に被害はかからない。僕が我慢すれば済むことで、君をむやみに怒らせたくなかった」
きつく握りしめた出久のシャツの胸元に益々シワが寄る。「でも終わりが見えなかった」
「終わりなんざねえはずだったわ」
終わらせる理由なんてなかった。てめえが応じるから、抱きたくてたまらなかったから。てめえを知りたかったから。
でもいくら抱いてもてめえがわからなかった。
「だから、自分の心を守ろうとしたんだと思う。自衛のための間違った心理状態なんだ。本物じゃなくて紛い物だ。恋じゃない。恋なわけがないよ。好きでなくたって勃つんだ男は。セックスできるんだから。君もそうなんだよ。ただ肌を合わせたから情が移ったんだよ。そんなの駄目に決まってる」
「何が悪いんだ。身体とか心とか、ざっくり分けられるわけねえわ」
「情なんかじゃなく、僕は君が本当に大事なんだよ」出久は言い聞かせるように言う。「僕にとって幼い頃の君は、とても大事な位置を占めてたんだ。壊さないでよ。大事なんだ。壊したくない。他ならない君に、もう壊して欲しくない。もう二度と間違えたくない」
出久は否定する。出久自身だけではなく、俺の気持ちまでも否定する。腸がふつふつと煮えくり返る。
「てめえ、クソが!オレが間違えてるって言いてえのかよ。馬鹿にすんじゃねえよ。てめえに俺の何がわかんだ」
「だってそうだろ。君は僕の身体を使ってマスターベーションしてただけじゃないのか」
かっと頭に血がのぼった。「デクてめえ!死ねやあ!」と叫んで飛びかかって、その後のことはよく覚えていない。
気付いたら出久に馬乗りになって殴りかかっていた。騒ぎに駆けつけたクラスメイト達に止められても、勝己は怒鳴り続けた。
「クソが!」
部屋に戻るなり、勝己は吠えた。
部屋は防音設備が完備されている。相当の音でなければ外に漏れはしない。
だからあらん限りの声で怒鳴った。
「クソが!クソが!勝手なこと言いやがって!出久の野郎!」
ようは今の俺は認めねえってことじゃねえか。
なんであんなこと言っちまったんだ。おまけにキスなんかしちまった。言い訳しようがねえ。あいつの瞳に誘われるようにやっちまった。
いや、言っちまったもんはしょうがねえわ。今更誤魔化すつもりはねえ。
関係が拗れなくても、俺はあいつにいつかは手を伸ばしただろう。何をしても俺についてきたから、俺と同じようにあいつも俺を想っていると信じていたから。多分、それだけは信じていたんだ。
なのに今更違ったのだというのか。あの頃のあいつが俺に向ける感情は初めっから違うもので、ずっと誤解していたと言うのかよ。
今更、今更だ。てめえは違ったとしても。もう俺は溢れてしまったてめえへの気持ちを、元に戻すことなんてできない。ずっと押さえて来たんだ。
たとえ無自覚であったとしても、てめえは俺を騙してたんだ。
ベッドに横になると、スボンのチャックを下ろして下着に手を突っ込み、性器を握った。上下に擦り、屹立させる。雁首を捻るように撫でて扱く。
さっき抱きしめた出久の体躯を思い浮かべると、ぐんと手の中の肉棒が太くなった。キスを、柔らかな唇の感触を思い出す。太腿で押し上げた股の感触も。熱が集まり、硬くなる。自分の下に組み敷いた身体。押さえつけられた出久が、熱を帯びた目で見上げる。怯えた表情に反抗的な瞳。捻じ伏せて意のままにする。何にも変えがたい快楽。身体を貫いて心を貫いて、一瞬だけ所有欲を満たす。
勝己は唸り、先端を掌に包み込んで射精した。掌を濡らす温かい白濁。荒くなった息を整える。手の中で、膨張が解け柔らかく戻ってゆく性器。
マスターベーションしてただけだろ、という出久の言葉が脳裏を過ぎる。
「クソが!」
頭にくる。精液を拭き取り、ティッシュをゴミ箱に投げ捨てる。
勝己は電灯の光に手を掲げた。燃えるように赤く透ける皮膚。この掌から生まれる爆破の個性であいつを苛んだ。この指で肌に触れて濡れた最奥の体温を弄った。
どんな形であれ、いつもあいつに触れていた手だ。
畜生が。気づかせやがって。忘れようとしたのに。俺は出久をまだ手に入れたいんだ。俺のものにしたいんだ。
だが何故なんだ。何故あいつだけをこんなにも欲しいんだ。
あいつは気づいたんだ。そうだろうよ
俺を嫌いこそすれ、好きになるわけがねえんだ
憧れってやつがあいつの目を眩ませていたんだ
年月が経って冷静になって気づいちまっただけだ
あまりにも早くに出会ってしまったんだ
恋というものを知る前にどうして恋を認められるんだ
気になってしょうがなくて、苛々させる存在をどう捉えられるってんだ
幼い心を奪われれて絡め取られて、どうしていいのかわからなくなったんだ
てめえだけが俺を仰いでるだけなら、俺が時折てめえに惑うくらいならよかった
てめえが離れていくことで動揺する俺に気づきたくなかった
俺の方があいつより上だと根拠もなく信じていた
俺のものだと思い込んでいた
ああ!クソがクソが!
姿を求め声を求め、面影を夢に見る
俺がてめえを抱いて夢中になっていたときに
てめえは何を感じていたんだ
てめえの身体を使って自慰をしてるだけだと、思ってやがったのか
ふざけたことを言いやがる
てめえじゃなくていいならとっくにそうしてるってんだ
他の奴じゃダメなんだ。
てめえに触れてる時だけ、俺は俺でいられたんだ
また俺から逃げんのか、デク
第3章
「昨日の劇はよくやった。正直、思った以上の出来栄えだったぞ」
相澤先生に褒められて、教室内の空気が和む。
文化祭二日目の朝のショートホームルーム。昨日の緊張した顔から一転、今日のクラスの奴らの表情は弛緩している。
「いやあ、俺らもやればできるんで」と誰かが調子に乗ったところで「しかし演技力は全然だったな。セットや衣装で、八百万の個性に頼ったところが大きいのは否めない。次やるのなら、個性に頼りすぎないようにな」とぴしゃりと戒められる。
褒めて落とすか、流石教育者だ。しかし、劇の出来はともかく昨日は散々な一日だったぜ。勝己は舌打ちする。出久とは寮での朝食の時に顔を合わせたが、腹が立ってずっと口をきいてない。
「さて、本題だ。劇も終わったし、今日はお前ら全員暇だろう」
相澤先生は教室を見回した。普通科ならクラスの活動が終わっても部活のシフトがあったりするが、A組で部活に入ってる奴はいない。
「他のクラスの出し物を見に行こうと思ってました。なんでしょうか」挙手して飯田が訊いた。
「実はお前らに手伝ってもらいたい仕事があってな。昨日、早朝から夕方まで怪しい人影が学校の周りをうろついていたらしい」
ざわっとクラスが騒つく。飯田が勢いよく立ち上がった。
「ヴィランですか?」
片手を上げて飯田を制すると、相澤先生は続けた。
「わからん。勘だがヴィランの可能性は高いな。今日はそいつはいないんだ。諦めたのならいいんだが、ひょっとしたら、客に紛れて既に侵入したのかも知れん。」相澤先生は声を低める。「もしくは客を使って侵入したか」
「セキュリティは万全ですよね。以前も」と出久は言いかけて「あ、その」と慌てて口を噤んだ。
相澤先生は出久に構わずに続ける。「ああ、だが万が一のこともある。ヴィランは総じて執念深いし、外部の客が入るイベント事は狙われやすい。用心に越したことはないからな。悪いがお前らに、ふたりずつ交替でパトロールをして欲しい」
ふたりずつと聞いて嫌な予感はしたが、案の定、勝己は出久とペアにされた。ふたりを職員室に呼ぶと、相澤先生は監視カメラの映像を見せながら説明を始める。
「まずは爆豪と緑谷、お前らは校内を回ってくれ。コイツをもし見かけたら、絶対に戦ったりするなよ。すぐに知らせろ。外は俺達教師でパトロールする」
「なんでデクとなんだ」
勝己は苦々しい思いで抗議し、背後に視線を送る。出久は慌てて目を伏せた。
「お前らもう仲悪くないだろうが」
「はあ?どこ見て言ってんだ。良くもねえよ」
「仕事で仲良しと組ませる理由はないぞ。それから緑谷、さっきもだが、お前は迂闊なとこがある。気を抜くな」
「はい、先生」出久はちらっと勝己を伺う。「すいません、頑張ります」
「確信がないから言わなかったんだが、カメラに映っているこのヴィランに、見覚えがある気がするんだ。個性は不明だが、気をつけろよ」
ふたりは職員室を出ると、早速パトロールを始めた。出久はぽてぽてと後ろを付いてくる。落ち着かない。苛つくよりも胸がざわつく。
早足で歩いて引き離そうか。いや、聞きたいことがあるな。勝己は歩を止めて、出久と足並みを合わせた。隣に来た勝己に出久は戸惑っている。
「おいデク、以前の文化祭でもヴィランが出たんだな」
勝己の言葉に出久は目を見開いた。やっぱり図星か。
「てめえが水際で防いだってとこか。おい」
返事を促すように、肩をぶつける。
「知ってどうするの?」
「どうもしねえ。答え合わせしてえだけだ」
出久は苦笑した。俺の嫌いな出久の表情。隠し事をしてる時の顔だ。
「かっちゃんはやっぱりすごいな」
出久は顔を上げて、窓の外を仰ぐ。見えるのは雲一つない、秋の始まりの高い空。遠くにある何かを探すように、出久の視線は彷徨う。
「本番のかっちゃん、カッコ良かったよ。ドラゴンの上のかっちゃんも、立ち回りもすごかった」
「うぜえわ。世辞はいらねえ。黙れ」
「あの、かっちゃん。昨日はごめん、言い過ぎたよ」
勝己は立ち止まった。出久も歩みを止める。
「へっ。何を謝ったりしてんだ。マスターベションつったことか?てめえの本心なんだろうが」
「かっちゃん、だから言い過ぎたって…」
「てめえが本気で嫌がってたんならなあ、俺だって何度もしてねえよ。呼べば毎回のこのこついてきやがって。てめえもやりたかったんじゃねえのかよ!」
「それが、おかしくなってたってことなんだ。そう言ったよね」
「俺のことが好きでなくて、勘違いだったってんなら、性欲で動いてたんだろ。てめえの本能も否定しやがるのか!」
「せ、性欲って、声が大きいよ。かっちゃん」
「誰もいねえわ」
「す、好意がなかったわけじゃないよ。だから、君とのまともになった関係をなくしたくないんだ」
受け入れなければ今の関係すら無くすぜ、と言ったらこいつはどうする?いや出久は頑固だ。納得せずに受け入れるくらいなら、無くす方を選ぶんだろう。そういう奴だ。また耐えられないのは俺の方なんだ。返事をしない勝己に、出久は続ける。
「君との関係を構築しなおしたいんだ。かっちゃん。同級生として、君と向き合いたいんだよ」
「ああ?何をどうしなおすってんだ。その先に何があるんだ」
「今はそうしたいとしか言えないよ」
「その先に、てめえが俺のもんになる選択肢はあんのか?」
「わ、わからないよ。その時にならないと」
どこまでがこいつの本心なんだ。
「長くは待てねえぞ。俺は気が短けえんだ」
「うん、でも、少なくとも、中学の時の延長線上では付き合えないよ。あんなのは紛い物の関係だ。あの関係の先には何もない。普通好きな人に、あんな風にはしないだろ。いくら君だって」
「普通なんて知らねえよ!てめえしかいなかったのによ」
気まずい沈黙が流れる。ふたりは黙ったまま並んでパトロールを続けた。
各教室もお化け屋敷やコスプレ喫茶店や脱出ゲームや、工夫を凝らした企画をしている。人気のある教室は、廊下も教室の中も人混みで溢れていたが、怪しい客は混じってはいないようだ。A組の奴らも客になって並んでいて、「おお、お前ら二人で回ってんのかよ」と言われ、「仕事中だ、クソが」と顔を顰めて言い返した。
勝己の心は千々に乱れる。求めて止まない存在を隣にして身体が渇く。あの頃は憤懣を出久本人にぶつけた。出久の心を踏みにじり身体を貪った。
一方的な行為だっただろう。でもてめえも俺も同じように、求めているんじゃないのか。なのにそれを嘘だと否定するのか。
自覚させられた思いは、どこへ向ければ良いのだろう。情が移ったってんなら、それでもいいんじゃねえのかよ。てめえはどうなんだ。てめえのせいで俺はまた惑うんだ。
廊下の突き当たりまで来ると、人込みが途絶えた。交替まで時間が迫っている。
「二手に分かれようか」と出久は言った。
「指図すんじゃねえよ!クソナードが」勝己は舌打ちして答える。「俺は上に行くわ」
「う、うん。じゃあ、僕は下に行くね」
出久は階段を降りていった。階下から「迷子になったの?」と出久の声がする。手摺から覗くと3、4歳の子供が1人だけでいるようだ。出久は呼びかけて近寄っていった。
迷子くらいあいつ1人で大丈夫だろう、と階段を登っていこうとした時だ。
出久のいる方向から悲鳴と爆音が轟いた。
「いきなりかよ。クソが!デク!何があった!」
勝己は手摺に手を掛けると、飛び降りて階下に走った。
視界が土埃に遮られる。天井からバラバラと瓦礫の屑が落ち、壁にひびが入っている。窓硝子が粉々になって床に散っている。
出久が個性を使ったのだろうか。それともヴィランか?
土煙の先に出久が倒れているのが見えた。
服が裂け、シャツは血塗れで床に血溜まりができている。
「クソが!おい、ヴィランが出たのか。何とか言えや」
光が反射して、無数の針状のものが空中に浮かんでいるのが見えた。出久を包囲している。窓硝子の破片か?いや、違う。
ぞくりとした。あれはヤバイもんだ。
「かっちゃん」と出久が顔をもたげた。
「どうした!、爆豪、緑谷」
轟と飯田が駆けつけた。次のパトロールの2人だ。真面目な飯田のことだ。早めに集合していたのだろう。
「子供が叫んで逃走してきたぞ。何があったんだ」飯田が言った。
「その子、その子を追って」と出久は叫んだ。「攻撃はしないでね。多分ヴィランじゃなくて普通の子供だ」
「わかった。爆豪君、轟君、後を頼む。」
飯田は爆走して引き返した。
その足音に反応したかのように、出久の頭上に無数の針が降り注ぐ。
「クソが!」
「伏せろ緑谷!」
出久が頭を下げた瞬間、轟はその頭上すれすれに炎の絨毯を敷いた。
全ての針が赤い舌に舐めるように焼き払われた。
針は消し炭になり、ぼろぼろと崩れる。
はあ?何してやがんだ。
「バカかお前!全部焼いちまったら、正体がわからなくなるじゃねえか」
勝己は怒鳴った。こっちはそれで躊躇してたってのに。
「そうか、サンプルが必要だな」
轟は炎を消し、凍らせて消火する。
氷柱が出久を囲むように聳え、黒焦げの針が中に閉じ込められた。
「焦げてない針もあるかも知れねえ。だが探すのは後だな」轟は出久に駆け寄ると尋ねた。「何があった、緑谷」
出久はよろけながら立ち上がる。
「子供が1人でいたから迷子かと思って、声をかけたんだ。でも振り向いた子供の目から、蜘蛛の糸のようなものが抜け出て、 広がって網みたいになって」
その後、子供は我に返ったように、悲鳴を上げて走り去ったという。
出久は幾重にも網に囲まれて戦いようがなく、抗ううちに網の目が砕け、細かい針状の破片が降ってきて負傷したらしい。
「破片?さっきのか。網の一部というより、あの針のひとつひとつが、意思持って動いたようだったぞ」轟は首を捻る。
「針が本来の形かも知れない。ヴィラン本人ではなく、客に寄生して、しかも子供を送り込んて来るなんて」
「子供だからって油断しやがったんだろ。クソが」
悔しそうに拳を握る出久に、勝己は言った。
「う、うん、そうだね。誤算だったよ」
出久の声が掠れてきた。顔色が悪い。傷口すらわからないような細かい傷から、血が流れ続けている。ポタポタ落ちて、床の血だまりが広がってゆく。
細かい擦り傷ばかりで大きな傷はないのに、何故出血が酷いんだろう。
「とりあえず保健室に行こう。肩を貸すぞ、緑谷」
「は!まどろっこしいわ」
「え?あ?かっちゃん」
勝己は轟を押しのけて、出久を肩に担いだ。他の奴に触らせるかよ。
保健室に到着する頃には出久の意識はなくなっていた。ベッドに寝かせたが、シーツがみるみる赤く染まる。
「やべえな。緑谷の血が止まらねえ。傷を塞がなきゃなんねえし、輸血も必要だ」
「クソが!リカバリーガールは外の保健室出張所にいんぞ。連れてくるか」
勝己が保健室を出ようとしたところで、飯田が駆けつけた。
「子供は確保したぞ。先生に理由を話して預けてきた。緑谷くんの様子はどうだ?」
容体を話すと、青くなった飯田は自分がリカバリーガールを呼んでくる、と逆走していった。
「飯田が呼びに行ったぞ」
勝己は振り向いた。
目の前の光景に凍りつく。
出久が起き上がり、轟の首に腕を巻きつけていた。
キスをねだるように。誘うように誘われるように。
夢でも見てんのか。くらりと惑う。
次に頭が沸騰した。なわけねえ、夢じゃねえわ。
「何やってんだ、てめえ!」
両掌を暴発させて勝己は怒鳴った。
「おい?爆豪、保健室だぞ」轟が顔を向ける。
「あ、れ?僕、何して」
出久は勝己に気づき、びくりと震えた。腕をほどくと慌てて頭から布団を被る。
「おい、デクてめえ、逃げんのか」
布団を引き剥がそうとしたが、轟に「落ち着けよ、爆豪」と止められる。
「んだと、てめえもだ、轟!」
「何があったか、説明する。まずは落ち着け」
「クソが!」勝己は何とか気を鎮める。「言えよ、轟、何があった」
「大したことねえよ。お前が外に出てる間に緑谷が目を覚まして、俺に捕まって身体を起こしたんだ」
「出久からやったのかよ」
「ああ、ぼんやりして夢遊病みてえな感じだったけど」
「それだけか」
「他に何があるんだ」
何でもねえのか。ほんとにねえのかよ。
輸血を終えたと言って、教室に出久は戻ってきた。
傷跡は綺麗になくなっている。元々傷自体は多いとはいえ針で突かれたものだ、浅い傷ばかりだったのだろう。
教室には轟と自分の他は誰もいない。皆文化祭を楽しんでいるのだろう。
轟が問うた。「身体はもう大丈夫なのか?」
「うん、この通りだよ。心配かけてごめん。あの、かっちゃんも」
何もなかったように出久はヘラっと笑う。さっきの苛立ちが蘇ってくる。
「うぜえわ、クソナード」
「先生に連絡しなきゃな。下に救護室があるだろ」轟がこちらを向く。
「あ?指図してんのか、クソが!」
「いや、そのつもりはないんだが」
窓際にいた勝己はふと下に目をやった。丁度相澤先生が校庭を歩いてる。
「おい、相澤先生」窓から首を出して呼んだ。呼ばれたことに気づいてるようだが、相澤先生はなかなか上を見上げない。
「上だ!上!ああ、クソ!」と窓から乗り出して大声を上げる。
「緑谷、気配が違うな。匂いというのだろうか」轟は近寄り、出久の首元を嗅ぐ。「うん、匂い、じゃないな、でもなにか」
出久の手が轟の肩に手をかけられた。
「さっきから何言ってんだ、半分やろ…」
勝己が振り向くと目に入ったのは。
さっきも見た光景だ。
轟の首に縋り付くように腕を巻きつけ、抱きついている。
「クソデク!てめえ」
爆破音を轟かせながら「てめえ、何してやがる」と勝己は2人の間に飛び込み、引き離した。
「危ねえな、爆豪」
「え?かっちゃん、僕、…ごめん、轟くん」
勝己の形相を見て、青くなった出久は、慌てて逃げ出した。
「待ちやがれ!クソデク!」
勝己はその背中を追う。轟の声が背後から聞こえるが、知ったこっちゃねえ。
追いかけて、階段の手前で出久を捕まえた。壁に叩きつけ、怒りのままに声を荒げる。
「2度目だ!てめえ、あいつにモーションかけてやがったろ」
「かけるわけないだろ!変なこと言うなよ」
「轟ならいいってのか!クソデク」
「そんなわけない!違うよ。僕は…」
出久の言葉が途中で途切れた。
様子がおかしい。
顎を掴んで顔を上げさせる。目の焦点が合ってない。
「おい、どうした?」
匂いが、違う?さっき轟が言っていたように。勝己の肩に出久が手を乗せた。
「デク?」
名を呼ぶとはっと出久の目に光が戻り、「わ、かっちゃん」と慌てて勝己を突き放した。
勝己は一瞬呆けたが、我に返って怒鳴る。
「何しやがる!てめえ」
後ずさった出久は頭に両手をやり、泣きそうな面で髪をくしゃくしゃとかき乱した。
「ごめん、ごめん、かっちゃん。まただ。僕おかしいんだ。知らないうちに変な事してるんだよ」
第4章
「戻って来なきゃいいと思ってたがな」
相澤先生は自分達の顔を見るなり渋面を作った。そんな風に言うということは、戻ってくることを予期していたってことか。追いついてきた轟も一緒に保健室についてきやがった。リカバリーガールは出張所に戻ったらしい。
勝己の説明を聞いて相澤先生は嘆息した。
「緑谷、残念だが、やはり寄生されていたようだな。寄生生物はあの子供からお前に侵入したんだ」
「あの子は、どうなりました?」開口一番、出久は問うた。
「迎えに来た両親も心配していたし、帰らせたよ」
「よかった」
てめえの状態も忘れて、出久は安堵したらしい。
「バカかてめえは。良かねえよ。先生、ガキ見つかったのに、帰らせちゃ何もわかんねえだろうが」苛ついて勝己は言った。
「あの子供の個性じゃないとわかったからな。ただ、寄生生物の媒介として使われただけだ。奴が抜けたから普通の子供に戻っていたよ。誰に会ったかも、ここに来たことも何も覚えてないらしい」
「より強い個体、デクに移ったってわけかよ」
「寄生生物は体内にいるはずだ。さっきは緑谷の身体をスキャンしても、何処にも見当たらなかったがな。巧妙に隠れているのか、擬態しているのか、どんな性質の寄生生物なのか、調べなければ分からん」相澤先生は溜息をつく。「なにせ情報が足りない。この個性を持っている敵を捕まえられればいいんだがな。寄生生物はそいつが作ったやつなのか、口田みたいに操っているのか。せめて寄生生物の一部でも、手に入れられれば良かったんだが」
「すまねえ、俺が全部燃やしちまったばかりに」沈んだ調子で轟が言った。
「まったくよお!残らず消し炭にしやがって」
出久が戻る前に確認しに行ったが、氷漬けにした針も全部炭化していた。下手すりゃ出久も黒焦げだったわ。もっとも、自分が一瞬躊躇している間に轟が片付けてしまったことが一番気に入らない。
「そんな、轟君のせいじゃないよ。僕はほら、全然大丈夫だし」
「ああ?んな訳ねえだろーが!クソデクが」
どこが大丈夫なんだと勝己は憤る。てめえさっき何しやがったのか忘れたのかよ。
「もしかしたら現場に何が残ってるかも知れねえ。探してみる」と轟は言った。
「頼んだぞ。こっちはとりあえず、もう一度緑谷を調べてみよう。症状に出たからには、奴が見つかるかもしれん」
出久を残して、轟と勝己は保健室を辞した。「おい」と轟に呼び止められる。おいじゃねえと苛つく。てめえと話すことなんかねえわ。
「んだよ、てめえは焼け跡に行くんだろーが!俺は行かねえぞ」
「ああ、俺だけで行くつもりだ。というか、お前はこの件に関わらない方がいいんじゃねえのか?」
「はあ?てめえ、何言ってやがる」
「緑谷が関わることになると、お前の反応は過剰になる。それじゃ冷静に判断できねえだろ。それに」と轟は続ける「緑谷も望まねえだろう」
「俺は冷静だ。関わろうが何だろうが、てめえに関係ねえわ!」
「緑谷はお前との関係を、もう間違えたくねえと言っていた。昔と同じことは繰り返したくねえんだろ」
「ああ?てめえに俺らの何がわかんだよ」
「高校以前のお前らに何があったのかは知らねえよ。けど、あいつには辛かったんだろうってことはわかるぜ。チャラにして、新しくお前と友人関係を築き直したいっていう、あいつの気持ちを俺は尊重するぜ。俺も親父との関係築き直してえからな」
「てめえの家庭の事情と一緒にすんじゃねえ」
轟の口から出久の名前が出ると、心底腹が立つ。奴が出久に戦線布告しやがった時からだ。俺以外誰も見てなかった出久を、奴も特別視しやがったからだ。煽られて戦って出久に救われたくせに、落ち着いてやがるからだ。
一番こいつが気に食わねえのは、出久が求める理想の友人関係って奴を、俺に見せつけてきやがるからだ。
何も知らねえくせに。友人関係だと?俺と出久が友達なんぞになれるわけねえんだ。くそくらえ。
何度も試みたんだ
ただの石ころだと、何度も思い込もうとしたんだ
川に落ちた時、救われたと思っちまった
他の奴だったなら何とも思わなかったろう
否定したかった
手を差し伸べた出久の姿に、オールマイトがだぶって見えたなんて
俺の心細さを弱さを見透かすように
大丈夫、一人じゃない、僕がいる
うねり光る水面、逆光の中の人影、白い小さな手、木々を伝い響く蝉の声
いつまでも忘れることのできない光景
出久がどういうつもりだったのかは関係ない
俺がそう思った、そう見えちまった
あの瞬間、あいつは俺の中で特別になっちまったんだ
出久より上にならなければ、俺は俺を許せない
上でいればあいつをどうでもいいと思えるはずだ
この俺があいつを意識するなんておかしいんだ
だがどんなに石ころだと思おうとしても、あいつは俺の中で存在感を増すのだ
どこにいても目の端に出久の姿を探す、声を探す
いつも気になって苛ついて、顔を見れば、気に触る癪に障る
一人じゃない、僕がいる
俺に手を差し伸べた瞬間から、あいつは俺の中に棲みついちまったんだ
「おい、デク」と背後から呼んだ。
保健室の前でウロウロしていた出久は、びくりと反応して振り返る。
「てめえ、なんで教室に戻らねえんだ。検査終わったんだろうが」
「うん、済んだよ。やっぱり何も見つからなかったって」
「しょうがねえ。じゃ、教室戻んぞ」
「戻れないよ。もし女子に抱きついたりしたら、もう僕、恥ずかしくてその子の顔が見れなくなるよ」
「はあ?理由を言えばいいだろうが」
「だって、無理だよ。自分が無理」と出久は首を振る。
こいつはまだ女子を神聖視してやがんのかよ。馬鹿か。女子っつってもヒーロー目指すような奴らだぞ。
轟ならいいのかよ、と聞きそうになり、なんとか堪えて勝己は言った。
「おいデク、来い。ここにいたら邪魔になんだろーが」
図書室に文化祭の展示はないが、閉鎖されてるわけではない。ポツポツと行き場に迷った生徒達が、一休みしている。壁際に並んだ端末の前に出久を座らせ、勝己は隣の席から椅子を持ってきて隣に寄せて腰掛けた。
「なんで図書室に来たの?」
「手がかりがねえなら、寄生生物の性質について調べるしかねえだろ。」
「なるほど、そうだね。何もしないよりいいね」と言ってから、出久は首を傾げる。「でも部屋のパソコンでも調べられるのに」
「図書室ならいくつも監視カメラがあるし、何かあれば誰かが駆けつける。俺も対処できるしな」と言ってから付け加える。「部屋で俺と2人きりでもいいぜ」
「わ、わかったよ。調べよ」
「警戒してんのかよ」
「そういうわけじゃないよ」
図書室に所蔵してる図書は電子書籍になっているので、端末から全文見ることができる。期限付きの電子データで貸し出しも出来る。紙の書籍もあるが、大多数はデータを選ぶようだ。
寄生生物で検索すると相当な数の書籍が出てきた。適当に選んでクリックする。
・寄生生物は宿主を己の奴隷にする
ハリガネムシに寄生されたコオロギは、成長したハリガネムシを放流するために、水に飛び込む。
クモヒメバチは蜘蛛に寄生して、自分のために網を作らせる
エメラルドゴキブリバチはワモンゴキブリに卵を産み、生かしたまま食料とし自分のための部屋を作らせる
フクロムシはカニを去勢し自分の卵を育てさせる
冬虫夏草はオオアリに寄生して、草に登らせて噛み付かせ、周囲に胞子を散布する
冬虫夏草。ガキの頃に出久が見つけたやつだ。背筋がぞわりとする。こんなのにとりつかれたのだとしたら。
暫くして出久は「全然頭に入らないよ」と呟いた。「てめえ、真面目にやれや」と勝己は出久の足に蹴りを入れる。
「いた!違うんだ。寄生生物関連書籍の文字列が認識できないんだ。普通の文字は読めるのに」出久は弱音を吐いた。
「ああ?寄生生物はてめえの脳にいるんじゃねえのか」
言ってからはっと気づく。そうなのか。夢遊病みたいだったと轟が言っていた。自分に抱きついた時も何かおかしかった。出久は頭の中の何かに操られているのか。
「そうかも知れない。嫌だな。今だって気を抜けば、意識をふっと持ってかれそうになる。実を言うと、僕、理性を保つのに必死なんだよ」
「意識を持ってかれたら、てめえはどうなる?」
「わかんない。理性を失えば何をするか。でも多分、さっき轟くんに抱きついたみたいにしちゃうんじゃないかな」
「轟にモーションかけてるみてえだったよな」
「やめてよ、かっちゃん」
「しなだれかかって、腕を首に巻きつけてよ」
「やめてってば。僕の意思じゃないよ」
あの光景を見て、どれだけ腹わたが煮えくりかえったか。
「構わねえ。俺にやってみろや」
「嫌だよ。絶対に嫌だ」
「散々俺に抱かれてたろうが。轟に出来て俺に出来ねえのかよ!」
「君と轟くんは違うだろ」
声が大きくなってしまい、静かにと司書に窘められた。舌打ちし、気をとりなおして、端末の画面に向かう。
寄生生物の奴は出久の中で何をしてえと思ってんだ。目的はなんだ。対処のために寄生生物の習性を知らなくちゃいけねえ。
てめえを寄生生物の餌にするわけにはいかねえんだ。
・寄生生物は被捕食者を次の宿主である捕食者に狙われやすくする。
吸虫に寄生されたメダカは、水面で派手に動き鳥に捕食される
ロイコクロリディウムに寄生されたカタツムリは、改造され動きが素早くなり、物陰から出て鳥に捕食される
・寄生されることで活動的になる例もある。
マラリアに寄生された蚊は一層獲物を噛むようになる。
狂犬病の犬が噛みつきたがるのは唾液に菌を持つからである
・幼生と成体で異なる宿主を持つ寄生生物について
幼生の宿主を中間宿主、成体の宿主を終宿主という。中間宿主では幼生期の発育を、終宿主では繁殖を行う。中間宿主を介さず終宿主に侵入しても成長することはない。
ロイコクロリディウムはカタツムリが中間宿主で、鳥が終宿主である。
トキソプラズマは中間宿主が人や豚であり、終宿主は猫である
寄生生物は中間宿主の中で成長した後に、体外に出て行くか、体内で終宿主に捕食されるのを待つ。
中間宿主と終宿主の橋渡しの役割のみを果たす宿主を待機宿主という
ワンフォーオールにとって、デクもオールマイトも中間宿主みてえなもんか。
正義の名のもとに心を支配して、パワーを与えて命を捧げさせるんだ。そうして、次の宿主に移るんだろう。
出久、てめえも自分のすべてをOFAに捧げんだろ。オールマイトがしたように。まるで寄生生物が己の目的のため宿主の心をコントロールするみてえじゃねえか。
継承者はワンフォーオールの奴隷なのだろうか。
捕食者と被捕食者の関係とは何だろう
寄生生物を体内に宿す被捕食者が捕食者を求める。
被捕食者の中の寄生生物が食わせるために捕食者を誘う。
飢える捕食者のために寄生生物を持つ被捕食者が現れ捕食者は腹を満たす。
果たして捕食者にとって寄生生物は害と言い切れるのか。
ポケットの中の携帯がぶるんと震えた。
第5章
「これを見てほしいんだが」と轟が掌に乗せた氷を示した。「氷を融かした後に、まだ廊下の隅に氷塊が残っていたんだ」
中に針状の物体が閉じ込められている。
携帯で呼ばれ、勝己と出久は急いで保健室に駆けつけた。轟が手掛かりを見つけたらしいという。急かすふたりに、見てみろと相澤先生は手招きした。
轟の手の中の禍々しいもの。
「無傷みたいだな。生きてるかもしれない」
相澤先生は氷塊を受け取ってシャーレに乗せ、慎重に周囲の氷を融かして、出久に見るように促した。
「これか、緑谷」
「はい、あ」くらりと出久はよろけたが、何とか踏ん張り「それです」と答える。
針がうねうねとくねり出した。
「危ねえ!」と轟が手をかざす。
相澤先生が個性を発動し、凝視すると針は動かなくなった。ほうっと出久は息を吐く。
針を透明なケースに仕舞うと、相澤先生は言った。
「校舎の外をうろついていたヴィランのことだが、寄生生物を人に取り付かせる個性を持つ奴だ。指名手配されてるが、今までなかなか尻尾を掴ませなかった。ヴィランのDNAが手に入ったのは収穫だな」
「自分は動かねえで、他の奴を操るわけかよ。けったくそわりい」
罪のない宿主を盾にするようなやり方だ。卑怯な野郎だと勝己は憤慨する。
「これを見ると、生物というより亜生物というべきか。実在する生き物をモデルに個性で作ったものだな。八百万の個性に似てるが、逆だ。八百万の個性は元素単位から構成して、生物以外の本物を創造する。これは本人の細胞を培養して、亜生物を作る個性だろう」
「生物を創造するんですか。すごい」
状況を忘れたのか、出久は感心しているようだ。勝己は苛ついて出久の背中を思いっきり叩く。
「てめえ、クソが!感心してんじゃねえよ。わかってんのか。てめえがその個性を食らってんだろうが」
「いたあ!わ、わかってるよ。かっちゃん。でも命を作るなんてすごいと思わない?」
「命じゃないぞ。亜生物だ」相澤先生が言う。「どんなに模倣しても本物の生物じゃなく、本人の細胞に過ぎない。いわば爪や髪の毛みたいなもんだ。元がその個性をもつ人間の細胞だからこそ、本体さえ目視できれば、俺の個性で止めることができるわけだな」
「つまり、緑谷の身体から追い出しさえすれば、捕獲できるんだな」轟が言う。
「ああそうだ。だが、体内の何処にいるかわからない以上、手の出しようがない。せめて体内の潜伏場所の特定が出来れば、いざとなれば手術するなりして対処できるんだが。」
出久の身体をスキャンしても、何処にいるのかわからなかったのだ。出久の身体の何処かで眠っているのだろうか。そこが脳なのか脊髄なのか心臓なのか。
活動する様子はない。ならば出久の奇行の意味は。ひとつだろう。
勝己は言った。「こいつのモデルになった寄生生物は、幼生と成体で異なる宿主を持つやつなんじゃねえか」
「なるほどな。宿主の移動をしようとしているのか。モデルになった寄生生物の性質も模倣してるかも知れんな。調べよう」
相澤先生はパソコンに向かい、暫くして検索した結果を見せた。
「これだろうな。動物とか4歳以前の子供とか、個性のない個体に食らいつき、成長してから、個性持ちの宿主に移って繁殖するタイプだ。本物は現在はほぼ駆除されている」
「じゃあ、そいつと同じ性質なのかよ。やべえだろ。緑谷ん中で繁殖すんじゃねえのか」轟が心配そうに言う。
「そこが不思議なんだがな。緑谷の中じゃ繁殖していないようなんだ。幼生の宿主を中間宿主、成体の宿主を終宿主というが、緑谷は何故か中間宿主もしくは待機宿主に当たるらしい。寄生生物は繁殖はせず、次の宿主を探している状態だな」
「おかしいだろ。個性に反応するなら、何故緑谷の中では繁殖しないでスルーするんだ?」
「出久がガキなんだろ」と勝己は素知らぬ素振りで嘯く。
轟は知らないのだ。出久の力は借り物だということを。勝己と出久とオールマイトの3人だけの秘密なのだから。
そうか、出久は元々無個性だ。OFAを得ても個性因子自体はないのだろう。だから、終宿主にならなかったんだ。寄生生物は子供の中でもう成体に成長したのだ。出久は望まれざる宿主なのだ。なら、個性のある奴に侵入しなかったのは、不幸中の幸いだったと考えるべきなのか。
「僕でよかった」とポツリと出久が呟いた。
いや、幸いなわけねえわ。ざけんじゃねえ。何がよかった、だ。てめえの呑気さには頭にくるわ。
出久が寄生生物に侵入されてから、勝己は今まで以上に、出久に引き寄せられる。おそらく轟もなのだろう。出久に抱きつかれていた時の奴の様子は、平常ではないように見えた。
より強い個体に引き寄せられるのだろうか。それとも宿主になる奴なら誰でもいいのか。どちらにしろ個性持ちに渡ったなら、そいつが終宿主になるんだろう。
それが奴の狙いならば、と勝己は相澤先生に提案した。
「どこにいるかわからない寄生生物なら、次の個体に移動する瞬間がチャンスだ。寄生生物をおびき寄せ、移動するときに捕まえるしかねえだろ。そいつがデクから移動する瞬間を狙えばいい」
「なるほどな。なら俺が囮になろう」
勝己の案に乗って轟が言いだした。何だこいつ。おれが先に言ったんだろうが。
「ざけんなてめえ!」
「ダメだよ。もし捕獲できなくて君に移ったら繁殖するかもしれないんだろ。そんなのダメだ」
出久は首を振る。相澤先生も有無を言わさない口調で言う。
「緑谷の言うとおりだ、轟。これ以上生徒を危険な目に合わせるわけにはいかない。どんなタイミングで移動しようとするかも不明なんたからな。とりあえずお前らは教室に戻るんだ」
「ああ、わかった」轟は渋々といった様子で戸を開け、勝己の方を振り向いた。「爆豪、行かないのか?」
勝己は轟を睨み、出久に視線を移した。出久は所在無さげに戸惑っている。轟は答えない勝己を暫く見つめて、先に行ってると静かに言った。
轟が保健室を出て行くと、勝己は口を開いた。
「俺が囮になる。あんたはそれを阻止するんだ、先生」
「お前な。駄目だ危険すぎる。許可できん」
相澤先生は眉を顰め、厳しい表情になった。勝己は拳を握ると相澤をまっすぐ見据える。
「デクん中にヴィランがいるなんて、気色悪くて我慢できねえんだ」
「ちょっと待ってよ」と出久が慌てた。「僕がおかしくなったの、見てるだろ。君や轟くんに抱きついたんだよ。あんなの、先生達の見てる前でなんて、嘘だろ」
「ああ?てめえ、仕方ねえだろうが。おい、先生!」
「駄目だ、駄目だよ」と必死で出久は首をぶんぶんと振る。「危険過ぎるよ」
「さっきも言ったがそれはないな」と相澤は嘆息する。「これ以上、生徒を危険に晒すことはできない。戻っていいぞ、二人とも。手段はなんとか考えよう」
ふたりは保健室を辞した。歩き始めた勝己の後ろを出久は付いてくる。
「早く来い」と勝己が言うと、
「うん」と答える。
いつかのように。
遠く、文化祭の賑やかな声が聞こえる。
職員室のあるこの階の廊下には、自分たちの他には誰もいない。
出久の上履きが後ろでペタペタと音を立てる。
出久とふたりきりになったな、と思う。
「おいデク」
返事がない。
足音が止んだ。出久が立ち止まったのだ。
ゆっくりと振り返る。
出久の虚ろな視線が彷徨う。
やっぱり来やがったな。
こいつはターゲットが一人になったと認識したら出てくるんだ。他の奴がいると出てこねえ。保健室では俺が出て行って轟とふたりになった時、教室では俺が窓の外の先生を呼んでいる隙に出やがったからな。
勝己は踵を返して歩み寄り、出久の身体に手を伸ばした。ふわりと匂いが漂ってくる。捕食者を誘うフェロモンのようなものなのだろう。
出久の腰を抱きしめ、引き寄せて両腕を背中に回す。すっぽりと腕に収まる出久の温もり。シャツの下の筋肉の感触。足を出久の足の間に入れて太腿で股をじりっと押す。
出久の腕が勝己の肩に縋り付き、そろりと首に回された。
止めなければいい。出久が俺を求めてるんだ。
寄生生物を宿した被捕食者として捕食者の俺を。
理性など吹っ飛ぶほどの抗いがたい本能。
宿主は捕食者の心をコントロールする。寄生生物があいつをより美味そうに見せるのだ。鳥の前に腹を見せて翻る魚のように。こいつを喰らえと吠えるんだ。
出久、俺はてめえの捕食者なんだ。
「限界なんだクソが」小声で囁く。「大人しく犯されろよ、デク」
出久の瞳が揺れる。僅かに意識は残っているのかもしれないが、それとは裏腹に抵抗できないようだ。
ボタンを外し、シャツを肌ける。素肌に手を這わせても、為すがままな出久に興奮する。
頬ずりして、唇に触れる。少し開いた唇に吸い付き、舌を口内に押し入れて、貪るようにキスをする。吐息が熱い。目眩がしそうだ。
出久の瞳が反転したように見えた。
いや、白目が黒く何かに覆われたのだ。
勝己は出久を壁に押さえつけた。これが寄生生物の移動する瞬間だ。
「かかったな!寄生野郎が!俺の他には誰もいねえ。安心して出てきやがれ」
出久の眼球から蜘蛛の糸のように細い糸が飛び出てきた。
糸を放出しながら、出久は壁を背にして崩折れる。
「おい、デク。てめえ!寝てんじゃねえぞ!」
出久の足元の空間に糸が積まれてゆく。霧のような細密な糸。暫くして糸が出なくなった。全て出尽くしだのだろうか。出久の閉じた目から血が流れている。無事か。
糸がむくりと動き出した。ひと塊になり勝己の方に向かってくる。
咄嗟に飛び退くと、うねる糸の塊を爆破する。
だがパラリと崩れても糸はまた寄り集まる。
細密な蜘蛛の糸のように空中に広がり、編まれ広がってゆく。
「起きろデク!クソカス!」
勝己は出久を抱き起こし、ガクガクと揺さぶる。
「…ん、起きてるよ。動けないんだ。かっちゃん、僕のことはいいから逃げてよ」
「ああ?何言ってやがんだ。カス!」
出久は目を開けた。白目は元に戻っているが、酷く充血している。
「頭の中からそいつがなくなったからやっと言えるよ。衝撃タイプの攻撃がきかないんだよ。バラバラに解けるだけなんだ。かっちゃん、逃げ、いや、相澤先生を呼んできて」
「てめえ、喋んな、黙れ!」
クソが。逃げられるかよ。逃げたらまたこいつがてめえん中に戻るだけだろうが。
網は2人を包みこもうと狭まってくる。
勝己は出久を糸の包囲網の外に突き飛ばした。
よく見ると糸じゃなく、針状の寄生生物が寄り集まって、網状の形を成しているのだ。
網は勝己の腕に触れてバリバリと皮膚を裂いた。プツプツと血が吹き出す。
「傷を負っちゃ駄目だ。本体が傷口を狙ってくる」
「ってーな!これは本体じゃねえのか」
「多分、武器だ。寄生先への侵入ルートを作るための」
「きめえ。本体はどこだ、デク」
「網の何処かに包み込まれてる」
どこから入ろうとするんだ?目からか口からか。皮膚を破って入るなら手や足からか?
ピリッと皮膚が割かれる痛み。無数の針が服の腕からでも皮膚を刺す。
さして痛くもないのに、シャツがみるみる赤く染まる。
血が止まりにくくする何かを出しているのだ。出久の時と同じように。
「クソが!」
「かっちゃん!逃げてよ、かっちゃん」
出久は這いつくばりながら、勝己の方にじり寄ろうと足掻いている。
網の中心に針と同じ大きさだが、形の歪な白い塊が見える。
あれが本体って奴か。クソが!
続けざまに爆破してみるが、びくともしない。
畜生が!目視出来てるのに爆破出来ねえのかよ。
一気に消し炭にするとか、まとめて凍らせるならいけるんだろうか。轟の個性のように。クソ!轟なんかに任せられるかよ。
網がバラバラと崩れた。爆破、効いたのか?
だが違った。
夥しい針の群れは空中に放射状に広がり、勝己を幾重にも取り囲んだ。
「かっちゃん!」
「クソが!」
針が一斉に勝己に襲いかかる。
無数の針が皮膚を裂いた。
「爆豪!」
廊下に響く怒鳴り声。
途端に針の動きが止まった。バラバラと床に落下して山を築く。
相澤先生が駆けつけたのだ。
「相澤先生、よかった」出久は身体を起こす。
「いってーな!クソが!」
安堵したのが悔しく、勝己は足で蹴って針の山を崩す。
寄生生物は捕獲された。
「よくやった爆豪」ほっとした声で相澤が言った。
「遅えよ!」
「相澤先生、かっちゃんと組んでたの?僕を騙してたの?先生まで?危険じゃないか」
出久は目を擦りながら、非難めいた声音で問う。
「いや、組んではいないぞ。爆豪は止めても聞かないだろうからな。様子を伺っていたんだ。あれでな」先生は監視カメラを指差す。
「そうなんですか。かっちゃんは、それを見越してたのか、でも…」
「てめえの脳が寄生されてんだとしたら、てめえの中の寄生生物とやらを、本気で期待させねえと駄目だろうが」
さっきまでの心をもぎ取られるような衝動は止んだ。あの場で本気で出久を抱こうとしていた。寄生生物を持つ被捕食者は捕食者を誘うのだ。抗いがたい力で。
「褒めていいものか迷うところだが。爆豪は自分を囮にしたんだ。なかなかできることじゃないぞ」
「ああ、はい、そうですけど、でも」出久はもじもじと続ける。「ありがとう、かっちゃん」
「へっ!」
出久の中に他の奴が居るのが、我慢ならなかったのだ。人だろうが、人じゃなかろうが。結局は俺はてめえを求めているのだ。誰にも渡したくねえんだ。
「まあ、いつ出ていっていいものかどうか、迷ったがな」
「なんのことですか?」
相澤先生の言葉に、出久は首を傾げている。先生が見張ってると知りながらキスしたことか。あん時はもう出久は意識を乗っ取られていただろうから、覚えてねえんだろう。
ガチでやるわけねえだろうが。けど、やっちまってもいいと思った。途中で止められたから不完全燃焼だ。足りねえ。
くらりと頭が揺れる。ぽたぽたと血が滴れる。シャツから血が染み出してくる。血も足りねえってか。
「クソが。貧血か。血が出過ぎたみたいだ」
てか、止まらねえ。そうか、そういう手口か。出血させて、体力を奪い動きを鈍らせ、宿主の抵抗力をなくしてから、本体が取り付く。
出久だけなら奴を避けて逃げることも出来たはずだ。きっと出久は子供を抱き上げて、両手を使えない状態で襲われたのだろう。子供を逃がした時には遅かったんだ。
「かっちゃん!」と呼ぶ出久の声が遠くなる。
倒れんな、俺の身体。あいつの前で倒れんな。あいつは強い俺しか見てないんだ。もし俺が弱くなれば。俺を見やしないんだ。
保健室の天井がぼんやりと見えた。
大量出血のせいか、目眩がして頭を起こせない。血が不足してるのだ。
切羽詰まった出久の声が聞こえる。
「輸血なら僕の血を上げて!」
「爆豪は何型だ」
「A型だよ。ぼくはO型だから、僕の血をあげられる。相澤先生!」
出久は錯乱しているようだ。
「落ち着け、緑谷。型の違うお前のより保管してるA型血液の方がいい。今リカバリーガールが輸血の用意をしている」
「かっちゃんは強いんだ。負けないんだ」
出久は血相変えてまるで子供のようにただをこねる。相澤先生は珍しく慌てているようだ。きっと先生には、今の出久があいつらしくなくて理不尽に見えるんだろう。
俺を強くてタフだと信じている。勝つことを諦めないのが君じゃないかと押し付ける。我儘で頑固で融通がきかない。それがあいつだ。出久は信じてるんだ。俺を。
勝己は怒鳴った。「リカバリーガール、いねえのかよ!」
「ここにいるよ、なんだい」
奥から点滴の道具を持って、リカバリーガールが顔を出した。
「かっちゃん、起きたんだ」出久は泣きそうな顔だ。
「今すぐ怪我を全部治せや」
無数の針で刺されたような傷。見えない傷口から血の玉が転がり落ちる。血はまだ止まっていない。
「ひとつひとつは塞ぐのは簡単だろ。塞いじまえば傷なんか」
「いや、緑谷の時より傷が多くて深いんだ。刺さった針の数が尋常じゃない。一度に治せば、お前の体力が持たないかもしれないぞ」相澤先生は言う。
「輸血しながら、ゆっくり直したほうがいいよ」
リカバリーガールが子供を宥めるように言う。
「舐めんなできるわ」
あいつが俺を見てるんだ。あいつが俺を信じてるんだ。俺がへこたれるわけにはいかねえんだ。強くなければあいつは俺を見ない。
俺はどうだ。俺は出久が弱くなったなら。
ひょっとしたら、歓喜するのかもしれない。
弱くなれば他の奴らは出久から離れていくかも知れない。でも俺にとってどんな出久でも出久は出久だ。俺は絶対に離れねえ。
そうなれば出久も俺から離れることなんできねえだろ。中学生の頃みたいに、俺だけのものになんだ。
ああくそ!思考がぐちゃぐちゃだ。
雄英の奴らはそんな奴らじゃねえってわかってる。
たとえあいつが弱くなっても、今更もう手に入るわけねえわ。
俺は捕食者だったのだ。自覚する前からあいつは俺の獲物だったのだ。いつかは皮膚を囓り肉を噛み裂くのだ。だからあいつは無意識に警戒していたのかもしれない。
捕食者は獲物よりも運動性能が優れてなければ食いっぱぐれる。だから俺はあいつより強くなければならないのだ。
一人の人間にとって自分が特別でありたいと渇望するのは、自分にとって相手が特別であるからだ。どんなに相手をつまらない者だと、取るに足らないと貶めようとしても、心の奥底が求めて止まないんだ。
自分だけが相手の唯一の存在でありたいと。
第6章
傷は全て治療されたものの、体力を消耗した勝己は半日寝込んだ。目を覚ました時には既に日は傾き、黄昏の橙色に部屋が染まっていた。
「やっと起きたんだね」
出久が枕元に座っていた。目元が赤いようだ。顔を染める夕焼けのせいか、泣いていたのか。
保健室の窓の外から音楽が聞こえる。外で何をしているのか、時々歓声が上がった。
「今、後夜祭をしてるんだよ」勝己が問う前に出久は答える。
「てめえは行かねえのか」
「うん」出久は済まなそうに目を伏せる。「打ち上げは行ったよ。皆も君を心配してた。君が回復したら寮でまた打ち上げしようって」
「いらねえよ」
「後夜祭の後には戻ってきて、後片付けするそうだよ。僕も行くけど。あ、そうだ」
出久は手に持ってた袋を開けて、中を見せた。
「ちょっと食べ物を持ってきたんだ。かっちゃんが起きたらお腹空いてるかなと思って。打ち上げの時の残りだけど」
そういや腹が減ったな。「寄越せ」と勝己は出久が袋から出したパンや菓子をがっつく。「かっちゃん、お茶もあるよ」と差し出されたペットボトルをひったくるように受け取る。喉を鳴らして嚥下する。冷たさが胃にしみる。
「ごめんよ、かっちゃん」
「ああ?」
「元はと言えば全部僕が迂闊だったせいだ。僕が気をつけてれば、こんなことにならなかった」
「あ?ざけんじゃねえぞ。デク!」勝己は眉根を寄せて睨みつける。「てめえのはてめえのミスだ。俺のは俺の判断だ!謝んじゃねえよクソが。起き抜けに苛つかせんじゃねえ」
怒鳴ってから、確認していなかったことに気づく。奴は本当に出久の中から抜けたのか。
「てめえん中には、もういねえんだな」
「うん、僕は大丈夫。先生呼んでくるね」
勝己の身体は完全とは言えないが回復したらしい。「無茶をしたけれども、大したタフネスだね」とリカバリーガールは驚き半分呆れ半分。もう帰っていいと保健室から送り出された。
「かっちゃん、後夜祭行く?寮に戻る?」
「教室に行くわ。来い、デク。てめえに話がある」
勝己はそう告げて「あ、うん、あの」ともぞもぞと言い淀む出久の腕を掴む。
夕暮れの教室には柔らかな黄色い光が差し込んでいる。教室には誰もいない。まだ後夜祭は終わらないようだ。
「デク」と名を呼ぶ。怒りを帯びてない声で名を呼ぶのは、随分と久しぶりな気がする。
「何、かっちゃん」戸惑い気味に出久は答える。
「てめえを抱いたのは、マスターベーションなんかじゃねえよ」
「い、いきなり何、その話はもう。かっちゃん」
狼狽える出久に構わず勝己は続ける。
「てめえがどうだろうとな。俺のやりてえことは変わんねえ。てめえが俺への認識を改めてえってんなら、それまで待ってやる。てめえは俺のもんになるしかねえんだ。逃さねえからな」
「かっちゃん、僕は応えられないよ」
「先はわからねえって言ったのは、てめえだろうが。俺は諦めるつもりはねえ」
触れてしまったのだ。そう簡単に手放せやしねえんだ。出久は唇を噛んで俯いた。外から生バンドの演奏する音楽と歓声が聞こえる。黙ってんじゃわかんねえよ。勝己は焦れた。
「何だよ、言いたいことあんなら言えや」
「無理なんだ」出久は漸く口を開いた。「君と新しい関係を構築するなんて、無理なんだよ。僕は結局、君を皆と同じようには思えないんだ。認識は変えられない。だから待っても無理なんだ」
「なんだとてめえ!」
「君に情が移った事を、過去の話として轟君に話してたのに。よりによって君に聞かれてしまった。」
「俺のことだろうが。俺が聞いたからってなんだ」
出久は俯いて言葉を紡ぐ。
「知られても、それだけだと思った。でも君がまたやろうって言うなんて。僕は怖くなった。付き合ったって、また昔の繰り返しになるだけじゃないか」
「ああ?なら待てっつったのはなんだ。俺をその気にさせて、てめえ、この俺を騙しやがったのか」
「できると思ったんだ。本当だよ。でもやっぱり無理だ。僕にとってやっぱり君は君なんだ。僕は憧れるだけで良かったんだ。手の届かない君に。 君が応える可能性なんて有り得なかった。なのに中学の頃、あんな形で僕は君と関係してしまった。心も身体も踏みにじられて、君の形を刻み付けられて、自分の弱さが辛かった。君を怒らせるのが怖かった。君が憎かったよ」
出久はシャツの合わせ目を掴む。ぎゅうっと掴んで指が白くなるほどに。
「それなのに君に情が移ってしまうなんて。そしたら今度は見捨てられるのが怖くなった。酷い形でも、僕に関わってくるのは君だけだったから。セックスしてる一瞬だけは、君のことが怖くなかったから。でもそんなのおかしいだろ。憧れて憎くて怖くて、僕はどうしたいんだろうって、混乱して自分が壊れてしまいそうだった」
出久は顔を上げて薄く微笑んだ。
「君との関係が終わった時、ほっとしたんだ。もう僕は抱えきれない混乱から解放されたんだって。だから、もう二度と君に応える気はない。応えちゃいけないんだ」
「てめえ。またかよ。またてめえは嘘をつきやがった!」
繰り返し繰り返し、俺を偽り続けるんだ。勝己は掴みかかり、出久の首元を締め上げる。なんで俺は嘘ばかりつくこいつが欲しいんだ。出久は抵抗もせずに勝己を見上げる。
「君が眩しいんだ。今も昔も。君は僕を捩じ伏せるために抱いたんだろう。君には一時の気の迷いや好奇心に過ぎなくても、僕は潰れてしまう。また囚われるんだ。僕を否定した君に。呪縛なんだ。そう思うのは錯覚なんだってわかってるのに」
「 はっ!てめえは全部錯覚だった言うのかよ」
「君も錯覚だろ。ちょっと血迷っただけだ。情欲とは言うけど情と欲は別物だよ。欲で動いて情で惑う。また間違った形の繰り返しになるだけなんだ」
またか、てめえは俺を何だと思ってやがるんだ。俺がてめえを失うことをどれだけ恐れているのか、考えた事もねえんだろ。
「ああ、確かに俺はてめえを捩じ伏せたかった。反抗的で何考えてるかわかんねえてめえを支配したかった。その発露がセックスだ。否定はしねえよ。だがな、なんとも思ってねえ奴を何度も抱くほど暇じゃねえわ」
「君は変わらないな。でも僕は変わらない君がいいと思ってる。君は特別だよ。僕にとっていつまでも」
「てめえ、俺の言ったこと聞いてんのかよ」
てめえには何一つ伝わらねえ。どう言やあわかるんだ。
「僕は君が大事なんだ。君との関係がなにより大切なんだ。君が思う以上に。今度は間違うわけにはいかない。やっと対等になれたんだ。今みたいな幸せなんて、昔は考えられなかった。君を憎まず純粋に憧れていられる。僕は今幸せなんだよ。君には近づき過ぎちゃいけないんだ」
てめえが俺に嘘をついて、そんなことを心に決めた、その矢先に寄生生物騒ぎが起こったってわけか。
「てめえ、俺に抱きついて誘ったよな。本当に寄生されたからって理由だけかよ。ああ?デク」
轟まで誘ったことは忘れる。
「そうだよ。それ以外にあるわけない。君が僕に惹きつけられるのも、僕が君に惹きつけられるのも寄生生物のせいだった。被捕食者と捕食者の関係だ。また心が間違った方向に狂わされたんだ。今は余波が残ってるけど、この気持ちも静まるはずだ。あんな心が壊れてゆくような混乱は、もうゴメンなんだ」
最初に間違ってしまったから、もう手遅れなのかよ。クソが。
迷いも全部寄生生物のせいにしやがるのかよ。
余波だと。
余波と言ったか。そうか。
出久の混乱は昔じゃねえ。今の話なんだ。
「はは!そうか。そうかよ、てめえ!ほんとに迂闊だよなあ、デク」
勝己は高笑いをする。
「かっちゃん?」
出久は訝しげだ。自分で言ったことに気づいてねえ。
「つまり、今てめえは俺が欲しいんだな」
「ちが、違うよ、なんでそうなるの?かっちゃん」
「余波があんだろ。でももう寄生生物はてめえの中にいねえよなあ。そう言ったよなあデク。ごちゃごちゃ言いやがって、結局誤魔化してんじゃねえか!なあ、そうだろ」
「違うよ!」
「こっちに来やがれ。確かめてやるわ」
余波が残ってるってんなら好都合じゃねえか。てめえには言葉じゃ通じねえんだ。身体でわからせるしかねえんだ。
拳で殴り合って、身体をぶつけ合って。毟りあって、無茶苦茶になって。
そうするしかねえだろ。
俺らはずっとそうしてきたんだからよ。
てめえは虫けらなのだと言い聞かせた
取るに足らない存在だと思おうとした
どうしてもそう思えないからこそ足掻いた
てめえに俺を認めさせれば、何もかも上手くいくと根拠もなく信じていた
それが不可能なのだとわかったとき
俺の中に棲みついたてめえがどんどん大きくなり
もうてめえの呪縛から逃れることはできないと知ったとき
もうてめえを逃さないと決めたのだ
だからてめえも逃げんな
勝己は空き教室に出久を連れ込んだ。
舞台の道具置き場にしていた場所だ。ベニヤ板が隅に積まれ、余った大量のサテンの生地が無造作に散乱している。
勝己は出久を床の上に倒し、両手首を片手で纏めて押さえつけた。「かっちゃん」と開けられた口に被せるようにキスをする。出久の舌を絡めとり、擦り合わせる深いキス。頭が痺れるようだ。角度を変えては深く口づける。
てめえの皮膚の下の熱さを誰も知らない。俺の他に誰も知ることはねえんだ。
身体の奥に俺を刻みこむんだ。てめえの全ては俺のものだと。
出久の胸に頭を押し付けて、荒くなった呼吸を整える。
肌の温もり。トクトクと耳に届く出久の心音。汗だくの体躯を強く抱きしめる。
「デク、デク」と掠れた声で呼ぶ。
「かっちゃん」と喘ぎ疲れた声で出久が呼ぶ。
顔を起こしてそっと髪に触れる。髪で隠れていた翡翠のような瞳が勝己を捉える。確かな視線で見つめる。
勝己の肩に触れる出久の手。抱きつくでもなく引き離そうとするでもなく。揺蕩う手を掴んで一本一本、指に口付ける。
「かっちゃん」出久は口を開く。「僕は君としたからじゃなく、きっと昔から君に惹かれてた。そう思いたい。でももう別のものがいっぱい混じってしまって、わからないんだ」
「同じことじゃねえか。どう違うってんだ」
「惹かれてる気持ちだけを、育てていけたんだ。関係を結ばなければ、できたんだ」
「そんなもんはいらねえ。てめえに良くても、俺には良くねえわ」
どんなに近づいても、こいつと俺はわかり合うことはないかもしれない。だが触れ合うことで、一瞬でも境界を穿つことはできる。ひとつに溶け合うことができる。
気休めなのかも知れねえとしても。だからなんだ。正しくねえからなんだってんだ。間違っているからなんだってんだ。
嘘つきなてめえでも、身体を重ねてる時だけは嘘をつけねえ。何度だって隔たりを溶かしてしまえばいいんだ。
俺たちはずっと昔から共生関係なんだ。OFAがてめえを見つけるずっと前から。
俺はてめえが欲しくて、てめえは俺に縛られてる。
OFAが次の宿主に移ったなら、まっさらになったてめえの全ては今度こそ俺だけのもんだ。
一方的な関係なんてな、両方が想っていたら不可能なんだよ。
「戻ろうよ、皆後片付けしてる。手伝わなきゃ」
「ここのもん片付けりゃあいいだろが。生地汚しちまったしよ」
「そ、そそ、そうだね。見られたら困るよね」
「使い道があったな。役にたったわ」
勝己はにやりと笑う。出久の顔が真っ赤になった。慌ててサテンの海に埋もれた服を探し始める。
「何焦ってんだ、クソデク」
出久の腰を引き寄せ、胡座をかいた膝に乗せ、後ろから抱えるように抱きしめる。まだ裸の素肌に触れていたい。肩口に顔を埋める。出久の匂いだ。捕食者を誘うフェロモンみたいな偽物じゃない。本当の出久の匂い。
「あの、かっちゃん?放してくれる?」
「ケツ動かしてんじゃねえよ、また勃っちまうわ」と腰を突き上げる。
「わ、そ、それは、かっちゃん、誰か来るかも、ねえ」
「こっちまですぐには来ねえだろ」
身体を捩っていた出久も、放そうとしない勝己に観念したらしい。大人しく身を持たせかける。
同じことをしたとしても、同じ結果になんてならない。
毎夜違う夢を見るように。毎日違う朝が来るように。
今ならきっと違う道をいける。違う結果を見出せるはずなんだ。
ふと、舞台で出久の言った台詞を思い出した。
「おいデク、てめえは劇のクライマックスでの掛け合いの台詞を覚えているか」
抱きしめる腕に力を込めて勝己は問うた。
「気持ちがわからないと、てめえが拘っていた台詞だ」
密かにそうありたいと思った言葉だ。その意味をてめえは今もわからないのか。
「あの言葉」と呟いて、出久は答える。「少しは、わかる。わかるよ」
終章
(全員が客席からステージ上に上がる)
(緑谷、爆豪は背中あわせになる)
緑谷 「今のうちに君に話したいんだ」
爆豪 「あんだ?」
緑谷 「僕は君のことは覚えてるよ。でも君とどんな時を過ごしたか、あまり覚えてないんだ。日々の鍛錬や冒険の中で、自分のことで手いっぱいだったし。子供の頃のことはどんどん薄れていってしまった」
爆豪 「んだと、てめえ」
緑谷 「でも覚えてるよ。楽しかったこともあったけど、悪いことも、沢山あったよね」
爆豪 「ああ?こんな時にまだ怒らせてえのか。てめえは!」
緑谷 「でも、きっと。僕は君にもう一度出会うために、旅に出たんだ」
END
パラサイト・フェスタ(R18版)

序章
「かっちゃん、あれ何だろ」
幼い頃、ふたりで林の中に遊びに行った時だ。後ろを歩いていた出久が言った。
ふらふら余所見をしているから、ついてくるのが遅れて、待ってよかっちゃん、と追いかけてくるのが常だった。この日は2人だけだから、歩くペースを合わせてやってる。
「あんだ。どうした?デク」
「この虫、どうしてこんなとこで動かなくなってるのかな」
出久の指差す方向にいたのは、草の先に噛み付いたまま死んでる蟻だった。
「ああ、その蟻は冬虫夏草に寄生されてんだ」
「この蟻の中に寄生虫がいるの?」
「いや、寄生虫じゃなくキノコの一種だな。そいつに寄生されると蟻が自分の意思を支配されて、草に登って落ちないように噛み付いて死ぬ。そしたら蟻の中の冬虫夏草が身体から伸びてきて、胞子を周りに撒き散らし、次の寄生先の蟻を待つってわけだ」
自分も本物見るのは初めてだ。かっちゃんはなんでも知ってるね、と出久は微笑む。そうじゃねえよ。てめえがなんでも聞くから勉強してんだろーが。
「蟻にも心があるのかな」
「人間みてえな感情はねえだろ。あるのは本能だけじゃねえか」
「本能。頭の中に聞こえる声じゃあ、自分のものか誰かの声なのかわからないよね」
頭の中で死へと誘う声。判断を狂わせるほどに抗いがたいのものなのだろうか。気味が悪いなと思う。
勝己の袖をそっと掴んで、出久は囁いた。
「怖いね、かっちゃん」
「ほら、早く言わねえともっと奥まで入れちまうぜ。言えよ。欲しいっていえよ。俺のをよお。なあ、デク」
シャツをめくり乳首をコリコリと撫でる。潰しながら捏ねると芯ができてプクリと勃ってくる。
「うあ、や、は、」と出久は苦しげに喘ぐ。
乳首をペロリと舐めて勝己は嫣然と微笑む。密着した下半身が汗ばんでくる。腰をゆるりと進めた。猛るものがさらに食い込む。開脚させて押さえつけた身体がビクリと震える。
カーテンを閉めた勝己の部屋。薄い布は夕方の日差しを遮り切れず、薄明るく出久の肌を浮かび上がらせる。床には脱ぎ散らかした二人分の制服。勝己は出久の足首に引っかかっていた下着を剥ぎ取って、ぞんざいに服の上に放る。
「ほら、てめえのここ、美味そうに俺のものを呑み込んでるぜ」
後孔を限界まで広げて挿入した怒張。さらに埋めると窄まりがきゅっと締まった。奥も収縮し、雁を締め付けられて気持ちがいい。
熱に浮かされたように「あ、あっ」と出久は小さく喘ぎ声を漏らす。
「言えよ、デク。ゴムつけてないんだからよ、奥でイクと俺の精液がてめえの腹の中に残っちまうなあ。良いのかよ、なあ」
出久と身体を繋げるようになってから、コンドームを常備するようにしている。でも今は装着していない。直に中の感触を味わいたかったからだ。絡みつく襞の感触も熱く湿った温もりも、薄膜越しとは比べ物にならない。
まだ出久の体内の奥深くに射精したことはない。もっとも、亀頭だけを突っ込んで後孔の入り口で擦り、中で達したことはある。出し入れするたびに何度も雁で窄まりを広げられて、出久は苦しげに喘いでいたけれども。 後で洗い易いように配慮してやったつもりだ。
コンドームをせず生でペニス全体を締め付けられ射精する。それはどんなに気持ちいいだろう。
「俺を身体の内側に埋められて。どう感じてンんだ。なあデク」
出久はうっすらと目を開き、掠れた声で呟く。
「嫌だ、別の生き物が中にいるみたいだ。うねって這いまわる生き物だ。嫌だ」
「ああ?てめえ、生き物だと?ふざけんなよなあ!てめえん中にあんのは俺んだ。俺のなんだよ」
苛立ちのままに腰を強く打ちつけて、ぐっぐっと出久の中に深く沈める。首を振って出久は脚をバタつかせる。
「暴れんな、クソが!抜けちまうだろうが」
腰を強く振って一気に捩じ込んだ。屹立の付け根まで全て埋まり、出久と身体が隙間なく繋がる。
「っや、ああ!」と出久は叫ぶ。
「はっは、全部入れちまったぜ。遅えんだよ、ばあか」
熱くてうねる出久の体内。腰を掴んで固定して、引き抜いては突き上げる。初めはゆっくりと次第に激しく熱を叩きつけて律動し、身体を揺さぶる。ローションのお陰で抜き挿しがスムーズだ。
「ぬるっと入っから、性器に突っ込んでるみてえだな」誂うように、勝己は笑う。
「僕にそんな器官、ない」
喘ぎつつも出久は生意気に言い返す。もうここはてめえの性器だろ。開発してやったんだからよ。ずり上がる出久の身体に、逃がさないとばかりに覆い被さり、肌を打ち付ける。腹の下に萎えた出久の性器が挟まれた。ぐりぐりと刺激すると、出久は首を振って悶える。
は、は、と互いの息遣いだけが部屋に響く。ねっとりと空気が淀む。内側からてめえを喰らい尽くしてやる。喘いでいる出久の唇に軽くキスをする。唇を食み、深く合わせて舌を滑りこませ、舌を絡める。その間も休みなく肉襞を擦る。長いストロークで抽送しては奥まで貫く。
いきそうだ。スピードを上げて激しく揺さぶる。腰をぐっと突き上げる。熱が竿をせり上がってくる。頭の中がスパークし、先端が弾けた。最奥で達する。
「う、はあ」と勝己は唸る。
腰が痺れ、快感が身体を駆け巡る。 どくどくと断続的に精液が溢れ出ている。出久の中を満たしていくようだ。
「デク、わかるか、いったぜ。俺のだ。てめえん中で出してやったわ」
熱いよ、と出久が譫言のように呟く。粘膜はどのくらい感覚を感知するものだろうか。
引き抜き、小刻みに揺らして飛沫を出し切って拭き取る。出久の中に押し入り、俺の存在を植え付けてやった。勝己はほくそ笑む。
何一つ自分に本音を言わなくなった出久。下手くそな作り笑いで苛つかせる嘘つきな出久。でも肌を合わせることで、少しだけこいつが隠している内側に触れられる気がした。
触れれば触れるほど、出久の肌に熱に飢える。抗いがたい衝動だ。
けれども時折、身体を重ねた後の、虚ろな出久の瞳を見るたびに、胸を硝子の破片のような棘が刺す。
出久はどう思ってるんだ。
「おい、デク」
身体を繋げている時は、気づかないでいられる心の虚。身体を起こし、乱れた出久の髪をかき上げて瞳を覗く。抱かれながらも反抗的な光を宿していた瞳。快楽に濡れて情動を揺さぶった翡翠のような瞳。今は何を映しているのかわからない硝子玉のようだ。
出久だって肌を合わせることに慣れてきているんだ。身体を重ねることで情が移ったりしねえのか。
俺のことを。
いや、どうだっていいじゃねえか。出久の気持ちなんか置き去りで構わない。抱いて溺れさせてしまえばいいんだ。
中学生の頃の放課後の熟れた時間。高校生になって、たとえ別々の学校になったとしても続くはずだった関係。だがそれはヘドロヴィラン事件と、雄英入学と共に出久が個性を得たことで、あっさり終わりを告げた。
あれから出久に触れていない。
第1章
文化祭に劇をすると決めたのは誰だっただろうか。しかも手間のかかるファンタジーだと?
「アホかよ。稽古する暇なんざねえわ」
勝己は文句を言ったが、面白そう、台詞覚えるの大変そうだけどやってみたい、とクラスの連中からは賛成の声が大きく、多数決で決まってしまった。ちらっと背後を伺うと出久も挙手してやがる。クソナードが。
「めんどくせえわ、クソが。てめえらでやってろよ」
勝己は毒づいた。つかつかと飯田が近寄ってくる。おい、HR中だろうが。相澤先生はいねえけど。
「爆豪くん、やる前から面倒だと決めるのは良くないぞ」
「まあまあ、飯田、爆豪は口ではこう言っても、結構真面目にやるんだぜ。前のバンドの時だって、率先して練習仕切ってたしよ」
上鳴の野郎、余計なことを言いやがる。勝己は睨みつけて顔を顰めた。
「そうだったのか、やる気があるんだな。君を誤解していたようだ。すまない爆豪君」
飯田は机に頭突きしそうな勢いで、腰を直角に曲げた。
「うっぜえええ!勝手にしろよ」
勝己は怒鳴って机を叩き、さりげなく振り向いた。目が合うと、出久は困ったように眉を下げて笑みを作る。胸がざわっと騒いだ。
実を言うと、全員で一つのことをするのに異論はない。一年生の時はバンド班とダンス班に分かれたから、ダンス班の出久が何やってたのか、わからなかったからだ。いまだに引っかかっていることがある。
文化祭当日、買い出しに行ったはずの出久の帰りが遅く、戻って来た時は明らかに消耗してやがった。明らかに何かやらかしたんだ。でも出久の班の奴らは何もあいつに聞かなかった。忙しかったとはいえ、気にならねえのかよ。
文化祭が終わってから呼び出して出久に問いただしたが、口止めされてるのか、答えられないという返事だった。腹が立ったがしょうがねえ。
今回は出し物はひとつだから、てめえに異変があれば丸わかりだ。俺に隠し事はさせねえ。
脚本はオリジナルでいくことになった。クラスコンペで選ばれた粗筋をベースにして、脚本担当の奴らがさらに推敲を重ねたらしい。全員が出演する内容になり、元とはまるで違う物に仕上がった。
期日が間近に迫ったここ数日は、準備でてんてこ舞いだ。衣装や小道具は八百万が個性で用意した。セレブな知識が生かされて、学生の舞台とは思えないゴージャスさだ。おかげで本格的な舞台になりそうだ。八百万に食わせるお菓子を作る係に砂糖が振り分けられたので、ある意味砂糖のおかげでもある。
だが舞台で使うサテン生地やベニヤ板などを作りすぎたようだ。教室がやけに狭くなった。
「食わせすぎじゃねえのか、太らせちまうぞ」と上鳴が余計なことを言って八百万が凹み、「デリカシー!上鳴、お前、謝れ!」と耳郎に怒鳴られている。
創造したものは元素から構成した本物らしいから、一度作ると消えない。使わねえもんは爆破するかと提案したが、もったいないし、まだ使い道があるかも知れないと、余った布や板は上の空き教室にぶち込まれた。
ベニヤ板を使ったセット作りは力仕事なので主に男子の仕事だ。衣装のデコレーションは主に女子が受け持った。
そのはずだったのだが。
「おい、爆豪、俺の衣装の胸に、このエンブレムつけてくれよ」「俺も肩あて縫い付けてくれよ。勇者っぽくよ」と何人かから何故か裁縫を頼まれた。
「ふざけんな、てめえら!自分でやれや」
「出来ねえから頼んでんだよ。女子には別に必要ないだろって断られちまったし」
「もう爆豪は衣装担当でいいんじゃね?女子よりうめえじゃん」
「はあ?てめえらなんでできねえんだ」
「うわ、出たよ、才能マン、世の中にはなあ、頑張ってもできねえことがあるんだよ」
「クソが!全部持って来い。ちゃっちゃと終わらせてやる」
衣装を受け取って出久の姿を探した。出久は窓の側でベニヤ板に覚束ない手付きで釘を打っている。危なっかしくてしょうがない。勝己は出久の側に椅子を寄せて座った。
出久は顔を上げる。「かっちゃん、手伝ってくれるの?」
「は?てめえの仕事だろうが。てめえでやれや。俺は衣装直しすんだよ」
「え、ここで?」
「うっせえ、どこでやろうが構わねえだろうが」
「見られてると、なんか緊張するなあ」と出久は屈託なさげに笑う。
擽ったいような、軽口を叩くような関係に、いつになったら慣れるだろう。クラスの奴らはもう、自分が出久の側にいても誰も不思議がらないが。
「でも、僕は嬉しいよ、かっちゃん」と出久は言う。「一年生の時は担当演目が違ったから、準備もリハーサルも別々だったもんね」
「へっ!近くで見ると、てめえの至らなさがよくわかるわ」
「ひどいなあ。かっちゃんみたいには出来ないよ」
衣装にエンブレムを縫い付けながら、出久を見下ろす。
屈んで金槌を打つ白い出久の頸。熱いのか第二ボタンまで外したシャツの襟から覗く肌。さっきまで静かだった胸の内にさざ波が立つ。
しっとりと手に馴染む、肌理の細かい肌を知っている。襟の合わせ目から手を滑り込ませて温もりを確かめたい。当たり前に抱いていたのが嘘のようだ。今はどう触れればいいのかわからない。
「貸せよ、下手クソが」
焦れて出久の手から金槌を引ったくる。指が触れるだけで、胸が騒めくのが忌々しい。隣にしゃがんで、出久の打った釘を残らず引っこ抜いて打ち直す。
「え?全部駄目?」と出久が言う。
「真っすぐ釘打つこともできねえのかよ」
「ごめん、ありがとう、かっちゃん」
「仲良いな、爆豪」通りかかった瀬呂に揶揄われ、「うるせえ!」と怒鳴る。
クラスの奴らは誰も中学生の頃、勝己と出久が身体の関係だったことを知らない。ガキッぽい出久が毎日のようにセックスしていたなんて、想像すら出来ないだろう。
俺もてめえがいなければ、まだ童貞だったかもな。てめえの他に情欲を掻き立てる奴はいねえんだ。
台詞の多い役は演技力度外視で、とにかく成績で決められた。台詞を覚えられなきゃ話にならねえってわけだ。地味な設定の主人公ということで、主役になっちまった出久や、飯田や轟や丸顔は出ずっぱりだ。台詞の多い奴らは放課後集まって、練習に余念がない。
自分も成績上位ではあるが、「出番の多い役はやらねえ」と言ったら当て書きしてきやがった。役柄はドラゴンマスター。ちょっと気に入った。
文化祭前日の今日はリハーサルだ。全員衣装を着て、セットも配置して、本場さながらである。
背景のセットや垂れ幕は峰田のもいだ玉でくっつけてある。よくくっつくので便利だが、峰田以外が触ると取れなくなるので注意が必要だ。
勝己は舞台裏で出演者の用意を手伝う。全員出演するため、出番のないシーンではそれぞれ裏方に回る形だ。
第一幕「旅の始まり」は旅に出た冒険者・緑谷が兵士・飯田と魔法使い・麗日に出会い意気投合し、魔物を退治するために来たという王子・轟に出会い、目的を合わせて行動を共にする。
第二幕「仲間との出会い」は魔物退治のために仲間を集める展開で、勝己以外のクラス全員が順に登場する。
勝己の出番は第三章からなので、前半はずっと裏方だ。出久が裏方に回るのは、勝己がアジトで報告を受けるシーンだけだ。丁度入れ替わりになる。
出番が終わった奴らからステージをはけて、裏方に回ってきた。
勝己のいるステージの下手に、出久と切島が歩いて来た。切島は笑いを堪えているような表情をしている。カーテンをくぐると、切島は「やったぜ!」と叫んで出久に抱きついた。うんうんと相槌を打って、出久も切島の背に腕を回す。
頭にかっと血が登った。
反射的に「おい、じゃれてんじゃねえ!」と怒鳴る。
切島はにかっと笑うと「いやー、初めて台詞間違えずに言えたから嬉しくてよ」とあっけらかんと言った。
「うん、良かったね」と朗らかに返す出久。
わかってる、これは八つ当たりだ。俺はクラスの奴らみたいに、出久の身体に何気なく触れられはしない。あんな風に抱きしめたりできはしないのだ。
第二幕が終わり、カーテンを下ろして勝己はステージに回った。クソ!今は考えるな!次は俺の出番だ。用意しなきゃいけねえ。
冒険者・緑谷は旅に出て仲間を集め火の山に辿り着いた。第三章は俺が竜のオブジェの上からあいつを見下ろすところからだ。
爆豪 「何か用かよ。ああ?」
轟 「この山に住んでるのはお前か」
爆豪 「それがどうした」
飯田 「麓の村が迷惑をしている。魔物を放つのをやめてくれないか」
爆豪 「なんの話かわからねえな」
轟 「口で言ってもわからないなら、腕付くでということになるが」
爆豪 「おもしれえ、やってみろよ」
緑谷 「待って!ねえ、君はほんとに魔物なの?人間にしかみえないんだけど」
麗日 「騙されたらあかん!魔物は人間に化けるんよ」
飯田 「そうだ。人間に化けて騙すのが奴らの手口だぞ」
緑谷 「でも彼は人間みたいだよ。ねえ、君が本当に麓の村を魔物に襲わせてたの?」
爆豪 「ああ?だから何の話だっつってんだろ。俺あ、ドラゴンマスターだ」
(一拍分黙り、おもむろに口を開く)
爆豪 「てめえは俺を忘れたのか?」
緑谷 「えっ?誰が?」
(緑谷、仲間を見回す)
(爆豪、緑谷を指差す)
爆豪 「てめえだ、クソが。子供の頃にてめえは森で俺と、何度も会ったことがあるはずだ。俺はすぐにわかったぜ」
轟 「お前、奴と友達だったのか」
緑谷 「君が僕の?嘘。覚えてないよ。ドラゴンマスターの友達なんて、いたら忘れないよ」
爆豪 「ああ?てめえ」
緑谷 「子供の頃に森の中に竜がいるって聞いてた。でもドラゴンマスターの竜だから安全だって。森にドラゴンマスターの友達がいたような気がするけど。ほんの小さな頃だけだよ」
(緑谷、ハッとして爆豪に視線を合わせる)
緑谷 「ドラゴンマスターの子供って君だったのか!ええ!全然雰囲気違うよ」
爆豪 「ああ、竜に乗せてやったりしたのに、てめえは段々来なくなった」
緑谷 「勇者の修行を始めたから、森に行かなくなったんだ」
爆豪 「何もかも忘れちまったのか。てめえはそういう奴だよな。クソが」
緑谷 「でもでも、この災厄の原因は君なのか?ええーと、何で悪い魔物みたいなことをするんだよ」
轟 「魔物が本当のことを言うはずがねえぞ。お前の知り合いのふりをしてんじゃねえのか」
爆豪 「ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ!こんなとこでてめえと会うとはな!やんのか?やんねえのか?ああ?かかってこいやデク!」
緑谷 「かっちゃん、台詞台詞、デクじゃないよ」
麗日 「デクくん、かっちゃんも違う!」
飯田 「麗日くん、デクくんじゃなく、ああしまった!
「わやくちゃだな。どうする?」
轟はライティングの八百万の方に視線を向けて声をかける。
「とりあえず映像映すから!通しでやりましょう」
頭を抱えた八百万が、巨大な魔王のシルエットを、ステージ後方のスクリーンに映し出した。
「魔王だ!」という出久の声を合図に、八百万の作った魔物兵人形が舞台袖からわらわらと登場し、客席側からステージにクラス全員が押し寄せた。
グラウンドベータから戻る帰り道。
勝己はオールマイトの後ろを出久と並んでついて行った。
出久の手足は爆破による火傷で赤く腫れ上がっている。俺がやったんだ。とはいえ、出久も思いっ切り殴りやがったから、おあいこだ。
口の中で血の味がする。ジャリッと砂の感触がしたので、地面に血混じりの唾を吐いた。
「オールマイト、いつから見てたんだ」と勝己は訊いた。
「君が罪悪感を吐露したあたりにはいたよ。本当にすまなかった」
「ほぼ初めからじゃねえか。あんた止めねえのかよ」
「止めるべきなのかもしれなかったけど」オールマイトは振り向いた。「止めたくなかった。君達には必要なことだったんだろう」
最初の授業の時だって、俺の暴走を止めなかった。オールマイトの基準はズレている。でもそのズレに俺は救われている。
「あんた、先生に向いてねえわ」
「かっちゃん」出久が困ったように言った。
「そうだね。相澤くん怒ってるよ。でも私のせいでもあるんだし、何とかとりなすよ」
「いらねえ、俺が全部悪いんだからよ」
「かっちゃん、でも応じた僕も悪いんだよ」
「全部俺のせいだっつうんだ!クソが!てめえはすっこんでろや」
てめえを呼び出した時から、退学でも停学でも覚悟の上なんだ。イラッとする。でも腹は立たない。わかっちまったからだろう。
俺のやることは変らねえと言ったけれど、本当は変わっちまった。出久を捩じ伏せればいいと思っていた。それが目的になっていた。でも縋りついて無理やり相手をさせた対決に達成感はなかった。
秘密を分けあって知った。出久はOFAの新しい宿主なのだ。もう目的が達成される日は来ないのだ。
すうっと心に吹き抜ける風。理解とは諦めに似ているのかも知れない。
脱線していた目的が元に戻っただけだ。てめえのように、真っ直ぐに前を見て行けばいいと。もうそうするしかないのだと。
代々受け継がれてきたDNA。DNAを取り込むなんて生々しいなと思う。そういう意味ならば、俺は何度も出久の中に俺のDNAを注ぎこんだんだ。髪の毛と精子は全然違うけれど。
でもてめえの中には何も残せなかったんだろう。
肩を並べた隣で、大きな目で出久が俺を見つめる。昔みたいに。
ガキの頃からてめえが俺に向ける視線が心地よかった。どんなに邪険にしてもついてくる。俺は、てめえが俺に好意を持っているからだと無邪気に信じていた。
瓦礫の下から人々を救う、オールマイトのニュースを一緒に見るまでは。
あの時、出久は俺を見るのと同じ目でオールマイトを見つめていた。
胸がざわついた。てめえはファザコンなんだ、と思った。無自覚にか自覚しているのか知らないが。めったに会えない父親のかわりに、指針となる存在を求めているのだ。はじめは俺だった。次はオールマイトなんだ。
オールマイトに出会ってからてめえは変わった。俺を否定し始めた。もう俺を必要としないのだ。もっと父親的な存在を見つけたから。
てめえが仰ぎ見る地上最強の男。俺はオールマイトを超えてやる。それ以外にてめえを取り戻す術はないんだ。
その手段さえ見失ったのは、ヴィランに攫われた時だ。俺のせいでオールマイトが力を失った。そんなことは望んじゃいなかったのに。俺は超えたかった。強くなることを望んだだけなんだ。
てめえは俺を見なくなった。もう俺を許さないのだろうか。弱い俺を見放すのだろうか。てめえは俺をどう思ってる。オールマイトを壊した俺を。このままもう二度と俺を見なくなるのか。
出久は俺に近寄らない。俺には近付く資格はない。俺からてめえに近寄れないのなら、側に寄る機会はないんだ。悪態もつけない。睨みつけるだけだ。腹の底に渦巻く苦しみはどこにもいけない。
この俺が出久を失う。こんな事態はあり得なかった。話すことも視線を交わすこともなく。負い目を持ったまま距離だけが開いてゆくのか。
限界だった。結局はてめえにぶつけるしかなかったのだ。
出久は何も気づいてなかった。
「君が責任を感じて悩んでたなんて思わなかったよ」と出久は言った。
「俺を鉄面皮だとでも思ってやがったのか」
「ごめん、思ってたかも。君はタフだから」
「クソが!」
あっけらかんと言う出久にムカついて、ペシリと出久の頭を叩く。こっちは頭ン中ぐちゃぐちゃになっていたってのに。
「君のせいじゃないよ、爆豪少年」
「わーってるってんだ、オールマイト。デク、てめえが強くなんなら、俺はその上をいく」
「じゃあ、僕はその上をいかなきゃ」
頭を摩りながら出久が言う。
今まででは考えられないくらい、まともな会話だ。まるで普通の幼馴染のように。少し、てめえに近づけたのか。近づいていけるのか。
どのくらい近づいたんだろう。あれから時々距離を確認する。
「おいデク、てめえは」
俺のことを、と問おうとしては躊躇する。
「何?かっちゃん」
「何でもねえよ」
俺の逡巡をよそに、やっぱりてめえは俺の聞きたいことに答えねえんだ。てめえが俺をどう見てるかじゃねえんだ。
てめえは俺のことをどう思ってるんだ。出久。
直前リハーサルが終わり、クラスの奴らがぞろぞろと講堂を出て行った。
帰る時間までまだ時間がある。何処で時間を潰そうか。
出久はまだ舞台の裏にいるようだ。セットの裏でひそひそと声が聞こえる。竜の張りぼての側で、出久が話しているのは轟だ。足を忍ばせて近寄ってみた。
「僕とかっちゃんの幼馴染設定だけど、必要なのかな」
「必要だろう。キーになるキャラと主人公に何らかの因縁があると、ドラマチックになるしな」
「それはスターウォーズでもあるから、理解できるんだけど」
「それに、演技に反映できるように、メイン役者の設定は本人のバックボーンに合わせてるらしいからな。俺は父親である王に反抗して出奔、飯田は騎士である憧れの兄を目指して武者修行、麗日は両親を手助けするため魔女を目指す。浮かす個性生かして、箒に乗って空飛ぶ魔女ができるからってのもあるな。気持ちが分かるほうが演じやすいって、脚本の奴らが考えたんだろう」
「うん、それはわかるんだけど」出久はポツリと言う。「僕とかっちゃんの役はどういう仲なんだろう」
俺の話かよ。気になってつい聞き耳を立てる。
「一般的な幼馴染と思えばいいんじゃないか」轟が言う。
「それってどんな感じなんだろ。難しいな。僕らは普通じゃなかったから」
「うちも普通の親父とは言い難いけどな。役と切り離して考えてもいいんじゃないか」
「うん。でもちょっとね、考えちゃって。それに魔物に向かって共闘する前にかっちゃんに言う台詞も、どういう気持ちで言えばいいのか、わかんないんだ」
「真面目なのはいいが、考えすぎるなよ」
「僕ね、轟くんちみたいに、いつも家にお父さんがいるのちょっと羨ましいんだ。君とお父さんの関係は難しかったって知ってるけど、僕は子供の頃から、ほとんどお父さんと会えないから」
「隣の芝生って奴だな」
「うん、お父さんよりかっちゃんとの思い出の方が、ずっと多いくらいだよ」
「お前らの関係は俺と親父のよりも、ややこしくみえるけどな」
「うんまあ」出久は苦笑している。「かっちゃんとは色々ありすぎたんだよ。僕の中で彼の存在は大きすぎるんだ。おかしいかな」
「いや、過ごした時間で情が移るものだからな。良くも悪くも」
「うん」と出久は相槌を打ち、ぽつりと続ける。「だから、情が移ってしまったんだよね」
なんだと、デク。
出久の言葉に、勝己は声を出しそうになった。情が移っただと。息を吸い込んでこらえる。
「あいつに比べれば会っていくらも経ってねえけど、お前の存在も俺には大きいぜ」轟が言った。
「轟くん、ありがとう。嬉しいよ」
ぽんぽん、と出久の肩を叩いて、轟はステージを降りて行った。
出久はまだ戻ろうとせず、皆の衣装を畳んでいるようだ。
こっそり聞いてしまった轟との会話。二人とも気づいていなかったのだから、知らないふりをすべきなのだろう。
だがそのつもりはさらさらない。俺には言わない出久の本音だ。直接本心を確かめないではいられない。
情が移ったのだと、確かに出久は言った。あれは俺達の関係を指してたんじゃないのか。
流石に中学生の頃に、俺と身体の関係があったことまでは、轟には言ってないだろうし、奴も気づいていないだろう。昔のことを何も知らない奴にだからこそ言えたんだ。
轟が講堂を出て行ったのを確認し、勝己は出久の側に歩み寄った。足音に気づいて出久は振り向き、目を見開く。
「かっちゃん、いたの?いつから?」
吃驚させたのだろう。出久の手から衣装が滑り落ちた。
「お前らが話し始めたところからだ」
「ええ!あ、あー、そうなんだ。かっちゃん。じゃあ、僕はもう行くね」とそそくさと立ち上がり、小走りに去ろうとする出久の腕を「待てや、コラ」と掴んで引き止める。
「てめえとは色々あったよな。昔っからよ」
「うん、そうだ、ね」
「てめえ、俺に情が移ってんだって?」直球で問うた。
「いや、その」
出久は狼狽して視線を彷徨わせる。もっとはっきり言ってやるか。
「あんだけセックスしたもんな。情も移るか。移るよな。俺もそうだったからよ。なあ、デク。どういう意味だ。ちゃんと言えや」
逃げは許さない。本心を吐くまで離さない。掴んだ腕に力が籠もる。出久はきゅっと唇を引き結んでいたが、溜息をつくと、漸く口を開いた。
「君には絶対に言わないつもりだった。僕は君に好意を持ってたよ」
でも、だから、と出久は俯いて口籠る。勝己は辛抱強く答えを待つつもりだった。だが邪魔が入った。
「おい、緑谷、行かねえのか」
講堂の出口の方から、轟の呼ぶ声が聞こえる。
「クソが!」思わず勝己は悪態をつく。
「うん、行くよ」と出久は轟に返事を返す。「じゃ、かっちゃんあの、手、放して」
まだ、言葉の途中だろ。全部聞いてねえよ。離そうとしない勝己の腕を振りほどこうと、出久は腕を振る。畜生、仕方ねえ。本心は聞いたんだ。解放してやると、出久は転がるように走って行った。
「あいつ、マジかよ」
出久は好意と言った。俺を好きなのかあいつは。いや、だから俺に抱かれてたのか。だよな。でなきゃ何度もやらせやしねえよな。
肌を合わせるほどに執着が沸いた。あいつの体温に匂いに溺れた。溺れてたのは俺だけじゃなかったのか。てめえもだったのか。ならまた欲しいと思っていいんだよな。
だが、出久の言葉の続きが引っかかる。てめえはなんと言おうとしたんだ。
第2章
文化祭一日目の朝。祭日和の雲ひとつない晴れた空。
午後のラストのプログラムであるA組の劇は滞りなく進んだ。
第四章は全員がステージに上がって乱闘するシーンが山場だ。舞台上の出久、勝己、轟、飯田、麗日以外は、見つからないように客席に隠れ、掛け声を上げながらステージに突入した。
魔王が登場すると勝己は人間の側につき、周囲の魔物と戦う展開だ。自分は魔物じゃなく、魔物と同じ山に移り住んでいただけだとかなんとか、出久と掛け合いしながら立ち回る。魔王に二人でとどめを刺すシーンは大いに盛り上がった。爆音を流してスクリーンに映った映像を消すだけだけなのだが。
台詞で大きなミスをする奴もいなかった。ちょっと怪しい奴もいたが、勢いで乗り切ったようだ。
台詞といえば、出久が拘ってた台詞はどれだったんだろう。掛け合いの中に、引っかかるような台詞は特に思い当たらない。
カーテンコールも済んで幕が降りたところで、勝己はステージから出久を連れ出した。盛り上がってるクラスの奴らは気づいてないようだ。
出久は「かっちゃん、戻らないと」と狼狽えたが、「昨日の話の続きだ」と人目につかないステージの裏に連れ込んだ。
通路にはセットや大道具が所狭しと立てかけてある。通り過ぎて隅に連れて行くと、出久の背を壁に押しつけた。
掴んだ腕が熱い。身体の芯が疼く。暫く忘れていた感覚が蘇ってくる。
「デクてめえ、俺が好きなんだろ。そう認めたよな」直球で問うた。
「かっちゃん、それは」
言いかけて出久はまた口籠り、目を逸らす。煮え切らない態度に苛つく。てめえ、今更誤魔化すつもりかよ。
「こっち見ろや」と顎を掴んで上を向かせる。
至近距離。今の出久の瞳に怯えの色はないが、視線はふらふらと迷い戸惑っている。
揺れる緑の瞳に誘われるように、唇を重ねた。濡れたやわらかな感触。肩を抱き、下肢を押し付ける。何度も身体を重ねて知りつくした体温。下半身が熱くなり、ズボンの中で性器が頭をもたげた。やべえ、このままやっちまいそうだ。静まれクソが。
唇を離して出久の顔を見つめる。頬がさっきより赤らんで見えるのは、気のせいではないはずだ。勝己は出久の両肩を掴んだ。
「情が移ってんだろデク。俺も同じなんだ。てめえもだってんなら」出久の耳元に囁く。「またつきあえや。俺と」
ひゅうっと出久から息を呑む音がした。今ならなんら問題ないはずだ。俺はてめえがいいんだ。周り道をしたが、やっとてめえの気持ちが分かった。なら中学生の時と違って、上手くやれんじゃねえか。
だが出久は腕を突っ張り、勝己の身体を突き離した。
「ないない、かっちゃん、ありえないよ」
「はあ?何故だ!」
意味が分からねえ。出久は胸に手を当てて、シャツの合わせ目を掴んで俯いた。何かを隠すかのように。
「てめえ、俺が好きなんだろ!」勝己は頭に来て怒鳴った。
「そ、好きとかじゃなくて、好意を持ってたと思ってたんだ」
「ああ?同じことだろーが。今更誤魔化してんじゃねえよ。認めただろうが。俺もそうだっつってんだろ。問題あんのかよ。あんなら理由を言えよ!」
「代償行為だったんだよ、かっちゃん」
「はあ?情が移ったことか、好意とやらか、何の代償だってんだ。違いあんのかよ」
「僕にとってあの頃の君は憧れで。目指す目標だった。普通はそういう対象は父親なんだろうけど、うちはあんまり会えなかったから、他に目標が必要だった。僕は目指すべき理想像が欲しくて、君にそれを見ていたんだ」
それは、俺がてめえに思っていたことだ。自覚してたのか。俺が出久を分析していたように、出久も自己分析していたのか。だが、それがどうしたというのか。
「俺はてめえの親父じゃねえよ」
「もちろん、本当に父親だなんて思ってないよ。目標だと掲げて、君自身を見てなかったってことなんだ。でもグラウンドベータで君と戦った時、やっと気付いた。君も僕も普通の高校生なんだって。僕の君への気持ちは違ったんだ。君に僕の理想を勝手に押し付けていただけなんだ。酷いことされても憧れる気持ちは変わらなかった。だから好意だと勘違いしてたんだ」出久は顔を上げる。「あれ、スト、なんとか症候群っていうのみたいに。自分の生存権を握る相手を憎みながらも、無意識の内に好きになろうとするっていう」
「ストックホルム症候群かよ」
「そうそれ。恐怖と防衛本能が認識を狂わせてしまうんだろうね。僕は君に憧れていたけど、逆らえば暴力を奮う君が怖かった。性的な遊びを僕相手に君が始めた時も、怖かったよ」
遊び。てめえは遊びだと思ってやがったのか。
「てめえは拒まなかったじゃねえか」
突っ込まれんのわかってんのに、呼べば来たじゃねえかよ。マゾかよ。俺に怯えてるのは知ってたわ。だがあの頃だって、大人しく言いなりになる奴じゃなかったはずだ。殴られても反抗する奴だったろうが。嫌なら逃げろよ、必死で抗えよ。
「今だけだ、すぐ君は飽きる、と思ってたんだ。他の人に被害はかからない。僕が我慢すれば済むことで、君をむやみに怒らせたくなかった」
きつく握りしめた出久のシャツの胸元に益々シワが寄る。「でも終わりが見えなかった」
「終わりなんざねえはずだったわ」
終わらせる理由なんてなかった。てめえが応じるから、抱きたくてたまらなかったから。てめえを知りたかったから。
でもいくら抱いてもてめえがわからなかった。
「だから、自分の心を守ろうとしたんだと思う。自衛のための間違った心理状態なんだ。本物じゃなくて紛い物だ。恋じゃない。恋なわけがないよ。好きでなくたって勃つんだ男は。セックスできるんだから。君もそうなんだよ。ただ肌を合わせたから情が移ったんだよ。そんなの駄目に決まってる」
「何が悪いんだ。身体とか心とか、ざっくり分けられるわけねえわ」
「情なんかじゃなく、僕は君が本当に大事なんだよ」出久は言い聞かせるように言う。「僕にとって幼い頃の君は、とても大事な位置を占めてたんだ。壊さないでよ。大事なんだ。壊したくない。他ならない君に、もう壊して欲しくない。もう二度と間違えたくない」
出久は否定する。出久自身だけではなく、俺の気持ちまでも否定する。腸がふつふつと煮えくり返る。
「てめえ、クソが!オレが間違えてるって言いてえのかよ。馬鹿にすんじゃねえよ。てめえに俺の何がわかんだ」
「だってそうだろ。君は僕の身体を使ってマスターベーションしてただけじゃないのか」
かっと頭に血がのぼった。「デクてめえ!死ねやあ!」と叫んで飛びかかって、その後のことはよく覚えていない。
気付いたら出久に馬乗りになって殴りかかっていた。騒ぎに駆けつけたクラスメイト達に止められても、勝己は怒鳴り続けた。
「クソが!」
部屋に戻るなり、勝己は吠えた。
部屋は防音設備が完備されている。相当の音でなければ外に漏れはしない。
だからあらん限りの声で怒鳴った。
「クソが!クソが!勝手なこと言いやがって!出久の野郎!」
ようは今の俺は認めねえってことじゃねえか。
なんであんなこと言っちまったんだ。おまけにキスなんかしちまった。言い訳しようがねえ。あいつの瞳に誘われるようにやっちまった。
いや、言っちまったもんはしょうがねえわ。今更誤魔化すつもりはねえ。
関係が拗れなくても、俺はあいつにいつかは手を伸ばしただろう。何をしても俺についてきたから、俺と同じようにあいつも俺を想っていると信じていたから。多分、それだけは信じていたんだ。
なのに今更違ったのだというのか。あの頃のあいつが俺に向ける感情は初めっから違うもので、ずっと誤解していたと言うのかよ。
今更、今更だ。てめえは違ったとしても。もう俺は溢れてしまったてめえへの気持ちを、元に戻すことなんてできない。ずっと押さえて来たんだ。
たとえ無自覚であったとしても、てめえは俺を騙してたんだ。
ベッドに横になると、スボンのチャックを下ろして下着に手を突っ込み、性器を握った。上下に擦り、屹立させる。雁首を捻るように撫でて扱く。
さっき抱きしめた出久の体躯を思い浮かべると、ぐんと手の中の肉棒が太くなった。キスを、柔らかな唇の感触を思い出す。太腿で押し上げた股の感触も。熱が集まり、硬くなる。自分の下に組み敷いた身体。押さえつけられた出久が、熱を帯びた目で見上げる。怯えた表情に反抗的な瞳。捻じ伏せて意のままにする。何にも変えがたい快楽。身体を貫いて心を貫いて、一瞬だけ所有欲を満たす。
勝己は唸り、先端を掌に包み込んで射精した。掌を濡らす温かい白濁。荒くなった息を整える。手の中で、膨張が解け柔らかく戻ってゆく性器。
マスターベーションしてただけだろ、という出久の言葉が脳裏を過ぎる。
「クソが!」
頭にくる。精液を拭き取り、ティッシュをゴミ箱に投げ捨てる。
勝己は電灯の光に手を掲げた。燃えるように赤く透ける皮膚。この掌から生まれる爆破の個性であいつを苛んだ。この指で肌に触れて濡れた最奥の体温を弄った。
どんな形であれ、いつもあいつに触れていた手だ。
畜生が。気づかせやがって。忘れようとしたのに。俺は出久をまだ手に入れたいんだ。俺のものにしたいんだ。
だが何故なんだ。何故あいつだけをこんなにも欲しいんだ。
あいつは気づいたんだ。そうだろうよ
俺を嫌いこそすれ、好きになるわけがねえんだ
憧れってやつがあいつの目を眩ませていたんだ
年月が経って冷静になって気づいちまっただけだ
あまりにも早くに出会ってしまったんだ
恋というものを知る前にどうして恋を認められるんだ
気になってしょうがなくて、苛々させる存在をどう捉えられるってんだ
幼い心を奪われれて絡め取られて、どうしていいのかわからなくなったんだ
てめえだけが俺を仰いでるだけなら、俺が時折てめえに惑うくらいならよかった
てめえが離れていくことで動揺する俺に気づきたくなかった
俺の方があいつより上だと根拠もなく信じていた
俺のものだと思い込んでいた
ああ!クソがクソが!
姿を求め声を求め、面影を夢に見る
俺がてめえを抱いて夢中になっていたときに
てめえは何を感じていたんだ
てめえの身体を使って自慰をしてるだけだと、思ってやがったのか
ふざけたことを言いやがる
てめえじゃなくていいならとっくにそうしてるってんだ
他の奴じゃダメなんだ。
てめえに触れてる時だけ、俺は俺でいられたんだ
また俺から逃げんのか、デク
第3章
「昨日の劇はよくやった。正直、思った以上の出来栄えだったぞ」
相澤先生に褒められて、教室内の空気が和む。
文化祭二日目の朝のショートホームルーム。昨日の緊張した顔から一転、今日のクラスの奴らの表情は弛緩している。
「いやあ、俺らもやればできるんで」と誰かが調子に乗ったところで「しかし演技力は全然だったな。セットや衣装で、八百万の個性に頼ったところが大きいのは否めない。次やるのなら、個性に頼りすぎないようにな」とぴしゃりと戒められる。
褒めて落とすか、流石教育者だ。しかし、劇の出来はともかく昨日は散々な一日だったぜ。勝己は舌打ちする。出久とは寮での朝食の時に顔を合わせたが、腹が立ってずっと口をきいてない。
「さて、本題だ。劇も終わったし、今日はお前ら全員暇だろう」
相澤先生は教室を見回した。普通科ならクラスの活動が終わっても部活のシフトがあったりするが、A組で部活に入ってる奴はいない。
「他のクラスの出し物を見に行こうと思ってました。なんでしょうか」挙手して飯田が訊いた。
「実はお前らに手伝ってもらいたい仕事があってな。昨日、早朝から夕方まで怪しい人影が学校の周りをうろついていたらしい」
ざわっとクラスが騒つく。飯田が勢いよく立ち上がった。
「ヴィランですか?」
片手を上げて飯田を制すると、相澤先生は続けた。
「わからん。勘だがヴィランの可能性は高いな。今日はそいつはいないんだ。諦めたのならいいんだが、ひょっとしたら、客に紛れて既に侵入したのかも知れん。」相澤先生は声を低める。「もしくは客を使って侵入したか」
「セキュリティは万全ですよね。以前も」と出久は言いかけて「あ、その」と慌てて口を噤んだ。
相澤先生は出久に構わずに続ける。「ああ、だが万が一のこともある。ヴィランは総じて執念深いし、外部の客が入るイベント事は狙われやすい。用心に越したことはないからな。悪いがお前らに、ふたりずつ交替でパトロールをして欲しい」
ふたりずつと聞いて嫌な予感はしたが、案の定、勝己は出久とペアにされた。ふたりを職員室に呼ぶと、相澤先生は監視カメラの映像を見せながら説明を始める。
「まずは爆豪と緑谷、お前らは校内を回ってくれ。コイツをもし見かけたら、絶対に戦ったりするなよ。すぐに知らせろ。外は俺達教師でパトロールする」
「なんでデクとなんだ」
勝己は苦々しい思いで抗議し、背後に視線を送る。出久は慌てて目を伏せた。
「お前らもう仲悪くないだろうが」
「はあ?どこ見て言ってんだ。良くもねえよ」
「仕事で仲良しと組ませる理由はないぞ。それから緑谷、さっきもだが、お前は迂闊なとこがある。気を抜くな」
「はい、先生」出久はちらっと勝己を伺う。「すいません、頑張ります」
「確信がないから言わなかったんだが、カメラに映っているこのヴィランに、見覚えがある気がするんだ。個性は不明だが、気をつけろよ」
ふたりは職員室を出ると、早速パトロールを始めた。出久はぽてぽてと後ろを付いてくる。落ち着かない。苛つくよりも胸がざわつく。
早足で歩いて引き離そうか。いや、聞きたいことがあるな。勝己は歩を止めて、出久と足並みを合わせた。隣に来た勝己に出久は戸惑っている。
「おいデク、以前の文化祭でもヴィランが出たんだな」
勝己の言葉に出久は目を見開いた。やっぱり図星か。
「てめえが水際で防いだってとこか。おい」
返事を促すように、肩をぶつける。
「知ってどうするの?」
「どうもしねえ。答え合わせしてえだけだ」
出久は苦笑した。俺の嫌いな出久の表情。隠し事をしてる時の顔だ。
「かっちゃんはやっぱりすごいな」
出久は顔を上げて、窓の外を仰ぐ。見えるのは雲一つない、秋の始まりの高い空。遠くにある何かを探すように、出久の視線は彷徨う。
「本番のかっちゃん、カッコ良かったよ。ドラゴンの上のかっちゃんも、立ち回りもすごかった」
「うぜえわ。世辞はいらねえ。黙れ」
「あの、かっちゃん。昨日はごめん、言い過ぎたよ」
勝己は立ち止まった。出久も歩みを止める。
「へっ。何を謝ったりしてんだ。マスターベションつったことか?てめえの本心なんだろうが」
「かっちゃん、だから言い過ぎたって…」
「てめえが本気で嫌がってたんならなあ、俺だって何度もしてねえよ。呼べば毎回のこのこついてきやがって。てめえもやりたかったんじゃねえのかよ!」
「それが、おかしくなってたってことなんだ。そう言ったよね」
「俺のことが好きでなくて、勘違いだったってんなら、性欲で動いてたんだろ。てめえの本能も否定しやがるのか!」
「せ、性欲って、声が大きいよ。かっちゃん」
「誰もいねえわ」
「す、好意がなかったわけじゃないよ。だから、君とのまともになった関係をなくしたくないんだ」
受け入れなければ今の関係すら無くすぜ、と言ったらこいつはどうする?いや出久は頑固だ。納得せずに受け入れるくらいなら、無くす方を選ぶんだろう。そういう奴だ。また耐えられないのは俺の方なんだ。返事をしない勝己に、出久は続ける。
「君との関係を構築しなおしたいんだ。かっちゃん。同級生として、君と向き合いたいんだよ」
「ああ?何をどうしなおすってんだ。その先に何があるんだ」
「今はそうしたいとしか言えないよ」
「その先に、てめえが俺のもんになる選択肢はあんのか?」
「わ、わからないよ。その時にならないと」
どこまでがこいつの本心なんだ。
「長くは待てねえぞ。俺は気が短けえんだ」
「うん、でも、少なくとも、中学の時の延長線上では付き合えないよ。あんなのは紛い物の関係だ。あの関係の先には何もない。普通好きな人に、あんな風にはしないだろ。いくら君だって」
「普通なんて知らねえよ!てめえしかいなかったのによ」
気まずい沈黙が流れる。ふたりは黙ったまま並んでパトロールを続けた。
各教室もお化け屋敷やコスプレ喫茶店や脱出ゲームや、工夫を凝らした企画をしている。人気のある教室は、廊下も教室の中も人混みで溢れていたが、怪しい客は混じってはいないようだ。A組の奴らも客になって並んでいて、「おお、お前ら二人で回ってんのかよ」と言われ、「仕事中だ、クソが」と顔を顰めて言い返した。
勝己の心は千々に乱れる。求めて止まない存在を隣にして身体が渇く。あの頃は憤懣を出久本人にぶつけた。出久の心を踏みにじり身体を貪った。
一方的な行為だっただろう。でもてめえも俺も同じように、求めているんじゃないのか。なのにそれを嘘だと否定するのか。
自覚させられた思いは、どこへ向ければ良いのだろう。情が移ったってんなら、それでもいいんじゃねえのかよ。てめえはどうなんだ。てめえのせいで俺はまた惑うんだ。
廊下の突き当たりまで来ると、人込みが途絶えた。交替まで時間が迫っている。
「二手に分かれようか」と出久は言った。
「指図すんじゃねえよ!クソナードが」勝己は舌打ちして答える。「俺は上に行くわ」
「う、うん。じゃあ、僕は下に行くね」
出久は階段を降りていった。階下から「迷子になったの?」と出久の声がする。手摺から覗くと3、4歳の子供が1人だけでいるようだ。出久は呼びかけて近寄っていった。
迷子くらいあいつ1人で大丈夫だろう、と階段を登っていこうとした時だ。
出久のいる方向から悲鳴と爆音が轟いた。
「いきなりかよ。クソが!デク!何があった!」
勝己は手摺に手を掛けると、飛び降りて階下に走った。
視界が土埃に遮られる。天井からバラバラと瓦礫の屑が落ち、壁にひびが入っている。窓硝子が粉々になって床に散っている。
出久が個性を使ったのだろうか。それともヴィランか?
土煙の先に出久が倒れているのが見えた。
服が裂け、シャツは血塗れで床に血溜まりができている。
「クソが!おい、ヴィランが出たのか。何とか言えや」
光が反射して、無数の針状のものが空中に浮かんでいるのが見えた。出久を包囲している。窓硝子の破片か?いや、違う。
ぞくりとした。あれはヤバイもんだ。
「かっちゃん」と出久が顔をもたげた。
「どうした!、爆豪、緑谷」
轟と飯田が駆けつけた。次のパトロールの2人だ。真面目な飯田のことだ。早めに集合していたのだろう。
「子供が叫んで逃走してきたぞ。何があったんだ」飯田が言った。
「その子、その子を追って」と出久は叫んだ。「攻撃はしないでね。多分ヴィランじゃなくて普通の子供だ」
「わかった。爆豪君、轟君、後を頼む。」
飯田は爆走して引き返した。
その足音に反応したかのように、出久の頭上に無数の針が降り注ぐ。
「クソが!」
「伏せろ緑谷!」
出久が頭を下げた瞬間、轟はその頭上すれすれに炎の絨毯を敷いた。
全ての針が赤い舌に舐めるように焼き払われた。
針は消し炭になり、ぼろぼろと崩れる。
はあ?何してやがんだ。
「バカかお前!全部焼いちまったら、正体がわからなくなるじゃねえか」
勝己は怒鳴った。こっちはそれで躊躇してたってのに。
「そうか、サンプルが必要だな」
轟は炎を消し、凍らせて消火する。
氷柱が出久を囲むように聳え、黒焦げの針が中に閉じ込められた。
「焦げてない針もあるかも知れねえ。だが探すのは後だな」轟は出久に駆け寄ると尋ねた。「何があった、緑谷」
出久はよろけながら立ち上がる。
「子供が1人でいたから迷子かと思って、声をかけたんだ。でも振り向いた子供の目から、蜘蛛の糸のようなものが抜け出て、 広がって網みたいになって」
その後、子供は我に返ったように、悲鳴を上げて走り去ったという。
出久は幾重にも網に囲まれて戦いようがなく、抗ううちに網の目が砕け、細かい針状の破片が降ってきて負傷したらしい。
「破片?さっきのか。網の一部というより、あの針のひとつひとつが、意思持って動いたようだったぞ」轟は首を捻る。
「針が本来の形かも知れない。ヴィラン本人ではなく、客に寄生して、しかも子供を送り込んて来るなんて」
「子供だからって油断しやがったんだろ。クソが」
悔しそうに拳を握る出久に、勝己は言った。
「う、うん、そうだね。誤算だったよ」
出久の声が掠れてきた。顔色が悪い。傷口すらわからないような細かい傷から、血が流れ続けている。ポタポタ落ちて、床の血だまりが広がってゆく。
細かい擦り傷ばかりで大きな傷はないのに、何故出血が酷いんだろう。
「とりあえず保健室に行こう。肩を貸すぞ、緑谷」
「は!まどろっこしいわ」
「え?あ?かっちゃん」
勝己は轟を押しのけて、出久を肩に担いだ。他の奴に触らせるかよ。
保健室に到着する頃には出久の意識はなくなっていた。ベッドに寝かせたが、シーツがみるみる赤く染まる。
「やべえな。緑谷の血が止まらねえ。傷を塞がなきゃなんねえし、輸血も必要だ」
「クソが!リカバリーガールは外の保健室出張所にいんぞ。連れてくるか」
勝己が保健室を出ようとしたところで、飯田が駆けつけた。
「子供は確保したぞ。先生に理由を話して預けてきた。緑谷くんの様子はどうだ?」
容体を話すと、青くなった飯田は自分がリカバリーガールを呼んでくる、と逆走していった。
「飯田が呼びに行ったぞ」
勝己は振り向いた。
目の前の光景に凍りつく。
出久が起き上がり、轟の首に腕を巻きつけていた。
キスをねだるように。誘うように誘われるように。
夢でも見てんのか。くらりと惑う。
次に頭が沸騰した。なわけねえ、夢じゃねえわ。
「何やってんだ、てめえ!」
両掌を暴発させて勝己は怒鳴った。
「おい?爆豪、保健室だぞ」轟が顔を向ける。
「あ、れ?僕、何して」
出久は勝己に気づき、びくりと震えた。腕をほどくと慌てて頭から布団を被る。
「おい、デクてめえ、逃げんのか」
布団を引き剥がそうとしたが、轟に「落ち着けよ、爆豪」と止められる。
「んだと、てめえもだ、轟!」
「何があったか、説明する。まずは落ち着け」
「クソが!」勝己は何とか気を鎮める。「言えよ、轟、何があった」
「大したことねえよ。お前が外に出てる間に緑谷が目を覚まして、俺に捕まって身体を起こしたんだ」
「出久からやったのかよ」
「ああ、ぼんやりして夢遊病みてえな感じだったけど」
「それだけか」
「他に何があるんだ」
何でもねえのか。ほんとにねえのかよ。
輸血を終えたと言って、教室に出久は戻ってきた。
傷跡は綺麗になくなっている。元々傷自体は多いとはいえ針で突かれたものだ、浅い傷ばかりだったのだろう。
教室には轟と自分の他は誰もいない。皆文化祭を楽しんでいるのだろう。
轟が問うた。「身体はもう大丈夫なのか?」
「うん、この通りだよ。心配かけてごめん。あの、かっちゃんも」
何もなかったように出久はヘラっと笑う。さっきの苛立ちが蘇ってくる。
「うぜえわ、クソナード」
「先生に連絡しなきゃな。下に救護室があるだろ」轟がこちらを向く。
「あ?指図してんのか、クソが!」
「いや、そのつもりはないんだが」
窓際にいた勝己はふと下に目をやった。丁度相澤先生が校庭を歩いてる。
「おい、相澤先生」窓から首を出して呼んだ。呼ばれたことに気づいてるようだが、相澤先生はなかなか上を見上げない。
「上だ!上!ああ、クソ!」と窓から乗り出して大声を上げる。
「緑谷、気配が違うな。匂いというのだろうか」轟は近寄り、出久の首元を嗅ぐ。「うん、匂い、じゃないな、でもなにか」
出久の手が轟の肩に手をかけられた。
「さっきから何言ってんだ、半分やろ…」
勝己が振り向くと目に入ったのは。
さっきも見た光景だ。
轟の首に縋り付くように腕を巻きつけ、抱きついている。
「クソデク!てめえ」
爆破音を轟かせながら「てめえ、何してやがる」と勝己は2人の間に飛び込み、引き離した。
「危ねえな、爆豪」
「え?かっちゃん、僕、…ごめん、轟くん」
勝己の形相を見て、青くなった出久は、慌てて逃げ出した。
「待ちやがれ!クソデク!」
勝己はその背中を追う。轟の声が背後から聞こえるが、知ったこっちゃねえ。
追いかけて、階段の手前で出久を捕まえた。壁に叩きつけ、怒りのままに声を荒げる。
「2度目だ!てめえ、あいつにモーションかけてやがったろ」
「かけるわけないだろ!変なこと言うなよ」
「轟ならいいってのか!クソデク」
「そんなわけない!違うよ。僕は…」
出久の言葉が途中で途切れた。
様子がおかしい。
顎を掴んで顔を上げさせる。目の焦点が合ってない。
「おい、どうした?」
匂いが、違う?さっき轟が言っていたように。勝己の肩に出久が手を乗せた。
「デク?」
名を呼ぶとはっと出久の目に光が戻り、「わ、かっちゃん」と慌てて勝己を突き放した。
勝己は一瞬呆けたが、我に返って怒鳴る。
「何しやがる!てめえ」
後ずさった出久は頭に両手をやり、泣きそうな面で髪をくしゃくしゃとかき乱した。
「ごめん、ごめん、かっちゃん。まただ。僕おかしいんだ。知らないうちに変な事してるんだよ」
第4章
「戻って来なきゃいいと思ってたがな」
相澤先生は自分達の顔を見るなり渋面を作った。そんな風に言うということは、戻ってくることを予期していたってことか。追いついてきた轟も一緒に保健室についてきやがった。リカバリーガールは出張所に戻ったらしい。
勝己の説明を聞いて相澤先生は嘆息した。
「緑谷、残念だが、やはり寄生されていたようだな。寄生生物はあの子供からお前に侵入したんだ」
「あの子は、どうなりました?」開口一番、出久は問うた。
「迎えに来た両親も心配していたし、帰らせたよ」
「よかった」
てめえの状態も忘れて、出久は安堵したらしい。
「バカかてめえは。良かねえよ。先生、ガキ見つかったのに、帰らせちゃ何もわかんねえだろうが」苛ついて勝己は言った。
「あの子供の個性じゃないとわかったからな。ただ、寄生生物の媒介として使われただけだ。奴が抜けたから普通の子供に戻っていたよ。誰に会ったかも、ここに来たことも何も覚えてないらしい」
「より強い個体、デクに移ったってわけかよ」
「寄生生物は体内にいるはずだ。さっきは緑谷の身体をスキャンしても、何処にも見当たらなかったがな。巧妙に隠れているのか、擬態しているのか、どんな性質の寄生生物なのか、調べなければ分からん」相澤先生は溜息をつく。「なにせ情報が足りない。この個性を持っている敵を捕まえられればいいんだがな。寄生生物はそいつが作ったやつなのか、口田みたいに操っているのか。せめて寄生生物の一部でも、手に入れられれば良かったんだが」
「すまねえ、俺が全部燃やしちまったばかりに」沈んだ調子で轟が言った。
「まったくよお!残らず消し炭にしやがって」
出久が戻る前に確認しに行ったが、氷漬けにした針も全部炭化していた。下手すりゃ出久も黒焦げだったわ。もっとも、自分が一瞬躊躇している間に轟が片付けてしまったことが一番気に入らない。
「そんな、轟君のせいじゃないよ。僕はほら、全然大丈夫だし」
「ああ?んな訳ねえだろーが!クソデクが」
どこが大丈夫なんだと勝己は憤る。てめえさっき何しやがったのか忘れたのかよ。
「もしかしたら現場に何が残ってるかも知れねえ。探してみる」と轟は言った。
「頼んだぞ。こっちはとりあえず、もう一度緑谷を調べてみよう。症状に出たからには、奴が見つかるかもしれん」
出久を残して、轟と勝己は保健室を辞した。「おい」と轟に呼び止められる。おいじゃねえと苛つく。てめえと話すことなんかねえわ。
「んだよ、てめえは焼け跡に行くんだろーが!俺は行かねえぞ」
「ああ、俺だけで行くつもりだ。というか、お前はこの件に関わらない方がいいんじゃねえのか?」
「はあ?てめえ、何言ってやがる」
「緑谷が関わることになると、お前の反応は過剰になる。それじゃ冷静に判断できねえだろ。それに」と轟は続ける「緑谷も望まねえだろう」
「俺は冷静だ。関わろうが何だろうが、てめえに関係ねえわ!」
「緑谷はお前との関係を、もう間違えたくねえと言っていた。昔と同じことは繰り返したくねえんだろ」
「ああ?てめえに俺らの何がわかんだよ」
「高校以前のお前らに何があったのかは知らねえよ。けど、あいつには辛かったんだろうってことはわかるぜ。チャラにして、新しくお前と友人関係を築き直したいっていう、あいつの気持ちを俺は尊重するぜ。俺も親父との関係築き直してえからな」
「てめえの家庭の事情と一緒にすんじゃねえ」
轟の口から出久の名前が出ると、心底腹が立つ。奴が出久に戦線布告しやがった時からだ。俺以外誰も見てなかった出久を、奴も特別視しやがったからだ。煽られて戦って出久に救われたくせに、落ち着いてやがるからだ。
一番こいつが気に食わねえのは、出久が求める理想の友人関係って奴を、俺に見せつけてきやがるからだ。
何も知らねえくせに。友人関係だと?俺と出久が友達なんぞになれるわけねえんだ。くそくらえ。
何度も試みたんだ
ただの石ころだと、何度も思い込もうとしたんだ
川に落ちた時、救われたと思っちまった
他の奴だったなら何とも思わなかったろう
否定したかった
手を差し伸べた出久の姿に、オールマイトがだぶって見えたなんて
俺の心細さを弱さを見透かすように
大丈夫、一人じゃない、僕がいる
うねり光る水面、逆光の中の人影、白い小さな手、木々を伝い響く蝉の声
いつまでも忘れることのできない光景
出久がどういうつもりだったのかは関係ない
俺がそう思った、そう見えちまった
あの瞬間、あいつは俺の中で特別になっちまったんだ
出久より上にならなければ、俺は俺を許せない
上でいればあいつをどうでもいいと思えるはずだ
この俺があいつを意識するなんておかしいんだ
だがどんなに石ころだと思おうとしても、あいつは俺の中で存在感を増すのだ
どこにいても目の端に出久の姿を探す、声を探す
いつも気になって苛ついて、顔を見れば、気に触る癪に障る
一人じゃない、僕がいる
俺に手を差し伸べた瞬間から、あいつは俺の中に棲みついちまったんだ
「おい、デク」と背後から呼んだ。
保健室の前でウロウロしていた出久は、びくりと反応して振り返る。
「てめえ、なんで教室に戻らねえんだ。検査終わったんだろうが」
「うん、済んだよ。やっぱり何も見つからなかったって」
「しょうがねえ。じゃ、教室戻んぞ」
「戻れないよ。もし女子に抱きついたりしたら、もう僕、恥ずかしくてその子の顔が見れなくなるよ」
「はあ?理由を言えばいいだろうが」
「だって、無理だよ。自分が無理」と出久は首を振る。
こいつはまだ女子を神聖視してやがんのかよ。馬鹿か。女子っつってもヒーロー目指すような奴らだぞ。
轟ならいいのかよ、と聞きそうになり、なんとか堪えて勝己は言った。
「おいデク、来い。ここにいたら邪魔になんだろーが」
図書室に文化祭の展示はないが、閉鎖されてるわけではない。ポツポツと行き場に迷った生徒達が、一休みしている。壁際に並んだ端末の前に出久を座らせ、勝己は隣の席から椅子を持ってきて隣に寄せて腰掛けた。
「なんで図書室に来たの?」
「手がかりがねえなら、寄生生物の性質について調べるしかねえだろ。」
「なるほど、そうだね。何もしないよりいいね」と言ってから、出久は首を傾げる。「でも部屋のパソコンでも調べられるのに」
「図書室ならいくつも監視カメラがあるし、何かあれば誰かが駆けつける。俺も対処できるしな」と言ってから付け加える。「部屋で俺と2人きりでもいいぜ」
「わ、わかったよ。調べよ」
「警戒してんのかよ」
「そういうわけじゃないよ」
図書室に所蔵してる図書は電子書籍になっているので、端末から全文見ることができる。期限付きの電子データで貸し出しも出来る。紙の書籍もあるが、大多数はデータを選ぶようだ。
寄生生物で検索すると相当な数の書籍が出てきた。適当に選んでクリックする。
・寄生生物は宿主を己の奴隷にする
ハリガネムシに寄生されたコオロギは、成長したハリガネムシを放流するために、水に飛び込む。
クモヒメバチは蜘蛛に寄生して、自分のために網を作らせる
エメラルドゴキブリバチはワモンゴキブリに卵を産み、生かしたまま食料とし自分のための部屋を作らせる
フクロムシはカニを去勢し自分の卵を育てさせる
冬虫夏草はオオアリに寄生して、草に登らせて噛み付かせ、周囲に胞子を散布する
冬虫夏草。ガキの頃に出久が見つけたやつだ。背筋がぞわりとする。こんなのにとりつかれたのだとしたら。
暫くして出久は「全然頭に入らないよ」と呟いた。「てめえ、真面目にやれや」と勝己は出久の足に蹴りを入れる。
「いた!違うんだ。寄生生物関連書籍の文字列が認識できないんだ。普通の文字は読めるのに」出久は弱音を吐いた。
「ああ?寄生生物はてめえの脳にいるんじゃねえのか」
言ってからはっと気づく。そうなのか。夢遊病みたいだったと轟が言っていた。自分に抱きついた時も何かおかしかった。出久は頭の中の何かに操られているのか。
「そうかも知れない。嫌だな。今だって気を抜けば、意識をふっと持ってかれそうになる。実を言うと、僕、理性を保つのに必死なんだよ」
「意識を持ってかれたら、てめえはどうなる?」
「わかんない。理性を失えば何をするか。でも多分、さっき轟くんに抱きついたみたいにしちゃうんじゃないかな」
「轟にモーションかけてるみてえだったよな」
「やめてよ、かっちゃん」
「しなだれかかって、腕を首に巻きつけてよ」
「やめてってば。僕の意思じゃないよ」
あの光景を見て、どれだけ腹わたが煮えくりかえったか。
「構わねえ。俺にやってみろや」
「嫌だよ。絶対に嫌だ」
「散々俺に抱かれてたろうが。轟に出来て俺に出来ねえのかよ!」
「君と轟くんは違うだろ」
声が大きくなってしまい、静かにと司書に窘められた。舌打ちし、気をとりなおして、端末の画面に向かう。
寄生生物の奴は出久の中で何をしてえと思ってんだ。目的はなんだ。対処のために寄生生物の習性を知らなくちゃいけねえ。
てめえを寄生生物の餌にするわけにはいかねえんだ。
・寄生生物は被捕食者を次の宿主である捕食者に狙われやすくする。
吸虫に寄生されたメダカは、水面で派手に動き鳥に捕食される
ロイコクロリディウムに寄生されたカタツムリは、改造され動きが素早くなり、物陰から出て鳥に捕食される
・寄生されることで活動的になる例もある。
マラリアに寄生された蚊は一層獲物を噛むようになる。
狂犬病の犬が噛みつきたがるのは唾液に菌を持つからである
・幼生と成体で異なる宿主を持つ寄生生物について
幼生の宿主を中間宿主、成体の宿主を終宿主という。中間宿主では幼生期の発育を、終宿主では繁殖を行う。中間宿主を介さず終宿主に侵入しても成長することはない。
ロイコクロリディウムはカタツムリが中間宿主で、鳥が終宿主である。
トキソプラズマは中間宿主が人や豚であり、終宿主は猫である
寄生生物は中間宿主の中で成長した後に、体外に出て行くか、体内で終宿主に捕食されるのを待つ。
中間宿主と終宿主の橋渡しの役割のみを果たす宿主を待機宿主という
ワンフォーオールにとって、デクもオールマイトも中間宿主みてえなもんか。
正義の名のもとに心を支配して、パワーを与えて命を捧げさせるんだ。そうして、次の宿主に移るんだろう。
出久、てめえも自分のすべてをOFAに捧げんだろ。オールマイトがしたように。まるで寄生生物が己の目的のため宿主の心をコントロールするみてえじゃねえか。
継承者はワンフォーオールの奴隷なのだろうか。
捕食者と被捕食者の関係とは何だろう
寄生生物を体内に宿す被捕食者が捕食者を求める。
被捕食者の中の寄生生物が食わせるために捕食者を誘う。
飢える捕食者のために寄生生物を持つ被捕食者が現れ捕食者は腹を満たす。
果たして捕食者にとって寄生生物は害と言い切れるのか。
ポケットの中の携帯がぶるんと震えた。
第5章
「これを見てほしいんだが」と轟が掌に乗せた氷を示した。「氷を融かした後に、まだ廊下の隅に氷塊が残っていたんだ」
中に針状の物体が閉じ込められている。
携帯で呼ばれ、勝己と出久は急いで保健室に駆けつけた。轟が手掛かりを見つけたらしいという。急かすふたりに、見てみろと相澤先生は手招きした。
轟の手の中の禍々しいもの。
「無傷みたいだな。生きてるかもしれない」
相澤先生は氷塊を受け取ってシャーレに乗せ、慎重に周囲の氷を融かして、出久に見るように促した。
「これか、緑谷」
「はい、あ」くらりと出久はよろけたが、何とか踏ん張り「それです」と答える。
針がうねうねとくねり出した。
「危ねえ!」と轟が手をかざす。
相澤先生が個性を発動し、凝視すると針は動かなくなった。ほうっと出久は息を吐く。
針を透明なケースに仕舞うと、相澤先生は言った。
「校舎の外をうろついていたヴィランのことだが、寄生生物を人に取り付かせる個性を持つ奴だ。指名手配されてるが、今までなかなか尻尾を掴ませなかった。ヴィランのDNAが手に入ったのは収穫だな」
「自分は動かねえで、他の奴を操るわけかよ。けったくそわりい」
罪のない宿主を盾にするようなやり方だ。卑怯な野郎だと勝己は憤慨する。
「これを見ると、生物というより亜生物というべきか。実在する生き物をモデルに個性で作ったものだな。八百万の個性に似てるが、逆だ。八百万の個性は元素単位から構成して、生物以外の本物を創造する。これは本人の細胞を培養して、亜生物を作る個性だろう」
「生物を創造するんですか。すごい」
状況を忘れたのか、出久は感心しているようだ。勝己は苛ついて出久の背中を思いっきり叩く。
「てめえ、クソが!感心してんじゃねえよ。わかってんのか。てめえがその個性を食らってんだろうが」
「いたあ!わ、わかってるよ。かっちゃん。でも命を作るなんてすごいと思わない?」
「命じゃないぞ。亜生物だ」相澤先生が言う。「どんなに模倣しても本物の生物じゃなく、本人の細胞に過ぎない。いわば爪や髪の毛みたいなもんだ。元がその個性をもつ人間の細胞だからこそ、本体さえ目視できれば、俺の個性で止めることができるわけだな」
「つまり、緑谷の身体から追い出しさえすれば、捕獲できるんだな」轟が言う。
「ああそうだ。だが、体内の何処にいるかわからない以上、手の出しようがない。せめて体内の潜伏場所の特定が出来れば、いざとなれば手術するなりして対処できるんだが。」
出久の身体をスキャンしても、何処にいるのかわからなかったのだ。出久の身体の何処かで眠っているのだろうか。そこが脳なのか脊髄なのか心臓なのか。
活動する様子はない。ならば出久の奇行の意味は。ひとつだろう。
勝己は言った。「こいつのモデルになった寄生生物は、幼生と成体で異なる宿主を持つやつなんじゃねえか」
「なるほどな。宿主の移動をしようとしているのか。モデルになった寄生生物の性質も模倣してるかも知れんな。調べよう」
相澤先生はパソコンに向かい、暫くして検索した結果を見せた。
「これだろうな。動物とか4歳以前の子供とか、個性のない個体に食らいつき、成長してから、個性持ちの宿主に移って繁殖するタイプだ。本物は現在はほぼ駆除されている」
「じゃあ、そいつと同じ性質なのかよ。やべえだろ。緑谷ん中で繁殖すんじゃねえのか」轟が心配そうに言う。
「そこが不思議なんだがな。緑谷の中じゃ繁殖していないようなんだ。幼生の宿主を中間宿主、成体の宿主を終宿主というが、緑谷は何故か中間宿主もしくは待機宿主に当たるらしい。寄生生物は繁殖はせず、次の宿主を探している状態だな」
「おかしいだろ。個性に反応するなら、何故緑谷の中では繁殖しないでスルーするんだ?」
「出久がガキなんだろ」と勝己は素知らぬ素振りで嘯く。
轟は知らないのだ。出久の力は借り物だということを。勝己と出久とオールマイトの3人だけの秘密なのだから。
そうか、出久は元々無個性だ。OFAを得ても個性因子自体はないのだろう。だから、終宿主にならなかったんだ。寄生生物は子供の中でもう成体に成長したのだ。出久は望まれざる宿主なのだ。なら、個性のある奴に侵入しなかったのは、不幸中の幸いだったと考えるべきなのか。
「僕でよかった」とポツリと出久が呟いた。
いや、幸いなわけねえわ。ざけんじゃねえ。何がよかった、だ。てめえの呑気さには頭にくるわ。
出久が寄生生物に侵入されてから、勝己は今まで以上に、出久に引き寄せられる。おそらく轟もなのだろう。出久に抱きつかれていた時の奴の様子は、平常ではないように見えた。
より強い個体に引き寄せられるのだろうか。それとも宿主になる奴なら誰でもいいのか。どちらにしろ個性持ちに渡ったなら、そいつが終宿主になるんだろう。
それが奴の狙いならば、と勝己は相澤先生に提案した。
「どこにいるかわからない寄生生物なら、次の個体に移動する瞬間がチャンスだ。寄生生物をおびき寄せ、移動するときに捕まえるしかねえだろ。そいつがデクから移動する瞬間を狙えばいい」
「なるほどな。なら俺が囮になろう」
勝己の案に乗って轟が言いだした。何だこいつ。おれが先に言ったんだろうが。
「ざけんなてめえ!」
「ダメだよ。もし捕獲できなくて君に移ったら繁殖するかもしれないんだろ。そんなのダメだ」
出久は首を振る。相澤先生も有無を言わさない口調で言う。
「緑谷の言うとおりだ、轟。これ以上生徒を危険な目に合わせるわけにはいかない。どんなタイミングで移動しようとするかも不明なんたからな。とりあえずお前らは教室に戻るんだ」
「ああ、わかった」轟は渋々といった様子で戸を開け、勝己の方を振り向いた。「爆豪、行かないのか?」
勝己は轟を睨み、出久に視線を移した。出久は所在無さげに戸惑っている。轟は答えない勝己を暫く見つめて、先に行ってると静かに言った。
轟が保健室を出て行くと、勝己は口を開いた。
「俺が囮になる。あんたはそれを阻止するんだ、先生」
「お前な。駄目だ危険すぎる。許可できん」
相澤先生は眉を顰め、厳しい表情になった。勝己は拳を握ると相澤をまっすぐ見据える。
「デクん中にヴィランがいるなんて、気色悪くて我慢できねえんだ」
「ちょっと待ってよ」と出久が慌てた。「僕がおかしくなったの、見てるだろ。君や轟くんに抱きついたんだよ。あんなの、先生達の見てる前でなんて、嘘だろ」
「ああ?てめえ、仕方ねえだろうが。おい、先生!」
「駄目だ、駄目だよ」と必死で出久は首をぶんぶんと振る。「危険過ぎるよ」
「さっきも言ったがそれはないな」と相澤は嘆息する。「これ以上、生徒を危険に晒すことはできない。戻っていいぞ、二人とも。手段はなんとか考えよう」
ふたりは保健室を辞した。歩き始めた勝己の後ろを出久は付いてくる。
「早く来い」と勝己が言うと、
「うん」と答える。
いつかのように。
遠く、文化祭の賑やかな声が聞こえる。
職員室のあるこの階の廊下には、自分たちの他には誰もいない。
出久の上履きが後ろでペタペタと音を立てる。
出久とふたりきりになったな、と思う。
「おいデク」
返事がない。
足音が止んだ。出久が立ち止まったのだ。
ゆっくりと振り返る。
出久の虚ろな視線が彷徨う。
やっぱり来やがったな。
こいつはターゲットが一人になったと認識したら出てくるんだ。他の奴がいると出てこねえ。保健室では俺が出て行って轟とふたりになった時、教室では俺が窓の外の先生を呼んでいる隙に出やがったからな。
勝己は踵を返して歩み寄り、出久の身体に手を伸ばした。ふわりと匂いが漂ってくる。捕食者を誘うフェロモンのようなものなのだろう。
出久の腰を抱きしめ、引き寄せて両腕を背中に回す。すっぽりと腕に収まる出久の温もり。シャツの下の筋肉の感触。足を出久の足の間に入れて太腿で股をじりっと押す。
出久の腕が勝己の肩に縋り付き、そろりと首に回された。
止めなければいい。出久が俺を求めてるんだ。
寄生生物を宿した被捕食者として捕食者の俺を。
理性など吹っ飛ぶほどの抗いがたい本能。
宿主は捕食者の心をコントロールする。寄生生物があいつをより美味そうに見せるのだ。鳥の前に腹を見せて翻る魚のように。こいつを喰らえと吠えるんだ。
出久、俺はてめえの捕食者なんだ。
「限界なんだクソが」小声で囁く。「大人しく犯されろよ、デク」
出久の瞳が揺れる。僅かに意識は残っているのかもしれないが、それとは裏腹に抵抗できないようだ。
ボタンを外し、シャツを肌ける。素肌に手を這わせても、為すがままな出久に興奮する。
頬ずりして、唇に触れる。少し開いた唇に吸い付き、舌を口内に押し入れて、貪るようにキスをする。吐息が熱い。目眩がしそうだ。
出久の瞳が反転したように見えた。
いや、白目が黒く何かに覆われたのだ。
勝己は出久を壁に押さえつけた。これが寄生生物の移動する瞬間だ。
「かかったな!寄生野郎が!俺の他には誰もいねえ。安心して出てきやがれ」
出久の眼球から蜘蛛の糸のように細い糸が飛び出てきた。
糸を放出しながら、出久は壁を背にして崩折れる。
「おい、デク。てめえ!寝てんじゃねえぞ!」
出久の足元の空間に糸が積まれてゆく。霧のような細密な糸。暫くして糸が出なくなった。全て出尽くしだのだろうか。出久の閉じた目から血が流れている。無事か。
糸がむくりと動き出した。ひと塊になり勝己の方に向かってくる。
咄嗟に飛び退くと、うねる糸の塊を爆破する。
だがパラリと崩れても糸はまた寄り集まる。
細密な蜘蛛の糸のように空中に広がり、編まれ広がってゆく。
「起きろデク!クソカス!」
勝己は出久を抱き起こし、ガクガクと揺さぶる。
「…ん、起きてるよ。動けないんだ。かっちゃん、僕のことはいいから逃げてよ」
「ああ?何言ってやがんだ。カス!」
出久は目を開けた。白目は元に戻っているが、酷く充血している。
「頭の中からそいつがなくなったからやっと言えるよ。衝撃タイプの攻撃がきかないんだよ。バラバラに解けるだけなんだ。かっちゃん、逃げ、いや、相澤先生を呼んできて」
「てめえ、喋んな、黙れ!」
クソが。逃げられるかよ。逃げたらまたこいつがてめえん中に戻るだけだろうが。
網は2人を包みこもうと狭まってくる。
勝己は出久を糸の包囲網の外に突き飛ばした。
よく見ると糸じゃなく、針状の寄生生物が寄り集まって、網状の形を成しているのだ。
網は勝己の腕に触れてバリバリと皮膚を裂いた。プツプツと血が吹き出す。
「傷を負っちゃ駄目だ。本体が傷口を狙ってくる」
「ってーな!これは本体じゃねえのか」
「多分、武器だ。寄生先への侵入ルートを作るための」
「きめえ。本体はどこだ、デク」
「網の何処かに包み込まれてる」
どこから入ろうとするんだ?目からか口からか。皮膚を破って入るなら手や足からか?
ピリッと皮膚が割かれる痛み。無数の針が服の腕からでも皮膚を刺す。
さして痛くもないのに、シャツがみるみる赤く染まる。
血が止まりにくくする何かを出しているのだ。出久の時と同じように。
「クソが!」
「かっちゃん!逃げてよ、かっちゃん」
出久は這いつくばりながら、勝己の方にじり寄ろうと足掻いている。
網の中心に針と同じ大きさだが、形の歪な白い塊が見える。
あれが本体って奴か。クソが!
続けざまに爆破してみるが、びくともしない。
畜生が!目視出来てるのに爆破出来ねえのかよ。
一気に消し炭にするとか、まとめて凍らせるならいけるんだろうか。轟の個性のように。クソ!轟なんかに任せられるかよ。
網がバラバラと崩れた。爆破、効いたのか?
だが違った。
夥しい針の群れは空中に放射状に広がり、勝己を幾重にも取り囲んだ。
「かっちゃん!」
「クソが!」
針が一斉に勝己に襲いかかる。
無数の針が皮膚を裂いた。
「爆豪!」
廊下に響く怒鳴り声。
途端に針の動きが止まった。バラバラと床に落下して山を築く。
相澤先生が駆けつけたのだ。
「相澤先生、よかった」出久は身体を起こす。
「いってーな!クソが!」
安堵したのが悔しく、勝己は足で蹴って針の山を崩す。
寄生生物は捕獲された。
「よくやった爆豪」ほっとした声で相澤が言った。
「遅えよ!」
「相澤先生、かっちゃんと組んでたの?僕を騙してたの?先生まで?危険じゃないか」
出久は目を擦りながら、非難めいた声音で問う。
「いや、組んではいないぞ。爆豪は止めても聞かないだろうからな。様子を伺っていたんだ。あれでな」先生は監視カメラを指差す。
「そうなんですか。かっちゃんは、それを見越してたのか、でも…」
「てめえの脳が寄生されてんだとしたら、てめえの中の寄生生物とやらを、本気で期待させねえと駄目だろうが」
さっきまでの心をもぎ取られるような衝動は止んだ。あの場で本気で出久を抱こうとしていた。寄生生物を持つ被捕食者は捕食者を誘うのだ。抗いがたい力で。
「褒めていいものか迷うところだが。爆豪は自分を囮にしたんだ。なかなかできることじゃないぞ」
「ああ、はい、そうですけど、でも」出久はもじもじと続ける。「ありがとう、かっちゃん」
「へっ!」
出久の中に他の奴が居るのが、我慢ならなかったのだ。人だろうが、人じゃなかろうが。結局は俺はてめえを求めているのだ。誰にも渡したくねえんだ。
「まあ、いつ出ていっていいものかどうか、迷ったがな」
「なんのことですか?」
相澤先生の言葉に、出久は首を傾げている。先生が見張ってると知りながらキスしたことか。あん時はもう出久は意識を乗っ取られていただろうから、覚えてねえんだろう。
ガチでやるわけねえだろうが。けど、やっちまってもいいと思った。途中で止められたから不完全燃焼だ。足りねえ。
くらりと頭が揺れる。ぽたぽたと血が滴れる。シャツから血が染み出してくる。血も足りねえってか。
「クソが。貧血か。血が出過ぎたみたいだ」
てか、止まらねえ。そうか、そういう手口か。出血させて、体力を奪い動きを鈍らせ、宿主の抵抗力をなくしてから、本体が取り付く。
出久だけなら奴を避けて逃げることも出来たはずだ。きっと出久は子供を抱き上げて、両手を使えない状態で襲われたのだろう。子供を逃がした時には遅かったんだ。
「かっちゃん!」と呼ぶ出久の声が遠くなる。
倒れんな、俺の身体。あいつの前で倒れんな。あいつは強い俺しか見てないんだ。もし俺が弱くなれば。俺を見やしないんだ。
保健室の天井がぼんやりと見えた。
大量出血のせいか、目眩がして頭を起こせない。血が不足してるのだ。
切羽詰まった出久の声が聞こえる。
「輸血なら僕の血を上げて!」
「爆豪は何型だ」
「A型だよ。ぼくはO型だから、僕の血をあげられる。相澤先生!」
出久は錯乱しているようだ。
「落ち着け、緑谷。型の違うお前のより保管してるA型血液の方がいい。今リカバリーガールが輸血の用意をしている」
「かっちゃんは強いんだ。負けないんだ」
出久は血相変えてまるで子供のようにただをこねる。相澤先生は珍しく慌てているようだ。きっと先生には、今の出久があいつらしくなくて理不尽に見えるんだろう。
俺を強くてタフだと信じている。勝つことを諦めないのが君じゃないかと押し付ける。我儘で頑固で融通がきかない。それがあいつだ。出久は信じてるんだ。俺を。
勝己は怒鳴った。「リカバリーガール、いねえのかよ!」
「ここにいるよ、なんだい」
奥から点滴の道具を持って、リカバリーガールが顔を出した。
「かっちゃん、起きたんだ」出久は泣きそうな顔だ。
「今すぐ怪我を全部治せや」
無数の針で刺されたような傷。見えない傷口から血の玉が転がり落ちる。血はまだ止まっていない。
「ひとつひとつは塞ぐのは簡単だろ。塞いじまえば傷なんか」
「いや、緑谷の時より傷が多くて深いんだ。刺さった針の数が尋常じゃない。一度に治せば、お前の体力が持たないかもしれないぞ」相澤先生は言う。
「輸血しながら、ゆっくり直したほうがいいよ」
リカバリーガールが子供を宥めるように言う。
「舐めんなできるわ」
あいつが俺を見てるんだ。あいつが俺を信じてるんだ。俺がへこたれるわけにはいかねえんだ。強くなければあいつは俺を見ない。
俺はどうだ。俺は出久が弱くなったなら。
ひょっとしたら、歓喜するのかもしれない。
弱くなれば他の奴らは出久から離れていくかも知れない。でも俺にとってどんな出久でも出久は出久だ。俺は絶対に離れねえ。
そうなれば出久も俺から離れることなんできねえだろ。中学生の頃みたいに、俺だけのものになんだ。
ああくそ!思考がぐちゃぐちゃだ。
雄英の奴らはそんな奴らじゃねえってわかってる。
たとえあいつが弱くなっても、今更もう手に入るわけねえわ。
俺は捕食者だったのだ。自覚する前からあいつは俺の獲物だったのだ。いつかは皮膚を囓り肉を噛み裂くのだ。だからあいつは無意識に警戒していたのかもしれない。
捕食者は獲物よりも運動性能が優れてなければ食いっぱぐれる。だから俺はあいつより強くなければならないのだ。
一人の人間にとって自分が特別でありたいと渇望するのは、自分にとって相手が特別であるからだ。どんなに相手をつまらない者だと、取るに足らないと貶めようとしても、心の奥底が求めて止まないんだ。
自分だけが相手の唯一の存在でありたいと。
第6章
傷は全て治療されたものの、体力を消耗した勝己は半日寝込んだ。目を覚ました時には既に日は傾き、黄昏の橙色に部屋が染まっていた。
「やっと起きたんだね」
出久が枕元に座っていた。目元が赤いようだ。顔を染める夕焼けのせいか、泣いていたのか。
保健室の窓の外から音楽が聞こえる。外で何をしているのか、時々歓声が上がった。
「今、後夜祭をしてるんだよ」勝己が問う前に出久は答える。
「てめえは行かねえのか」
「うん」出久は済まなそうに目を伏せる。「打ち上げは行ったよ。皆も君を心配してた。君が回復したら寮でまた打ち上げしようって」
「いらねえよ」
「後夜祭の後には戻ってきて、後片付けするそうだよ。僕も行くけど。あ、そうだ」
出久は手に持ってた袋を開けて、中を見せた。
「ちょっと食べ物を持ってきたんだ。かっちゃんが起きたらお腹空いてるかなと思って。打ち上げの時の残りだけど」
そういや腹が減ったな。「寄越せ」と勝己は出久が袋から出したパンや菓子をがっつく。「かっちゃん、お茶もあるよ」と差し出されたペットボトルをひったくるように受け取る。喉を鳴らして嚥下する。冷たさが胃にしみる。
「ごめんよ、かっちゃん」
「ああ?」
「元はと言えば全部僕が迂闊だったせいだ。僕が気をつけてれば、こんなことにならなかった」
「あ?ざけんじゃねえぞ。デク!」勝己は眉根を寄せて睨みつける。「てめえのはてめえのミスだ。俺のは俺の判断だ!謝んじゃねえよクソが。起き抜けに苛つかせんじゃねえ」
怒鳴ってから、確認していなかったことに気づく。奴は本当に出久の中から抜けたのか。
「てめえん中には、もういねえんだな」
「うん、僕は大丈夫。先生呼んでくるね」
勝己の身体は完全とは言えないが回復したらしい。「無茶をしたけれども、大したタフネスだね」とリカバリーガールは驚き半分呆れ半分。もう帰っていいと保健室から送り出された。
「かっちゃん、後夜祭行く?寮に戻る?」
「教室に行くわ。来い、デク。てめえに話がある」
勝己はそう告げて「あ、うん、あの」ともぞもぞと言い淀む出久の腕を掴む。
夕暮れの教室には柔らかな黄色い光が差し込んでいる。教室には誰もいない。まだ後夜祭は終わらないようだ。
「デク」と名を呼ぶ。怒りを帯びてない声で名を呼ぶのは、随分と久しぶりな気がする。
「何、かっちゃん」戸惑い気味に出久は答える。
「てめえを抱いたのは、マスターベーションなんかじゃねえよ」
「い、いきなり何、その話はもう。かっちゃん」
狼狽える出久に構わず勝己は続ける。
「てめえがどうだろうとな。俺のやりてえことは変わんねえ。てめえが俺への認識を改めてえってんなら、それまで待ってやる。てめえは俺のもんになるしかねえんだ。逃さねえからな」
「かっちゃん、僕は応えられないよ」
「先はわからねえって言ったのは、てめえだろうが。俺は諦めるつもりはねえ」
触れてしまったのだ。そう簡単に手放せやしねえんだ。出久は唇を噛んで俯いた。外から生バンドの演奏する音楽と歓声が聞こえる。黙ってんじゃわかんねえよ。勝己は焦れた。
「何だよ、言いたいことあんなら言えや」
「無理なんだ」出久は漸く口を開いた。「君と新しい関係を構築するなんて、無理なんだよ。僕は結局、君を皆と同じようには思えないんだ。認識は変えられない。だから待っても無理なんだ」
「なんだとてめえ!」
「君に情が移った事を、過去の話として轟君に話してたのに。よりによって君に聞かれてしまった。」
「俺のことだろうが。俺が聞いたからってなんだ」
出久は俯いて言葉を紡ぐ。
「知られても、それだけだと思った。でも君がまたやろうって言うなんて。僕は怖くなった。付き合ったって、また昔の繰り返しになるだけじゃないか」
「ああ?なら待てっつったのはなんだ。俺をその気にさせて、てめえ、この俺を騙しやがったのか」
「できると思ったんだ。本当だよ。でもやっぱり無理だ。僕にとってやっぱり君は君なんだ。僕は憧れるだけで良かったんだ。手の届かない君に。 君が応える可能性なんて有り得なかった。なのに中学の頃、あんな形で僕は君と関係してしまった。心も身体も踏みにじられて、君の形を刻み付けられて、自分の弱さが辛かった。君を怒らせるのが怖かった。君が憎かったよ」
出久はシャツの合わせ目を掴む。ぎゅうっと掴んで指が白くなるほどに。
「それなのに君に情が移ってしまうなんて。そしたら今度は見捨てられるのが怖くなった。酷い形でも、僕に関わってくるのは君だけだったから。セックスしてる一瞬だけは、君のことが怖くなかったから。でもそんなのおかしいだろ。憧れて憎くて怖くて、僕はどうしたいんだろうって、混乱して自分が壊れてしまいそうだった」
出久は顔を上げて薄く微笑んだ。
「君との関係が終わった時、ほっとしたんだ。もう僕は抱えきれない混乱から解放されたんだって。だから、もう二度と君に応える気はない。応えちゃいけないんだ」
「てめえ。またかよ。またてめえは嘘をつきやがった!」
繰り返し繰り返し、俺を偽り続けるんだ。勝己は掴みかかり、出久の首元を締め上げる。なんで俺は嘘ばかりつくこいつが欲しいんだ。出久は抵抗もせずに勝己を見上げる。
「君が眩しいんだ。今も昔も。君は僕を捩じ伏せるために抱いたんだろう。君には一時の気の迷いや好奇心に過ぎなくても、僕は潰れてしまう。また囚われるんだ。僕を否定した君に。呪縛なんだ。そう思うのは錯覚なんだってわかってるのに」
「 はっ!てめえは全部錯覚だった言うのかよ」
「君も錯覚だろ。ちょっと血迷っただけだ。情欲とは言うけど情と欲は別物だよ。欲で動いて情で惑う。また間違った形の繰り返しになるだけなんだ」
またか、てめえは俺を何だと思ってやがるんだ。俺がてめえを失うことをどれだけ恐れているのか、考えた事もねえんだろ。
「ああ、確かに俺はてめえを捩じ伏せたかった。反抗的で何考えてるかわかんねえてめえを支配したかった。その発露がセックスだ。否定はしねえよ。だがな、なんとも思ってねえ奴を何度も抱くほど暇じゃねえわ」
「君は変わらないな。でも僕は変わらない君がいいと思ってる。君は特別だよ。僕にとっていつまでも」
「てめえ、俺の言ったこと聞いてんのかよ」
てめえには何一つ伝わらねえ。どう言やあわかるんだ。
「僕は君が大事なんだ。君との関係がなにより大切なんだ。君が思う以上に。今度は間違うわけにはいかない。やっと対等になれたんだ。今みたいな幸せなんて、昔は考えられなかった。君を憎まず純粋に憧れていられる。僕は今幸せなんだよ。君には近づき過ぎちゃいけないんだ」
てめえが俺に嘘をついて、そんなことを心に決めた、その矢先に寄生生物騒ぎが起こったってわけか。
「てめえ、俺に抱きついて誘ったよな。本当に寄生されたからって理由だけかよ。ああ?デク」
轟まで誘ったことは忘れる。
「そうだよ。それ以外にあるわけない。君が僕に惹きつけられるのも、僕が君に惹きつけられるのも寄生生物のせいだった。被捕食者と捕食者の関係だ。また心が間違った方向に狂わされたんだ。今は余波が残ってるけど、この気持ちも静まるはずだ。あんな心が壊れてゆくような混乱は、もうゴメンなんだ」
最初に間違ってしまったから、もう手遅れなのかよ。クソが。
迷いも全部寄生生物のせいにしやがるのかよ。
余波だと。
余波と言ったか。そうか。
出久の混乱は昔じゃねえ。今の話なんだ。
「はは!そうか。そうかよ、てめえ!ほんとに迂闊だよなあ、デク」
勝己は高笑いをする。
「かっちゃん?」
出久は訝しげだ。自分で言ったことに気づいてねえ。
「つまり、今てめえは俺が欲しいんだな」
「ちが、違うよ、なんでそうなるの?かっちゃん」
「余波があんだろ。でももう寄生生物はてめえの中にいねえよなあ。そう言ったよなあデク。ごちゃごちゃ言いやがって、結局誤魔化してんじゃねえか!なあ、そうだろ」
「違うよ!」
「こっちに来やがれ。確かめてやるわ」
余波が残ってるってんなら好都合じゃねえか。てめえには言葉じゃ通じねえんだ。身体でわからせるしかねえんだ。
拳で殴り合って、身体をぶつけ合って。毟りあって、無茶苦茶になって。
そうするしかねえだろ。
俺らはずっとそうしてきたんだからよ。
てめえは虫けらなのだと言い聞かせた
取るに足らない存在だと思おうとした
どうしてもそう思えないからこそ足掻いた
てめえに俺を認めさせれば、何もかも上手くいくと根拠もなく信じていた
それが不可能なのだとわかったとき
俺の中に棲みついたてめえがどんどん大きくなり
もうてめえの呪縛から逃れることはできないと知ったとき
もうてめえを逃さないと決めたのだ
だからてめえも逃げんな
勝己は空き教室に出久を連れ込んだ。
舞台の道具置き場にしていた場所だ。ベニヤ板が隅に積まれ、余った大量のサテンの生地が無造作に散乱している。
勝己は出久を床の上に倒し、両手首を片手で纏めて押さえつけた。「かっちゃん」と開けられた口に被せるようにキスをする。出久の舌を絡めとり、擦り合わせる深いキス。頭が痺れるようだ。角度を変えては深く口づける。
「このまま突っ込んでやろうか」
ニヤリと笑って告げると、出久の身体をうつ伏せにして下着ごとズボンを膝まで脱がした。
「やだ、かっちゃん!」
もがく出久を押さえつけ、自分のズボンのチャックを下げて、勃起したものの先端を後孔に押し付ける。びくっと出久の身体が跳ねる。慣らさねえと入らねえだろうが、意思表示だ。
「今度こそ、てめえを犯すぜ、出久」
「かっちゃん」と震える声。
ゴクリと喉を鳴らす。飢えが頭を支配する。貫けばいい。穿てばいい。ベルトを外しズボンと下着を脱ぎ捨てる。再度剥き出しの出久の局部に押し付けて擦り付ける。
「やめ、かっちゃん、誰か来るよ!」
「構わねえよ!来た奴には見せつけてやりゃあいいんだ」
「嘘だろ!かっちゃん!」
「嘘つきはてめえだろうが!」
階下から生徒たちの声が聞こえてきた。後夜祭が終わり、教室に戻ってきたのだろう。騒がしく喋る声。展示物を片付けている音。
「でけえ声出したら、聞こえちまうぜ」
追い詰めるように勝己は囁く。寄生生物に取りつかれている時は無抵抗だったくせに、今更抗うのかと苛立つ。勝己は出久を押さえつけたまま自分のシャツを肌け、服を脱いで全裸になった。抵抗する出久を転がし、仰向けにして押さえつけ、衣服をひっぺがす。
脱いだほうが、もう俺が引かねえとわかるだろう、裸じゃこいつは逃げられねえし、見つかれば言い訳できねえしな。
出久に覆いかぶさり、裸の肌を重ねた。久しぶりに直に触れる体温。しっとりと手に馴染む皮膚の感触。掌で肌を撫でる。脇腹を腹を、太腿を愛撫する。乳首を弄り舐めて、片方が固くなるともう片方を舐める。出久は声を押さえて、悶えているようだ。肌を舐めると薄く塩辛い。出久の味だ。余ったサテンの生地を引き寄せて、下に無造作に敷いた。汗ばむ肌を合わせ、足を絡ませる。
勃ちかけた出久のものに触れ。互いの性器を密着させると、出久はヒュと息を呑み、「かっちゃん」と掠れた声で呼ぶ。
この肌に溺れていた中学生の頃を思い出す。匂いも反応も、喘ぐ声も吐息も、五感の全てで味わっていたことを。
てめえの身体で俺の知らない部分なんてひとつもねえんだ。何処がてめえの感じるとこなのか、嫌がるところなのか。何年たったとしても、触れれば昨日のようによくわかる。体格は多少逞しくなっても、何も変わっちゃいない。快感によがらせてやるわ。
股の間に手を滑らせ、出久の陰茎を握り、扱き始める。
「ま、待ってよ、かっちゃん」と出久は弱々しく勝己の手に触れる。
勝己は雁首を摘まんで、人差し指と親指で輪を作り優しく撫でる。ここの手触りも変わらねえ。袋を揉んで幹を根本から扱いて勃たせる。屹立の先端にキスをすると、鈴口を舌でつつき、口を開けて深く咥える。
「あ、あ!かっちゃん!やめて」
出久は驚いたようだ。必死で抗議し、身体を捩る。
うるせえ。何度もしたことあんだろが。てめえの口を塞いでやろうか。
勝己は出久の頭を跨いで、シックスティナインの体位になった。出久の顔の前に屹立した自身を突き出す。
「舐めろよデク」と勝己は言った。口淫は何度もさせたことがあるだろ。
「てめえのもんが人質だぜ。やらねえならてめえのを咬んでやるわ」
「どうしても?かっちゃん」
まごつく出久に焦れて少し歯を立てると、「うわ!本気で、やめ」と出久は慌てた。
「さっさとやれや」
亀頭に柔い舌が触れる。出久は勝己のものを口内に含んだようだ。先端が熱い粘膜に包み込まれる。勝己は歯を立てるのをやめて、舌を平にして舐める。
くっくっと喉の奥で笑う。言われたからって、普通やすやすと人のイチモツを咥えたりしねえんだよ。てめえはもうおかしくなってんだ。昔だって俺だけが気持ちいいだけじゃなく、てめえも気持ちよかったはずなんだ。てめえの本能に逆らってんじゃねえよ。
互いの性器を咥えて舐める水音。波打つサテンの生地の衣擦れの音。階下からは生徒たちの賑やかな声。まるでここは水底のようだ。
勝己はしゃぶりながら、出久の後孔に唾液を擦り付ける。指先を差し入れると反射的にきゅっと締まった。唾液の滑りを借りてゆっくりと沈めてゆく。んん、と出久は唸る。頬張っているもののせいで、言葉を紡げないのだろう。
指を二本に増やして、またぬるりと滑り込ませる。蠢き締め付けてくる温かい内壁。この中に突っ込んでやるのだ。痛みなど感じさせないくらいに、解して柔らかくしてやる。指を深く呑み込ませて広げるようにうごめかす。
「デク、もういい」
出久の口腔から引き抜いたペニスは、はち切れんばかりに膨張し、上に反っている。
「なんか、すごいね」と出久は困った顔で目を伏せる。
「おい、よく見ろや、てめえが元気にしたんだぜ。入れねえわけにはいかねえよな」
身体を起こし、出久の足を開かせて覆いかぶさる。手探りで陰部を探り、柔らかくなった後孔に亀頭を捻じ入れる。出久は観念したように目を瞑った。ずんっと腰を打ち付ける。
「あ、かっちゃん、う、んん」
挿入を始めると、出久の眉根が寄せられた。口から押し殺した苦痛の呻きが漏れる。ペニスへの圧迫感にふうっと息を吐く。丁寧に解したけど、久しぶりだから狭くなってんな。
勝己は上体を起こして、出久の片足を肩に乗せ、ゆっくりと腰を前後に振った。出久は揺するたびにん、ん、と声を堪えて悶える。目の前で自分の陰茎が出久の中に埋まってゆく。いい景色だ。出久は目を薄く開ける。
根元まで深く入れて一旦腰を引き、再び押し入り、内壁を広げていくように抉る。突き入れるたびに「あ、あ」と出久は声を抑え切れずに喘ぐ。
「締めんな。力抜けよ。覚えてんだろ」
「出来ない、よ」
「出来ねえじゃねえわ。やれや」
「う、ん、」
小刻みに動しているうち、中が慣らされてきて、スムーズに動けるようになってきた。気持ちいい。リズミカルに律動し腰を打ち付ける。
「俺を感じろよ、デク。セックスしてるんだ。マスターベーションなんかじゃねえんだよ。始めっから違えんだ、デク」
途方もない飢餓感が、俺にてめえを喰えと命ずる。抉れ、貫け、手に入れろ、俺のものにしろと。
俺の性器が出久の体内を行き来している。出久の熟れた肉が俺を温かく包みこむ。
前立腺の膨らみを探り、見つけて雁のえらで引っ掛けるように擦る。出久の身体が跳ねる。出久の嫌がる場所だ。良すぎて感じすぎて、ぽろぽろと泣きだすのだ。泣かせてみたいと、ぐりっと突き上げる。何度も突いては苛む。
「や、あ、かっちゃん」
涙ぐみ、喘ぐ出久の声に甘さが混じる。煽るような響き。
「隠すな。全部俺に見せろや」
顔を隠そうとする出久の腕を掴んで押さえつける。出久の目からぽろぽろと涙が溢れる。
ドクリと屹立が震える。
痺れが身体の奥から全身に広がってゆく。いきそうだ。深く突き上げると、出久は嬌声を上げた。勝己は唸り声を上げ、出久の奥深くに精を放つ。
ドクドクと迸る飛沫が、出久の中を濡らしているのだ。中に染み込んでしまえばいい。熱い、と出久が呟く。
下腹が濡れてるようだ。見ると出久のペニスから白濁がとろりと吹き出している。声を上げた時に、出久も同時に達したのだろう。
てめえの皮膚の下の熱さを誰も知らない。俺の他に誰も知ることはねえんだ。
身体の奥に俺を刻みこむんだ。てめえの全ては俺のものだと。
名残惜しく出久の後孔から性器を引き抜いた。孔がゆるりと閉じてしまう。自分のペニスと腹に散った出久の精液を拭き取ると、出久の胸に頭を押し付けて、荒くなった呼吸を整える。
肌の温もり。トクトクと耳に届く出久の心音。汗だくの体躯を強く抱きしめる。
「デク、デク」と掠れた声で呼ぶ。
「かっちゃん」と喘ぎ疲れた声で出久が呼ぶ。
顔を起こしてそっと髪に触れる。髪で隠れていた翡翠のような瞳が勝己を捉える。確かな視線で見つめる。
勝己の肩に触れる出久の手。抱きつくでもなく引き離そうとするでもなく。揺蕩う手を掴んで一本一本、指に口付ける。
「かっちゃん」出久は口を開く。「僕は君としたからじゃなく、きっと昔から君に惹かれてた。そう思いたい。でももう別のものがいっぱい混じってしまって、わからないんだ」
「同じことじゃねえか。どう違うってんだ」
「惹かれてる気持ちだけを、育てていけたんだ。関係を結ばなければ、できたんだ」
「そんなもんはいらねえ。てめえに良くても、俺には良くねえわ」
どんなに近づいても、こいつと俺はわかり合うことはないかもしれない。だが触れ合うことで、一瞬でも境界を穿つことはできる。ひとつに溶け合うことができる。
気休めなのかも知れねえとしても。だからなんだ。正しくねえからなんだってんだ。間違っているからなんだってんだ。
嘘つきなてめえでも、身体を重ねてる時だけは嘘をつけねえ。何度だって隔たりを溶かしてしまえばいいんだ。
俺たちはずっと昔から共生関係なんだ。OFAがてめえを見つけるずっと前から。
俺はてめえが欲しくて、てめえは俺に縛られてる。
OFAが次の宿主に移ったなら、まっさらになったてめえの全ては今度こそ俺だけのもんだ。
一方的な関係なんてな、両方が想っていたら不可能なんだよ。
「戻ろうよ、皆後片付けしてる。手伝わなきゃ」
「ここのもん片付けりゃあいいだろが。生地汚しちまったしよ」
「そ、そそ、そうだね。見られたら困るよね」
「使い道があったな。役にたったわ」
勝己はにやりと笑う。出久の顔が真っ赤になった。慌ててサテンの海に埋もれた服を探し始める。
「何焦ってんだ、クソデク」
出久の腰を引き寄せ、胡座をかいた膝に乗せ、後ろから抱えるように抱きしめる。まだ裸の素肌に触れていたい。肩口に顔を埋める。出久の匂いだ。捕食者を誘うフェロモンみたいな偽物じゃない。本当の出久の匂い。
「あの、かっちゃん?放してくれる?」
「ケツ動かしてんじゃねえよ、また勃っちまうわ」と腰を突き上げる。
「わ、そ、それは、かっちゃん、誰か来るかも、ねえ」
「こっちまですぐには来ねえだろ」
身体を捩っていた出久も、放そうとしない勝己に観念したらしい。大人しく身を持たせかける。
同じことをしたとしても、同じ結果になんてならない。
毎夜違う夢を見るように。毎日違う朝が来るように。
今ならきっと違う道をいける。違う結果を見出せるはずなんだ。
ふと、舞台で出久の言った台詞を思い出した。
「おいデク、てめえは劇のクライマックスでの掛け合いの台詞を覚えているか」
抱きしめる腕に力を込めて勝己は問うた。
「気持ちがわからないと、てめえが拘っていた台詞だ」
密かにそうありたいと思った言葉だ。その意味をてめえは今もわからないのか。
「あの言葉」と呟いて、出久は答える。「少しは、わかる。わかるよ」
終章
(全員が客席からステージ上に上がる)
(緑谷、爆豪は背中あわせになる)
緑谷 「今のうちに君に話したいんだ」
爆豪 「あんだ?」
緑谷 「僕は君のことは覚えてるよ。でも君とどんな時を過ごしたか、あまり覚えてないんだ。日々の鍛錬や冒険の中で、自分のことで手いっぱいだったし。子供の頃のことはどんどん薄れていってしまった」
爆豪 「んだと、てめえ」
緑谷 「でも覚えてるよ。楽しかったこともあったけど、悪いことも、沢山あったよね」
爆豪 「ああ?こんな時にまだ怒らせてえのか。てめえは!」
緑谷 「でも、きっと。僕は君にもう一度出会うために、旅に出たんだ」
END
胡蝶の通い路・後編(全年齢版)

後篇
4
勝己は扉のノブに手をかけてはたと止まった。
密やかな声に耳を澄ます。出久の声だ。
眠っている自分にこっそり語りかけている。くしゃくしゃだとかトゲトゲだとか。聞いたことのないような優しい口調で。部屋に入れば何かを壊してしまいそうだ。掌が硬直したように固まってしまう。
いや、何が壊れるっていうんだ。出久が余計なことをしてやがるだけだ。音を立てないようにそっとノブを回してドアを開け、隙間から部屋を覗く。二段ベッドの上段にいる出久は気づいていないようだ。優しく語りかけながら、眠っている勝己の髪を梳いている。こんな出久を見たことがない。声をかけられない。
眠る自分の身体に話しかける出久を見ているとだんだんムカついてきた。俺にはあんな風に話すことも、笑うこともねえじゃねえか。ああそうだ、誰のせいだといえば俺のせいだ。
我慢がならなかったんだ。
ここ最近出久に対して苛ついている。隠すことは出来ないし、するつもりもない。苛立ちに任せて怒鳴り散らすとあいつは戸惑い。怯えるあいつの面を見て、一瞬だけ溜飲が下がる。その後は胸を掻き毟りたくなるくらい苦しくなる。その繰り返しだ。
昔のように堂々巡りになるだけだ、間違った方法だと。わかっていてもそうする以外、手段が浮かばねえんだ。
グラウンドベータで対決して以後、出久は日毎に打ち解けてきた。いつも自分の顔を見ると、機嫌を伺うようにおどおどしていた出久が、物怖じせずに話しかけてくる。それだけでも長年のストレスが融解していった。柔らかな陽の下の木漏れ日のような。これがずっと求めていた関係なのだと思った。思い込もうとした。
だが次第に違和感を否定できなくなった。燠火のように腹の底で燻るもの。それが何なのか認識したのはあの日だ。
いつものように出久はトレーニングを済ませて寮に戻ってきた。自分は共有スペースに向かうために階段を降りていたところで、階段を駆け上がってきた出久と階段の踊り場でぶつかり、組み伏せる形で転んだ。
身体の下に出久がいる。
汗ばんだ出久の身体の存在感に、Tシャツ越しの体温に、心臓が早鐘を打った。ざあっと頭に血が上り、下腹部が熱くなった。
重なった身体の、押し付けた下腹部の、股間の膨らみに気づかれたんじゃないか。
だが、あいつは平然として言った。
「ごめんね、よそ見してたよ」
顔色も変えることもなくだ。俺が勃っていることもわかっただろうに、気にしてないのだ。組み伏せられても何とも思わないのだ、出久の野郎は。ふつふつと怒りが沸いた。
「気いつけろ!クソカスナード!」
不機嫌を露わにして返しても、俺の苛立ちに気づきもしない。へらっと謝罪の言葉をまた繰り返すだけだ。以前なら、俺が何らかのアクションをすれば出久はビクついていだろう。俺の機嫌を探るように見つめてきただろう。あいつを追い詰める俺の高揚と、あいつの緊張はある意味で共通していたのだ。今はどうしようもなく乖離している。
あいつに覚える勃起の感覚を、興奮しているからだとか疲れてるからだとか、もう言い訳は出来ないのだ。俺はここから始まると思っていた。なのに、出久にとって俺との関係はここがゴールなんだ。俺とあいつとは望む未来形が違うのだ。どこまで行っても平行線なんだ。
このままではだめだと確信した。壊さねばならないのだ。弛緩した関係に落ちて身動きが取れなくなる前に。
生温い関係なんざいらねえ。んなものは糞食らえだ。
俺の持っていた万能感を、さらに増長させたくせに、それを根こそぎ奪った出久。俺を満たすものはあいつが持っているのだ。取り戻さなきゃいけないのだ。悔しいのも苦しいのも、あいつのせいなのだ。そんな風に思い込んで。ぶつかり合って、弱さを認めて、自分を包んでいた殻が剥がれ落ちて、それでも残ったもの。それだけが確かなもの。
あいつが欲しい。必ず手に入れてやる。
きっとそれだけだったのだ。ならば無自覚な内から何年思い続けてきたと思っているのか。どれだけ想いを拗れさせてきたと思っているのか。
吐き出せない想いが胸に溜まってゆく。顔を見るだけで息が詰まって日に日に苦しくなる。苛立ちはつのるばかりだった。なまじ期待してしまった故に、自覚してからは一層憎らしくなった。まだこれまでのギスギスした関係の方がマシだとすら思ったのだ。
てめえに俺という存在を刻み付けられないで、何の意味がある。てめえは俺の気持ちを逆立てるくせに何も気付いてやしない。穏やかな関係なんざ俺たちには似合わねえ。俺はてめえを壊してえんだ。てめえが何を望んでいたとしても。
クソがクソが!腹が立ってしょうがねえ。こそこそ見ているなんて、俺らしくねえんだよ。
「おいデク!」
と怒鳴り、勝己は勢いよくドアを開けた。出久はびくりと震え、慌てた様子で勝己の方を振り返る。
「な、何、かっちゃん」
「今てめえ」と言いかけて勝己は踏みとどまった。言えば出久が眠ってる自分の髪を梳いているのを、覗いていたことがバレてしまう。「何でもねえ」と怒鳴って誤魔化す。
「ね、寝返りさせてたんだよ、かっちゃん」
見られていたとも知らずに、言い訳する出久に心底苛ついた。
その夜は広場でキャンプファイヤーが行われた。A組とB組合同での開催だ。
夕暮れになりB組の面々が合宿所に押し寄せてきた。
「おう!切島」「おう鉄哲!」と似た者同士で拳をぶつけて挨拶し合っている。女子達は「久しぶりー」「もっと合同イベントやりたいよね」と盛り上がっている。出久は班長同士で集まっているようだ。「1年生の時の林間学校ではできなかったからね。途中で中断してしまったからね」と物真似野郎がこっちを見ながら、思い出したくないことを蒸し返してきた。クソうぜえ。殺意を込めて睨みつける。
広くはないロビーがごった返してきて、喧しくなってきた。「班ごとに点呼をかけろ。全員揃ったら広場に出るように」と先生達が声をかけた。
広場では星明りと合宿所の明かり以外に光がない。少し離れるだけで、視界が黒いビロードのような闇に包まれる。
昼のうちに組んだ木組みに轟が火を付けた。ビロードを闇を焦がし、炎は次第に大きくなりパチパチと火花が爆ぜる。安定したところで、皆が輪になって炎を取り囲んだ。
火焔は舞い上がり、火の粉を吹いて闇を焦がす。金色の粉に煽られ、色鮮やかな蝶が幻のように現れた。眩さに誘われたのだろうか。蝶は焔と遊んでいるかのように戯れ、橙色の舌に巻かれて捉えられ、舞うように火に飛び込む。途端に蝶は影となり消えてしまった。跡を追うように、一匹また一匹と、炎に向かって蝶が飛んでくる。
身を焦がすとも知らずに炎に近寄る蝶に、誰も気づいてないのか、A組の奴らもB組の奴らも皆笑ってやがる。何がおかしいんだ。
炎から目を離している間に蝶がいなくなった。燃やし尽くしてしまったのか。
いや、蛾じゃあるまいし、夜に蝶なんて飛ばないだろう。幻影だったのだろうか。俺しか見てないのか。出久は見ていただろか。
勝己は輪の中に出久の姿を探した。名前も覚えてねえB組の連中を4,5人おいて出久は立っていた。癖っ毛が炎のように揺らめいている。焔に照らされた顔は嬉しそうでやけに眩しい。てめえはそんな顔もしやがるんだな。一瞬見惚れてしまう。網膜に焼き付く。
あれは俺のだ。胸に焼きつくような痛みが走る。なんでこの手の中にいないんだ。
先生の指示で輪になった隣同士で手を繋ぎ始めた。勝己はじっと掌を見つめる。厚い皮膚に覆われた、爆破の衝撃に耐える掌。苛ついて苛ついて、いつかのように、また俺はあいつの手を突き放したんだ。
輪から出ると、勝己は「どけ!」と出久の隣の生徒を押しやって、繋いでいた手をもぎ離し、隣におさまった。
「え!なに?かっちゃん?」と躊躇する出久の手を構わずにぎゅっと握る。出久は驚いて目を見開いたが、たどたどしく指を折り、手を繋いでぎこちなく勝己に微笑みかけた。
出久の作り笑いだ。反射的に勝己の眉根に縦皺が寄った。見るたびに苛立ってしょうがなかった。本当の笑みを向けるようになってきてたのだ。もっと先を渇望してやまなくて、苛立ちでてめえを遠ざけた。
永劫に交わらない平行線なんて耐えられない。それでも手放すことなんてできない。どうすればよかったんだ。
掌の温もり。じわりと侵食してくる出久の体温。
俺のもんだ。
炎は空気を孕んで巻き上げる。火の粉が夜に吸い込まれ、星になってゆく。
夜が明けたようだ。
瞼の裏が赤くなり、明るさを感じる。だが何故か目が開けられない。
「眠ってる君は側に寄っても怒らないね」と囁く聞き慣れた声。ころころと鼓膜を擽る出久の声。
優しく髪を梳く出久の指。勝手にてめえ、俺に触んな。髪に差し込まれた指が丁寧に髪を撫でる。触れられた頭皮の箇所がさわっと痺れる。すぐ傍に座っている出久の気配。動悸が早くなる。前髪を梳いていた指が額を撫でる。擽ったいけれど気持ちいい。
ドアが開く音。
「おいデク!」
自分の声が聞こえた。するっと手が離れてゆく。
「な、何、かっちゃん」と狼狽したような出久の声が応じた。
出久は梯子を降りて行った。待てよと引き止めたい。今のはなんのつもりだと問い詰めたい。なのに目は開けられず身体は動かない。クソが!
てめえはいつもそうだ。近づいてきてはそっと触れて、すぐ離れるんだ。てめえが気まぐれに触れるだけで、俺がどう思うのか考えもしねえんだろ。
自分の弱さを認めたことで、確かに俺は楽になった。てめえとガキの頃みたいに話せるようになった。だから俺は高望みをしちまった。てめえが手に入るんじゃねえかと。だがてめえは俺とお友達ごっこができれば満足なんだ。この先なんてねえんだ。くだらねえ。
俺は違う。てめえは考えたこともねえだろ。俺がてめえに欲情してるなんてよ。抱きてえって衝動を押さえつけてるなんて、ありえねえんだろ。
触れたらきっと押さえ切れねえ。今までてめえに対しての衝動を、律したことなんか一度もねえのに、今になって忍耐が必要になるなんて。なのにてめえは知りもしねえで、お気楽に俺に触れやがって。
目が覚めて飛び起きた。まだ日の出の前の薄暗さだ。
なんだ今の夢は。ただの夢にしてはやけに生々しかった。髪にまだデクの手の感触が残っているようだ。隣のベッドで出久は静かに寝息を立てている。
まさか、眠ってる自分の身体に入ったのか?
話していた内容は昨日の昼間にしていたあいつとの会話だった。昨日の自分の中だったのか。あり得ない。ただ記憶が夢で再現されただけじゃないのか。ならば頭皮に髪に残るあいつの感触はなんだ。
「おはよう、かっちゃん」
起きた出久は伺うように挨拶してきた。昨日のキャンプファイヤーで手を繋いだからか、心なしか気を許しているようだ。あんだけで弛緩してんじゃねえと、ちょっといらっとする。出久は呑気に布団を畳みはじめた。こいつはどうなんだろう。
「おいデク、変な夢を見なかったか」と聞いてみた。
出久はきょとんとしている。「昨日の夢は覚えてないよ。かっちゃんがそんなこと聞くなんて、どうしたの?」
「どうもしねえわ。うぜえ」
こいつは見てねえのか。ならただの夢に過ぎないのだろうか。
その夜、勝己は出久のベッドの上段に上がり、眠る出久の枕元に座った。穏やかに寝入っている顔を見つめる。出久は風呂に入ってるから暫くは戻って来ない。
そっと頬に触れる。柔らかくてすべすべした手触り。そばかすを数えるようにつつく。指を滑らせて、唇を形どるように撫でる。
てめえは夢ですら中途半端なんだよ。たとえ夢の中であったとしても、てめえが俺に触れるなら。俺も触ってやるわ。
勝己は出久に顔を近づけて、そっと触れるだけのキスをした。柔くて温かい。足りない。全然足りない。顎を掴んで口を開かせ唇を塞ぐ。口内に舌を差し入れて舌先で舐める。歯列を舐めて出久の舌に触れる。アイスクリームを舐めるように、濡れた柔らかさを味わう。離してもう一度、今度はもっと舌を絡ませて深いキスをする。夢中になってキスを繰り返す。唇が離れるたびに濡れた音がする。
わかってたことだ。触れてしまったら止められないってことは。
部屋の外で足音が聞こえた。聞き慣れた靴音。出久が戻ってきたのだ。それでももう少しだけ、後一回だけとキスを続ける。浅ましく求めてしまう。
出久がドアを開けた。ベッドの上段を見上げて首を傾げ、「何してるの?」と問うてくる。勝己は徐ろに頭を上げた。気づかれてはいないようだ。
勝己は何食わぬ顔で答えた。「何でもねえよ。てめえが息してんのか顔見て確認してただけだ」
「そう、なんだ。ありがとう。かっちゃん」
ベッドからジャンプして飛び降り、勝己は出久に告げた。「デク、今日から交替だ。俺が身体の面倒みてやるわ。俺のもてめえのも両方な」
「え?かっちゃんが?」
「今までご苦労だったな」
勝己はにやりと笑った。あ、うん。と出久は何か言いたげにしていたが、何も言わずに目を逸らした。
5
かっちゃんは何してたんだろう。僕の身体がある方のベッドで。顔を見てただけだと言っていたけれど。嘘をつく理由はないから、彼が言うならそうなんだろう。でもなんで僕の顔なんか。聞きたいけど、怒られそうで聞けない。
かっちゃんは僕と入れ替わりに風呂に入りに行ったから、まだ暫くは戻ってこない。戻って来たら聞いてみようか。空の隣のベッドを見ながらうとうとして、出久はいつの間にか眠りについた。
外が明るい。瞼の中に光が射してくる。朝になったみたいだ。なのに目が開けられない。身体も動かせない。金縛りだろうか。
側に人の気配を感じる。顔の上に被さる体温。唇に柔らかいものが触れる。誰かの唇だ。触れては離れる温もり。誰かの手が顎を掴んで口を開けさせた。唇を割って入って来たのは人の舌だ。ピタリと唇が合わせられ、口内を柔らかい舌が這う。口腔を余さず探られる。吐息を奪われる。舌を舐め上げられ、戯れるように絡む水音が直接耳に響く。ディープキスされてるのか。どうしよう。逃げられない。焦るのに身体が動かない。誰なんだ。
甘い匂いが鼻先を掠める。嗅いだことのあるような匂い。
そんなはずない。気づいてはいけない。頭の中で警鐘が鳴る。
何してるの、という声が聞こえる。名残惜し気に唇が離れた。覆い被さっていた人物が答える。
何でもねえよ、息してんのか確認してただけだ。
かっちゃんの声?今のはかっちゃんなのか?
驚いて飛び起きた。天窓には星明かり。瞼の裏は明るかったからてっきり朝だと思ったのに、まだ夜だったのか。動悸が速い。心臓が咽喉から飛び出そうだ。なんて夢見てしまったんだ。かっちゃんがそんなことするはずないじゃないか。昨日と同じ会話をしていた。きっと記憶を元にした僕の妄想だ。
眠ったらまた見てしまうかも知れない。出久はまんじりともせずに夜を過ごし、白々と夜が明けてほっとした。
勝己を起こさないように、音を立てないようにして部屋を出ると、洗面所に向かった。夢のはずなのに口の中に生々しく蘇る口付けの感触。朝なんだし、歯を磨いてから戻ることにしよう。
だが、歯磨きを済ませて何度うがいをしても、どうしても夢の中でのキスの感触が消えない。
唾液の味。口腔の粘膜を探る柔らかさ。脳に直接的聞こえた舌の触れ合う音。
顔が火照ってしょうがない。振り払うように水飛沫を上げて顔を洗う。顔を上げると鏡の中に勝己の顔が見えた。いつの間にか勝己が背後に立っていたのだ。
「うわ!かっちゃん」
「てめ、飛沫が撥ねんだろが!クソが!」
「ごめん、拭いておくよ」
出久は首にかけていたタオルで鏡を拭く。ゴシゴシ拭くとかえって鏡面が曇ってしまった。
「なあ、デク」背後で勝己が言う。「昨日変な夢見てねえか?」
問われてどきりとする。まるで見透かされているような口調。あんな夢見たなんて、君が知るわけないのに。聞かれたって誰にも言えるわけ無い。君に、言えるわけない。
曇った鏡から目を離さずに「別に夢なんて見てないよ」と答える。
「夢を見てないと思ってる奴でも、本当は見てるらしいぜ。忘れてるだけでよ」
「そ、そうなんだ。詳しいね」動揺してしまって振り返れない。とても今は顔を直視できない。
「ふうん」納得してはいないような訝しげな声だ。「こっち向いて答えろよ、デク」
耳のすぐ後ろで低く囁かれた。ひゅっと息を呑む。皮膚がざわつく。
「なあ、デク」勝己の手が肩に触れた。
「爆豪、緑谷、ここにいたのか。朝飯の前にちょっと部屋に来てくれ」
入り口の向こうから呼びかける声。相澤先生だ。身体の硬直が解けてゆく。
「ああ?んだよ」
勝己が背後から離れて、洗面所を出て行った。安堵して肩の力が抜けた。
「何かわかったんですか」
「まだ原因はわからない。やはり俺達の他にこの付近には誰もいなかった。衛星も監視カメラも確認したし、改竄の後もない。個性を食らったわけでもないようだ。」
出久の問いかけに、パソコン内のカメラの映像を示して、相澤先生は言った。
勝己は憤慨した。「結局なんもわかんねえんじゃねえか」
「だが手がかりはなくはない。宿泊施設の関係者に聞いたが、この山では時折不可思議な出来事が起こるらしい」
「どんなことがあったってんだ」
「数年前のことだ。山に登った子供達が合宿所で過ごしている内に、いつの間にか人数が1人増えていたそうだ。だが誰が増えたのかわからない。なにかの手違いなのかと思ってそのまま過ごしたが、数日たって下山する頃には、減って再び元の人数に戻っていたらしい。今度は逆に誰が減ったのかわからなかったそうだ」
「本当かよ。嘘くせえ」
「登山者の中に子供がいるときに、たまにこういった現象が起こるらしい。全く同じではなくても、類似の記録がいくつもあった。原因はわからないが、こういった現象は山にいる間だけで、下山する頃には元に戻っていたそうだ。今まで何事もなく済んでいるので公にしてないらしい」
出久は問うた。「ほっといていいんですか」
「調査はしたそうだが、個性の発現以後そういった学問は廃れ気味でな、専門家が少ないんで難航しているようだ」
「人に宿る個性でも、超常現象レベルのものもありますもんね」
轟や八百万の個性も勝己の個性も、個性の時代だからこそ普通に受け入れられているが、物理現象としては相当不可思議といえる。無論、OFAも。
「何かの個性の残滓が残っていたのかも知れないが、どちらかと言うと、やはり現象というべきだろう」相澤先生はふうっと息を吐いて続ける。「しかし、原因と思われる子供はいたらしいな」
勝己が乗り出した。「やっぱりいんじゃねえか、犯人がよ」
「え、でも個性ではないんですよね」出久は問うた。
「説明しにくいことだがな」相澤先生は続ける。「今までの事件の共通項は、子供達の中にえらく不安定な者がいたということなんだ。精神的にまいってたり鬱屈してたり、逆にハイになってたりな。そんな極端な心の波動が外部に影響を与えることがあるらしい」
「つまり今回も誰か原因になる奴がいるってことか。そうだな?」と勝己。
「ああ、おそらくだが」相澤先生は椅子を回して向き直る。「原因はお前達の方にあるようだな」
「はああ?俺らのせいだって言うのかよ!冗談言えよ」勝己はいきり立った。「そりゃあ憶測でしかねえんだろ」
相澤先生は静かに語る。「お前らに起こった現象なんだから、原因もお前ら自身と考えるのが自然だろうが。まあ確証はない。ただ、子供の精神力は強いんだよ。お前達の考える以上にな。現実を覆し幻を具現化させてしまうほどに」
「やっぱり分身作るとか、そういう個性の奴がいただけじゃないのかよ」
「残念だが該当するような個性の者はいなかったそうだ」
「新たに個性を得た奴がいたんじゃねえのか」
「個性は4歳までしか発動しない。例外はない。知っているだろう」
ちらっと勝己を伺って出久は返事をする。「はい、そうですね」
勝己は鼻を鳴らした。出久の個性が高校になっていきなり発現したと思われていた頃は、随分勝己を悩ませていただろう。
「だから現象としか言いようのないものだ。もう一度聞くが、お前達に合宿所に戻るまでの記憶はあるのか」
「言ったじゃねえか。ねえよ。霧の中で彷徨っていただけだ」勝己が言う。
「その前に何してたか覚えてるか。森の中に入ったことじゃなく、その前までの記憶だ」
出久が答える。「その前って、ベッドに入って眠って。気が付いたら森の中を歩いていたんです」
「なるほど。前の夜に睡眠した自覚はあるんだな」相澤先生はふっと笑った。「ひょっとして、お前たちは夢の中から来たのかも知れないな」
「はあ?何言ってんだ」勝己は言う。
「仮定だがな、お前たちは今、夢を見ているのかも知れんぞ。この合宿の夢をな。今話してる俺もお前らにとっては夢なんじゃないか」
「先生?そんなこと」
これが夢だなんて。飯盒炊飯もキャンプファイヤーも夢だなんて。出久はぐらりと足元が揺れたような気がした。
相澤先生は言う。「ま、冗談だがな」
「やめろよ、笑えねえ!」勝己は怒って言い返す。
「で、夜は眠れるのか?」
「ああ?ちゃんと寝てるわ!」
「どうだ、夢は見るのか」
一拍おいて勝己は答える。「夢なんざなんも見てねえよ」
「僕も見てないです」出久は嘘をついた。
その他に眠ってる自分達の身体に何か変わったことはないかと細かく聞かれ、何もないと二人とも答えた。
「変化なしか、様子を見るしかないな。今までのところ他の生徒達には何も起こってないようだ」
引き続き隔離するかのように、屋根裏部屋で寝ることになったが、意外なことに勝己は大人しく同意した。同室になった当初はあんなに文句を言っていたのに。
朝食の時間が近くなったので、2人は相澤先生の部屋を退出した。何故か歩調を合わせて勝己は出久の隣を歩いている。見られているようで落ち着かない。
勝己が口を開いた。「てめえ、夢見てねえのか」
「え?な、ないよ」ちょっと狼狽える。夢は見てるがとても言えない。
「かっちゃんも夢、見てないんだよね」
「聞いてんのは俺だ」
「見てないよ。本当だよ」
勝己が睨んでいる。見透かされているようで目を合わせられない。君が知るはずもないのに。
夜が来てしまった。
勝己のベッドからは寝息が聞こえてくる。もう眠ったようだ。
出久は溜息をついた。眠りたくない。またあんな夢を見てしまうかも知れない。だがベッドに入るとあっという間に睡魔が押し寄せた。
瞼の裏はとても明るい。どうやら昼間のようだ。梯子を登ってくる足音。ベッドがミシリと音を立てて軋んだ。顔の上に人の気配。唇に吐息を感じた。
誰かがキスを落とした。唇の感触は生々しくて夢とは思えない。指一つ動かせない。自分の上にいる人物はキスをしながら布団を剥がした。誰かの掌が身体に触れる。服の上から愛撫する。
Tシャツの裾から手が潜り込み、腹から胸を摩り、乳首を指先で撫でて摘む。ごつごつした手が動けない自分を弄ぶ。それなのに身動きできない。相手のなすがままだ。この掌をよく知っている。手の持ち主がデク、と囁いた。
切なげにデク、と名を呼ぶ勝己の声。何度も何度も。こんな優しい声なんて聞いたことがない。肌を探る手つきも優しくて、出久の気持ちは落ち着いてきた。だがそれは短い間だった。
腹を撫でていた手がハーフパンツの中に潜り込んできた。動転して目を開けようとしたができない。手は暫く布の上から性器を撫でていたが、するりとボクサーパンツの中に入って来た。強制的に快感を煽られ、嫌だと思っても指一つ動かせない。気持よくて怖い。知らない感覚を呼び覚まされる。やめてと声を出そうとしても果たせない。
目が覚めた。天窓から笑ってるような形の月が見えた。
声を上げてしまってやしないだろうか。シャツの中は汗だくだ。股間が膨れている。恐る恐る触れたが、濡れてはいない。夢精してなかったようでほっとする。
また変な夢を見てしまったのだ。感触が残っていて本当に起きたことのようだ。でもまさか。かっちゃんがそんな、僕に悪戯なんてするわけないじゃないか。万が一そんなことされたとしたら、流石に起きるだろう。
何度もあんな夢を見るなんて、彼への冒涜だ。ひょっとして僕の願望なのか。違う。彼への気持ちは憧れだ。そんなのあるわけない。
そろっと起き出してトイレに向かった。用を足そうと前をくつろげ、手が硬直する。
まるで本当にあったことのように生々しく蘇ってくる。なんでこんな夢を見るんだ僕は。おかしくなりそうだ。
この日も勝己はいつもどおり剣呑としていた。食事中もトレーニングの間も変わらない。けれども、時々探るような視線を向けられている気がした。
夢を思い出してしまって、彼の顔をまともに見られない。僕はどんな顔をしているんだろう。
6
夕食が終わり、勝己の後に風呂を済ませて、出久は部屋に向かった。
明日で合宿は終わる。前例通りというなら、原因不明のこの事象も終わるのだろうか。 変な夢も、見なくなるだろうか。先生は様子を見ると言ってたけど、もし何も変わらなかったらどうなるんだろう。考えに耽りながら部屋のドアを開けた。
「遅かったじゃねえか、デク」
低い勝己の声。暗い部屋の中、勝己が窓枠に座っている。月明かりに髪が金の焔のように揺らめいている。瞳の赤が光を反射して、まるで猛禽類のようだ。捕食されると錯覚したかのように体が震え、ざわっと総毛だつ。
「待ってたぜ、デク」
「かっちゃん?電気つけないの?部屋暗いよ」
恐れを堪えて明かりのスイッチを入れようと壁を探すと「つけんな!」と勝己は吠えた。びくっと手が止まる。
「デクてめえ、昨日はどんな夢を見たんだ?」
「何も、夢なんて何も見てないよ」
「見てんだろ?しかも誰にも言えないようなやつをよ」
心臓が跳ねる。まるで夢の内容を知っているような口調だ。君が知るわけない。あんな淫夢のような夢。
「そういうかっちゃんはどうなんだよ」逆に問うた。
「俺は見てるぜ。毎日な。どんな夢か聞きてえか?」
デクはゴクリと唾を飲んだ。聞いてはいけない気がして、首を横に振る。勝己がくくっと笑った。
「そこで眠ってる俺らはどんな夢を見てるんだろうな。デク」
「え?考えたこともないよ」突然話題を変えられて戸惑う。
「合宿の夢を見てるのかもな。今この時、てめえが入って来て、俺がこの窓枠に座ってる、この瞬間を夢に見てるのかもな。そう思わねえか」
「それじゃまるで、僕らが彼らの見ている夢みたいだね」
「ああ、かも知れねえぜ」
「相澤先生の言ってたのは冗談だよ、かっちゃん、ねえ、電気付けようよ」
「冗談、じゃねえんだよ」
出久がスイッチに手を伸ばした途端、手元に爆発の火花が飛んできた。
「付けんなっつってんだろーが!」
「あぶないよ、かっちゃん。スイッチに当たったら壊れちゃうよ」
「てめえが余計な事しなきゃやんねえよ」
仕方なく照明をつけずにドアを閉めた。月明かりだけが部屋を青白く照らしている。
勝己が言った。「なあ、デク、俺はこの部屋に来た初日から、眠るとあの身体にオーバーラップしてたんだぜ。知ってたか?」
頭が真っ白になった。まさか、眠っていると思っていた身体に、勝己の意識があったのか。自分がしていたことを、勝己は知ってるのか?
「嘘だろ?かっちゃん」
「やっぱり知らなかったんだな。だろうよ。てめえが寝てる俺に呼びかけてんのも、俺の髪梳いてんのも知ってるぜ。デク。俺がてめえを部屋に呼びに来た声まで聴いてる。間違いなく俺はその身体ん中にいたんだ」
かあっと顔が熱くなった。薄暗がりで良かった。きっと顔に出てしまっている。
でも、冷静になれ。勝己はカマをかけてるだけかも知れないのだ。肯定してはいけない。
「そういう、夢だっただけじゃないのかな?」出久は平静を装った。
「それを確かめようと、てめえと交代したんだ。眠ってる身体ん中に、てめえがいんのか呼びかけた。俺の声聞こえてたんじゃねえか?」
聞こえてた。デクと呼ぶ声。でも、それだけじゃない。とても言えない。
「ああ、呼んだだけじゃねえわ。確かめようとてめえに触れちまってな。歯止めがかからなくなった。俺が何したか、てめえ、知ってるよな?」
「かっちゃん、まさか」
「キスの味はどうだった?デク」勝己が言った。「寝てても勃つんだな。気持ち良かったか?」
身体の中で僕が覚醒しているのを知ってたのに、かっちゃんは僕の肌に触れて、僕のあれに触ってたのか。頭に上った熱で目眩がしそうだ。
「てめえは顔に出るよなあ。デク」勝己はさもおかしそうに笑う。「てめえは俺より先にはオーバーラップしてなかった。てめえがそうなったのは、俺と交替してからだろう。眠るてめえにキスしてから、態度がガラッと変わったからな。てめえは眠る身体には意識がねえと思ってたわけだよな。だから俺に触ったんだろ」
出久は震える声で言った。「ごめん、知っていたら、触れたりしなかった。君は怒るってわかってたから、でも僕は」
「てめえの言い訳なんざどうでもいいんだよ。俺がなんでてめえに触れたのか、気になんねえのか。聞かねえのか?聞けよ!デク」
触るなって言ってたのに僕が君に触ったから、仕返しされてたんじゃないだろうか。僕を辱めて。面と向かうとそうとしか思えない。何故こんな手段を。
「なんでこんな悪戯、したんだ?」
「悪戯か!は!てめえはすぐにてめえ勝手に解釈しやがる。クソが!まあいい、どうせこれからじっくり教えてやんだからよ。俺は謝らねえぜ。てめえは俺に触れたかったんだろ。俺も触れたかったんだ。なら同罪じゃねえか。罪とは思わねえ」
「かっちゃん」お互い様だから水に流そう、てことだろうか。
「この現象ってやつの仕組みの話だけどな」勝己は首を傾ける。「この身体が眠った時だけ、元の身体に戻ってるんだろうな」
「あっちの身体が本物だって認めるんだね、かっちゃん。じゃあ、僕らは」
「相澤先生の言った通り、俺らは元の身体の見ている夢なんだろうよ。夢が形を成して浮遊してるんだ。意識が身体に戻りつつある今、ほどなくこの身体の方は消えんだろ。多分、明日には。そういう気がすんだよ」
「じゃあ、あっちの身体で目覚めるんだ」こっちは消える。恥ずかしい思いごと、この身体は消えてしまえるのか。そうして、自分たちは元の身体に戻れるのか。
「いや、どっちの身体が消えちまうのかはわかんねえか。どちらが残るにしろ一つに戻るんだろ。だが、意識が眠る身体の方に戻ったら、この身体で経験したことは忘れちまうのかも知れねえ」
「元に戻るんだよ。かっちゃん」それでいいんじゃないか、と思う。
「ああ、だけど忘れちゃいけねえことがあんだろうが、デク」
勝己の瞳がすうっと細められる。「俺がてめえにしてたことはてめえにバレた。てめえが眠る俺に何してたのか、俺は知った。てめえの本心が知りたくて随分回り道しちまった。やっとてめえの気持ちがわかったってのによ」
勝己は窓枠から降りてゆらりと立ち上がった。「なのに、もし消えるってんなら、忘れちまうかも知れねえんなら、元の木阿弥だ。せめてその前にてめえを手に入れる」
薄暗がりの中で、勝己の赤い瞳だけが爛々と野生動物のように光った。捕食される、と頭の中に警鐘が鳴り響く。でも金縛りにかかったように手足が動かない。勝己は壁際に出久を追い詰めた。
「待って!仮定だろ、かっちゃん」
「なあ、デクてめえも俺に触ってたろ。こうやって髪に触ってたよな」
勝己は出久の手を掴んで髪に触らせる。指先にさらさらと触れる髪。眠っていた勝己の髪と同じ手触り。
「てめえは顔にこう、触ってたよな」勝己はさらに頬に掌を当てさせる。
「ごめん。かっちゃん」
「ああ?何をあやまってんだ。俺もてめえに触ってんだ」少し苛立ちが勝己の声に滲んだ。ごくっと勝己の喉仏が上下する。「デク、触んぞ」
Tシャツが捲られ、出久の肌を勝己の掌が滑る。指先が乳首に触れて円を描くようになぞる。出久の反応を引き出すように丁寧に愛撫する。
あ、と声を出してしまった。足の力が抜けてしまい、壁にもたれかかったまま、ずるずると崩折れて床に腰をつける。勝己もしゃがんで膝をつき、五指で胸筋の間をなぞる。指は腹筋に降りて文字を描くように触れる。夢で感じたのと同じ性的な指の感触だ。吐息が震える。
「寝てるてめえに触るよりずっといいな。反応があるからよ」
くっと笑うと、勝己の手は出久の下腹部を撫でてハーフパンツの中に入った。夢と同じように、下着の上から出久のものを撫でる。
震える声で出久は「かっちゃん」と呼んだ。
「なんだ、デク」と囁きながら勝己が唇を重ねる。貪るようなキスをする。ねっとりと口内を味わって、唇が離される。
「甘えな。夕飯のデザートか、歯磨いたんかよ」勝己は揶揄うように言った。
「磨いたよ」
「ああ、じゃあ、これはてめえの味か」
にっと笑い、勝己は再び唇を奪うと、キスをしながら床に組み伏せた。出久のTシャツを剥ぎ取り、勝己も脱いで肌を重ねる。均整のとれた筋肉質な身体の重み。勝己の唇が顎を辿り、首元まで降りてゆく。肌に唇を滑らせ、吸い上げる。さっき捏ねられて、膨れた乳首を舐めあげる。唇と舌で肌に与えられる、感じたことのない感覚。
「こんなの、間違ってるよ」震えが止まらない。「夢に踊らされてるんだ」
「それがどうした。逃げんな」
「かっちゃんだって、わかってるだろ」
出久は身体をずらして重みから逃れようとした。だが、勝己は緩慢に逃げをうつ身体を返して俯せにし、腰を持ち上げる。
「今更逃げんな、デク」
勝己が顔を近づけてくる。
月明かりに青白く照らし出された端正な輪郭。美しい金の獣だ。一瞬、この獣になら食われてもいいと思ってしまうほどに。
「デク、てめえから始めたんだ。眠ってる俺にてめえが触れた時からな」
7
霧に包まれた山頂で、虹の中に見えた2つの影。
並んで仲良く見えた2人の姿。
あれが僕らであったなら。あの時僕はそう思ったのだ。
隣で一緒に見上げていた君も、そう思っていたのだろうか。
瞼の裏に光が射した。天窓からの光。朝の光。出久は目を覚ました。
昨日よりも天井が近い。二段ベッドの上段だからだ。ということは眠っていたほうの身体だ。元の身体に戻ったということなのか。
身体を起こした。ずっと寝ていたから身体の節々が凝ってる。だが身体の内部に残るこの痛みはなんだろう。彼との性交による痛みなのだろうか。この身体ではないはずなのに。いや、あれはひょっとしてこの身体だったのか?
「おいデク」
反対側のベッドで勝己が立膝をついて出久を見つめている。
「かっちゃん」
君も目覚めたんだな。射るような強い視線。下段のベッドに勝己の身体はない。ならば自分の身体も下段にないのだろう。
勝己は跳躍してデクのベッドに飛び移った。反動でぎしっと軋む。
「てめえ、やっと起きやがったか。遅えわ」
勝己は出久の手を取って自分の頬に当てる。温かい肌。君の体温。
出久は口を開いた。「僕達は偽物なのかな。本物なのかな」
勝己は出久の頬に手を伸ばし、さらさらと撫でる。指が顎を辿り首筋に下りて、まるで確かめるように触れてゆく。出久は擽ったくなり、ふふっと笑う。
勝己は鼻先に顔を近づけた。赤い虹彩が灯火のようだ。
「デク、んなこたあ、どっちでもいいわ」
勝己は囁いた。その言葉を呑ませるかのように、触れた唇をそっと重ねた。
END
『胡蝶の夢』
荘子の故事から
自他の区別がつかない境地。
目的意識に縛られない自由な境地。
または現実と夢の区別がつかないことのたとえ。
人生のはかなさのたとえ。
もしくは物の形は変化しても本質は変わらないということ。